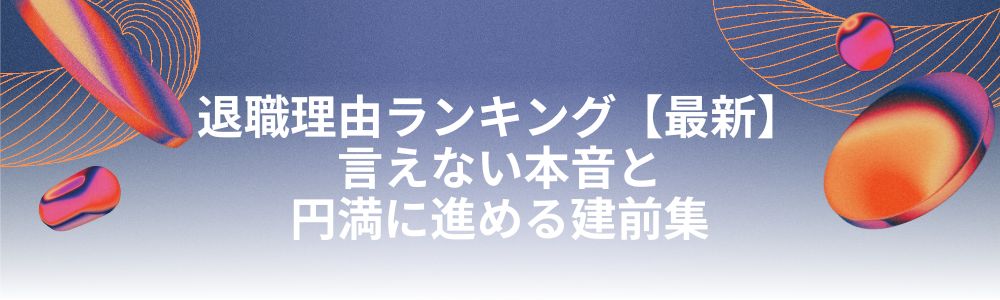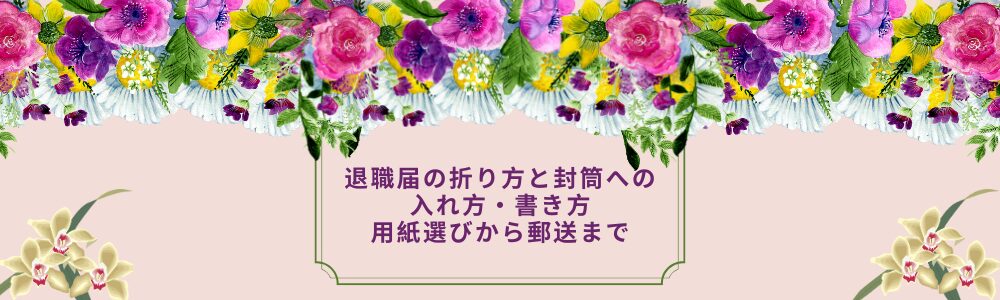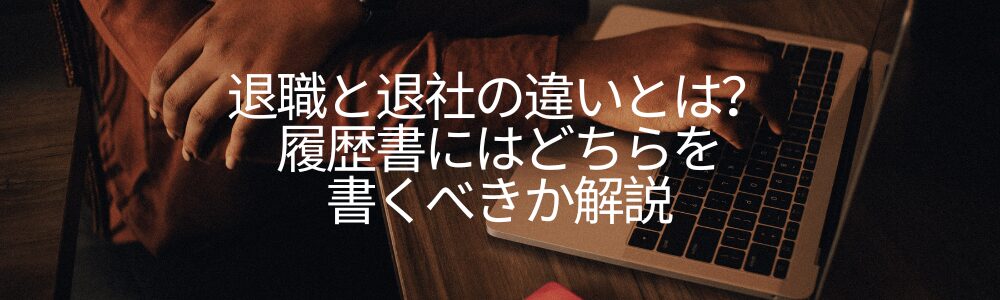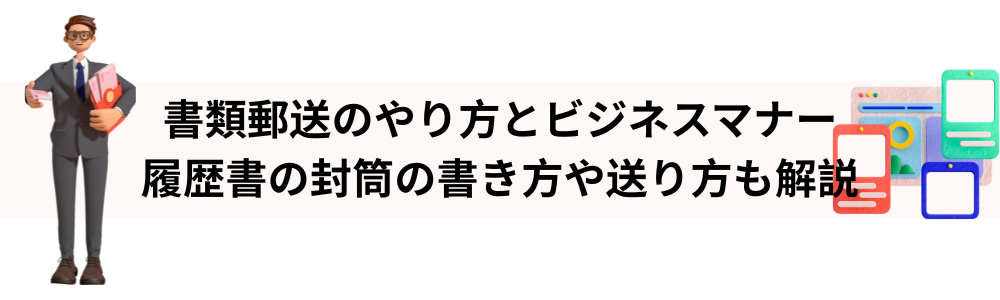

書類郵送のやり方とビジネスマナー|履歴書の封筒の書き方や送り方も解説
ビジネスシーンにおいて、書類の郵送は頻繁に行われる業務の一つです。
特に就職・転職活動で履歴書を送る際は、封筒の書き方や送り方のマナーが第一印象を左右することもあります。
このため、正しい書類郵送の仕方を知っておくことが不可欠です。
この記事では、書類郵送の基本的なルールから、ビジネスマナーに沿った封筒の選び方・書き方、書類の入れ方、そしてシーン別の郵送方法まで、具体的な手順を分かりやすく解説します。
書類を郵送する前に知っておきたい基本ルール
書類を郵送する際には、守るべき基本的なルールが存在します。
特に、特定の書類は法律によって郵送方法が定められており、正しい知識がないと意図せずルール違反をしてしまう可能性もあります。
郵送方法の選択肢は複数ありますが、送る書類の性質を理解し、適切な方法を選ぶことが重要です。
まずは、書類郵送における最も基本的な法律上の決まりについて確認し、安全で確実な郵送の第一歩としましょう。
「信書」に該当する書類は郵送方法が法律で定められている
「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする文書のことを指し、郵便法によって郵送方法が定められています。
請求書や納品書、領収書、履歴書、契約書といったビジネス文書の多くがこれに該当します。
身近な例では、個人的な手紙も信書です。
信書を送ることができるのは、日本郵便のサービス(郵便)と、国から許可を得た信書便事業者に限定されています。
そのため、宅配便や一般的なメール便で信書を送ることは法律で禁止されており、違反した場合は差出人が罰せられる可能性があります。
重要書類を送る際は、その書類が信書にあたるかどうかを確認し、適切な配送サービスを選択することが必須です。
【目的別】自分に合った書類の郵送方法を選ぼう
書類を郵送する方法は一つではありません。
日常的な書類を手軽に送りたい場合から、重要な契約書を確実に届けたい場合、あるいは提出期限が迫っていて急を要する場合まで、目的や状況に応じて最適なサービスを選ぶ必要があります。
ここでは、普通郵便をはじめ、配達記録が残る特定記録郵便、補償が付く簡易書留、A4サイズを手軽に送れるレターパック、そして急ぎの際に利用する速達など、代表的な郵送方法の特徴と利用シーンを解説します。
最も一般的な郵送方法「普通郵便」
普通郵便は、定形郵便と定形外郵便の総称であり、最も手軽で広く利用されている郵送方法です。
ポストへの投函で発送できるため、時間や場所を選ばず手軽に利用できる点が大きなメリットです。
料金は全国一律の重量制で、軽い書類であれば比較的安価に送ることが可能です。
そのため、重要度がそれほど高くない案内状やダイレクトメールなど、大量の書類を発送する際に適しています。
ただし、普通郵便には荷物の追跡サービスや、万が一の紛失・破損に対する補償が付いていません。
したがって、履歴書や契約書といった再発行が難しい、あるいは個人情報を含む重要書類を送る際には、他の郵送方法を検討するのが賢明です。
配達の記録が残る「特定記録郵便」
特定記録郵便は、普通郵便に160円の追加料金を支払うことで、郵便物の引き受け記録と配達状況の追跡が可能になるサービスです。
郵便物を差し出した際に受領証が発行され、インターネット上で配達状況を確認できるため、「相手に発送した」という事実を客観的に証明できます。
配達方法は受取人の郵便受けへの投函となり、対面での手渡しや受領印は必要ありません。
このため、相手に受領の手間をかけさせたくないが、配達された記録は残しておきたい場合に適しています。
例えば、各種通知書や応募書類など、確実に届けたいものの、書留にするほどではない書類の郵送に利用されます。
万が一の際に補償が付く「簡易書留」
簡易書留は、郵便物の引き受けから配達までの過程が記録され、万が一の事故に備えた保証が付く郵送方法です。
配達員から受取人へ対面で手渡しされ、その際に受領印または署名が必要となります。
これにより、相手に確実に届けたことを証明できます。
最大の特徴は、郵便物が届かなかったり、破損したりした場合に、原則として5万円までの実損額が補償される点です。
このため、現金や小切手、商品券、各種チケットなど、金銭的価値のあるものや、再発行が困難な重要書類を送る際に利用されます。
書留サービスの中では料金が比較的安価なため、ビジネスシーンでも広く活用されている信頼性の高い方法です。
A4サイズの書類を全国一律料金で送れる「レターパック」
レターパックは、A4サイズ・4kgまでの書類や荷物を、全国一律料金で送ることができる日本郵便のサービスです。
専用の封筒を郵便局の窓口やコンビニなどで購入して利用します。
追跡サービスが付いているため、配達状況をインターネットで確認できて安心です。
レターパックには2種類あり、「レターパックライト」は郵便受けへの投函、「レターパックプラス」は対面での手渡しで受領印が必要です。
どちらも信書を送ることが可能なため、契約書や履歴書といったビジネス書類の郵送にも適しています。
厚さに制限がある点(ライトは3cm、プラスは制限なし)に注意すれば、非常に利便性の高い郵送方法です。
書類を急いで届けたい場合に利用する「速達」
速達は、通常の郵便物やゆうメールに追加料金を支払うことで、配達を早くすることができるオプションサービスです。
他の郵便物よりも優先的に処理されるため、通常よりもスピーディーに相手先へ届けられます。
土曜日・日曜日・・休日にも配達が行われるため、週末を挟む場合でも安心です。
提出期限が迫っている書類など、とにかく早く届けたい場合に最適な方法と言えます。
料金は郵便物の重さによって異なり、250gまでなら+260円で利用できます。
最速での配達を希望する際は、郵便局の窓口で速達で送りたい旨を伝えれば、適切な手続きをしてもらえます。
【ビジネスマナー】書類郵送に使う封筒の選び方と書き方
書類を郵送する際、中身だけでなく封筒の選び方や書き方も、送り主の印象を決定づける重要な要素です。
特にビジネスシーンでは、マナーに沿った体裁が求められます。
書類を折らずに入れられる適切な封筒サイズを選び、宛名や差出人情報を正しく丁寧に記載することは、相手への配慮を示す第一歩です。
ここでは、基本的な封筒の選び方から、表面・裏面の書き方、切手の料金や貼り方のルールまで、ビジネスマナーの基本を解説します。
書類を折らずに入れる封筒サイズの選び方
ビジネス文書で最も多く使われるA4サイズの書類は、折らずにそのまま入れるのが基本マナーです。
そのため、A4用紙をクリアファイルに入れた状態でも余裕をもって収まる「角形2号(角2)」サイズの封筒を選ぶのが一般的です。
履歴書などで使用されるB5サイズの書類の場合は「角形3号」が適しています。
地図や図面などA3サイズの大きな書類は、中央で丁寧に二つ折りにして角形2号封筒に入れます。
請求書などでやむを得ず書類を折る場合は、きれいに三つ折りにして「長形3号」封筒を使用します。
封筒の色は、事務的な用途では茶色のクラフト封筒も使われますが、履歴書や契約書といった重要書類を送る際は、よりフォーマルな印象を与える白色の封筒を選ぶのが望ましいです。
【表面】宛先の正しい書き方を解説
封筒の表面には、届け先の情報を正確に記載します。
基本は縦書きで、まず右側に郵便番号を記入し、その下に住所を都道府県から省略せずに書きます。
ビル名や部署名、階数も忘れずに明記しましょう。
会社名は中央に正式名称で書き、「(株)」などと略さず「株式会社」と記載します。
宛名は会社名より一回り大きく、封筒の中央に配置します。
会社や部署といった組織宛ての場合は敬称を「御中」、個人宛ての場合は「様」とします。
担当者名が分かっている場合は「〇〇株式会社〇〇部御中〇〇様」とはせず、「〇〇株式会社〇〇部〇〇様」と書き、「御中」と「様」は併用しません。
左下には「履歴書在中」など内容物がわかるように朱書きすると、相手に親切です。
【裏面】差出人情報の正しい書き方を解説
封筒の裏面には、差出人である自身の情報を記載します。
裏面の左下に、郵便番号、住所、氏名を記入するのが一般的です。
住所や氏名は、表面の宛名よりも少し小さめの文字で書くとバランスが良くなります。
会社として送る場合は、会社所在地、会社名、部署名、そして氏名をこの順で記載します。
また、いつ投函したかが分かるように、左上には送付する日付を「令和〇年〇月〇日」のように漢数字で書き添えるのが丁寧なマナーです。
すべての情報を書き終えたら、封筒の綴じ目の中央に「〆」や「封」といった封字を黒ペンで書きます。
これは「確かに封をしました」という印であり、第三者による開封を防ぐ意味合いも持ちます。
切手の料金と正しい位置への貼り方
切手は、封筒のサイズと重さによって決まる正しい料金のものを貼る必要があります。
料金が不足していると、差出人に返送されたり、最悪の場合は相手に不足分を支払わせてしまったりと、大変失礼にあたります。
料金に不安がある場合は、郵便局の窓口で重さを量ってもらい、正確な料金分の切手を購入するのが最も確実です。
切手を貼る位置は、縦長の封筒であれば左上、横長の封筒であれば右上に貼るのがルールです。
複数枚の切手を貼る場合は、見た目が整然とするように、縦または横にきれいに並べて貼ります。
ビジネスシーンでは、キャラクターものや派手なデザインの記念切手は避け、一般的なデザインの普通切手を使用するのが無難です。
【ビジネスマナー】丁寧さが伝わる書類の入れ方と封の仕方
書類を郵送する際、中身が整っていることはもちろんですが、書類の入れ方や封の仕方といった細部への配慮が、相手に丁寧な印象を与えます。
受け取った相手が気持ちよく開封し、スムーズに内容を確認できるよう、書類を保護するクリアファイルの使い方から、送付状の同封マナー、封筒に入れる向きや順番、そして糊付けの方法まで、一連の作業におけるビジネスマナーを理解しておくことが重要です。
書類を保護するクリアファイルへの入れ方
郵送する書類は、配送中に雨で濡れたり、折れ曲がったりするのを防ぐため、クリアファイルに入れてから封筒に入れるのがビジネスマナーです。
使用するクリアファイルは、柄や色が付いていない、新品の無色透明なものを選びましょう。
書類を入れる際は、まず送付状を一番上にし、その下に履歴書、職務経歴書といった指定された順番で重ねます。
そして、受け取った相手がファイルから出してすぐに読めるように、書類の表側とファイルの開いている側を同じ向きに揃えて入れます。
こうした細やかな配慮が、書類を大切に扱っているという姿勢を示し、相手に良い印象を与えることにつながります。
送付状(添え状)を同封する際のマナー
ビジネスで書類を郵送する際には、送付状(添え状)を同封するのがマナーです。
送付状は、挨拶の役割を果たすと同時に、誰が・誰に・何を・どれだけ送ったのかを明確にするための書類です。
本文には、簡単な挨拶文とともに、同封した書類の内容と枚数を箇条書きで記載します。
これにより、受け取った側は内容物の過不足をすぐに確認できます。
送付状は、受け取った人が最初に目にする書類であるため、すべての書類の一番上に重ねてクリアファイルに入れます。
もし、相手に署名・捺印のうえ返送してほしい書類がある場合は、その旨と返送期限を明記し、切手を貼った返信用封筒を同封すると、相手の手間を省くことができ、より丁寧な対応となります。
書類を封筒に入れる正しい向きと順番
書類を封筒に入れる際には、受け取る相手への配慮として、向きと順番に気を配ることが求められます。
まず、全ての書類(送付状、履歴書、その他書類)をクリアファイルにまとめたら、封筒の表面(宛名が書かれている面)と、中に入れる書類の正面(書き出し部分)の向きを揃えて封入します。
こうすることで、開封した相手が書類を取り出したときに、上下逆さにならず、すぐに内容を読み始めることができます。
書類を入れる順番は、挨拶状の役割を持つ送付状を一番上にし、次に履歴書、職務経歴書、その他の提出書類と続けます。
複数の書類を同封する場合は、クリップで左上を一部だけ留めておくと、バラバラになるのを防げます。
封筒を糊付けして「〆」マークを記載する方法
書類を封筒に入れたら、封をします。
ビジネス文書の郵送において、セロハンテープやホッチキスで封をすることはマナー違反とされています。
剥がれやすく、見た目も雑な印象を与えてしまうためです。
封をする際は、スティックのりよりも粘着力の強い液体のりや、テープのりを使用し、封のフタ部分全体に均一に塗ってしっかりと貼り合わせましょう。
このとき、のりがはみ出して封筒を汚さないように注意が必要です。
しっかりと封をしたら、最後に綴じ目の中央部分に黒いペンで「〆」という封字を書きます。
これは「確かに封をしました」という印であり、第三者が開封していないことを示す役割も果たします。
【シーン別】履歴書や重要書類の郵送方法
書類郵送のマナーは共通していますが、送る書類の種類や目的によって、特に注意すべき点や最適な郵送方法が異なります。
例えば、就職・転職活動で送る履歴書と、税務署に提出する確定申告の書類、あるいは企業間で交わされる契約書では、求められる丁寧さや確実性のレベルが変わってきます。
ここでは、それぞれのシーンに特化した郵送方法のポイントと注意点を具体的に解説し、状況に応じた適切な対応ができるようにします。
就職・転職活動で履歴書を送る場合の注意点
就職・転職活動(就活)において、履歴書の郵送は応募者の第一印象を決める重要なプロセスです。
まず、封筒は清潔感のある白色の角形2号を選び、応募書類を折らずにクリアファイルに入れて郵送するのが基本マナーです。
封筒の表面、左下には「応募書類在中」または「履歴書在中」と朱書きし、定規で四角く囲みます。
これにより、企業側で他の郵便物と区別され、採用担当者の手へスムーズに渡りやすくなります。
郵送方法は、ポスト投函で済ませられる普通郵便でも問題ありませんが、到着したか不安な場合は、配達状況が追跡できる特定記録郵便の利用が推奨されます。
提出期限を守るのはもちろんのこと、締め切り間際ではなく余裕をもって発送しましょう。
確定申告の書類を郵送する場合のポイント
確定申告の書類を税務署へ郵送する際は、いくつかのルールを守る必要があります。
まず、確定申告書は「信書」に該当するため、送付方法は郵便(第一種郵便物)または信書便に限られます。
宅配便やメール便では送れないので注意が必要です。
宛先は、自身の住所地を管轄する税務署となり、宛名は「〇〇税務署御中」と記載します。
提出の控えに税務署の収受印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒と、提出用の申告書のコピー(控え)を必ず同封します。
提出期限は原則として「通信日付印(消印)が提出期限内」であれば認められるため、郵便局の窓口から発送すると消印が確実に押されるので安心です。
契約書や請求書などの重要書類を送る場合
契約書や請求書、納品書といった企業間の取引に関する重要書類は、相手に確実に届けることが絶対条件です。
これらの書類はすべて「信書」に該当するため、郵送方法は郵便か信書便に限られます。
郵送トラブルによる紛失や遅延は、ビジネス上の大きな損害につながる可能性があるため、配達過程が記録される方法を選ぶのが賢明です。
具体的には、配達記録が残り、万が一の際の補償も付く「簡易書留」や、対面手渡しで受領印がもらえる「レターパックプラス」が適しています。
特に契約書のように、相手に署名・捺印を依頼して返送してもらう必要がある場合は、送付状でその旨を明確に伝え、切手を貼った返信用封筒を同封するのがビジネスマナーです。
書類を郵送するときに押さえておきたい注意点
書類の郵送準備が完了しても、発送する前にもう一度確認しておきたい注意点があります。
どんなに丁寧に書類を作成し、マナーに沿って封入しても、発送段階での小さなミスがトラブルにつながる可能性があります。
提出期限に間に合わせるためのスケジュール管理、料金不足といった単純ながらも致命的なミスを防ぐ方法、そして改めて確認すべき「信書」のルールなど、確実な郵送を実現するための最終チェックポイントを解説します。
提出期限から逆算して余裕をもって発送する
書類の提出期限には、「当日消印有効」と「必着」の二種類があり、その意味を正しく理解しておく必要があります。
「消印有効」は、郵便局で押される消印の日付が期限内であれば受け付けられるというもの。
一方、「必着」は、期限日までに相手方に書類が到着していなければなりません。
特に必着の場合は、郵便物が届くまでの日数を考慮する必要があります。
日本郵便のウェブサイトで配達日数の目安を調べられますが、天候や交通事情で遅れる可能性もゼロではありません。
いかなる場合でも期限に間に合うよう、締め切りの数日前には発送を済ませるなど、常に余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
料金不足や切手の貼り忘れを防ぐなら郵便局の窓口へ
郵便料金が不足したまま投函してしまうと、差出人に返送されるか、受取人が不足分を支払うことになります。
返送されれば提出期限に間に合わなくなる恐れがあり、受取人払いの場合は相手に金銭的負担と手間をかけさせる大変失礼な行為となります。
特に定形外郵便物は、書類にクリアファイルや送付状を加えることで、想定より重くなりがちです。
こうした料金不足のリスクを確実に避けるためには、ポストに投函するのではなく、郵便局の窓口に直接持ち込むのが最も安全です。
窓口であれば、その場で正確な重さとサイズを計測し、正しい料金を案内してもらえます。
その場で切手を購入して貼付すれば、料金を間違う心配は一切ありません。
「信書」はメール便で送れないことを覚えておく
ビジネスで扱う請求書、納品書、契約書、履歴書などは、法律上の「信書」に該当します。
信書を送ることができる配送サービスは、郵便法により日本郵便の「郵便サービス」と国が許可した「信書便事業者」に限定されています。
ヤマト運輸の「クロネコDM便」や佐川急便の「飛脚メール便」といった、一般的にメール便と呼ばれる安価なサービスでは、信書を送ることはできません。
もし誤って信書を送付してしまうと、差出人が法律違反で罰せられる可能性があります。
書類を送る際には、その書類が信書にあたるか、そして利用しようとしている配送サービスが信書の送付に対応しているかを、事前に必ず確認する習慣をつけましょう。
まとめ
書類の郵送は、単に物を送る作業ではなく、送り主のビジネスマナーや信頼性が問われるコミュニケーションの一環です。
適切な封筒を選び、正しい書き方で宛名を記し、受け取る相手を配慮した書類の入れ方を実践することで、丁寧で誠実な印象を与えられます。
また、送る書類の重要度や緊急性に応じて、普通郵便、特定記録、簡易書留、レターパックといった多様な郵送方法の中から最適なものを選択する判断力も求められます。
信書のルールや提出期限、料金不足といった基本的な注意点を押さえ、余裕を持った発送を心がけることが、円滑なビジネスコミュニケーションの基礎となります。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む