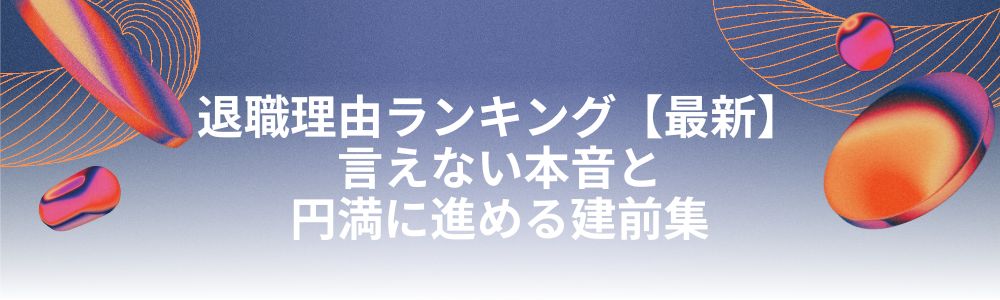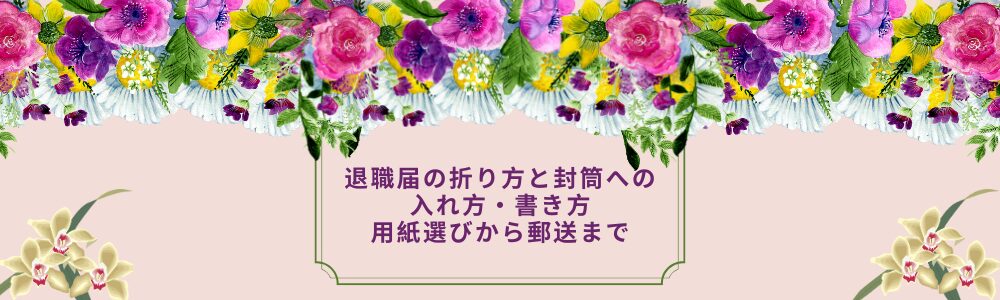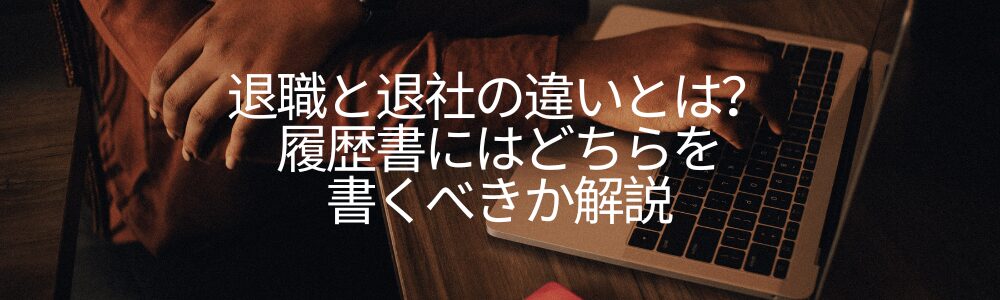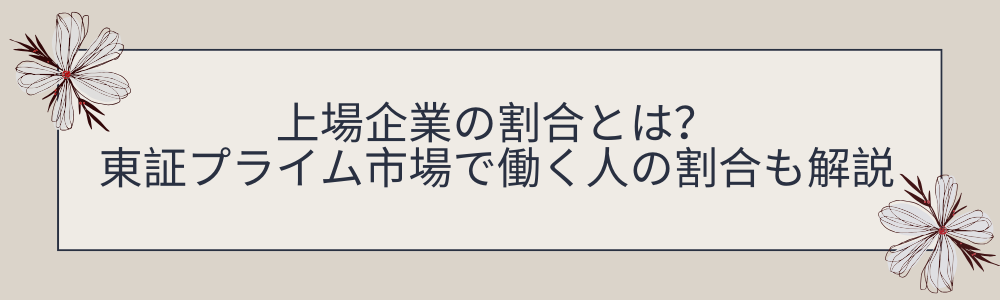

上場企業の割合とは?東証プライム市場で働く人の割合も解説
日本には非常に多くの会社が存在していますが、その中で上場している企業はごくわずかです。
実際、上場企業の割合は1%程度とされており、この割合の小ささに驚く人もいるかもしれません。
この記事では、上場企業の定義や具体的な割合、そして勤める人の割合について解説します。
また、上場企業で働くことのメリット・デメリットにも触れるため、就職や転職を考える際の参考にしてください。
まずは基本から!「上場企業」の定義をわかりやすく解説
上場企業とは、株式会社が発行する株式を証券取引所で誰でも自由に売買できるように公開している企業のことです。
株式を公開するためには、証券取引所が定める厳しい審査基準をクリアしなくてはなりません。
一方、株式を公開していない企業は非上場企業と呼ばれます。
日本に存在する株式会社のほとんどは非上場企業であり、上場はすべての株式会社にとって必須の手続きではありません。
【結論】日本における上場企業の割合はたったの0.1%
日本における上場企業の割合は、全企業数のうち約0.1%と非常に低い水準です。
国税庁のデータによると、日本の企業数は約400万社存在しますが、そのうち上場している企業の数は4,000社に満たないのが現状です。
この数字からも、上場企業がいかに少数であるかがわかります。
日本の企業の大半は非上場の中小企業であり、厳しい審査を通過して上場を維持している企業は、ごく限られた存在です。
東証プライム・スタンダード・グロース市場別の企業数
東京証券取引所は、2022年4月に市場区分を再編し、現在は「プライム」「スタンダード」「グロース」の3つの市場で構成されています。
かつての東証一部に代わるプライム市場は、主に国際的な大企業が対象で、最も厳しい上場基準が設けられています。
スタンダード市場は、中堅企業向けの市場です。
グロース市場は、高い成長可能性を持つ新興企業を対象としています。
2024年時点での企業数を見ると、プライム市場に約1,600社、スタンダード市場に約1,600社、グロース市場に約600社が上場しており、日本経済全体を牽引する役割を担っています。
上場企業で働いている人はどのくらい?就業者の割合を解説
上場企業で働いている人の割合は、日本の全就業者数から見ると決して多くありません。
日本の就業者総数が約6,700万人であるのに対し、上場企業で勤務している社員や役員の人数は約600万人と推定されています。
この数字を基に計算すると、上場企業に勤めている人の割合は全就業者の約9%です。
企業数に占める割合が0.1%であることと比較すると、一社あたりの社員数が多いため割合は高くなりますが、それでも上場企業での勤めは少数派であることがわかります。
上場企業と非上場企業は何が違う?3つの視点で比較
上場企業と非上場企業の最も大きな違いは、株式を証券取引所で公開しているか否かという点です。
この違いは、企業の経営スタイルや組織運営に大きな影響を与えます。
具体的には、資金調達の方法、社会的な信用度、経営の自由度という3つの視点から、両者の差異を比較することで、それぞれの特徴がより明確になります。
非上場企業が大多数を占める中で、上場企業が持つ特性を理解することは重要です。
資金調達の方法と規模
上場企業は株式市場を通じて不特定多数の投資家から直接資金を調達できるため大規模な資金集めが可能です。
新株発行による資金調達は返済義務がなく企業の成長投資や研究開発に活用しやすいという利点があります。
一方非上場企業は主に金融機関からの借入や経営者自身または縁故者からの出資によって資金を調達します。
そのため調達できる金額や手段が限定される傾向にあります。
上場企業は多様な株主から資金を得る代わりに業績や経営状況を情報開示する責任を負います。
社会的な信用度と知名度
上場企業は、証券取引所の厳しい審査基準をクリアしているため、経営の透明性や安定性が高く評価され、社会的な信用度が高いです。
この信用力は、金融機関からの融資や大手企業との取引において有利に働きます。
また、メディアで報道される機会も多く、企業の知名度が向上しやすい点も特徴です。
これにより、優秀な人材の確保にもつながります。
非上場企業の中にも大企業は存在しますが、一般的に倒産リスクが低いというイメージから、上場企業の方が高い信用を得やすい傾向にあります。
経営の自由度と意思決定プロセス
経営の自由度においては、非上場企業の方が高い傾向にあります。
非上場企業は、株主が経営者やその親族などに限定されていることが多く、外部からの干渉を受けずに迅速な意思決定が可能です。
一方、上場企業は多くの株主の意向を経営に反映させる必要があり、経営判断が株価に与える影響も考慮しなくてはなりません。
重要な意思決定には株主総会の承認が必要となるため、プロセスが複雑化し、時間がかかることがあります。
そのため、経営の自由度は非上場企業に比べて制約される側面があります。
上場企業で働くことによって得られるメリット
上場企業に就職することには、多くのメリットが存在します。
企業の安定性や福利厚生の充実は、働く上での安心感につながり、多くの人が上場企業への入社を目指す理由の一つです。
また、社会的な信用の高さは、個人のライフプランにも好影響を与える可能性があります。
キャリア形成の観点からも、上場企業での経験は貴重な財産となり得ます。
ここでは、上場企業に就職できることで得られる具体的なメリットを解説します。
安定した経営基盤と充実した福利厚生
上場企業は厳しい審査基準を通過しているため、一般的に経営基盤が安定しており、倒産のリスクが低いとされています。
この安定性は、従業員にとって継続的な雇用の確保や安定した収入につながります。
また、上場企業は優秀な人材を確保・維持するために、福利厚生制度を充実させている場合が多いです。
例えば、住宅手当や家族手当、退職金制度、育児・介護休業制度などが整備されており、従業員が長期的に安心して働ける環境が整っています。
これは、ワークライフバランスを重視する人にとって大きな魅力となります。
社会的信用が高くローンなどの審査で有利になる
上場企業に勤務しているという事実は、個人の社会的信用を高める一因となります。
企業の経営が安定していると見なされるため、従業員の収入も安定していると判断されやすいからです。
その結果、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードといった金融機関の審査において、有利に働くケースが多く見られます。
将来的なライフイベントを見据えた際、ローンの審査が通りやすいことは大きなメリットです。
企業の信用力が個人の信用力を補完する形となり、生活設計を立てやすくなります。
知名度や実績が転職活動でプラスに働く可能性がある
上場企業での勤務経験は、転職市場において有利に働く可能性があります。
企業の知名度が高いため、採用担当者は企業名を検索するだけで事業内容や規模を把握でき、そこで培われたスキルや経験に対する信頼度が高まります。
特に、大規模なプロジェクトに関わった経験や、体系化された業務プロセスを学んだ実績は、次のキャリアでも高く評価される傾向にあります。
非上場企業への転職はもちろん、他の上場企業へ移る際にも、前職での経験が強みとなり、キャリアアップにつながることも少なくありません。
優秀な人材が集まりやすく大規模な仕事に携われる
上場企業は、その安定性やブランド力、待遇の良さから、多様な分野の優秀な人材が集まりやすい環境です。
優れた同僚や上司と働くことは、自身のスキルアップや知見の拡大につながり、大きな刺激となります。
また、豊富な資金力と組織力を背景に、社会的に影響力の大きい大規模なプロジェクトに携わる機会も多いです。
例えば、革新的な製品の製造や、社会インフラに関わる事業など、個人や中小企業では経験できないスケールの大きな仕事に挑戦できる点は、上場企業で働く大きな魅力の一つです。
上場企業で働く際に知っておきたいデメリット
上場企業で働くことには多くの魅力がある一方で、デメリットも存在します。
特に、企業の規模が大きいことや、株主をはじめとする多くのステークホルダーが存在することに起因する課題が挙げられます。
これらのデメリットを理解しておくことは、入社後のミスマッチを防ぎ、自分に合った働き方を見つける上で非常に重要です。
ここでは、上場企業で働く際に考慮すべき点を解説します。
縦割り組織で意思決定に時間がかかることがある
上場企業の多くは、機能や事業部ごとに組織が細分化された「縦割り組織」の構造をとっています。
このため、一つの企画を通すにも、直属の上司から始まり、部長、役員といった複数の階層の承認を得る必要があり、意思決定に時間がかかる傾向があります。
特に複数の部署が関わる案件では、各部署との調整に多くの手間と時間を要することも少なくありません。
市場の変化に迅速に対応する必要がある業務や、スピード感を重視する働き方を求める人にとっては、このプロセスがもどかしく感じられる場合があります。
個人の裁量が小さく業務の自由度が低い場合がある
大企業である上場企業では、業務が標準化・細分化されていることが一般的です。
そのため、従業員一人ひとりが担当する業務範囲は限定的になりがちで、個人の裁量で仕事を進められる領域が狭くなる傾向にあります。
業務の進め方や手順がマニュアルで厳密に定められていることも多く、自分の判断で柔軟に対応することが難しい場面も出てきます。
決められた枠組みの中で効率的に業務をこなすことが求められるため、自らのアイデアを活かして自由に仕事を進めたい人にとっては、窮屈さを感じる可能性があります。
厳格な社内ルールで働き方を制限されることも
上場企業は、法令遵守(コンプライアンス)や情報管理に対する社会的な要請が厳しいため、社内ルールも厳格に定められていることがほとんどです。
例えば、情報セキュリティの観点からPCの利用方法に制限があったり、企業の信用を損なわないために副業が禁止されていたりするケースがあります。
また、服装規定や勤務時間に関するルールが細かく決められていることも少なくありません。
これらの規則は、組織全体の秩序を保ち、リスクを管理するために必要ですが、個人の自由な働き方を制約する要因ともなり得ます。
まとめ
日本に存在する企業のうち、上場企業の割合は約0.1%と極めて少数です。
上場企業は厳しい審査を通過しており、安定した経営基盤や社会的な信用の高さが特徴です。
そこで働くことは、充実した福利厚生やキャリア形成における有利な点など、多くのメリットをもたらします。
その一方で、組織の規模が大きいがゆえの意思決定の遅さや、個人の裁量の小ささといったデメリットも存在します。
上場企業への就職や転職を検討する際は、これらのメリットとデメリットの両方を深く理解し、自身の価値観やキャリアプランと合致するかを見極めることが求められます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む