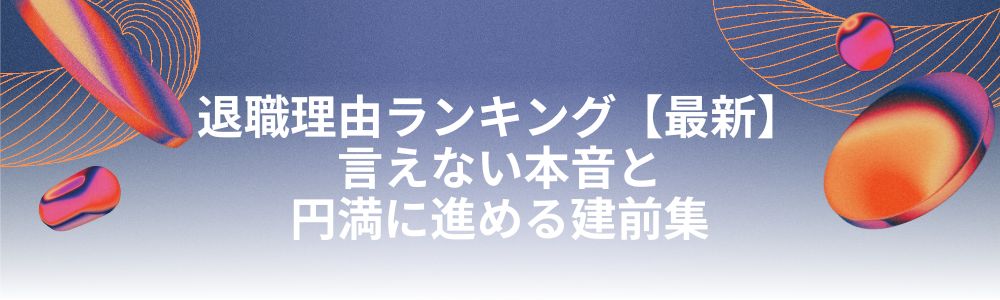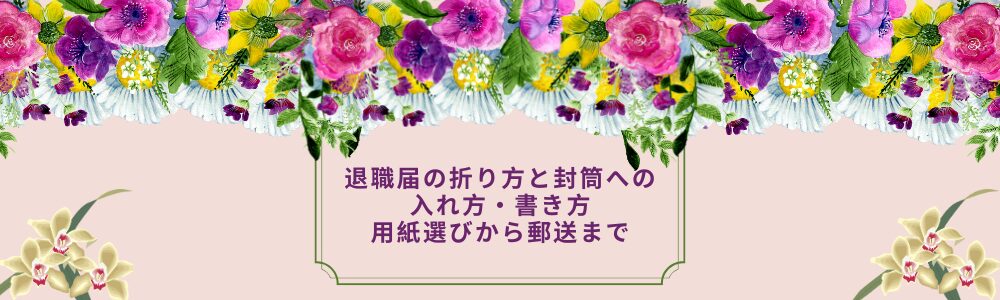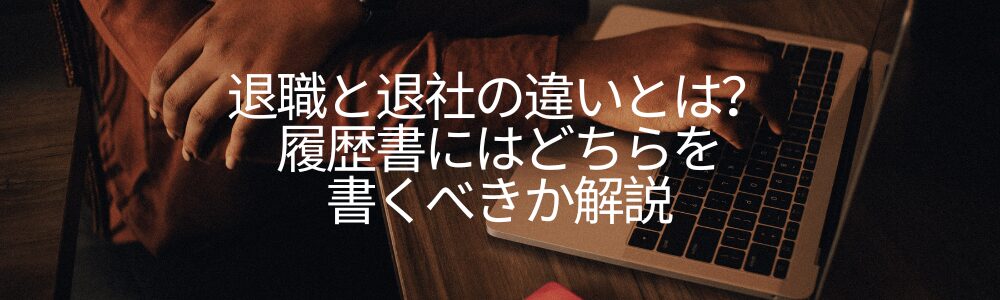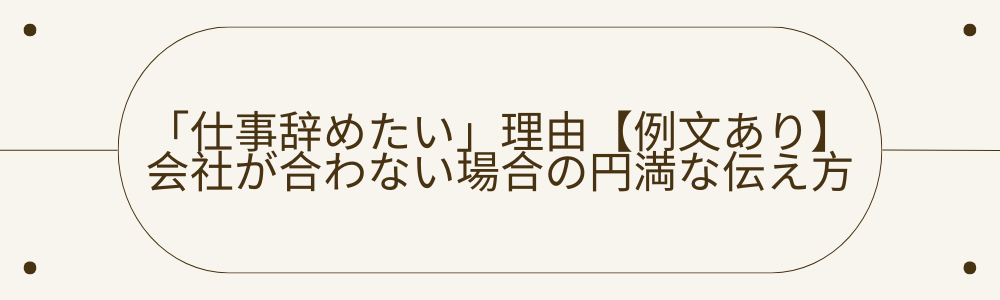

「仕事辞めたい」理由【例文あり】会社が合わない場合の円満な伝え方
今の仕事を辞めたいと感じるタイミングは人それぞれですが、「会社が合わない」「やりがいを感じない」など、辞めたい理由には共通点も多く見られます。
ただし、仕事を辞めたいと思っても、感情のままに動くと後悔につながることも。
特に、退職理由の伝え方や準備が不十分なまま進めるのは避けたいところです。
この記事では、仕事を辞めたいと感じる代表的な理由を整理し、後悔しない判断基準や伝え方のコツを具体例とともに紹介。
さらに、仕事を辞めると決めてから実際に退職するまでの流れや必要な手続きについても、わかりやすく解説します。
【7つの本音】多くの人が口にする仕事を辞めたい理由
仕事を辞めたい理由には、人間関係や給与、仕事内容など様々なものがあります。
各種調査の退職理由ランキングでも、常に上位には共通の項目が挙げられており、多くの人が同様の悩みを抱えていることがうかがえます。
自分だけが特別ではないと知ることで、現状を客観的に見つめ直すきっかけにもなるでしょう。
ここでは、多くの人が退職理由として挙げる代表的な7つの本音を掘り下げていきます。
給料が仕事量や成果に見合わず辞めたい
自身の業務量や上げた成果に対して、給与が見合っていないという不満は、仕事を辞める大きな動機の一つです。
特に、同業他社や同年代の平均年収と比較して著しく低い場合や、残業が多く拘束時間が長いにもかかわらず収入が増えない状況では、仕事へのモチベーションを維持することが困難になります。
自身の貢献が昇給や賞与といった形で正当に評価されていないと感じると、働く意欲は削がれてしまいます。
自分の能力や経験を適正に評価してくれる環境を求めて、より良い待遇の企業へ転職を考えるのは自然な流れと言えます。
職場の人間関係が悪くて仕事を辞めたい
職場の人間関係は、日々の業務効率や精神的な健康状態に直接的な影響を及ぼします。
特定の上司との相性が悪い、同僚間で円滑なコミュニケーションが取れない、あるいは無視や嫌がらせといった問題が存在する場合、職場そのものが大きなストレス源となり得ます。
個人的な関係だけでなく、チーム全体の雰囲気が悪く、常に緊張感が漂っているような環境では、孤立感や劣等感を抱きやすくなります。
人間関係の問題は個人の努力だけでは解決が難しいことも多く、心身の健康を損なう前に環境を変えるという選択も必要になります。
やりがいを感じられず仕事内容が合わないために辞めたい理由
日々の業務にやりがいを見出せない、あるいは自身の適性や興味と仕事内容が合わないと感じることも、退職を考えるきっかけとなります。
例えば、子どもが好きで保育士になったものの、実際には書類作成などの事務作業が多く理想とのギャップを感じるケースや、憧れの業界に入社したものの、配属された労務部門の仕事が単調に感じてしまうことなどがあります。
自分のスキルや能力を活かせている実感がなく、成長している感覚が得られない状況が続くと、仕事への情熱は次第に薄れていきます。
自身のキャリアプランを見つめ直し、より充実感を得られる仕事を求めるようになります。
長時間労働や休日出勤が続く仕事を辞めたい
恒常的な長時間労働や休日出勤によってプライベートの時間が確保できない状況は、心身の深刻な疲弊を招きます。
仕事が常に忙しい状態が続くと、家族や友人と過ごす時間、趣味や自己啓発に費やす時間がなくなり、ワークライフバランスが著しく崩れてしまいます。
休息が不十分なまま働き続けることは、健康を害するリスクを高めることにもつながります。
その一方で、仕事が暇すぎて時間を持て余し、自身の成長を感じられないという状況も、仕事への意欲を失う一因となり得ます。
どちらのケースも、個人の生活を犠牲にするような働き方は、長期的に継続することが困難です。
会社の将来性や経営方針に不安を感じ辞めたい
所属している会社の将来性や経営方針に対して不安を抱くことも、退職を検討する重要な要因です。
業界全体が縮小傾向にある、会社の業績が長期的に悪化している、といった状況では、自身の雇用やキャリアの安定性に懸念が生じます。
また、経営陣が打ち出す方針に共感できない場合や、頻繁な方針転換によって現場が混乱しているような状況では、会社への信頼が揺らぎ、組織に貢献しようという意欲も低下してしまいます。
自身のキャリアを長期的な視点で考えたとき、この会社で働き続けることにリスクを感じると、より安定性や成長性が見込める企業への転職を視野に入れるようになります。
努力が報われず仕事を辞めたい
成果を出しても評価されない、あるいは評価基準が曖昧で不透明な職場環境は、従業員のモチベーションを著しく低下させます。
自身の努力が昇進や昇給に結びつかないと感じると、仕事への意欲を維持することは難しくなります。
大きな貢献をしたにもかかわらず見過ごされたり、逆に些細なミスを過度に追及されたりすると、自分は無能なのではないかと自己肯定感が下がってしまうこともあります。
公平な評価制度が機能していない職場では、貢献意欲が削がれ、自身の働きを正当に評価してくれる環境を求めて転職を考えるのは当然のことです。
会社の文化や価値観に合わず辞めたい
会社の文化や価値観、いわゆる社風が自分に合わないというのも、見過ごせない退職理由の一つです。
例えば、体育会系の厳しい上下関係が根付いている、業務時間外の付き合いや飲み会への参加が半ば強制されている、あるいは個人の意見が尊重されずトップダウンで全ての物事が決まる、といった風土があります。
こうした環境で働き続けることは、大きな精神的苦痛を伴います。
仕事内容や待遇に直接的な不満がなくても、企業文化が合わないと日々の業務にストレスを感じ、組織の一員としてのエンゲージメントを保つことが難しくなります。
仕事を辞めたいと感じる前に確認すべき判断の理由
「辞めたいけど、本当に今がそのタイミングなのか」と迷うことは少なくありません。
一時的な感情の勢いだけで退職を決めると、後で後悔する可能性があります。
辞められない事情もあるかもしれません。
ここでは、退職という大きな決断を下す前に、一度立ち止まって考えるべき判断基準を解説します。
自身の状況が退職すべきサインに当てはまるのか、それともまだ改善の余地があるのかを見極めるきっかけとしてください。
心身の不調が仕事を辞めたい理由なら迷わず検討を
仕事が原因で心身に不調が現れている場合、それは退職を真剣に検討すべき明確なサインです。
朝起き上がれない、食欲がない、夜眠れないといった身体的な症状や、常に気分が落ち込んでいる、何事にも興味が持てないといった精神的な症状は、うつ病などの兆候かもしれません。
「仕事に行くのが苦しい」「もう無理だ」と感じている状態を我慢し続けると、回復までに長い時間が必要になることもあります。
自身の健康は何よりも優先されるべきであり、休職制度を利用するか、それが難しい場合は退職して療養に専念できる環境を整えることが必要です。
会社の業績悪化が仕事を辞めたい理由になる場合
会社の将来性や業績に客観的かつ深刻な問題が見られる場合も、退職を判断する重要な基準となります。
例えば、主力事業が市場の変化に対応できずに赤字が続いている、希望退職者の募集が繰り返し行われている、あるいは給与の支払いに遅れが生じているといった状況は、企業の経営状態が極めて不安定であることを示しています。
こうした経営上の問題は、一個人の努力では到底解決できるものではなく、自身のキャリアや生活に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
安定した環境で働き続けるためには、将来性のある企業へ移ることを検討すべきです。
ハラスメントが原因で仕事を辞めたい理由と対処法
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどが横行し、会社として適切な対策を講じていない職場は、即座に離れるべき環境です。
人事部やコンプライアンス窓口に相談しても状況が改善されない、あるいは相談したことでかえって不利益な扱いを受けるような場合は、その企業に自浄作用は期待できません。
ハラスメントは個人の尊厳を深く傷つけ、心身に深刻なダメージを与えます。
自身の安全と健康を守ることが最優先であり、我慢して働き続ける必要は一切ありません。
可能な範囲で証拠を確保しつつ、速やかに転職活動を進め、安全な環境に移ることが求められます。
異動や部署変更で仕事を辞めたい理由が解消する可能性
現在の退職理由が、特定の部署の業務内容や上司との人間関係に限定されている場合、異動によって問題が解決する可能性があります。
会社自体の方針や待遇に大きな不満がなく、他の部署であれば自分の能力を発揮できそうだと感じるのであれば、すぐに退職を決断するのではなく、まずは上司や人事部に異動の希望を相談してみるという選択肢があります。
異動が認められれば、転職という大きな環境変化を伴わずに問題を解決できるかもしれません。
ただし、希望が必ずしも通るとは限らないため、相談と並行して情報収集を進めるなど、次の選択肢も視野に入れておくことが賢明です。
辞めたい理由が一時的な感情かどうか見極める仕事の判断
仕事で大きなミスをした直後や、上司から理不尽な叱責を受けた後など、一時的な感情の高ぶりから「辞めたい」と考えていないか、冷静に自分自身を振り返ることが重要です。
明確な理由がわからないまま、「もう何もかもめんどくさい」と感じて勢いで辞意を固めるのは避けるべきです。
なぜ辞めたいのか、その根本的な原因が何なのかを突き詰めずに退職すると、次の職場でも同じような不満を抱えてしまう可能性があります。
一度冷静になり、自分の感情と向き合い、退職したい理由が一時的なものなのか、それとも構造的・長期的な問題に起因するものなのかを見極めることが求められます。
【理由別】円満退職につながる上手な伝え方と例文
退職の意思を伝える際、理由は非常に重要です。
たとえ本音が会社への不満であっても、それをストレートに伝えると角が立ち、円満な退職が難しくなることがあります。
だからといって、完全に嘘の理由を伝えるのも避けるべきです。
ここでは、会社の納得を得やすく、かつ良好な関係を保ったまま退職するための上手な伝え方と、理由別の具体的な例文を紹介します。
ネガティブな本音をポジティブな表現に変換するコツを掴むことが重要です。
退職理由を伝える際に押さえるべき3つの基本
退職理由を伝える際には、三つの基本を押さえることが重要です。
第一に、会社の不満や批判を直接的な理由にしないこと。
待遇や人間関係への不満を述べても、「改善するから」と引き止められるだけで、話がこじれる可能性があります。
第二に、退職理由はあくまで個人的な都合とし、会社のせいではないというスタンスを貫くことが大切です。
「一身上の都合」を基本としつつ、質問された際に備えて前向きな理由を用意しておきます。
第三に、退職の意思は相談ではなく報告の形をとり、決意が固いことを明確に伝えること。
「退職させていただきたく、ご報告に参りました」というように、毅然とした態度で臨みます。
【例文】キャリアアップを理由に前向きな姿勢を伝える
この度、一身上の都合により退職させていただきたく、ご報告に参りました。
現職で培った〇〇のスキルを、より専門的に活かせる環境で挑戦したいという気持ちが強くなりました。
具体的には、〇〇分野の専門性を高め、将来的には〇〇のようなキャリアを築きたいと考えております。
現在の会社では得難い経験を積める機会があり、大変恐縮ではございますが、退職を決意いたしました。
このように、現職での経験への感謝を示しつつ、将来の目標達成のために転職が必要であるという、前向きな姿勢を伝えることがポイントです。
会社側も、個人の成長を応援するという観点から引き止めにくく、納得を得やすい理由となります。
【例文】家庭の事情を理由に納得してもらう伝え方
この度、一身上の都合により退職させていただきたく、ご報告に参りました。
実は、家族の介護が必要な状況となり、現在の勤務形態を続けることが困難になりました。
家族と話し合った結果、一度仕事から離れて介護に専念するという結論に至りました。
会社には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、退職させていただきたく存じます。
家庭の事情は、プライベートな領域であり、会社側が深く介入しにくい理由であるため、強い引き止めにあいにくい傾向があります。
介護や結婚、配偶者の転勤など、具体的かつ個人的な事情を理由にすることで、会社側も納得せざるを得ない状況を作りやすくなります。
ただし、詳細を話しすぎると矛盾が生じる可能性もあるため、簡潔に伝えることが重要です。
【例文】体調不良を理由にする場合の誠実な伝え方
この度、一身上の都合により退職させていただきたく、ご報告に参りました。
以前から体調が優れない日があり、医師からも一度治療に専念することを勧められております。
このままでは業務に支障をきたし、皆様にご迷惑をおかけしてしまうと考え、誠に勝手ながら退職を決意いたしました。
まずは療養に専念したいと考えております。
体調不良を理由にする場合、診断書の提出を求められる可能性も考慮しておく必要があります。
伝える際は、業務への影響を懸念しているという姿勢を示すことで、無責任な印象を与えず、誠実な気持ちが伝わります。
自身の健康を理由にされると、会社側も無理に引き止めることは難しくなります。
【例文】本音をポジティブに変換する伝え方(人間関係・給与など)
人間関係や給与への不満が本音であっても、それをポジティブな理由に変換して伝えることが円満退職の鍵となります。
例えば、「人間関係が悪く連携が取れない」という本音は、「チーム一丸となって協力し、より大きな目標を達成するスタイルの職場で自分の力を試したい」と言い換えることが可能です。
「給与が低い」という不満は、「成果がより正当に評価される環境で、これまで以上の責任を伴う仕事に挑戦し、自身の市場価値を高めたい」と変換できます。
このように、不満をそのまま伝えるのではなく、自身の成長意欲や責任感をアピールする形で表現することで、前向きな転職であるという印象を与え、会社側も納得しやすくなります。
後悔しないために!仕事を辞めると決めたらやるべき準備
仕事を辞めると固く決意したら、感情的に行動するのではなく、計画的に準備を進めることが後悔しないためのポイントです。
退職を切り出す前に、転職活動の準備や退職後の生活設計などを済ませておくことで、スムーズかつ安心して次のステップに進むことができます。
ここでは、実際に会社を辞める前に必ずやっておくべき準備について、具体的な項目を挙げて解説していきます。
自分の市場価値を把握するために転職サイトに登録する
退職を決意したら、まずは転職サイトに登録し、自身の市場価値を客観的に把握することが重要です。
自分のこれまでの経歴やスキルが、転職市場でどの程度評価されるのか、どのような求人が存在するのかを知ることで、現実的なキャリアプランを立てられます。
複数の転職サイトや転職エージェントに登録し、自分の経験に合致する求人を探したり、キャリアアドバイザーに相談したりすることで、自分の強みや弱みを客観的に分析できます。
この情報を基に、次の職場で求める条件を具体的に考えることが可能になります。
次の仕事に求める条件を明確にリストアップする
なぜ現在の仕事を辞めたいのか、その理由を裏返し、次の仕事に求める条件を具体的にリストアップすることが、後悔しない転職につながります。
給与、勤務地、労働時間、仕事内容、社風、福利厚生など、様々な観点から「譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確に順位付けしておきましょう。
例えば、「給与への不満」が退職理由なら「年収〇〇円以上」を必須条件にするなど、具体的な数値を設定すると良いです。
このリストが、転職活動における企業選びの明確な軸となり、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
退職後の生活費がどれくらい必要か計算しておく
退職してから次の仕事が決まるまでの期間、収入が途絶えることを想定し、生活費がどれくらい必要か事前に計算しておくことが不可欠です。
家賃、光熱費、食費といった毎月の固定費に加え、健康保険や年金の支払いも考慮に入れる必要があります。
在職中は会社が半額を負担していた社会保険料が、退職後は全額自己負担となるため、支出が増えることを念頭に置かなければなりません。
少なくとも3ヶ月から半年分の生活費を貯蓄として確保しておくと、焦らずに転職活動に集中でき、精神的な余裕を持つことができます。
業務の引き継ぎリストを少しずつ作成しておく
退職の意思を上司に伝える前から、自分が担当している業務の引き継ぎリストを少しずつ作成しておくと、退職手続きがスムーズに進みます。
担当業務の内容、作業手順、関係者の連絡先、関連資料の保管場所などを文書にまとめておきましょう。
これを準備しておくことで、退職が決まった際に慌てずに済み、後任者への引き継ぎを円滑に行うことが可能です。
丁寧な引き継ぎは、会社や同僚に対する社会人としての最後の責任であり、円満退職のためにも非常に重要です。
立つ鳥跡を濁さずの精神で、最後まで責任を持って業務を遂行する姿勢を示します。
有給休暇の残り日数を確認し消化計画を立てる
退職日までに有給休暇をすべて消化できるよう、残り日数を正確に確認し、計画を立てておくことが重要です。
有給休暇の取得は労働者に与えられた権利であり、会社側は原則としてその申し出を拒否できません。
退職の意思を伝える際に、最終出社日と正式な退職日を調整し、その間に有給休暇を消化するスケジュールを上司と相談するとスムーズに進みます。
引き継ぎに必要な期間を十分に考慮しつつ、いつから有給休暇に入るのかを明確に伝えます。
消化期間は、心身のリフレッシュや転職活動、次の生活への準備に充てることができます。
円満退職を実現するスムーズな退職手続きの進め方
退職を決意し準備が整ったら、次は会社での手続きを進める時です。
急に「明日やめる」と伝えるのは、社会人としてわからない人も多いかもしれませんが避けるべき行動です。
やめる時の疲れや不安を感じることもありますが、円満退職には適切なタイミングと手順がとても重要です。
「すぐにでも辞めたい」という気持ちが強くても、会社の規則や人間関係を考慮し、順序立てて進めることが求められます。
もしわからないことがあれば、信頼できる紹介先のエージェントに相談するのもおすすめです。
ここでは、退職の意思を伝えてから最終出社日までにやるべき具体的なステップをわかりやすく解説しますので、スムーズにやめる準備を進めましょう。
Step1. 直属の上司に退職の意思を口頭で伝える
退職の意思は、まず直属の上司に直接、口頭で伝えるのが社会人としてのマナーです。
法律上は2週間前の申し出で退職可能ですが、会社の就業規則では1〜3ヶ月前と定められていることが多いため、それに従うのが望ましいです。
例えば勤続1年や3年といった節目や、異動が多い4月を避けるなど、会社の繁忙期を考慮してタイミングを見計らいます。
事前にアポイントを取り、会議室など他の人に話を聞かれない場所で「個人的なご相談があります」と切り出し、退職の意思を明確に伝えます。
同僚や他部署の上司に先に話すのは、直属の上司の顔を潰すことになるため避けるべきです。
Step2. 上司と話し合い退職日を正式に決定する
退職の意思を伝えたら、次に上司と退職日について話し合い、正式に決定します。
自分の希望する退職日を伝えつつも、業務の引き継ぎや後任者の選定、人員補充にかかる期間を考慮し、会社側の都合にも配慮する姿勢を示すことが円満な話し合いのポイントです。
通常、退職交渉では引き止めにあうことも想定されますが、退職の意思が固いことを冷静に伝え、交渉に応じます。
最終出社日と、有給消化期間を含めた正式な退職日をこの場で明確に合意します。
この話し合いで決定した内容が、今後の手続きの基準となるため、双方の認識に齟齬がないよう確認することが求められます。
Step3. 会社の規定に従い退職届を提出する
上司との話し合いで退職日が正式に決定したら、会社の規定に従って退職届を提出します。
退職届のフォーマットや提出先については、就業規則を確認するか、人事部に直接問い合わせて確認しましょう。
一般的に、自己都合退職の場合は理由を「一身上の都合」とし、合意した退職日と氏名を記入、捺印して提出します。
一度提出すると原則として撤回は難しいため、内容に間違いがないか十分に確認してから提出します。
提出方法は、上司に手渡しするのが一般的ですが、会社のルールに従うことが基本です。
Step4. 後任者へ丁寧に業務の引き継ぎを行う
正式な退職日が決まってから最終出社日までの期間は、後任者への業務の引き継ぎを責任を持って行います。
事前に作成しておいた引き継ぎリストやマニュアルを活用し、口頭での説明と並行して、実際の業務を行いながら丁寧に伝えます。
後任者がまだ決まっていない場合は、誰が見ても業務内容が理解できるように、資料を整理し、詳細な手順書として残しておくことが重要です。
取引先への挨拶回りも、後任者と一緒に行うなど、スムーズな移行を心がけます。
引き継ぎが不十分だと、退職後に会社や後任者から問い合わせが来ることになり、迷惑をかけてしまいます。
Step5. お世話になった社内外の関係者へ挨拶回りをする
最終出社日が近づいてきたら、これまでお世話になった社内外の関係者へ挨拶回りを行います。
社内の人たちには、これまでの感謝の気持ちを直接伝えるのが望ましいです。
部署のメンバーには朝礼などの場で挨拶し、特にお世話になった先輩や上司には個別に声をかけます。
社外の関係者には、後任者を紹介するとともに、これまでの感謝と退職の挨拶をメールや電話、あるいは直接訪問して伝えます。
この際、退職理由を詳細に話す必要はなく、あくまで感謝の気持ちを伝えることに留めます。
良好な関係を保って退職することで、将来どこかで再び関わる可能性にもつながります。
Step6. 備品の返却と必要書類の受け取りを済ませる
最終出社日には、会社から貸与されていた備品をすべて返却します。
健康保険証、社員証、名刺、パソコン、制服、業務で作成したデータなどが対象となります。
デスク周りの私物も忘れずに持ち帰りましょう。
同時に、退職後に必要な書類を受け取るか、後日郵送されるスケジュールを確認します。
具体的には、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票などです。
これらの書類は、失業保険の受給手続きや転職先での年末調整に必要となります。
受け取り漏れがないか事前にリストアップして確認しておくことが、その後の手続きをスムーズに進めるために重要です。
まとめ:円満退職に向けた理由の伝え方
仕事を辞めたいと感じた時、まずはその理由を冷静に分析することが大切です。
一時的な疲れや感情に流されてやめる決断をしてしまうと、後で後悔することもあるため、慎重に見極めましょう。
退職の意思を会社に伝える際には、ネガティブな本音をそのまま話すのではなく、今後のキャリアプランなどポジティブな理由に変換して説明するのがおすすめです。
やめる時は、会社の繁忙期を避けて直属の上司に最初に報告し、円満退職を目指して計画的に準備を進めます。引き継ぎは責任を持って丁寧に行い、最終日には備品の返却や必要書類の受け取りも忘れずに済ませましょう。わからないことがあれば、信頼できるエージェントの紹介や相談を活用するのも良い方法です。
こうした手順をしっかり踏むことで、会社や人間関係に無用なトラブルを避けつつ、次のステップへスムーズに進めます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む