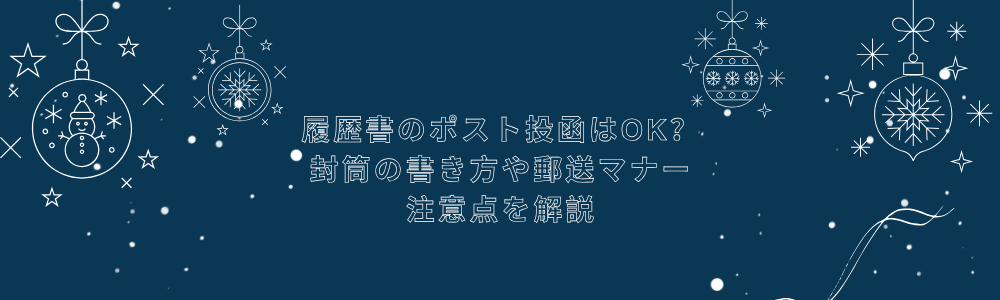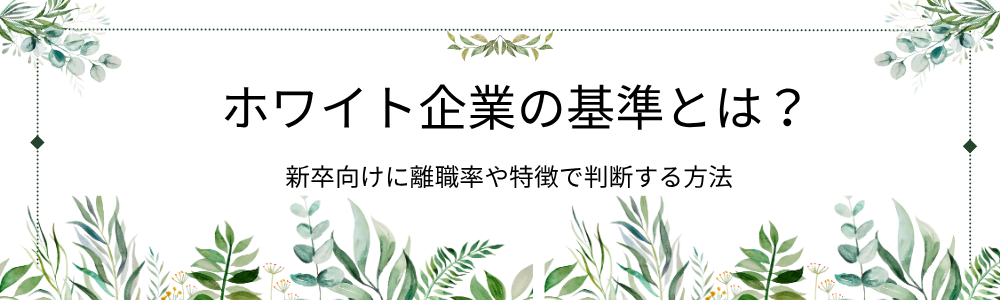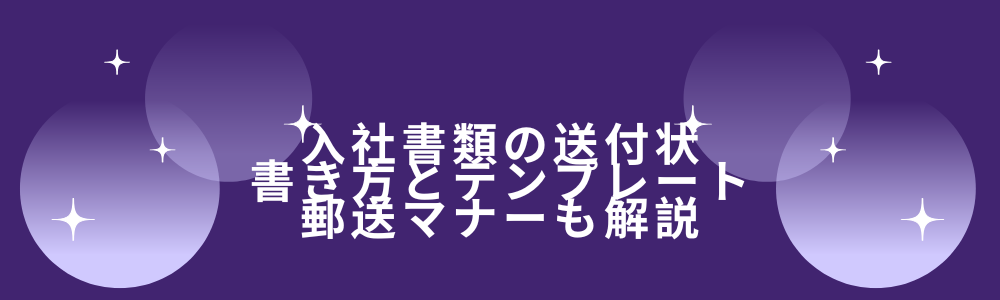

入社書類の送付状 書き方とテンプレート 郵送マナーも解説
入社を控えた新社会人や転職活動を終えた方にとって、入社書類の提出は最初の重要な手続きです。
この書類送付の際に、ビジネスマナーとして送付状を同封することが推奨されます。
本記事では、入社書類に添える送付状の正しい書き方やテンプレート、郵送時の封筒の選び方や注意点まで、具体的なマナーを網羅的に解説します。
そもそも入社書類に送付状は同封すべき?
企業から特に指示がない場合でも、入社時の書類を郵送する際には送付状を同封するのが一般的なビジネスマナーです。
送付状には、誰が、どのような書類を、何通送ったのかを明確に伝える役割があります。
これにより、受け取った採用担当者は内容物をスムーズに確認でき、書類の不足や入れ間違いといったトラブルを防げますます。
また、送付状を添えることで、丁寧な印象を与え、入社への意欲を示すことにもつながります。
必須ではないケースもありますが、社会人としての気配りとして、特別な理由がない限りは同封することをおすすめします。
今後、ビジネス文書を作成する機会は多いため、この機会に正しい書き方を覚えておくと良いでしょう。
【コピーして使える】入社書類に添える送付状のテンプレート
ここでは、入社書類を送付する際にすぐに使える送付状のテンプレートを紹介します。
以下の例文をコピーし、日付や宛名、自身の情報、同封書類リストなどを、ご自身の状況に合わせて書き換えて活用してください。
このテンプレートは基本的な構成要素を含んでいるため、他のビジネス文書を送付する際にも応用が可能です。
送付状の書き方を7つの項目別に解説
送付状は決まった型に沿って書くのが基本です。
いきなり作成するとなると難しく感じるかもしれませんが、構成要素を一つひとつ理解すれば、誰でもマナーに沿った文書を作成できます。
ここでは、送付状を構成する7つの項目について、それぞれの書き方と注意点を詳しく解説します。
これから説明する日付から「以上」までの流れに沿って作成すれば、正しい送付状が完成します。
1. 日付は投函日を右上に記載する
送付状に記載する日付は、書類を作成した日ではなく、郵便局の窓口に提出する日、またはポストに投函する日を記入します。
用紙の右上に記載するのが基本です。
年号は西暦(例:2025年4月1日)でも和暦(例:令和7年4月1日)でも構いませんが、履歴書など他の提出書類と表記を統一するようにしましょう。
ビジネス文書では算用数字を用いるのが一般的です。
郵送に数日かかることを想定し、実際に送付する直前に日付を記入すると間違いがありません。
もし提出日が前後する可能性がある場合は、空欄にしておき、投函する際に手書きで記入する方法もあります。
2. 宛名は会社名・部署名・担当者名を正確に書く
宛名は日付の下、用紙の左上に記載します。
会社名は「(株)」などと省略せず、「株式会社」のように正式名称で正確に書きましょう。
会社名、部署名、役職名、担当者氏名の順に記載します。
入社手続きの案内などで担当者名がわかっている場合は、その氏名をフルネームで記載し、敬称は「様」をつけます。
部署宛てに送る場合や担当者名が不明な場合は「人事部御中」や「採用ご担当者様」と記載してください。
会社や部署といった組織に宛てる場合は「御中」、個人に宛てる場合は「様」を使い分け、「御中」と「様」を併用しないように注意が必要です。
3. 差出人情報は右下に自分の氏名と連絡先を記載
差出人の情報は、宛名よりも下の右側に記載します。
誰からの書類であるかを明確にするため、郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレスを正確に記入しましょう。
住所は都道府県から書き始め、アパートやマンション名、部屋番号まで省略せずに記載します。
氏名はフルネームで書きます。
電話番号やメールアドレスは、日中に連絡がつきやすいものを記載してください。
企業側が書類の内容について問い合わせをしたい場合に、すぐに連絡先がわかるようにしておくことは、相手への配慮にもなります。
これらの情報は、封筒の裏面に記載する差出人情報と同じものを記入します。
4. 件名は「入社書類の送付について」が分かりやすい
件名は、差出人情報の下、中央に配置します。
受け取った担当者が一目で何の書類か理解できるよう、簡潔で分かりやすい内容にすることが重要です。
「入社書類の送付について」や「入社手続き書類のご送付」といった件名が一般的です。
件名を【】(隅付き括弧)で囲むと、本文と区別されてより見やすくなります。
企業には毎日多くの郵便物が届くため、担当者が内容をすぐに把握できる件名をつけることで、その後の処理がスムーズに進みます。
これも社会人としての配慮の一つと言えるでしょう。
5. 本文は「頭語・時候の挨拶・主文・結びの挨拶・結語」で構成する
本文はビジネス文書の基本構成に沿って作成します。
まず、書き出しの頭語として拝啓を置きます。
次に時候の挨拶ですが、季節を問わず使える時下、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。といった表現が便利です。
続く主文では、採用されたことへの感謝と今後の抱負を簡潔に述べた後、つきましては、ご指示いただきました下記の書類をお送りいたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。のように、書類を送付した旨を伝えます。
最後に末筆ながら、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。といった結びの挨拶で締め、右詰めで結語の敬具を記載します。
拝啓と敬具はセットで使うのがルールです。
6. 中央に「記」と書き、同封書類を箇条書きで列挙する
主文を結んだ後、1行空けて中央に「記」と記載します。
その下に、同封した書類の名称と部数を箇条書きで具体的にリストアップしてください。
例えば「雇用契約書1通」「身元保証書2部」のように、誰が見ても内容が正確にわかるように書きます。
このリストがあることで、送付側と受領側の双方で提出書類の確認が容易になり、書類の不足や入れ間違いといったミスを防ぐことができます。
書類を封筒に入れる際は、この箇条書きの順番通りに重ねてクリアファイルに収納すると、受け取った担当者が確認しやすくなり、より丁寧な印象を与えられます。
7. 最後に「以上」と右詰めで記載する
同封書類のリストを箇条書きで全て書き終えたら、その下の行に右詰めで「以上」と記載します。
これは、「記」から始まった箇条書きがここで終わりであることを明確に示すための締めくくりの言葉です。
ビジネス文書において、「記」と「以上」は必ずセットで用いるのがルールです。
この「以上」を書き忘れてしまうと、まだ書類リストに続きがあるかのような印象を与えかねないため、忘れずに記入するようにしましょう。
これにより、送付状全体の構成が整い、正式なビジネス文書として完成します。
【ケース別】書類提出が遅れた場合の送付状の書き方と例文
やむを得ない事情で書類の提出が期日に間に合わない場合は、まず担当者に電話などで直接連絡し、遅れる理由と具体的な提出予定日を伝えるのが最優先です。
その上で、書類を郵送する際の送付状にも、お詫びの言葉と提出が遅れた理由を簡潔に添えましょう。
ここでは、提出が遅れた場合に使える送付状の書き方と例文を紹介します。
主文に「この度は、〇〇(理由)により、書類の提出が遅れましたことを、心よりお詫び申し上げます。」といった一文を加えることで、誠意が伝わります。
入社書類を郵送する際の基本マナー
送付状を正しく作成できても、郵送時のマナーが守られていなければ、相手にマイナスの印象を与えかねません。
入社書類は会社に提出する最初の公式な書類であり、社会人としての第一印象を左右する可能性があります。
ここでは、書類の入れ方から封筒の選び方、宛名の書き方、おすすめの郵送方法まで、押さえておくべき郵送の基本マナーを解説します。
細かな点にも配慮することで、丁寧で信頼できる人物であるという評価につながります。
書類はクリアファイルに入れて折らずに郵送する
入社書類には個人情報が含まれる重要なものが多いため、丁寧に扱う必要があります。
郵送中に雨で濡れたり、折れ曲がったりするのを防ぐため、すべての書類をまとめてクリアファイルに入れるのがマナーです。
書類は三つ折りなどにせず、きれいな状態で提出するのが基本です。
複数の書類がある場合は、送付状を一番上にし、会社から指定された順番、もしくは送付状の箇条書きに記載した順に重ねてからファイルに収めましょう。
このひと手間で、書類が保護されるだけでなく、受け取った担当者が確認しやすくなり、配慮の気持ちが伝わります。
封筒はA4サイズが入る「角形A4号」か「角2号」を選ぶ
入社書類は折り曲げずに郵送するため、A4サイズのクリアファイルがそのまま入る大きさの封筒を選びます。
具体的には、「角形A4号(角A4)」または「角2号」というサイズの封筒が適しています。
「角形A4号」はA4サイズがぴったり収まるサイズで、「角2号」はA4サイズより一回り大きく、書類の枚数が多い場合でも余裕を持って入れることができます。
封筒の色については、事務的な用途で使われる茶封筒よりも、白の封筒を選ぶ方がフォーマルで丁寧な印象を与えます。
重要な書類を送付する際は、中身が透けにくい厚手の白い封筒を使用することをおすすめします。
封筒の表面・裏面の正しい書き方
封筒の表面には、宛先の郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名を正確に記載します。
住所は都道府県から書き、ビル名や階数なども省略しません。
敬称は送付状と同様に、組織宛なら「御中」、個人宛なら「様」を使い分けます。
また、表面の左下に赤色のペンで「入社書類在中」と書き、定規を使って四角く囲んでおきましょう。
これにより、他の郵便物と区別され、担当者の手元へスムーズに届きやすくなります。
裏面には、左下に自分の郵便番号、住所、氏名を記載します。
最後に、封をしたら中央に「〆」や「封」といった封字を書くのが丁寧なマナーです。
追跡可能な「簡易書留」や「レターパック」で送ると安心
入社書類には個人情報が記載された重要書類や再発行が難しい書類が含まれるため普通郵便で送るのは避けるべきです。
万が一の郵便事故に備え配達状況を追跡できるサービスを利用しましょう。
代表的な方法として「簡易書留」や「レターパック」があります。
「簡易書留」は郵便局の窓口での手続きが必要ですが引受と配達が記録され5万円までの損害賠償制度も付いています。
「レターパック」は専用の封筒を購入すればポストからも投函でき追跡サービスが付いています。
対面での手渡しを希望する場合は受領印が必要な「レターパックプラス」を選ぶとより確実です。
これらの方法で送付すれば書類が企業に届いたことを自身で確認できるため安心です。
入社手続きで郵送できる書類と控えるべき書類
入社にあたり提出を求められる書類は多岐にわたりますが、すべての書類を無条件に郵送してよいわけではありません。
特に、機微な個人情報を含む書類については、その取り扱いに細心の注意が必要です。
ここでは、一般的に郵送で提出しても問題ない書類と、情報漏洩のリスクを考慮して郵送を避けるべき、もしくは特別な配慮が必要な書類の例を解説します。
提出方法に迷った際は、自己判断せず担当者に確認することが最も確実です。
郵送で提出しても問題ない書類の例
一般的に郵送での提出が可能な入社書類としては、雇用契約書や入社承諾書(誓約書)、身元保証書などが挙げられます。
これらは入社の意思確認や契約内容の同意を示すもので、署名・捺印後に返送を求められることが多いです。
また、年金手帳(基礎年金番号通知書のコピー)、雇用保険被保険者証、給与振込先の届書、健康保険被扶養者(異動)届、扶養控除等(異動)申告書といった社会保険や税金関係の書類も郵送で提出するケースが一般的です。
ただし、これらも重要な個人情報であることに変わりはないため、会社の指示に従い、追跡可能な方法で送付することが望ましいです。
個人情報保護の観点から郵送を避けるべき書類
特に慎重な取り扱いが求められるのは、マイナンバーカードのコピーや通知カードのコピー、マイナンバーが記載された住民票の写しなどです。
マイナンバーは非常に機微な個人情報であり、その収集・管理方法は法律で厳しく定められています。
そのため、企業によっては情報漏洩リスクを避ける目的で、郵送ではなく入社初日に原本を持参し、その場で担当者が確認・複写する形式をとることが多いです。
もし郵送を指示された場合は、必ず簡易書留やレターパックプラスといった、対面手渡しで配達記録が残る方法を選択してください。
提出方法に不安がある場合は、事前に人事担当者に確認するのが最も安全です。
まとめ
入社書類に添える送付状は、単に書類を送るためだけの紙ではなく、社会人としてのマナーや入社への誠意を示すための重要なツールです。
本記事で解説した送付状の書き方の基本構成やテンプレート、郵送時の封筒の選び方や宛名の書き方、書類の入れ方といった一連のポイントを実践することで、採用担当者に良い第一印象を与えることができます。
特に、提出期限の遵守や、遅れる場合の事前連絡は信頼関係を築く上で不可欠です。
書類の提出方法など不明な点があれば、自己判断せずに担当部署に確認しましょう。
丁寧な手続きを心がけることが、スムーズな社会人生活のスタートにつながります。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書のポスト投函はOK?封筒の書き方や郵送マナー、注意点を解説
就職活動では、企業から履歴書の郵送を求められることが少なくありません。 その際、「履歴書をポストに投函しても大丈夫なのか?」「手渡しや窓口での提出が望ま… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書 学歴の書き方を記載例で解説|入学・卒業年の西暦和暦早見表
履歴書の学歴欄の書き方について、記入例を交えながら詳しく解説します。 履歴書の学歴の記入は、いつからどこまで書くのか、中退や留学などの特殊なケースはどう… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部上場・非上場企業の見分け方とは?簡単な調べ方と株式の違いを解説
就職活動や転職活動では、企業の規模や安定性を判断する指標の一つとして「上場企業」か「非上場企業」かという点が注目されます。 しかし、両者の具体的な違いや… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ホワイト企業の基準とは?新卒向けに離職率や特徴で判断する方法
就職活動を進める多くの新卒学生にとって、働きやすい環境である「ホワイト企業」への入社は大きな目標の一つです。 しかし、ホワイト企業の明確な定義や基準はな… 続きを読む