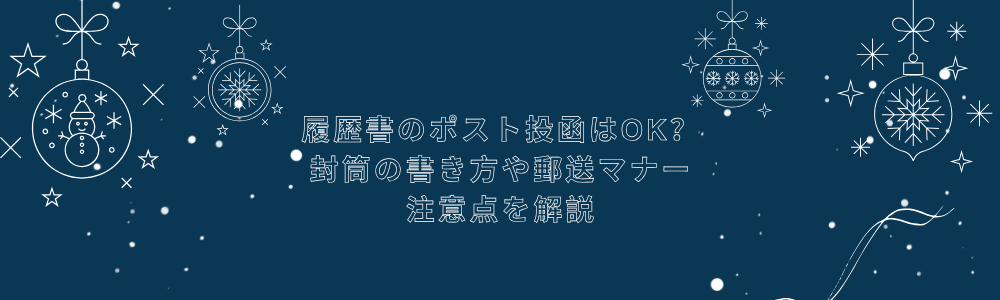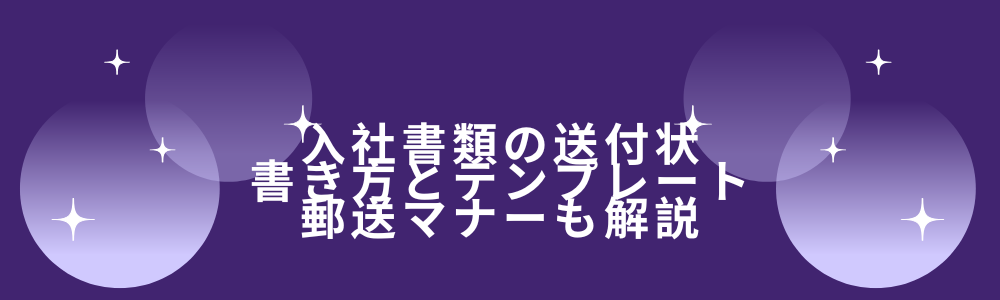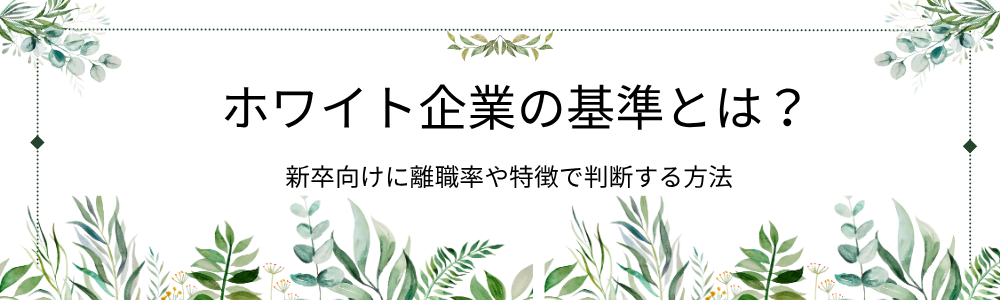履歴書 学歴の書き方を記載例で解説|入学・卒業年の西暦和暦早見表
履歴書の学歴欄の書き方について、記入例を交えながら詳しく解説します。
履歴書の学歴の記入は、いつからどこまで書くのか、中退や留学などの特殊なケースはどうすれば良いのか、迷う点が多くあります。
この記事では、履歴書の書き方の基本的なルールから状況別の書き方まで網羅的に説明し、学歴計算が不要になる入学・卒業年の西暦・和暦の早見表も用意しました。
正しい暦の例を参考に、採用担当者に分かりやすく伝わる履歴書を作成しましょう。
まずは見本で確認!履歴書の学歴欄の正しい書き方
履歴書の作成において、学歴の記入は基本的な項目の一つです。
まずは見本を参考に、正しいフォーマットを確認しましょう。
学歴欄は、年月を記載する欄と学歴職歴を記載する欄に分かれています。
年月は入学卒業した年と月を書き、右側の欄に学校の正式名称と「入学」「卒業」を記載するのが基本です。
学歴を書くときは、まず1行目の中央に「学歴」と明記し、次の行から実際の経歴を古い順に書いていきます。
テンプレートによって多少の違いはありますが、この基本的な構成を理解しておくことで、どのようなフォーマットの履歴書でもスムーズに作成できます。
履歴書の学歴を書く前に押さえるべき4つの基本ルール
履歴書の学歴欄を記入する際には、守るべき基本的なルールがいくつか存在します。
まず、学歴職歴欄の1行目中央に「学歴」と記載し、次の行から実際の学歴を書き始めます。
学校名は「高校」などと略さず、正式名称で書くことが重要です。
また、履歴書全体で年号は西暦か和暦のどちらかに統一する必要があり、生年月日や職歴欄の元号表記と揃えなければなりません。
これらのルールは、採用担当者が応募者の経歴を正確に把握するために不可欠です。
改行や空白の使い方も含め、読みやすく分かりやすい記述を心がけましょう。
1行目の中央に「学歴」と記載する
学歴を書き始める際は、まず学歴・職歴欄の1行目の中央に「学歴」と記載します。
これは、ここから学歴が始まることを明確に示すためのルールです。
実際の学歴は、その下の2行目から時系列に沿って書き進めていきます。
このルールは学歴だけでなく職歴も同様で、学歴をすべて書き終えた後、一行空けて中央に「職歴」と記載し、その次の行から具体的な職務経歴を記入します。
このように項目名を最初に示すことで、採用担当者が学歴と職歴をはっきりと区別でき、内容をスムーズに把握できるようになります。
学歴は高校卒業から書くのが一般的
履歴書に記載する学歴は、義務教育の終了時点である中学校卒業以降の経歴を書くのが基本です。
そのため、一般的には高等学校(高校)の入学から書き始めます。
小学校や中学校の卒業歴を記載する必要はありません。
最終学歴が中学校卒業である場合に限り、中学の卒業年月を記載します。
高校から書き始めることで、採用担当者は応募者の義務教育以降の教育経歴を効率的に確認できます。
学歴詐称を疑われないためにも、高校以降の学歴はすべて正確に記入することが求められます。
学校名・学部・学科は省略せず正式名称で記入する
学校名を記入する際は、必ず正式名称を用いなければなりません。
「○○高校」ではなく「○○県立○○高等学校」のように、都道府県名や「立」の種類(県立、私立など)から正確に記載します。
大学の場合は、学部、学科、専攻コース名まで省略せずに書きましょう。
特に、学校法人の名称がある私立大学などは、法人名から書くとより丁寧な印象を与えます。
これは、応募書類が正式な文書であるため、略称を用いるのは不適切とされるからです。
正確な名称を記載することで、経歴の信頼性を担保します。
年号は和暦か西暦のどちらかに統一する
履歴書に記入する年号は、和暦(昭和、平成、令和など)か西暦のどちらかに統一するのがルールです。
学歴欄だけでなく、生年月日や職歴、資格取得の年月など、履歴書内のすべての日付表記を揃える必要があります。
例えば、生年月日を和暦で書いたなら、学歴の入学・卒業年も和暦で記載します。
どちらを選ぶかは自由ですが、一般的に外資系企業やIT業界では西暦が好まれる傾向があります。
年度の区切りである3月卒業、4月入学を基本としつつ、自身の正しい卒業年月日は卒業証書などで確認して記載しましょう。
【計算不要】生まれ年別!入学・卒業年の西暦・和暦早見表
履歴書作成時、「卒業したのは西暦何年だったか」と分からなくなることは少なくありません。
そのような時に便利なのが、生まれ年から入学・卒業年を簡単に確認できる早見表です。
この表を使えば、面倒な計算は不要で、自分の年齢に応じた学歴の該当年をすぐに検索できます。
浪人や留年などを経験していない場合、この早見表を参照することで、西暦と和暦の両方を間違いなくスムーズに記入することが可能です。
履歴書作成の時間を短縮し、正確な情報を記載するために活用しましょう。
2000年(平成12年)〜2005年(平成17年)生まれ
2000年(平成12年)から2005年(平成17年)生まれの方の学歴早見表です。
例えば、2004年(平成16年)生まれの場合、中学校卒業は2020年(令和2年)3月、高校入学は同年4月となります。
この世代には、2001年、2002年、2003年生まれの方などが含まれます。
ただし、1月1日から4月1日までの早生まれの方は、表の各年から1年引いた年が該当するため注意が必要です。
例えば、2003年(平成15年)2月生まれの方の高校卒業年は、2020年ではなく2021年3月となります。
ご自身の経歴に合わせて正確な年月をご確認ください。
2000年(平成12年)〜2005年(平成17年)生まれ
| 生年 | 和暦 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 平成12 | 2006(H18)4月 | 2012(H24)3月 | 2015(H27)3月 | 2018(H30)3月 | 2022(R4)3月 |
| 2001 | 平成13 | 2007(H19)4月 | 2013(H25)3月 | 2016(H28)3月 | 2019(R1)3月 | 2023(R5)3月 |
| 2002 | 平成14 | 2008(H20)4月 | 2014(H26)3月 | 2017(H29)3月 | 2020(R2)3月 | 2024(R6)3月 |
| 2003 | 平成15 | 2009(H21)4月 | 2015(H27)3月 | 2018(H30)3月 | 2021(R3)3月 | 2025(R7)3月 |
| 2004 | 平成16 | 2010(H22)4月 | 2016(H28)3月 | 2019(R1)3月 | 2022(R4)3月 | 2026(R8)3月 |
| 2005 | 平成17 | 2011(H23)4月 | 2017(H29)3月 | 2020(R2)3月 | 2023(R5)3月 | 2027(R9)3月 |
1990年(平成2年)〜1999年(平成11年)生まれ
1990年(平成2年)から1999年(平成11年)生まれの方の学歴をまとめた早見表です。
この年代には、平成3年、平成4年、平成5年、平成6年、平成7年、平成8年、平成9年といった平成一桁代の生まれ年が多く含まれます。
例えば、1998年(平成10年)生まれの場合、大学卒業は2021年(令和3年)3月が一般的です。
もし浪人や留年を経験している場合は、この表の卒業年にその期間を加算して計算する必要があります。
自身の経歴を正確に振り返り、正しい卒業年月を記載することが重要です。
1990年(平成2年)〜1999年(平成11年)生まれ
| 生年 | 和暦 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 平成2 | 1997(H9)4月 | 2003(H15)3月 | 2006(H18)3月 | 2009(H21)3月 | 2013(H25)3月 |
| 1991 | 平成3 | 1998(H10)4月 | 2004(H16)3月 | 2007(H19)3月 | 2010(H22)3月 | 2014(H26)3月 |
| 1992 | 平成4 | 1999(H11)4月 | 2005(H17)3月 | 2008(H20)3月 | 2011(H23)3月 | 2015(H27)3月 |
| 1993 | 平成5 | 2000(H12)4月 | 2006(H18)3月 | 2009(H21)3月 | 2012(H24)3月 | 2016(H28)3月 |
| 1994 | 平成6 | 2001(H13)4月 | 2007(H19)3月 | 2010(H22)3月 | 2013(H25)3月 | 2017(H29)3月 |
| 1995 | 平成7 | 2002(H14)4月 | 2008(H20)3月 | 2011(H23)3月 | 2014(H26)3月 | 2018(H30)3月 |
| 1996 | 平成8 | 2003(H15)4月 | 2009(H21)3月 | 2012(H24)3月 | 2015(H27)3月 | 2019(R1)3月 |
| 1997 | 平成9 | 2004(H16)4月 | 2010(H22)3月 | 2013(H25)3月 | 2016(H28)3月 | 2020(R2)3月 |
| 1998 | 平成10 | 2005(H17)4月 | 2011(H23)3月 | 2014(H26)3月 | 2017(H29)3月 | 2021(R3)3月 |
| 1999 | 平成11 | 2006(H18)4月 | 2012(H24)3月 | 2015(H27)3月 | 2018(H30)3月 | 2022(R4)3月 |
1980年(昭和55年)〜1989年(平成元年)生まれ
1980年(昭和55年)から1989年(平成元年)生まれの方の学歴早見表です。
この年代は、昭和から平成への移り変わりを経験しており、特に1989年生まれは平成元年にあたります。
転職活動で履歴書を作成する機会が多い世代であり、学歴を正確に記載することは、これまでのキャリアの信頼性を示す上で非常に重要です。
この表を参考に、自身の学歴を間違いなく記入しましょう。
和暦と西暦の対応を間違えやすいため、提出前には必ず再確認することが求められます。
1980年(昭和55年)〜1989年(平成元年)生まれ
| 生年 | 和暦 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 昭和55 | 1987(S62)4月 | 1993(H5)3月 | 1996(H8)3月 | 1999(H11)3月 | 2003(H15)3月 |
| 1981 | 昭和56 | 1988(S63)4月 | 1994(H6)3月 | 1997(H9)3月 | 2000(H12)3月 | 2004(H16)3月 |
| 1982 | 昭和57 | 1989(H1)4月 | 1995(H7)3月 | 1998(H10)3月 | 2001(H13)3月 | 2005(H17)3月 |
| 1983 | 昭和58 | 1990(H2)4月 | 1996(H8)3月 | 1999(H11)3月 | 2002(H14)3月 | 2006(H18)3月 |
| 1984 | 昭和59 | 1991(H3)4月 | 1997(H9)3月 | 2000(H12)3月 | 2003(H15)3月 | 2007(H19)3月 |
| 1985 | 昭和60 | 1992(H4)4月 | 1998(H10)3月 | 2001(H13)3月 | 2004(H16)3月 | 2008(H20)3月 |
| 1986 | 昭和61 | 1993(H5)4月 | 1999(H11)3月 | 2002(H14)3月 | 2005(H17)3月 | 2009(H21)3月 |
| 1987 | 昭和62 | 1994(H6)4月 | 2000(H12)3月 | 2003(H15)3月 | 2006(H18)3月 | 2010(H22)3月 |
| 1988 | 昭和63 | 1995(H7)4月 | 2001(H13)3月 | 2004(H16)3月 | 2007(H19)3月 | 2011(H23)3月 |
| 1989 | 平成1 | 1996(H8)4月 | 2002(H14)3月 | 2005(H17)3月 | 2008(H20)3月 | 2012(H24)3月 |
1970年(昭和45年)〜1979年(昭和54年)生まれ
1970年(昭和45年)から1979年(昭和54年)生まれの方の学歴早見表です。
この年代の方は社会人経験が長く、職歴が豊富な場合が多いため、学歴は最終学歴の一つ前からなど、要点を押さえて記載することも考えられます。
学歴が長い場合でも、基本的なルールに沿って高等学校卒業から記載するのが一般的です。
職務経歴が豊富な方は、学歴欄を簡潔にまとめ、職歴欄で実績を詳しくアピールするのが効果的です。
この表はあくまで標準的なケースの補足として活用し、ご自身の経歴に合わせて調整してください。
1970年(昭和45年)〜1979年(昭和54年)生まれ
| 生年 | 和暦 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 昭和45 | 1977(S52)4月 | 1983(S58)3月 | 1986(S61)3月 | 1989(H1)3月 | 1993(H5)3月 |
| 1971 | 昭和46 | 1978(S53)4月 | 1984(S59)3月 | 1987(S62)3月 | 1990(H2)3月 | 1994(H6)3月 |
| 1972 | 昭和47 | 1979(S54)4月 | 1985(S60)3月 | 1988(S63)3月 | 1991(H3)3月 | 1995(H7)3月 |
| 1973 | 昭和48 | 1980(S55)4月 | 1986(S61)3月 | 1989(H1)3月 | 1992(H4)3月 | 1996(H8)3月 |
| 1974 | 昭和49 | 1981(S56)4月 | 1987(S62)3月 | 1990(H2)3月 | 1993(H5)3月 | 1997(H9)3月 |
| 1975 | 昭和50 | 1982(S57)4月 | 1988(S63)3月 | 1991(H3)3月 | 1994(H6)3月 | 1998(H10)3月 |
| 1976 | 昭和51 | 1983(S58)4月 | 1989(H1)3月 | 1992(H4)3月 | 1995(H7)3月 | 1999(H11)3月 |
| 1977 | 昭和52 | 1984(S59)4月 | 1990(H2)3月 | 1993(H5)3月 | 1996(H8)3月 | 2000(H12)3月 |
| 1978 | 昭和53 | 1985(S60)4月 | 1991(H3)3月 | 1994(H6)3月 | 1997(H9)3月 | 2001(H13)3月 |
| 1979 | 昭和54 | 1986(S61)4月 | 1992(H4)3月 | 1995(H7)3月 | 1998(H10)3月 | 2002(H14)3月 |
【状況別】履歴書の学歴欄の書き方と例文
履歴書の学歴欄は、すべての人が同じ書き方で済むわけではありません。
新卒の就職活動や社会人の転職、再就職など、応募者の状況によって記載内容は異なります。
例えば、在学中、大学院修了、中退、留学、編入といった多様なケースが存在します。
また、アルバイトや派遣社員から正社員を目指す場合や、職業訓練校や専門学校での学びをアピールしたい場合もあるでしょう。
ここでは、ハローワークや企業の採用担当者が正確に経歴を理解できるよう、様々な状況に応じた学歴欄の書き方を例文とともに解説します。
在学中の場合:「卒業見込み」と記載する
大学や専門学校などに在学中で、卒業を予定している学生が履歴書を提出する場合、卒業予定の年月のあとに「卒業見込み」と記載します。
「卒業見込」と略さず、正式に書きましょう。
例えば、「令和7年3月 ○○大学○○学部○○学科 卒業見込み」のように記入します。
卒業が確定していないものの、卒業する予定である場合には「卒業予定」と書くことも可能です。
インターンの応募などで履歴書を作成する際も同様の書き方です。
これにより、採用担当者は応募者がいつから就業可能かを正確に把握できます。
大学院を修了した場合:「修了」と記載する
大学院を卒業した場合は、「卒業」ではなく「修了」という言葉を使います。
修士課程(博士前期課程)を終えた場合は「修士課程修了」、博士課程(博士後期課程)を終えた場合は「博士課程修了」と記載するのが正しい書き方です。
大学院での研究内容をアピールしたい場合は、専攻名のあとに研究テーマを簡潔に書き添えることも有効です。
博士課程の単位は取得したものの論文未提出で退学した場合は、「博士課程単位取得後退学」と事実を正確に記載します。
学校を中退した場合:「中途退学」と理由を添える
学校を中途退学した場合は、その事実を隠さずに学歴欄に明記する必要があります。
「○○高等学校 中途退学」のように記載し、その理由を簡潔に添えるのが一般的です。
理由は「経済的理由のため」や「進路変更のため」など、事実を正直に書きましょう。
やむを得ない事情や、前向きな目的のための退学であったことを伝えられれば、採用担当者にネガティブな印象を与えにくくなります。
中退の事実は正直に伝えつつ、面接で詳しく説明できるよう準備しておくことが大切です。
浪人や留年をした場合:入学・卒業年月を正確に書けばOK
浪人や留年をした経験について、履歴書の学歴欄に「浪人」「留年」と直接記載する必要はありません。
高等学校の卒業年月と大学の入学年月に1年以上の空白期間があれば、採用担当者は浪人経験を推測します。
同様に、大学の在学期間が標準の4年間より長ければ、留年の可能性を考慮します。
そのため、入学と卒業の年月を正確に記載するだけで十分です。
面接で空白期間について質問される可能性はありますが、その際に理由をきちんと説明できれば問題ありません。
休学経験がある場合:休学期間と理由を簡潔に書く
大学在学中に休学した経験がある場合は、その事実を学歴欄に記載します。
休学した学校名と学部名の次の行に、休学した期間と理由を簡潔に書きましょう。
記載例としては、「令和○年○月~令和○年○月 病気療養のため休学(現在は完治しており、業務に支障はありません)」や「語学習得のため休学し、○○へ留学」といった形です。
理由が留学などのポジティブなものであれば、自己PRにもつながります。
休学の事実と理由を正直に記載することで、経歴の透明性を示せます。
留学経験がある場合:1年以上の留学は学歴欄に記載する
留学経験の記載は、その期間によって判断が分かれます。
一般的に、1年以上の正規留学や交換留学は学歴とみなされるため、学歴欄に記載します。
その際は、留学先の国名、学校名、学部名、留学期間を明記しましょう。
例えば、「○○大学○○学部在学中、△△大学へ交換留学(令和○年○月~令和○年○月)」のように書きます。
一方で、1年未満の短期留学や語学研修、ワーキングホリデーなどは学歴には含まれないため、自己PR欄や語学スキル欄でアピールするのが適切です。
学部や学科を編入した場合:編入学の事実を明記する
短期大学や高等専門学校、専門学校などから大学の学部に編入した場合は、その経歴を学歴欄に正確に記載します。
まず、編入前の学校の入学と卒業を書き、その次に編入先の大学名、学部・学科名に続けて「編入学」と明記します。
これにより、最終学歴に至るまでの経緯が採用担当者に明確に伝わります。
学習意欲の高さやキャリアプランに基づいた進路変更であることを示せれば、ポジティブな評価につながる可能性もあります。
採用担当者は学歴欄のどこをチェックしている?
採用担当者は、学歴欄から応募者の基礎的な能力や人柄を推測しています。
まず確認するのは最終学歴ですが、学校名だけで合否を決めることは多くありません。
むしろ、何を学んできたのかという専攻分野や学部を見て、自社の事業や募集職種との関連性を判断します。
また、入学から卒業までの期間に不自然な空白がないかを確認し、もしあれば面接でその理由を質問しようと考えます。
学歴欄は、応募者がどのような知識や素養を身につけてきたのかを知るための重要な情報源としてチェックされています。
履歴書の学歴に関するよくある質問
履歴書の学歴欄を作成する際には、「学歴はいつから書くべきか」「書き間違えた場合はどうすればよいか」など、細かな点で疑問が生じることがあります。
これらの疑問を解消しておかなければ、不正確な書類を提出してしまいかねません。
ここでは、学歴と職歴の区分の仕方や、最後に「以上」と書くべきかなど、多くの人が迷いがちなポイントをQ&A形式で解説します。
基本的なルールを再確認し、自信を持って履歴書を完成させましょう。
Q. 学歴はいつから書くべき?中学校卒業から?
履歴書に記載する学歴は、いつから書くかという明確な決まりはありませんが、一般的には高等学校卒業から書くのが通例です。
小学校や中学校は義務教育期間であるため、記載を省略します。
したがって、学歴はどこから書くべきか迷った際は、高校卒業からと覚えておくと良いでしょう。
ただし、最終学歴が中学校卒業の場合は、その卒業年月を記載します。
また、応募先の企業から特に指定がある場合は、その指示に従って記入してください。
Q. 書き間違えた場合、修正液を使ってもいい?
履歴書は公的な応募書類であるため、書き間違えた際に修正液や修正テープを使用するのは避けるべきです。
修正した跡は見栄えが悪く、採用担当者に「準備が雑」「志望度が低い」といったマイナスの印象を与えかねません。
手書きで作成中にミスをした場合は、手間がかかっても新しい用紙に最初から書き直すのがマナーです。
このような間違いを防ぐためにも、事前に下書きをする、パソコンで作成して印刷するといった対策が有効です。
Q. 学歴と職歴の間に一行空ける必要はある?
学歴をすべて書き終えた後、職歴を書き始める際には、学歴の最後の行と「職歴」という見出しの間に一行空ける必要はありません。
学歴の最終行を書き終えたら、そのすぐ下の行の中央に「職歴」と記載し、さらにその次の行から入社・退職の経歴を書き始めるのが一般的です。
行間を空けずに詰めて書くことで、学歴と職歴の区分が明確になり、レイアウトがすっきりと見やすくなります。
職歴がない場合は、学歴の下に「職歴」と記載し、「なし」と書きます。
Q. 学歴欄の最後に「以上」と書くのはなぜ?
学歴欄の最後に「以上」と記載する必要はありません。
「以上」という表記は、記載すべき経歴がすべて終了したことを示すためのものです。
したがって、学歴を書き終え、その後に職歴を記載する場合は、職歴をすべて書き終えた最後の行の右端に「以上」と書きます。
もし職歴がない場合は、学歴の最後の行までを記入し、その次の行の右端に「以上」と記載します。
学歴のみを書き終えた段階では、まだ職歴が続くため、「以上」は不要です。
まとめ
履歴書の学歴欄は、基本的なルールに従って正確に記入することが重要です。
学校名は省略せず正式名称で書き、年号は西暦か和暦に統一します。
学歴は一般的に高校卒業から記載し、中退や留学といった特殊な経歴も正直に書きましょう。
英検や各種免許、資格は学歴ではないため、学歴欄には書かないように注意が必要です。
これらは資格欄に記載します。
職歴がない場合のみ、学歴を書き終えた最後の行の右下に「以上」と記入します。
履歴書の学歴欄は、入学・卒業年の年度を正確に書き、学校の正式名称を略すことなく記載することが基本です。
特に新卒や転職、無職からの再スタート、アルバイト・パート・派遣の応募など、どの応募形態でも書き方は共通です。
記入例や見本、テンプレートを参考にすれば、誰でも迷わず記入できます。
学歴の書き方で多いミスは、「卒」や「卒業予定」の記載漏れ、スクール・専門学校の名称省略、法人名を誤って書くなどがあります。
正社員・アルバイト問わず、人事担当者は職務・自己PRと同じくらい学歴欄の正確性を見ています。
特に学年と年度がずれると不自然なブランクが出るため注意しましょう。退職後の空白期間を書く際も、「○年○月~現在に至る」と記載すれば問題ありません。
入学・卒業年の計算が面倒な場合は、当サイトの計算ツールや自動計算できる早見表を使うと便利です。
西暦・和暦の一覧で確認でき、誰でも素早く正しい年度が判断できます。活動歴が多い方やスクール卒の方も、フォーマットに沿って書くだけでスムーズにまとめられます。
履歴書の学歴は、あなたのこれまでの学びと活動を示す大切な情報です。
正しい方法で落ち着いて記入し、自分らしい職務経歴書やPRにつなげていきましょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書のポスト投函はOK?封筒の書き方や郵送マナー、注意点を解説
就職活動では、企業から履歴書の郵送を求められることが少なくありません。 その際、「履歴書をポストに投函しても大丈夫なのか?」「手渡しや窓口での提出が望ま… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部入社書類の送付状 書き方とテンプレート 郵送マナーも解説
入社を控えた新社会人や転職活動を終えた方にとって、入社書類の提出は最初の重要な手続きです。 この書類送付の際に、ビジネスマナーとして送付状を同封すること… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部上場・非上場企業の見分け方とは?簡単な調べ方と株式の違いを解説
就職活動や転職活動では、企業の規模や安定性を判断する指標の一つとして「上場企業」か「非上場企業」かという点が注目されます。 しかし、両者の具体的な違いや… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ホワイト企業の基準とは?新卒向けに離職率や特徴で判断する方法
就職活動を進める多くの新卒学生にとって、働きやすい環境である「ホワイト企業」への入社は大きな目標の一つです。 しかし、ホワイト企業の明確な定義や基準はな… 続きを読む