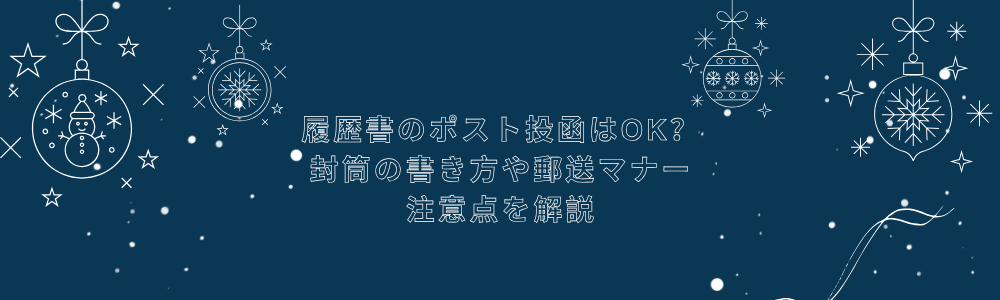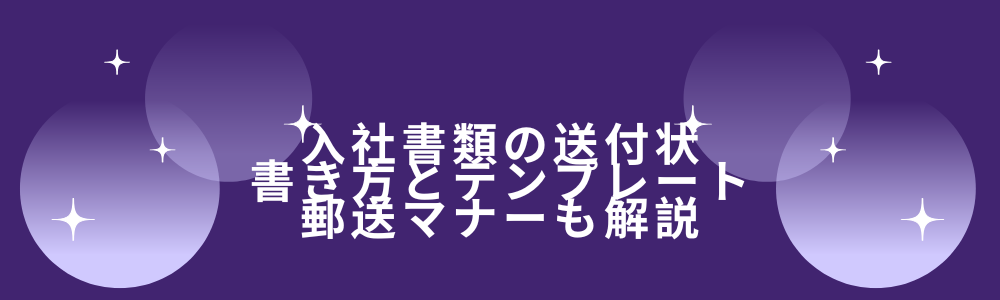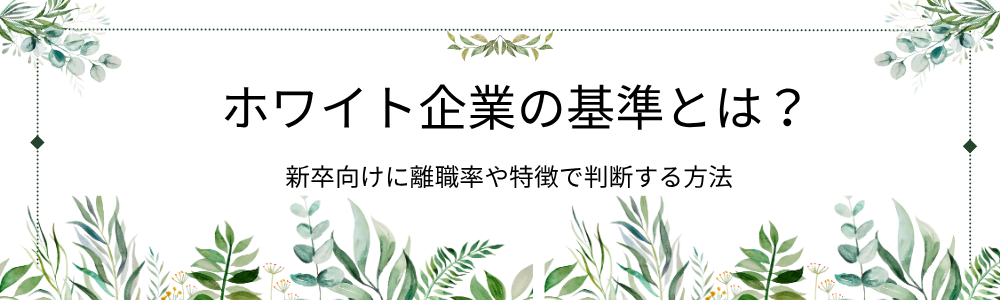上場・非上場企業の見分け方とは?簡単な調べ方と株式の違いを解説
就職活動や転職活動では、企業の規模や安定性を判断する指標の一つとして「上場企業」か「非上場企業」かという点が注目されます。
しかし、両者の具体的な違いや簡単な見分け方を知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、上場と非上場の定義から、誰でも簡単にできる調べ方、見分け方それぞれの企業で働くメリット・デメリットまでを解説します。
上場・非上場の見分け方は企業の株式が市場で取引されているかどうかが大きな違いであり、企業の経営方針や働き方にも影響を与えます。
そもそも上場企業とは?非上場企業との根本的な違いを解説
上場企業とは、証券取引所が定める基準をクリアし、自社の株式が市場で誰でも売買できるように公開している会社のことです。
一方、非上場企業は株式を公開しておらず、限られた株主のみが保有しています。
この株式の公開性の違いが両者の最も根本的な違いです。
株式を上場するには厳しい審査を通過する必要があるため、上場企業は一般的に社会的な信用度や透明性が高いと評価されます。
【初心者でも簡単】上場企業かどうかを見分ける3つの方法
気になる企業が上場しているかどうかを調べる方法は、決して難しくありません。
専門的な知識がなくても、インターネットを使えば誰でも簡単に確認できます。
ここでは、就職活動や転職活動中に企業の情報を集める際に役立つ、代表的な3つの調べ方を紹介します。
これらの方法を知っておけば、企業研究をより効率的に進めることが可能です。
方法1:証券取引所の公式サイトで会社名を検索する
最も確実な方法は、日本取引所グループの公式サイトで調べることです。
JPXのサイトには、東京証券取引所に上場している全企業の情報を検索できるページがあります。
ここに企業名を入力して検索し、ヒットすればその企業は上場企業であると判断できます。
検索結果では、どの市場に上場しているかや、証券コードなども確認可能です。
公的な機関のサイトであるため、情報の正確性が非常に高く、企業研究の第一歩として信頼できる情報源となります。
スマートフォンからも手軽にアクセスできるため、面接の直前など、急いで確認したい時にも便利な方法です。
方法2:企業の公式ホームページでIR情報を確認する
企業の公式ウェブサイトを確認することも有効な手段です。
上場企業は、株主や投資家向けに経営状況や財務情報を公開する義務があります。
そのため、公式サイトには「IR情報(InvestorRelations)」や「株主・投資家の皆様へ」といった専門ページが設けられているのが一般的です。
このページが存在すれば、その会社は上場している可能性が非常に高いと言えます。
IR情報ページには、決算短信や有価証券報告書など、企業の詳細な経営データが掲載されており、企業の健全性や将来性を分析する上でも貴重な情報源です。
企業のウェブサイトを隅々までチェックする習慣は、企業理解を深める上で大変役立ちます。
方法3:金融情報サイトやアプリで銘柄を検索する
Yahoo!ファイナンスや各証券会社のウェブサイト、ニュースアプリの経済・株式関連ページなど、金融情報を提供しているメディアで企業名を検索する方法も手軽です。
これらのサイトやアプリで企業名を検索して、株価やチャート、銘柄コードが表示されれば、その企業は上場しています。
また、過去の業績推移や配当金の情報なども一覧で確認できるため、企業の収益性や株主還元の姿勢を把握するのに役立ちます。
特に、配当の実績は企業の安定性を示す一つの指標となるでしょう。
多くのサイトが無料で利用できるため、複数の企業を比較検討する際に非常に便利です。
上場企業は3種類に分類される!各市場の特徴を理解しよう
東京証券取引所に上場している企業は、その特性に応じて「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つの市場に区分されています。
それぞれの市場には異なる上場基準が設けられており、企業の規模や成長ステージが異なります。
自分が興味のある企業がどの市場に属しているかを知ることは、その企業の立ち位置や将来性を理解する上で重要です。
就職活動や転職活動においても、市場の違いを把握しておくことで、より多角的な企業分析が可能になります。
プライム市場:日本を代表する大企業向け
プライム市場は、3つの市場の中で最も厳しい上場基準が設けられている市場です。
ここに上場しているのは、国際的に事業を展開し、高いガバナンス水準を持つ、日本を代表する大企業が中心です。
時価総額や収益性の基準が高く、投資家との建設的な対話を重視する企業が集まっています。
安定した経営基盤を持ち、グローバルな影響力を持つ企業が多く含まれるため、安定志向の学生や、大規模なプロジェクトに携わりたい社会人にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
日本経済を牽引するような有名企業の大半がこの市場に属しており、社会的な知名度や信用度も非常に高いのが特徴です。
スタンダード市場:実績のある中堅企業向け
スタンダード市場は、日本の株式市場の中核をなす市場と位置付けられています。
プライム市場ほどの厳しい基準はないものの、公開された市場における投資対象として十分な流動性やガバナンス水準を備え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す企業が対象です。
業種も多岐にわたり、特定の分野で高いシェアを誇る中堅企業や、長年の実績を持つ優良企業が多く含まれます。
安定した経営基盤を維持しつつ、今後の成長も期待できる企業が多く、就職先・転職先としてバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。
グロース市場:高い成長性が見込まれる新興企業向け
グロース市場は、高い成長可能性を有する新興企業向けの市場です。
現時点での事業実績よりも将来の成長性を重視する点が特徴で、新しい技術やビジネスモデルを持つベンチャー企業などが多く上場しています。
そのため、上場基準においては、事業計画の合理性や成長可能性が重点的に審査されます。
企業の成長と共に自分自身も成長したいと考える人や、変化の速い環境で裁量権を持って働きたい人にとっては、非常にやりがいのある職場となる可能性があります。
ただし、事業の変動リスクは他の市場に比べて高い傾向にあるため、企業の将来性を見極めることが重要になります。
企業が株式を上場する4つのメリット
企業が厳しい審査基準をクリアし、多大なコストをかけてまで株式上場を目指すのには、多くのメリットがあるからです。
資金調達の円滑化や社会的な信用の向上など、上場によって得られる恩恵は企業の成長に大きく貢献します。
ここでは、企業が株式を上場することで得られる代表的な4つのメリットについて解説します。
これらのメリットを理解することは、企業の経営戦略や将来性を読み解く一助となります。
メリット1:資金調達の選択肢が広がる
上場の最大のメリットは資金調達がしやすくなることです。
株式市場を通じて広く一般の投資家から直接資金を調達できるようになります。
これにより銀行からの借入や社債発行といった従来の方法に加えて大規模な資金調達の選択肢が増えます。
調達した資金は新規事業への投資設備投資研究開発などに活用され企業のさらなる成長を後押しします。
非上場企業の場合資金調達の方法が限られるためスピーディーな事業拡大が難しいケースも少なくありません。
上場は企業の成長戦略を実現するための強力なエンジンとなるのです。
メリット2:社会的な信用度と知名度が向上する
上場するためには、証券取引所による厳しい審査を通過しなければなりません。
この審査では、企業の収益性や財産の健全性、コーポレート・ガバナンスの体制などが厳しくチェックされます。
そのため、「上場企業である」ということ自体が、社会的に高い信用力を持つことの証明になります。
信用度が高まることで、金融機関からの融資が受けやすくなったり、他の企業との取引が有利に進んだりする効果が期待できます。
また、株式市場やメディアで企業名が報じられる機会が増えるため、製品やサービスの知名度向上にもつながり、営業活動においても有利に働くことが多いでしょう。
メリット3:優秀な人材を採用しやすくなる
社会的な信用度や知名度の向上は、人材採用の面でも大きなメリットをもたらします。
上場企業は経営の安定性や将来性に対する期待感から、就職活動中の学生や転職希望者にとって魅力的な選択肢と映ります。
求人募集を行った際に多くの優秀な人材からの応募が集まりやすくなるため、採用競争において優位に立つことが可能です。
また、従業員にとっても、社会的に認められた企業で働いているという自負や安心感につながります。
ストックオプション制度などを導入することで、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材の定着を図ることも可能になります。
メリット4:内部管理体制が強化される
上場企業には、投資家保護の観点から、厳格な情報開示と内部管理体制の構築が求められます。
上場審査の過程および上場後も、社内規定の整備、コンプライアンス体制の強化、取締役会などによる業務執行の監督機能の確立が必要です。
これにより、経営の透明性が高まり、どんぶり勘定のような経営から脱却し、健全で効率的な組織運営が実現されます。
結果として、企業の持続的な成長基盤が強化されることになります。
働く従業員にとっても、ルールが明確で公正な環境で業務に取り組めるというメリットがあります。
知っておきたい株式上場の3つのデメリット
多くのメリットがある一方で、株式上場にはデメリットやリスクも存在します。
上場を維持するためのコスト負担や、経営の自由度が制限される可能性など、企業が負うべき責任も増大します。
これらのデメリットを理解することで、なぜ全ての企業が上場を目指すわけではないのか、その理由が見えてきます。
就職先や転職先を検討する際には、メリットとデメリットの両面から企業を評価することが重要です。
デメリット1:上場の維持に多額のコストがかかる
上場企業であり続けるためには、多額のコストが発生します。
例えば、証券取引所に支払う年間上場料や、監査法人に支払う監査報酬、株主総会の運営費用、IR活動に関連する費用など、様々な維持コストが継続的にかかります。
特に、内部統制報告制度(J-SOX)への対応や、四半期ごとの決算開示など、上場企業に課せられる義務を果たすためには、専門知識を持つ人材の確保やシステムの導入も必要となり、人件費や管理コストが増大する傾向にあります。
これらのコストは企業の利益を圧迫する要因となり得るため、経営上の負担は決して小さくありません。
デメリット2:敵対的買収をされるリスクが発生する
株式を市場に公開するということは、誰でもその企業の株主になれることを意味します。
これにより、経営陣の意向に反して株式を買い占め、経営権を奪おうとする「敵対的買収」のリスクに常に晒されることになります。
敵対的買収を仕掛けられると、経営陣は防衛策に多大な時間とコストを費やすことになり、本来の事業活動に集中できなくなる可能性があります。
そのため、上場企業は買収防衛策を講じるなどの対策が必要となりますが、それでもリスクを完全に排除することは困難です。
経営の安定性を揺るがしかねないこのリスクは、上場企業が常に抱える課題の一つです。
デメリット3:経営の自由度が制限される可能性がある
上場企業は株主全体の利益を最大化する責任を負っているため、経営者は常に株主の厳しい視線に晒されます。
特に、短期的な利益を求める株主からの圧力により、長期的な視点での投資や、大胆な経営判断が難しくなる場合があります。
株価を意識するあまり、目先の業績向上を優先せざるを得ない状況に陥ることも少なくありません。
創業者や経営者が思い描く独自のビジョンや理念に基づいた経営をスピーディーに実行したい場合、株主の意向を都度確認する必要があるため、経営の自由度が非上場企業に比べて制限されると感じる場面も多くなります。
【就職・転職者向け】上場企業で働くメリット
企業が上場しているかどうかは、そこで働く従業員にとっても大きな意味を持ちます。
一般的に、上場企業は経営の安定性や福利厚生の充実度が高い傾向にあり、多くの求職者にとって魅力的に映ります。
ここでは、就職・転職活動をする上で知っておきたい、上場企業で働くことの具体的なメリットを3つの観点から解説します。
自分のキャリアプランと照らし合わせながら、企業選びの参考にしてください。
経営が安定しており倒産リスクが低い
上場企業は厳しい審査基準をクリアしているため、経営基盤が安定している会社が多いのが特徴です。
一定の収益性や健全な財務状況がなければ上場を維持できないため、非上場企業に比べて倒産のリスクは低いと言えます。
また、万が一経営が傾いた場合でも、社会的な影響の大きさから金融機関などの支援を受けやすい傾向にあります。
安定した環境で長期的にキャリアを築きたいと考える人にとって、この経営の安定性は大きな安心材料となるでしょう。
会社の将来に対する不安を感じることなく、日々の業務に集中できる点は大きなメリットです。
給与水準が高く福利厚生も充実している
上場企業は、一般的に非上場企業と比較して給与水準が高い傾向にあります。
豊富な資金力や高い収益性を背景に、従業員へ利益を還元できる体力があるためです。
また、優秀な人材を確保し、長く働き続けてもらうために、福利厚生制度の充実に力を入れている企業が多く見られます。
住宅手当や家族手当、退職金制度、育児・介護休業制度などが整備されているだけでなく、独自の研修制度や資格取得支援制度などを設けている場合も少なくありません。
こうした手厚い待遇は、働く上でのモチベーション維持や生活の安定に直結する重要な要素です。
社会的影響の大きい仕事に携われる
特にプライム市場に上場しているような大企業は、国内外で広く事業を展開しており、その製品やサービスが多くの人々の生活に影響を与えています。
このような企業で働くことは、社会的な影響力の大きい大規模なプロジェクトや、最先端の技術開発に携わる機会を得やすいことを意味します。
自分の仕事が社会にどのように貢献しているかを実感しやすく、大きなやりがいを感じられるでしょう。
また、多様なバックグラウンドを持つ優秀な同僚と働く機会も多く、互いに刺激し合いながらスキルアップを目指せる環境も魅力の一つです。
【就職・転職者向け】上場企業で働くデメリット
安定性や待遇面で多くのメリットがある上場企業ですが、その規模の大きさや組織構造ゆえのデメリットも存在します。
個人の裁量権や意思決定のスピードなど、働き方の面で非上場企業とは異なる側面があります。
ここでは、上場企業で働く際に留意しておきたい2つのデメリットを解説します。
自分に合う働き方を見つけるために、メリットと合わせて理解しておくことが大切です。
担当する業務の範囲が限定されやすい
上場している大企業では、組織が細かく分業化されていることが一般的です。
多くの従業員が効率的に業務を遂行するため、一人ひとりが担当する業務範囲は専門的かつ限定的になる傾向があります。
そのため、ジェネラリストとして幅広い業務を経験したい人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
特定の分野の専門知識を深く追求したい人には向いていますが、会社全体の業務の流れを把握したり、様々な職種を経験したりする機会は限られがちです。
自分の専門性を高めたいのか、あるいは幅広く経験を積みたいのか、キャリアの方向性を考える上で重要なポイントになります。
意思決定のスピードが遅い傾向にある
上場企業は、組織の規模が大きく、コンプライアンスや社内規定が厳格に定められています。
そのため、新しいプロジェクトを始めたり、何かしらの変更を加えたりする際には、多くの部署や役職者の承認を得る必要があり、意思決定に時間がかかる傾向があります。
稟議書の作成や度重なる会議など、手続きが煩雑に感じられる場面も少なくないでしょう。
自分のアイデアをスピーディーに形にしたい、裁量権を持って仕事を進めたいと考える人にとっては、もどかしさを感じるかもしれません。
ボトムアップでの変革よりも、トップダウンで決められた方針に従って業務を遂行することが多くなります。
非上場企業にも優良企業は多数存在する
上場企業に注目が集まりがちですが、日本に存在する株式会社の99%以上は非上場企業です。
その中には、特定の分野で圧倒的な技術力やシェアを誇る優良企業が数多く存在します。
非上場企業は、株主からの短期的な利益追求の圧力に晒されにくいため、長期的な視点に立った経営や、独自の理念を追求した事業展開がしやすいというメリットがあります。
また、意思決定が迅速で、若手にも裁量権が与えられやすい傾向にあるため、個人の成長機会が多い環境であるとも言えます。
上場・非上場という枠組みだけで企業を判断するのではなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の価値観やキャリアプランに合う企業を見つけることが重要です。
まとめ
上場企業と非上場企業の最も大きな違いは、株式が証券取引所で公開されているか否かにあります。
上場しているかどうかは、日本取引所グループの公式サイトや企業のIR情報ページなどで簡単に調べることが可能です。
上場には資金調達の多様化や社会的信用の向上といったメリットがある一方、維持コストの発生や経営の自由度が制限されるといったデメリットも存在します。
働く側にとっても、経営の安定性や待遇の良さといったメリットと、業務範囲の限定や意思決定の遅さといったデメリットがあります。
就職や転職の際には、上場・非上場という区分だけでなく、各企業の事業内容や社風など、多角的な視点から自分に合う会社を選ぶことが求められます。
上場企業と非上場企業の違いを理解することは、就活や転職で「自分に合う職場」を選ぶうえで非常に重要です。両者の定義や調べ方、企業選びで見るべきポイントをまとめて解説します。まず、上場企業とは、株式会社が自社株式を証券取引所(プライム、スタンダード、グロース、TOKYO PRO Market など)に公開している会社を指します。反対に、非上場企業は株式を公開しておらず、社内体制や情報公開の範囲が限られる場合があります。
上場企業かどうかの調べ方は意外と簡単です。最も手軽なのは web で企業名+「上場」「プライム」「スタンダード」などで検索する方法 です。企業HPにも「企業情報」欄に株式情報が掲載されていることが多く、学生でも短い時間で調べられます。dodaや求人ボックスなどの求人メディアでも「上場企業」の絞り込み一覧があり、働きたい企業が上場かどうかすぐに確認できます。
上場企業は情報公開義務があるため、コンプライアンス体制や福利厚生が整い、健全な経営が求められます。一方、非上場企業は買収リスクが低く、意思決定が早い、自由度の高いプロジェクトに関われるなど、ならではの魅力をもつ企業も多数存在します。あなたがどんな職業観を持ち、どんな働き方を望むかによって、選び方は大きく変わります。
企業選びに迷う場合は、診断サービスや求人メディアの「適職診断」を活用するのも有効です。就活生にとっても社会人にとっても、上場・非上場の違いは単なるラベルではなく、「どの環境が自分に合うか」を判断するための大切な指標になります。記事全体を通じて、自分が勤める企業をしっかり調べ、後悔のないキャリア選びにつなげてください。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書のポスト投函はOK?封筒の書き方や郵送マナー、注意点を解説
就職活動では、企業から履歴書の郵送を求められることが少なくありません。 その際、「履歴書をポストに投函しても大丈夫なのか?」「手渡しや窓口での提出が望ま… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部入社書類の送付状 書き方とテンプレート 郵送マナーも解説
入社を控えた新社会人や転職活動を終えた方にとって、入社書類の提出は最初の重要な手続きです。 この書類送付の際に、ビジネスマナーとして送付状を同封すること… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書 学歴の書き方を記載例で解説|入学・卒業年の西暦和暦早見表
履歴書の学歴欄の書き方について、記入例を交えながら詳しく解説します。 履歴書の学歴の記入は、いつからどこまで書くのか、中退や留学などの特殊なケースはどう… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ホワイト企業の基準とは?新卒向けに離職率や特徴で判断する方法
就職活動を進める多くの新卒学生にとって、働きやすい環境である「ホワイト企業」への入社は大きな目標の一つです。 しかし、ホワイト企業の明確な定義や基準はな… 続きを読む