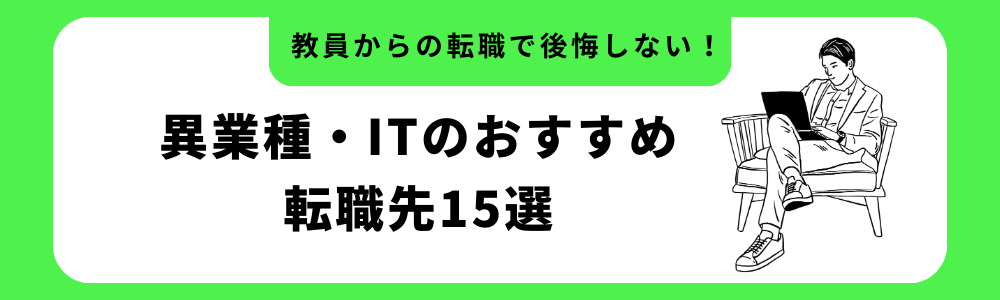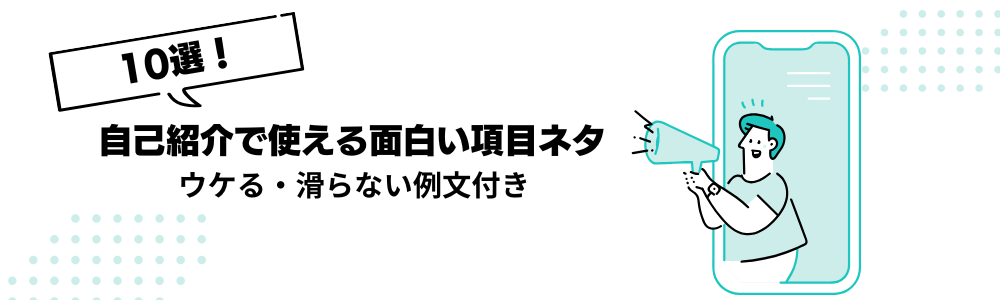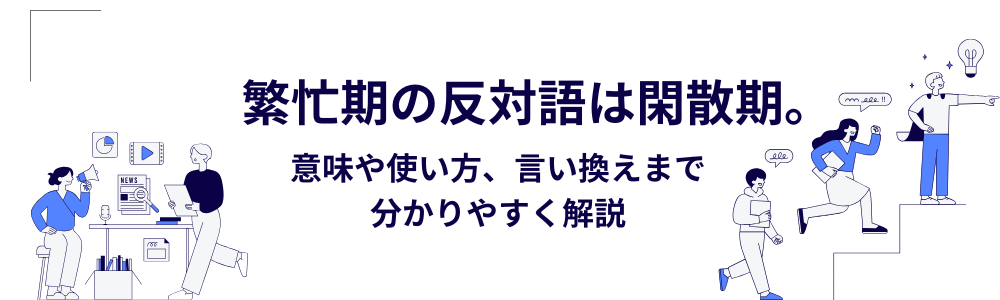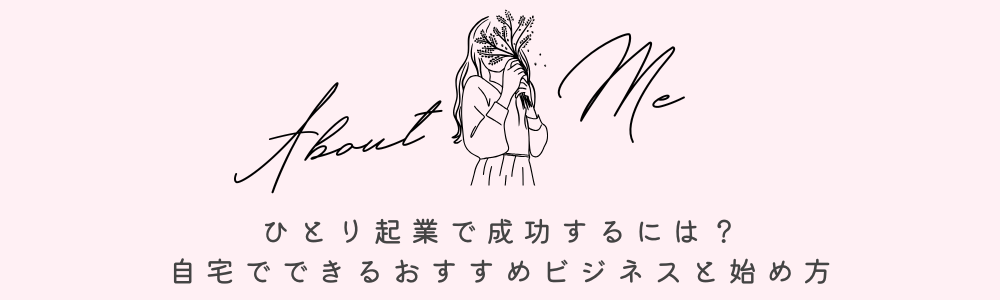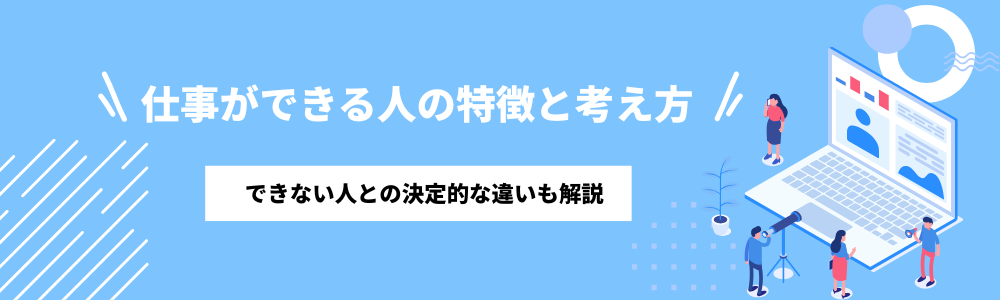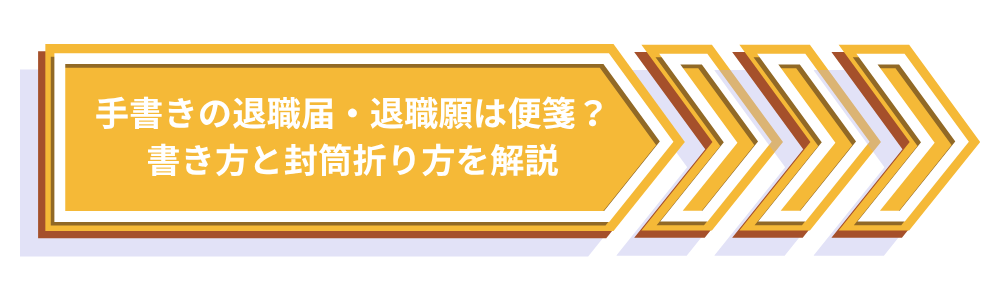

手書きの退職届・退職願は便箋?書き方と封筒折り方を解説
退職の意思を伝える際に提出する退職届は、これまでお世話になった会社への感謝と誠意を示す重要な書類です。
特に手書きで作成する場合、使用する便箋の選び方から退職届の書き方、封筒のマナーまで、守るべき作法がいくつか存在します。
この記事では、初めて退職届を手書きで作成する方に向けて、便箋や封筒の選び方、正しい書き方の例文、きれいな折り方と封入方法まで、一連の流れを分かりやすく解説します。
円満退職に向けた第一歩として、正しい知識を身につけましょう。
退職願に最適な便箋の選び方
退職願を作成する最初のステップは、適切な用紙を選ぶことです。
退職願はフォーマルな書類であるため、使用する便箋があなたの印象を左右することもあります。
用紙の色やサイズ、罫線の有無など、基本的なマナーを押さえておくことが重要です。
どのような便箋を選べば失礼にあたらないのか、具体的な選び方のポイントを解説します。
ここで適切な便箋を選ぶことで、相手に誠実な姿勢を伝えることができます。
基本は白無地!罫線ありの便箋でも問題ない
退職願に使用する便箋は、白の無地が最もフォーマルで適しています。
ビジネス文書の基本であり、清潔感と誠実な印象を与えることができます。
もし文字をまっすぐに書くのが苦手な場合は、罫線入りの便箋を使用してもマナー違反にはなりません。
その際も、罫線はシンプルなものを選びましょう。
キャラクターが描かれていたり、色が付いていたりするデザイン性の高い便箋は、退職というフォーマルな場面にはふさわしくないため避けるべきです。
また、コピー用紙を代用することも不可能ではありませんが、薄くて安価な印象を与えかねないため、できるだけしっかりとした上質の便箋を用意することをおすすめします。
サイズはB5が一般的、A4でも可
退職願の用紙サイズに厳密な決まりはありませんが、一般的にはB5サイズが最も多く使用されています。
B5サイズは、A4サイズよりもやや小ぶりで控えめな印象を与えるため、退職を願い出るという場面に適しているとされています。
また、市販の退職届セットもB5サイズで用意されていることが多いです。
もちろん、A4サイズの便箋を使用してもマナー違反になることはありません。
特に会社で指定されているフォーマットがA4である場合や、職務経歴書など他の書類とサイズを揃えたい場合にはA4を選んでも問題ありません。
どちらのサイズを選ぶか迷った際は、会社の慣習などを確認するか、B5サイズを選んでおくと無難です。
便箋はどこで買える?文具店や100円ショップで入手可能
退職願に適した便箋や封筒は、身近な場所で手軽に購入できます。
品揃えが豊富な文具専門店のほか、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの文具コーナーでも取り扱っています。
また、ダイソーなどの100円ショップでも、シンプルな白無地の便箋と封筒のセットが販売されており、手軽に準備を整えることが可能です。
退職届専用のセットとして、便箋、封筒、下敷きが一緒になっている商品も便利です。
購入する際は、便箋のサイズ(B5かA4か)と、封筒が郵便番号枠のない白無地であることを確認しましょう。
複数の選択肢の中から、自分の書きやすいものや用意したいサイズに合わせて選ぶと良いです。
【例文あり】便箋への退職願の正しい書き方
適切な便箋を用意したら、次はいよいよ退職願を作成します。
退職願の書き方には、守るべき基本的なルールやマナーがあります。
ここでは、作成前に用意すべきものから、縦書きを基本とした具体的な記載項目、そして分かりやすい例文までを詳しく解説します。
誤字脱字なく、丁寧な文字で書くことを心がけることで、あなたの誠意がより伝わります。
円満退職に向けて、ミスのない書類を作成するためのポイントを押さえていきましょう。
事前に用意するものリスト(黒のボールペンなど)
退職願を書き始める前に、必要なものをすべて揃えておくとスムーズです。
まず、筆記用具は黒のボールペンまたは万年筆を用意しましょう。
鉛筆やシャープペンシル、消えるタイプのボールペンは公的な書類にふさわしくないため使用できません。
次に、捺印のための印鑑と朱肉、そしてきれいに押印するための捺印マットも準備します。
印鑑は認印を使用し、シャチハタは避けてください。
また、文字をまっすぐきれいに書くために、下書き用の鉛筆と消しゴム、定規があると便利です。
特に罫線のない無地の便箋に縦書きで作成する場合は、鉛筆で薄く線を引いておくと、バランスの整った美しい仕上がりになります。
縦書きが基本!退職願の記載項目と例文
退職願は、縦書きで作成するのが正式なマナーです。
まず、一行目の中央に「退職願」と表題を記します。
次の行は一番下から「私儀(わたくしぎ)」または「私事(わたくしごと)」と書き始めます。
本文では、退職理由を「一身上の都合により」とし、具体的な理由は記載しません。
続いて、退職希望日を和暦で記入します。
本文を書き終えたら、提出する年月日、所属部署、そして自分の氏名をフルネームで書き、名前の下に捺印します。
最後に、会社の正式名称と代表取締役の役職・氏名を、自分の名前より高い位置に記載し、敬称は「殿」とします。
横書きが許容される場合もありますが、フォーマルな形式を重んじる場合は縦書きを選びましょう。
横書きの便箋を使ってもマナー違反にはならない
退職願は縦書きが伝統的なマナーとされていますが、横書きの便箋を使用したり、パソコンで横書きのフォーマットで作成したりしても、一概にマナー違反となるわけではありません。
特に、外資系企業やIT業界など、普段からビジネス文書を横書きで作成する文化が根付いている会社では、横書きの退職願でも問題なく受理されることがほとんどです。
ただし、歴史のある企業や、上司が礼儀を重んじるタイプの場合は、縦書きの方がより丁寧な印象を与える可能性があります。
どちらで作成すべきか迷った際は、会社の就業規則を確認するか、過去の慣例をそれとなく調べてみると良いでしょう。
横書きで作成する場合でも、記載すべき項目や封筒の選び方といったマナーは変わりません。
退職願を入れる封筒の選び方とマナー
退職願を書き終えたら、次はそれを入れる封筒の準備です。
退職願は会社への最終的な意思表示となる大切な書類であり、提出する際の封筒もマナーに沿ったものを選ぶ必要があります。
封筒の色やサイズ、郵便番号枠の有無といった選び方の基本から、表面・裏面の正しい書き方まで、相手に失礼のないよう細やかな配慮が求められます。
ここでは、退職願の提出にふさわしい封筒の選び方と、それに伴うマナーについて詳しく解説します。
郵便番号枠なしの白無地封筒を選ぼう
退職願を入れる封筒は、白色で無地のものを選ぶのが基本です。白はフォーマルな色であり、誠実さや清潔感を伝えるのに適しています。最も重要なポイントは、郵便番号の印刷枠がない封筒を選ぶことです。郵便番号枠は郵送を前提としたものであるため、直接手渡しする退職願にはふさわしくありません。
また、事務用品として一般的に使われる茶封筒は、請求書や社内資料のやり取りに用いられることが多く、改まった書類には不適切です。中身が透けて見えないように、二重構造になっている封筒を選ぶと、より丁寧な印象を与えます。適切な封筒を選ぶことは、中に入れる便箋の折り方にも関係してくるため、慎重に選びましょう。
封筒に適したサイズは?用紙のサイズに合わせるのが基本
封筒のサイズは、中に入れる便箋の大きさに合わせて選ぶのがマナーです。
便箋を三つ折りにした状態でぴったりと収まるサイズを選びましょう。
一般的に、B5サイズの便箋を使用した場合は「長形4号」の封筒が適しています。
A4サイズの便箋を使用した場合は、それより一回り大きい「長形3号」の封筒を選びます。
用紙に対して封筒が大きすぎると中で書類が動き、小さすぎると便箋に不要な折り目がついてしまう可能性があります。
適切なサイズの封筒を用意することで、見た目もすっきりと美しく収まり、相手にスマートで配慮のある印象を与えることができます。
【図解】封筒の表面・裏面の書き方
封筒の書き方にも決まったマナーがあります。
まず表面ですが、中央に少し大きめの文字で「退職願」と記載します。
これは中身が重要な書類であることを示すためです。
そして、宛名は書かずに提出するのが一般的ですが、もし書く場合は左下に提出する相手の部署名と氏名を書きます。
会社の代表者に提出するため、宛名は「代表取締役社長 〇〇〇〇殿」のように記載します。
裏面には、左下に自分の所属部署と氏名をフルネームで記入します。
これにより、誰が提出した書類なのかが一目で分かります。
文字はすべて黒のボールペンまたは万年筆を使い、丁寧に書きましょう。
最後に封をしたら、封じ目の中央に「〆」マークを書き入れます。
きれいに封入するための便箋の折り方と入れ方
退職願の作成と封筒の準備が整ったら、最後は便箋をきれいに折って封筒に入れる作業です。
この最終ステップも、相手への配慮を示す大切なマナーの一部です。
雑に折ったり、逆向きに入れたりすると、せっかく丁寧に書いた書類の印象が損なわれてしまう可能性があります。
ここでは、一般的な三つ折りの方法から、封筒への正しい入れ方、そして封の仕方まで、一連の封入作業について詳しく解説します。
最後まで丁寧な対応を心がけることが、円満退職につながります。
三つ折りが基本!用紙サイズ別の折り方
退職願の便箋は、三つ折りにするのが最も一般的で丁寧な折り方です。
まず、便箋の文章が書かれている面を上にして置きます。
次に、下から3分の1を、書き出し部分にかぶせるように上へ折り上げます。
その後、上部の残りの3分の1を、下から折り上げた部分に重なるように下へ折ります。
この時、折り目がずれないように、定規などを当ててまっすぐ丁寧に折ると美しく仕上がります。
この折り方をすることで、受け取った相手が封筒から便箋を取り出した際に、まず「退職願」という表題が目に入るようになります。
これは、相手が書類の内容をすぐに確認できるようにするための配慮であり、ビジネスマナーの基本です。
封筒への正しい入れ方と封の仕方
三つ折りにした便箋を封筒に入れる際にも、向きに注意が必要です。
封筒を裏側(自分の名前を書いた面)から見て、便箋の右上が書き出し部分(「退職願」という表題がある部分)になるように入れます。
こうすることで、受け取った相手が封筒の表側から開封し、便箋を取り出したときに、すぐに読み始められる状態になります。
便箋を封筒に入れたら、封をします。
このとき、セロハンテープやホッチキスを使うのは避け、液体のりやテープのりを使ってしっかりと貼り付けましょう。
最後に、フラップ(封筒のふた)と本体が重なる中央部分に、黒いペンで「〆」という締めマークを書き入れます。
「〆」マークには、確かに封をしたこと、そして途中で誰にも開封されていないことを示す意味があります。
退職願を手書きする際のよくある質問
退職願の作成を進める中で、「パソコンで作るのはダメなのか」「退職願と退職届、どちらを出すべきか」といった様々な疑問が浮かぶことがあります。
特に初めて退職手続きを行う場合、細かい点で不安を感じることも少なくありません。
このセクションでは、退職願を手書きする際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
パソコン作成の是非や書類の種類の違い、書き損じた際の正しい対処法などを解説し、スムーズな退職手続きをサポートします。
パソコンで作成した退職願は失礼にあたる?
退職願は手書きで作成する方が誠意が伝わりやすく丁寧な印象を与えるため一般的には推奨されています。
しかしパソコンでの作成が直ちに失礼にあたるわけではありません。
会社の就業規則でフォーマットが指定されている場合やIT企業のように文書作成をパソコンで行うのが通例となっている職場ではパソコンで作成した退職願でも問題なく受理されます。
判断に迷う場合は自社の慣習を確認するのが最も確実です。
もしパソコンで作成する場合でも最後の署名欄だけは自筆で記入し捺印をすることで形式的になりすぎず丁寧な印象を保つことができます。
手書きかパソコン作成かは会社の文化や状況に応じて柔軟に判断しましょう。
「退職願」と「退職届」どちらを提出すべき?
「退職願」と「退職届」は似ていますが、法的な効力が異なります。
「退職願」は、「会社を辞めたいのですが、よろしいでしょうか」という退職の合意を求めるための書類であり、会社が承諾するまでは撤回が可能です。
一方、「退職届」は、「私は〇月〇日をもって退職します」という退職を届け出るための書類で、受理された後の撤回は原則としてできません。
一般的に、自己都合で円満退職を目指す場合は、まず直属の上司に口頭で退職の意向を伝え、その後「退職願」を提出するのがスムーズな流れです。
会社の指示があった場合や、退職日が確定した後に、改めて「退職届」を提出するケースもあります。
まずは「退職願」から手続きを始めるのが無難です。
書き損じた場合は修正液を使っても良い?
退職願は公的な意味合いを持つ重要な書類であるため、書き損じた場合に修正液や修正テープを使用することはマナー違反です。
修正した跡があると、書類の信頼性が損なわれるだけでなく、相手に対して失礼な印象を与えてしまいます。
たとえ一文字の間違いであっても、手間を惜しまず新しい便箋に最初から書き直すのが正しい対応です。
書き損じを防ぐためには、いきなりペンで書き始めるのではなく、まず鉛筆で薄く下書きをし、その上をボールペンでなぞる方法がおすすめです。
インクが完全に乾いたのを確認してから、下書きの線をきれいに消しゴムで消せば、ミスのない美しい退職願を作成できます。
まとめ
退職願を手書きで作成する際は、使用する便箋や封筒の選び方、書き方の作法、折り方や封入方法に至るまで、細やかなマナーが求められます。
便箋は白無地か薄い罫線の入ったB5サイズ、封筒は郵便番号枠のない白無地の長形4号を選ぶのが基本です。
作成時には黒のボールペンを用い、縦書きで丁寧に記述します。
書き損じた場合は修正せず、新しい用紙に書き直すのが正式な作法です。
これらのマナーを守って作成した退職願は、あなたの誠実な気持ちを会社に伝え、円満な退職手続きを進める一助となります。
会社の就業規則も併せて確認し、定められた手順に沿って手続きを進めることが重要です。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部教員からの転職で後悔しない!異業種・ITのおすすめ転職先15選
教員を辞めて、異業種やIT業界への転職を考える先生が増えています。 長時間労働や特有の人間関係から解放され、新たなキャリアを築きたいと願うものの、教員を辞… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自己紹介で使える面白い項目ネタ10選!ウケる・滑らない例文付き
初対面の場で自分を印象付けたいとき、自己紹介に「おもしろ」要素を加えるのは有効な手段です。 ありきたりな内容では、大勢の中に埋もれてしまいがちですが、少… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部繁忙期の反対語は閑散期。意味や使い方、言い換えまで分かりやすく解説
ビジネスシーンで頻繁に耳にする「繁忙期」という言葉ですが、その正確な意味や使い方、そして反対語を正しく理解しているでしょうか。 繁忙期の反対語は「閑散期… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ひとり起業で成功するには?自宅でできるおすすめビジネスと始め方
ひとり起業は、自分の裁量で自由に働ける魅力的な選択肢です。 特に近年は、インターネットを活用することで、自宅で始められるビジネスが増え、未経験からひとり… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部仕事ができる人の特徴と考え方|できない人との決定的な違いも解説
周囲から高い評価を受ける「仕事ができる人」には、共通する特徴や考え方が存在します。 本記事では、具体的な行動特性や思考のパターンを多角的に分析し、仕事の… 続きを読む