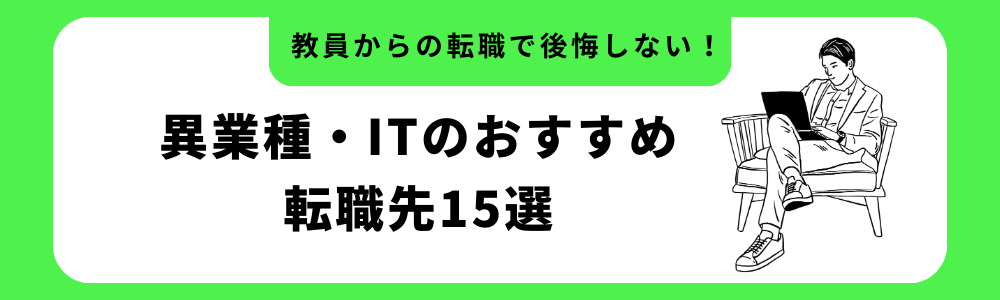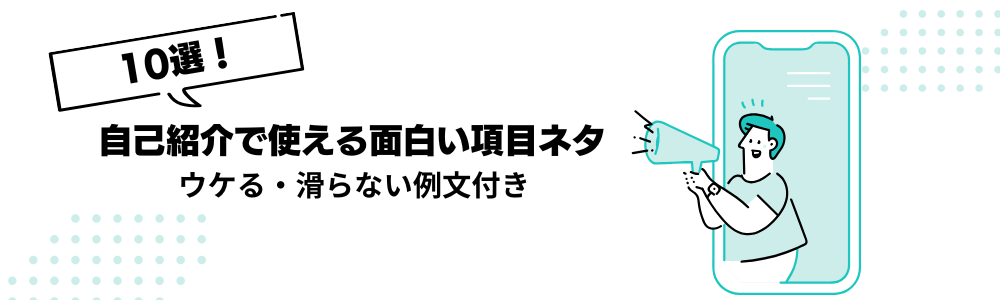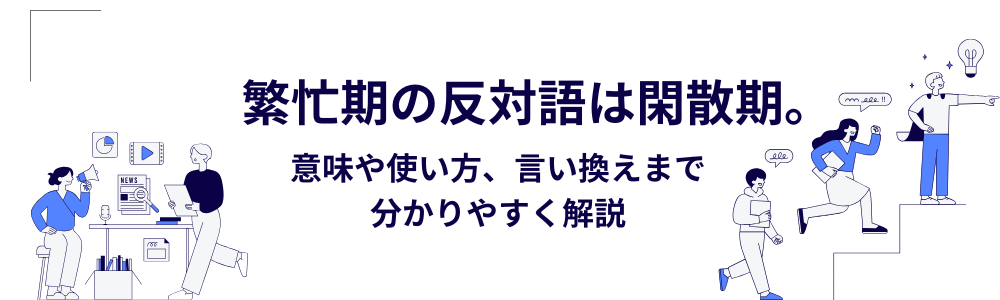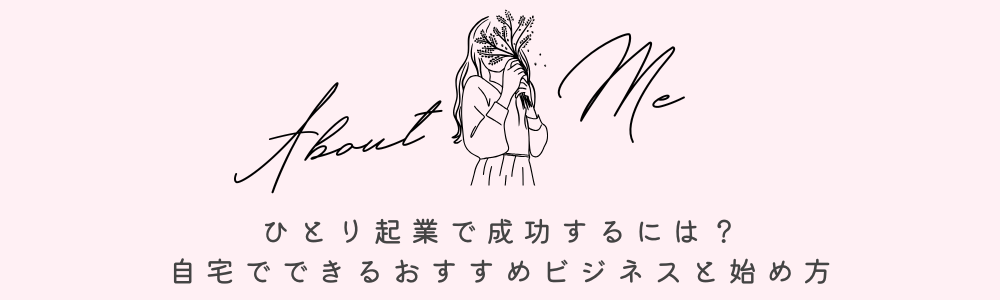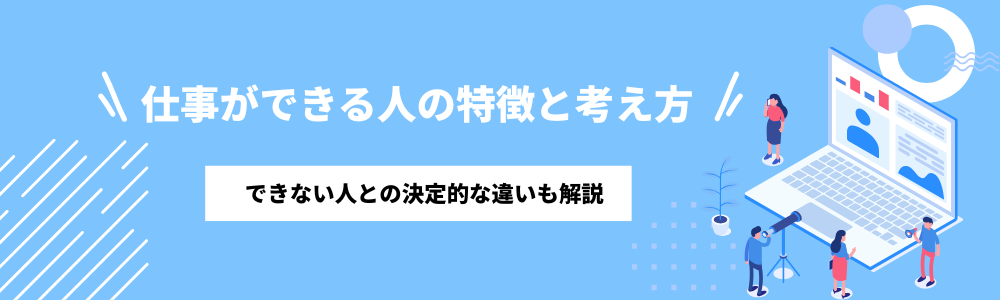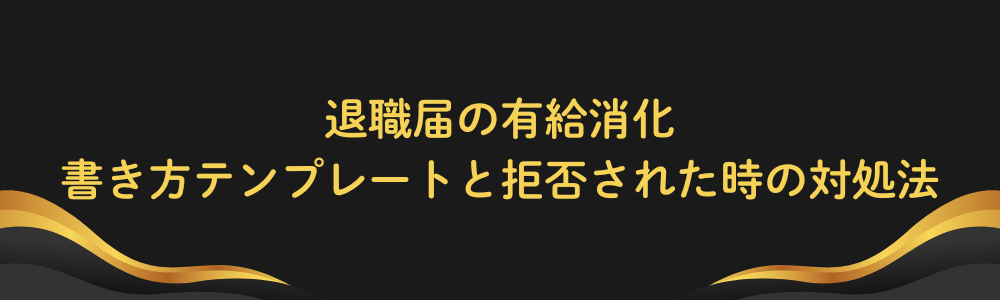

退職届の有給消化|書き方テンプレートと拒否された時の対処法
退職届の有給消化|書き方テンプレートと拒否された時の対処法
退職を決意した際、残っている有給休暇をすべて消化したいと考えるのは当然の権利です。
しかし、会社へどのように伝えればよいか、退職届にどう書けばよいか悩む人も少なくありません。
本記事では、有給消化を前提とした退職届の書き方や具体的なテンプレート、円満に手続きを進めるためのステップを解説します。
また、万が一会社に有給消化を拒否された場合の法的な対処法についても詳しく紹介するため、安心して退職準備を進められます。
退職時の有給休暇消化は労働者に認められた権利
退職時に残った年次有給休暇を消化することは、労働基準法第39条で定められた労働者の正当な権利です。
会社は原則として、労働者からの有給休暇取得の申し出を拒否できません。
会社側には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得日を変更できる「時季変更権」がありますが、退職予定日を超えて取得日を変更することはできないため、退職時の有給消化に対して時季変更権を行使することは不可能です。
したがって、退職日までに残っている有給休暇はすべて取得できます。
有給消化を前提とした退職届の書き方【テンプレート付き】
有給休暇を消化して退職する場合、その意思を明確に書面で示すことが後のトラブル防止につながります。
退職届の書き方には、有給消化の希望を盛り込む方法と、退職届とは別に有給休暇申請書を提出する方法の2種類があります。
どちらの方法を選択するにせよ、会社側に誤解を与えないよう、最終出社日と退職日、そして有給休暇の取得期間を正確に記載することが重要です。
ここでは、具体的な記載項目と例文を交えながら解説します。
退職届に必ず記載すべき5つの基本項目
退職届には、法的に定められた形式はありませんが、一般的に記載すべき基本項目が存在します。
まず、「退職届」という表題を明記し、本文には「一身上の都合により」といった簡潔な退職理由を記載します。
次に、有給消化期間を含めた最終的な在籍終了日となる「退職日」を明記することが不可欠です。
そして、この書類を会社へ提出する日付である「届出年月日」も忘れずに記入します。
最後に、所属部署と氏名を書き、捺印をすることで、正式な書類として完成します。
これらの項目を正確に記載し、円満な手続きを進めましょう。
【そのまま使える】有給消化の希望を伝える退職届の例文
退職届で有給消化の希望を伝える際は、簡潔かつ丁寧に記載することが重要です。
基本的な退職届のフォーマットに、最終出社日と有給休暇の取得期間を明記する一文を追加します。
【例文】
退職届
私儀
この度、一身上の都合により、来たる令和〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。
誠に勝手ながら、最終出社日を令和〇年〇月〇日とさせていただき、下記の期間にて残りの年次有給休暇〇〇日を取得させていただきたく、お願い申し上げます。
年次有給休暇取得期間:令和〇年〇月〇日〜令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【所属部署】〇〇部〇〇課
【氏名】〇〇〇〇印
有給休暇の申請書を別途提出する方法
会社の就業規則によっては、退職届とは別に、所定のフォーマットで有給休暇の申請手続きを求められる場合があります。
この場合、まずは上司に退職の意思を伝えた後、人事部や総務部に連絡し、正式な休暇申請のプロセスを確認することが推奨されます。
退職届には有給消化について触れず、別途、社内システムや指定の申請書を用いて、最終出社日の翌日から退職日までの期間を有給休暇として申請します。
口頭での確認だけでなく、書面で申請した記録を残しておくことで、後の「言った言わない」といったトラブルを防ぐことにもつながります。
退職と有給消化を円満に進めるための3ステップ
有給休暇を消化して退職するためには、事前の準備と計画的な行動が不可欠です。
いきなり退職届を提出するのではなく、まず自身の有給残日数を確認し、引き継ぎ期間を考慮したスケジュールを立てることが重要になります。
その上で、直属の上司に退職の意思と有給消化の希望を伝えるという段階的なアプローチを取ることで、会社との無用な摩擦を避け、円満な退職を実現しやすくなります。
ここでは、そのための具体的な3つのステップを解説します。
ステップ1:自分が取得できる有給休暇の残り日数を確認する
円満な有給消化の第一歩は、取得可能な年次有給休暇の残日数を正確に把握することです。
確認方法としては、給与明細の記載事項をチェックする、社内の勤怠管理システムで確認する、人事部や総務部に直接問い合わせるといった手段があります。
問い合わせる際は、退職を検討していることを伝える必要はありません。
また、退職日までに新たに付与される予定の有給休暇があるかどうかも確認しておくと、より正確なスケジュールが立てられます。
この残り日数の確認が、最終出社日や退職日を決定する上での基礎情報となります。
ステップ2:最終出社日と有給消化期間から退職日を逆算する
有給休暇の残日数が確定したら、次に具体的な退職スケジュールを組み立てます。
まずは、業務の引き継ぎに必要な期間を考慮して「最終出社日」を設定します。
一般的に、引き継ぎには2週間から1ヶ月程度を見込むのが適切です。
最終出社日が決まったら、その翌日から残っている有給休暇の日数を消化し、その最終日を「退職日」とします。
例えば、最終出社日が10月31日で有給が10日残っている場合、土日祝日を除いて10営業日を消化した日が退職日となります。
この逆算によって、計画的でスムーズな退職プロセスが可能になります。
ステップ3:退職の意思と有給消化の希望を直属の上司に伝える
退職スケジュールが固まったら、直属の上司に退職の意思を伝えます。
退職届を突然提出するのではなく、まずは口頭で相談の時間を設けてもらうのがマナーです。
民法上は退職の2週間前までに申し出ればよいとされていますが、円満な退職を目指すなら、会社の就業規則を確認し、引き継ぎ期間も考慮して退職希望日の1〜2ヶ月前には伝えるのが一般的です。
その際に、ステップ2で算出した最終出社日と退職日を伝え、残りの有給休暇を消化したい旨を明確に申し出ます。
誠意ある態度で交渉に臨むことが、円滑な合意形成につながります。
会社から有給消化を拒否された場合の対処法
労働者の権利である有給休暇の消化を会社が拒否するケースは、残念ながら存在します。
引き継ぎや人手不足を理由に難色を示されることがありますが、法的には退職時の有給消化を会社側は拒めません。
もし拒否された場合でも、感情的にならず冷静に対処することが重要です。
まずは法的な根拠を示して交渉し、それでも解決しない場合は、労働基準監督署などの外部機関に相談するという段階的な対応を検討します。
ここでは、具体的な対処法を順に解説していきます。
会社側は原則として有給取得を拒否できないことを伝える
もし上司や会社から有給消化を拒まれた場合、まずは冷静に、有給休暇の取得が労働基準法で認められた労働者の権利であることを伝えましょう。
具体的には、労働基準法第39条を根拠に、会社は労働者からの申し出を原則として拒否できないと定められています。
会社側が主張する可能性がある「時季変更権」は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ行使できる権利ですが、これはあくまで取得時期をずらすためのものです。
退職日を超えて時期を変更することはできないため、退職を控えた従業員の有給消化申請に対しては適用されないという点を、落ち着いて説明することが有効です。
引き継ぎや人手不足を理由にされたら退職日の再調整を提案する
会社が有給消化を拒否する理由として、引き継ぎが完了しない、あるいは人手不足といった業務上の懸念が挙げられることがよくあります。
このような場合、一方的に権利を主張するのではなく、歩み寄りの姿勢を見せることも円満解決の一つの方法です。
例えば、引き継ぎが不十分であると指摘された際には、最終出社日を少し後ろ倒しにして引き継ぎ期間を十分に確保する、あるいは有給消化期間中に限定的ながら連絡が取れる体制を整えるといった代替案を提案してみましょう。
会社側の事情に配慮する姿勢を示すことで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
消化しきれない有給休暇の買い取りを交渉する
法律上、会社に有給休暇を買い取る義務はありません。
しかし、会社との合意があれば、退職時に消化できない有給休暇を買い取ってもらうことは可能です。
特に、会社側の都合でどうしても有給休暇を消化させることが難しい場合や、引き継ぎが長引いてしまった結果、消化しきれない日数が発生した場合などには、トラブルを避けるために会社側が買い取りに応じるケースがあります。
ただし、これはあくまで交渉の選択肢の一つであり、強制力はありません。
買い取りを希望する場合は、1日あたりの買い取り金額なども含めて、会社側と話し合う必要があります。
トラブルが解決しない場合は労働基準監督署へ相談する
会社との話し合いを重ねても有給消化が認められずトラブルが解決しない場合は、最終手段として労働基準監督署へ相談することを検討します。
労働基準監督署は、労働基準法などの法令に基づいて企業を監督・指導する行政機関です。
有給休暇を取得させないことは労働基準法違反にあたるため、相談すれば会社に対して是正勧告などの行政指導を行ってくれる可能性があります。
相談に行く際は、これまでの会社とのやり取りの経緯を時系列でまとめたメモや、メール、録音などの客観的な証拠を持参すると、状況を正確に伝えられ、よりスムーズに相談が進みます。
退職時の有給消化に関するよくある質問
退職に際して有給休暇を消化するにあたり、多くの人がさまざまな疑問を抱きます。
例えば、有給消化中にボーナスはもらえるのか、転職活動はしてもよいのか、あるいは残日数が非常に多い場合や、派遣社員の場合の扱いはどうなるのか、といった点です。
これらの疑問を解消しておくことで、より安心して退職手続きを進めることができます。
ここでは、退職時の有給消化に関して頻繁に寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすく回答します。
Q. 有給消化期間中にボーナス(賞与)は支給されますか?
ボーナスが支給されるかどうかは、会社の就業規則や賃金規程に定められている「支給日在籍要件」によります。
多くの会社では、「賞与支給日に在籍していること」を支給の条件としています。
そのため、有給消化期間中であっても、賞与の支給日に会社に在籍していれば、原則として受け取る権利があります。
ただし、ボーナスの金額は査定期間中の勤務評価や出勤日数に基づいて算定されるため、査定期間の途中で最終出社日を迎えた場合などには、満額ではなく減額された金額が支給される可能性があります。
Q. 有給消化をしながら転職活動をしても問題ありませんか?
有給消化期間中に転職活動を行うことは法的に何ら問題ありません。
在籍中ではありますが業務からは離れているため面接などの時間を自由に確保しやすくなります。
この期間は次のキャリアに向けた準備を進める絶好の機会と捉えることができます。
ただし注意点として現在の会社の機密情報を漏洩したり競合他社に不利益をもたらすような行為を行ったりすることは就業規則違反や後のトラブルにつながるため厳に慎むべきです。
退職後の円満な関係を維持するためにも社会人としての節度ある行動が求められます。
Q. 残りの有給が40日以上ある場合でもすべて消化できますか?
年次有給休暇の時効は2年であるため、前年度からの繰り越し分を合わせると、残日数が労働基準法上の年間最大付与日数である20日を超える、例えば40日以上になるケースも十分にあり得ます。
法律上、労働者は保有するすべての有給休暇を取得する権利があるため、残日数が40日以上であっても、すべて消化してからの退職は可能です。
ただし、長期間の有給消化となるため、後任者への引き継ぎ期間を十分に確保する必要があります。
円満な退職のためには、できるだけ早い段階で上司に退職の意向を伝え、退職日や最終出社日について計画的に相談・調整を進めることが不可欠です。
Q. 有給消化中に次の会社でアルバイトはできますか?
有給消化期間中は、まだ現在の会社に在籍している状態です。
多くの会社の就業規則では、副業や兼業を禁止、あるいは許可制としています。
そのため、現在の会社に無断で次の会社や別の場所でアルバイトを始めると、就業規則違反に問われる可能性があります。
もしアルバイトを検討している場合は、まず現在の会社の就業規則を確認することが重要です。
規則で禁止されている、または許可が必要とされている場合には、トラブルを避けるためにも、正式な退職日以降に勤務を開始するのが最も安全な選択です。
まとめ
退職時に有給休暇をすべて消化することは、法律で認められた労働者の権利です。
円満に退職するためには、まず自身の有給残日数を確認し、引き継ぎ期間を考慮した上で最終出社日と退職日を決定するという計画的な準備が重要になります。
退職届の書き方としては、有給消化の希望を明記する方法があり、本記事で紹介したテンプレートを参考にすることで、意思を明確に伝えられます。
会社との交渉では、一方的に権利を主張するだけでなく、誠実な対話を心がけることが円滑な手続きにつながります。
万が一、有給消化を拒否されるなどのトラブルが発生した場合は、法的な対処法も理解しておくことで、安心して対応できます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部教員からの転職で後悔しない!異業種・ITのおすすめ転職先15選
教員を辞めて、異業種やIT業界への転職を考える先生が増えています。 長時間労働や特有の人間関係から解放され、新たなキャリアを築きたいと願うものの、教員を辞… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自己紹介で使える面白い項目ネタ10選!ウケる・滑らない例文付き
初対面の場で自分を印象付けたいとき、自己紹介に「おもしろ」要素を加えるのは有効な手段です。 ありきたりな内容では、大勢の中に埋もれてしまいがちですが、少… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部繁忙期の反対語は閑散期。意味や使い方、言い換えまで分かりやすく解説
ビジネスシーンで頻繁に耳にする「繁忙期」という言葉ですが、その正確な意味や使い方、そして反対語を正しく理解しているでしょうか。 繁忙期の反対語は「閑散期… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ひとり起業で成功するには?自宅でできるおすすめビジネスと始め方
ひとり起業は、自分の裁量で自由に働ける魅力的な選択肢です。 特に近年は、インターネットを活用することで、自宅で始められるビジネスが増え、未経験からひとり… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部仕事ができる人の特徴と考え方|できない人との決定的な違いも解説
周囲から高い評価を受ける「仕事ができる人」には、共通する特徴や考え方が存在します。 本記事では、具体的な行動特性や思考のパターンを多角的に分析し、仕事の… 続きを読む