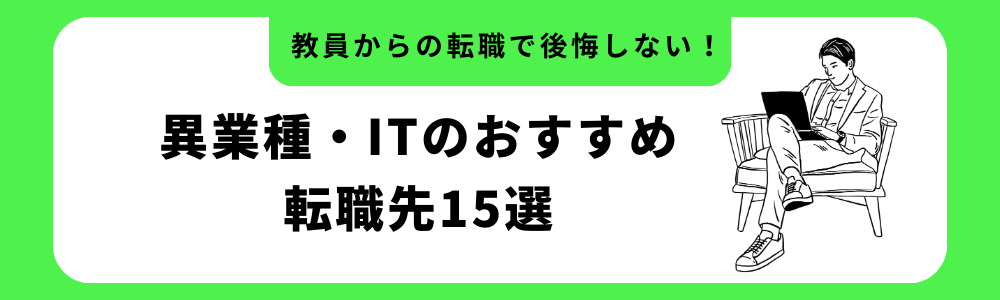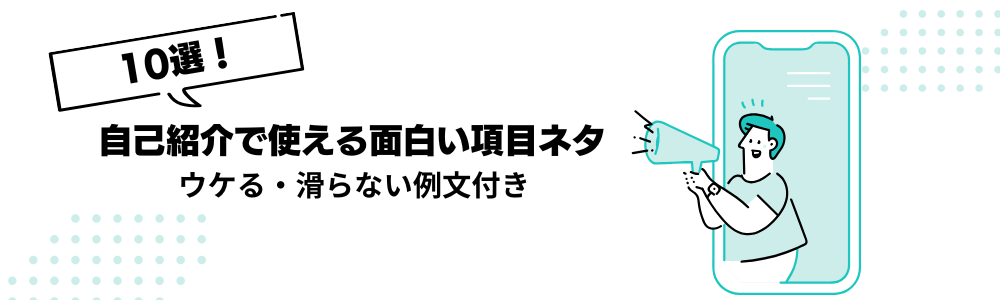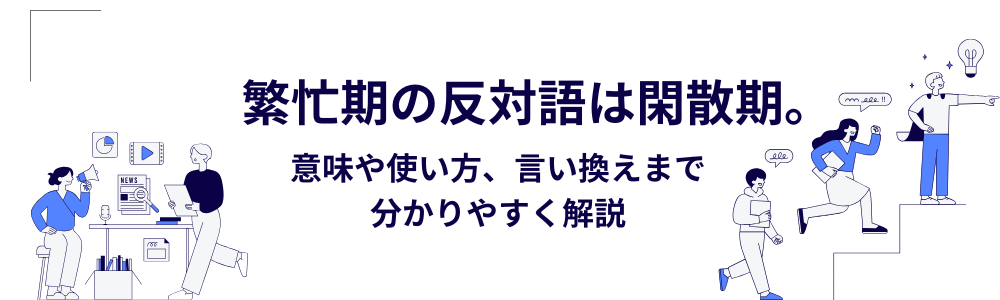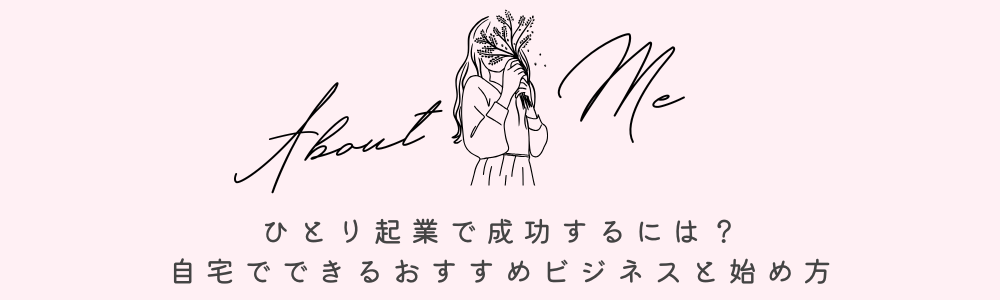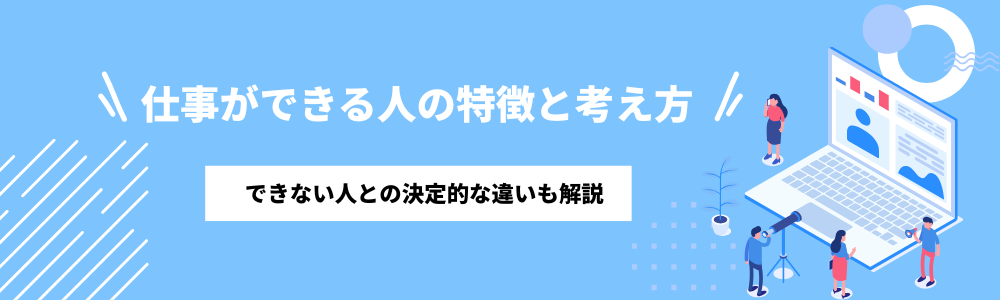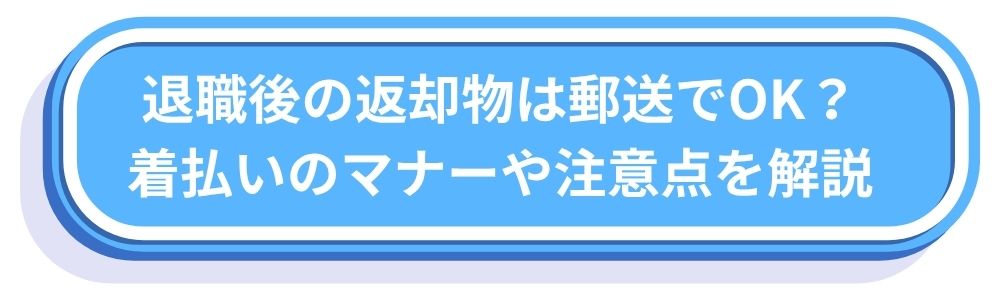

退職後の返却物は郵送でOK?着払いのマナーや注意点を解説
退職後の返却物は郵送でOK?着払いのマナーや注意点を解説
退職後は健康保険証や社員証、会社から貸与された備品など、多くの返却物があります。
最終出社日に直接返却するのが基本ですが、難しい場合は郵送でも対応可能です。
しかし、郵送する際には送料の負担や梱包方法、添え状の有無など、守るべきマナーが存在します。
後々のトラブルを避け、円満に退職手続きを終えるために、正しい返却方法と注意点を事前に確認しておきましょう。
退職時に会社へ返さなければいけないもの一覧
退職する際には、会社から貸与された様々な物品を返却する義務があります。
返却するものには、身分証明書から業務で使用した貸与品、制服などの服装まで多岐にわたります。
返却漏れは会社に迷惑をかけるだけでなく、トラブルの原因にもなりかねません。
貸与された者本人が責任を持って、このリストを参考に、返却すべきものを正確に把握し、漏れがないか最終チェックを行いましょう。
健康保険証や社員証などの身分証明書
健康保険証は、退職日の翌日から使用できなくなるため、速やかに返却しなければなりません。
扶養家族がいる場合は、その家族の分の保険証も忘れずにまとめて返却します。
誤って退職後に使用すると、医療費の返還義務が生じるため注意が必要です。
社員証や入館証、社章、名札なども会社の所有物であり、身分を証明するものなので必ず返却します。
これらは悪用されるリスクもあるため、郵送する際は普通郵便ではなく、配達記録が残る簡易書留などで送るのが確実です。
会社から支給された自分の名刺
在職中に使用していた自分の名刺は、たとえ残っていたとしても会社の所有物です。
退職後はその会社の一員ではなくなるため、手元に残った名刺はすべて返却する必要があります。
また、業務上受け取った取引先の名刺も、会社の顧客情報という重要な資産にあたるため、私物化せずに必ず会社へ返却、または後任者へ引き継ぎます。
会社の情報を持ち出すことは情報漏洩につながるため、個人情報保護の観点からも厳重な取り扱いが求められます。
クリーニングが必要な会社の制服
会社から制服や作業着、ユニフォームなどを貸与されていた場合、それらも返却対象です。
会社の備品であるため、長年使用して汚れている場合は、感謝の気持ちを込めてクリーニングに出してから返却するのが社会人としてのマナーです。
ただし、会社によってはクリーニングが不要であったり、会社側でまとめて業者に依頼したりする規定があることも考えられます。
自己判断せず、就業規則を確認するか、事前に上司や総務担当者にクリーニングの要否を確認しておきましょう。
業務で使用したパソコンやスマートフォンなどの貸与品
業務で使用していたノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ポケットWi-Fiといった電子機器は、すべて返却の対象です。
これらの貸与品は会社の資産であり、重要な情報が含まれているため、取り扱いには細心の注意を払います。
返却前には、必ず個人のデータやファイル、履歴などを完全に消去し、業務関連のデータは後任者や担当部署へ適切に引き継ぎます。
充電器やケーブル、マウスといった付属品も忘れずに揃え、一式をまとめて返却するようにしましょう。
経費で購入した事務用品や備品
ボールペンやノート、ファイル、電卓など、会社の経費で購入した事務用品や書籍も、原則としてすべて会社の備品です。
退職時には、自分のデスク周りやロッカーを整理し、これらの備品を然るべき場所へ戻します。
どこまでが返却対象になるか判断に迷う消耗品については、自己判断で持ち帰ったり処分したりせず、上司や担当者に確認することが大切です。
会社の備品を無断で持ち帰ると、横領とみなされる可能性もあるため、慎重に対応しましょう。
仕事で作成した書類やデータ
在職中に作成した企画書、報告書、顧客リスト、設計図といった紙媒体の書類や、USBメモリなどに保存した電子データは、すべて会社の業務上の成果物であり、知的財産です。
したがって、これらの所有権は会社に帰属するため、退職時に必ず会社へ返却するか、適切に引き継がなければなりません。
私物のパソコンで作成したデータであっても、業務に関連する情報は会社の資産です。
退職後にこれらの情報を保持し続けることは情報漏洩にあたり、重大なトラブルに発展するリスクがあります。
退職後の返却物を郵送する際の基本マナー
やむを得ない事情で最終出社日に返却物を返せない場合、後日郵送での返し方が認められることがあります。
その際は、いつまでに、どこへ送るべきか事前に会社へ確認が必要です。
送料を自己負担するのか、会社負担の着払いで良いのかも必ず確認しましょう。
また、ただ品物を送るだけでなく、添え状(送付状)を同封するのがビジネスマナーです。
指定された日までに届くよう、余裕を持って発送しましょう。
送料は自己負担(元払い)が原則
退職に際して発生する返却物の郵送費用は、自己都合で退職する場合、返却する側が負担する「元払い」が原則です。
会社から特に指示がない限り、着払いで送付するのはマナー違反と受け取られる可能性があります。
着払いは受け取り側に金銭的負担と手間をかけさせることになるため、円満退職を目指す上では避けるべきです。
配送業者に荷物を預ける際に元払いの伝票を使用し、丁寧な対応を心がけることで、最後まで良好な関係を保つことにつながります。
会社に着払いで送って良いか事前に確認する
送料は自己負担が基本ですが、会社によっては着払いを指示されることもあります。
例えば、会社都合による退職や、返却物の量が多くて送料が高額になる場合、会社側が返却を急いでいるケースなどです。
そのため、郵送での返却が決まったら、まずは上司や人事部の担当者に「送料は着払いで送付させていただいてよろしいでしょうか」と、メールなどで事前に確認を取りましょう。
許可を得た場合はその指示に従い、許可がない場合は元払いで送るのが適切な対応です。
郵送先は人事部など担当部署を必ず確認する
返却物を郵送する際は、送付先の部署や担当者を正確に確認することが非常に重要です。
一般的には本社の人事部や総務部が窓口になることが多いですが、所属していた支社や特定の担当者宛てに送るよう指示される場合もあります。
宛先を間違えると、社内での確認や転送に時間がかかり、返却手続きが遅延する原因になります。
最悪の場合、輸送中に紛失するリスクも考えられるため、部署名だけでなく、担当者名まで確認しておくとより確実です。
感謝の気持ちが伝わる添え状を同封する
返却物を郵送する際には、品物だけを送りつけるのではなく、添え状(送付状)を同封するのが社会人としてのマナーです。
添え状には、宛先、自分の氏名・連絡先、送付日、時候の挨拶、同封した返却物の品名と数量を記載したリスト、そして在職中のお礼などを簡潔に記します。
これにより、誰から何が届いたのかが一目で分かり、会社側の確認作業がスムーズになります。
書式は手書きでもパソコン作成でも構いませんが、感謝の気持ちを伝えることを意識しましょう。
【品物別】安全に返却物を郵送するための梱包・発送方法
返却物を郵送する際には、輸送中に品物が破損したり、個人情報が漏洩したりするリスクを考慮しなければなりません。
特に、健康保険証などの重要書類やパソコンなどの精密機器は、その特性に合わせた梱包と発送方法を選ぶことが不可欠です。
適切な方法を選択することで、会社に迷惑をかけることなく、安全かつ確実に返却物を届けることができます。
ここでは、品物別に具体的な梱包・発送のポイントを解説します。
重要書類(健康保険証など)は追跡可能な書留で送る
健康保険証や社員証、機密情報を含む書類など、紛失や悪用のリスクがある重要書類は、普通郵便で送るべきではありません。
必ず、荷物の引き受けから配達までを記録し、追跡サービスで配送状況を確認できる方法を選びます。
具体的には、郵便局の「簡易書留」や「レターパックプラス(対面受け取り)」などが適しています。
これにより、万が一の郵便事故のリスクを低減でき、相手に確実に届いたことを確認できます。
発送した際の控えは、会社から受領連絡があるまで大切に保管しておきましょう。
制服や備品はダンボールで丁寧に梱包する
制服やパソコン、事務用品などをまとめて郵送する場合は、輸送中の衝撃で破損しないよう、丁寧に梱包することが求められます。
クリーニング済みの制服はきれいに畳んで水濡れ防止のビニール袋に入れ、パソコンなどの精密機器は気泡緩衝材で厳重に包みます。
これらを適切な大きさのダンボール箱に詰め、品物同士がぶつからないよう隙間に丸めた新聞紙などの緩衝材を詰めて固定します。
箱の表面には「ワレモノ注意」や「精密機器」といったシールを貼ると、より安全な配送につながります。
返却物をなくしてしまった場合の正しい対処法
退職準備を進める中で、会社から貸与されていた備品などを紛失してしまったことに気づく場合があります。
このような事態では慌ててしまいがちですが、事実を隠したり放置したりすることは、問題をさらに深刻化させるだけです。
発覚した時点で正直に報告し、誠実に対応することが、トラブルを最小限に抑え、円満退職を実現するために最も重要です。
ここでは、返却物を紛失した場合の適切な対処法を解説します。
気づいた時点ですぐに上司や担当者へ報告・相談する
会社からの貸与品を紛失したことに気づいたら、その時点ですぐに直属の上司や人事部の担当者に報告し、謝罪することが最優先です。
報告が遅れるほど、会社側の対応も遅れ、心証も悪くなります。
「いつ、どこで紛失した可能性があるか」といった状況を正直に伝え、その後の対応について指示を仰ぎましょう。
特に社員証や健康保険証、機密情報が入ったUSBメモリなどの場合は、悪用を防ぐために緊急の利用停止手続きが必要になることもあるため、一刻も早い報告が求められます。
会社の備品を紛失した場合は弁償を求められる可能性も
紛失した物品によっては、会社から弁償を求められることがあります。
特にノートパソコンやスマートフォンなどの高価な貸与品や、会社の信用に関わるものをなくした場合は、その可能性が高まります。
弁償の要否や金額については、就業規則や貸与品に関する誓約書に定められていることが一般的です。
ただし、故意や重大な過失がなければ、減価償却を考慮した価格が適用され、全額請求されるケースは少ないです。
自己判断で同じものを購入したりせず、まずは会社の指示に従い誠実に対応することが重要です。
退職時に会社から受け取るべき重要書類リスト
退職手続きにおいては、会社へ物品を返却するだけでなく、会社から「返却されるもの」や新たに発行される書類を受け取ることも同様に重要です。
これらの書類は、失業保険の給付手続きや転職先での社会保険手続き、税金の確定申告など、退職後の生活に不可欠なものばかりです。
受け取り漏れがあると後の手続きが大幅に遅れる可能性があるため、何をいつ受け取るべきか事前にリストアップして確認しておきましょう。
転職や失業保険の手続きに必要な「離職票」
離職票は、正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、ハローワークで失業保険(基本手当)の受給手続きをする際に必ず必要となる書類です。
退職理由や退職前の賃金などが記載されています。
通常、退職日から10日〜2週間ほどで会社から郵送されてきます。
転職先が既に決まっている場合は不要ですが、万が一に備えて受け取っておくと安心です。
もし指定の期間を過ぎても届かない場合は、速やかに人事部や総務部に問い合わせましょう。
年末調整で使う「源泉徴収票」
源泉徴収票は、その年に会社から支払われた給与や賞与の総額と、天引きされた所得税額が記載された書類です。
年内に転職する場合、新しい勤務先で年末調整を行うために提出が必須となります。
年内に再就職しない場合でも、自身で確定申告を行う際に必要です。
通常、最後の給与支払日以降に発行され、退職後1ヶ月以内に郵送されるのが一般的です。
退職者への発行は法律で定められた会社の義務なので、必ず受け取れます。
会社に預けていた「年金手帳」
年金手帳は、基礎年金番号が記載された公的年金の加入証明書です。
入社時に厚生年金への加入手続きのため会社に預けている場合、退職時に返却されます。
転職先が決まっている場合は新しい会社に提出し、国民年金に切り替える場合は市区町村の役場で手続きを行う際に必要です。
現在は「基礎年金番号通知書」に切り替わっていますが、年金手帳も引き続き有効です。
もし紛失した場合は、年金事務所で再発行が可能です。
雇用保険の手続きに使う「雇用保険被保険者証」
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類で、被保険者番号が記載されています。
入社時に会社から渡され、そのまま会社で保管されていることが多いため、退職時に返却されるのが一般的です。
この書類は、転職先での雇用保険加入手続きや、ハローワークでの失業保険受給手続きの際に必要となります。
もし退職時に受け取れなかったり、紛失してしまったりした場合は、ハローワークで再発行の手続きができます。
まとめ
退職時には、会社への返却物と会社から受け取る書類があり、どちらも漏れなく対応することが重要です。
返却物を郵送する際は、自己判断で進めず、まず会社に送料の負担や送付先を確認するのが基本です。
その上で、元払いでの発送や添え状の同封といったビジネスマナーを守ることで、良好な関係を保ったまま退職手続きを完了できます。
返却物の紛失など不測の事態が起きた際も、速やかに報告・相談することで、問題の拡大を防げます。
退職後の手続きをスムーズに進めるため、返すべきものと受け取るべきものを正確に把握し、計画的に準備を進めましょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部教員からの転職で後悔しない!異業種・ITのおすすめ転職先15選
教員を辞めて、異業種やIT業界への転職を考える先生が増えています。 長時間労働や特有の人間関係から解放され、新たなキャリアを築きたいと願うものの、教員を辞… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自己紹介で使える面白い項目ネタ10選!ウケる・滑らない例文付き
初対面の場で自分を印象付けたいとき、自己紹介に「おもしろ」要素を加えるのは有効な手段です。 ありきたりな内容では、大勢の中に埋もれてしまいがちですが、少… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部繁忙期の反対語は閑散期。意味や使い方、言い換えまで分かりやすく解説
ビジネスシーンで頻繁に耳にする「繁忙期」という言葉ですが、その正確な意味や使い方、そして反対語を正しく理解しているでしょうか。 繁忙期の反対語は「閑散期… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ひとり起業で成功するには?自宅でできるおすすめビジネスと始め方
ひとり起業は、自分の裁量で自由に働ける魅力的な選択肢です。 特に近年は、インターネットを活用することで、自宅で始められるビジネスが増え、未経験からひとり… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部仕事ができる人の特徴と考え方|できない人との決定的な違いも解説
周囲から高い評価を受ける「仕事ができる人」には、共通する特徴や考え方が存在します。 本記事では、具体的な行動特性や思考のパターンを多角的に分析し、仕事の… 続きを読む