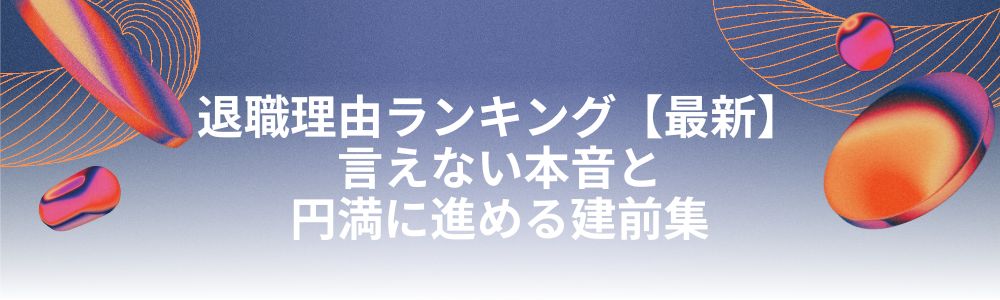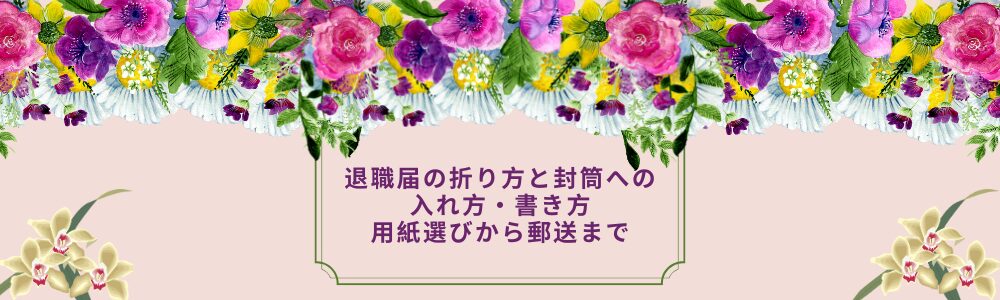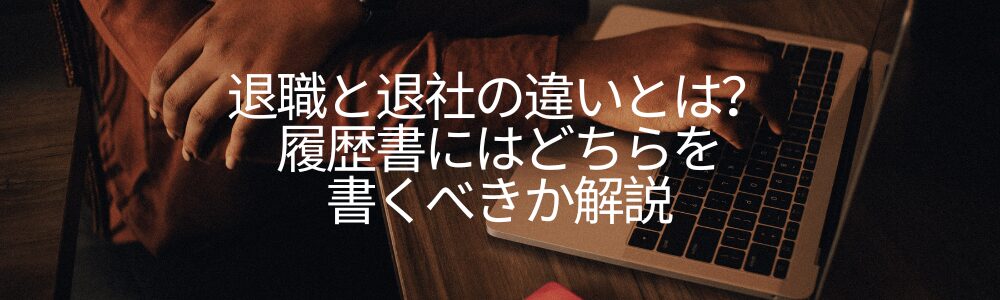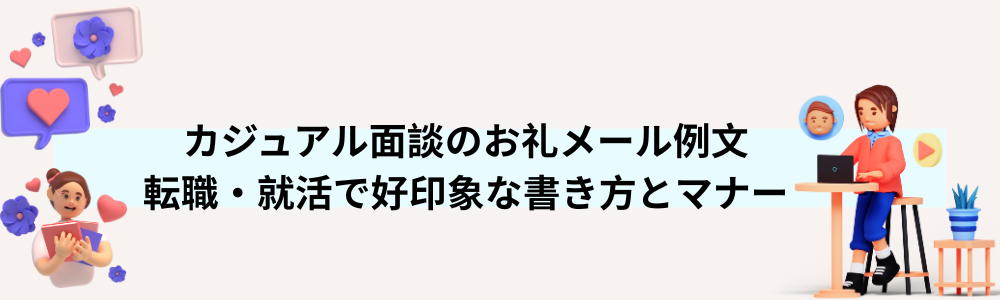

カジュアル面談のお礼メール例文|転職・就活で好印象な書き方とマナー
カジュアル面談は、選考前に企業と候補者が互いを理解する貴重な機会です。
面談後には、時間を割いてくれた担当者への感謝の気持ちを伝えるため、カジュアル面談のお礼メールを送ることが推奨されます。
お礼メールを送る一手間が、転職や就活において採用担当者に好印象を与え、その後の選考を有利に進めるきっかけになり得ます。
本記事では、カジュアル面談のお礼メールの書き方やマナー、具体的な例文を解説し、効果的なアピール方法を紹介します。
カジュアル面談後にお礼メールは送るべき?送付が推奨される3つの理由
カジュアル面談後に、お礼のメールを送るべきか迷う人もいるかもしれません。
選考ではないため必須ではありませんが、基本的には送ることを推奨します。
お礼メールの送付は、ビジネスマナーとして丁寧な印象を与えるだけでなく、入社意欲をアピールする機会にもなります。
感謝の気持ちを伝えることは、相手との良好な関係構築の第一歩であり、送っておいて損はありません。
後から送らなかったことを後悔しないためにも、特別な理由がなければ送付を検討しましょう。
理由1:面談の時間を設けてくれたことへの感謝を伝えられるため
採用担当者は、日常業務と並行して面談の時間を作っています。
お礼メールを送ることで、自分のために時間を割いてくれたことへの感謝の意を明確に示せます。
これは、社会人としての基本的なマナーであり、相手への配慮ができる人物であるという印象を与えます。
特にカジュアル面談は、企業側が候補者のために設ける特別な場であることが多いため、感謝を伝えることは非常に重要です。
丁寧な言葉で感謝の気持ちを表現することにより、誠実な人柄が伝わり、コミュニケーション能力の高さも評価される可能性があります。
理由2:入社意欲の高さや誠実な人柄をアピールできるため
お礼メールは、面談の場では伝えきれなかった入社への熱意を改めてアピールできる効果的な手段です。
面談で感じた魅力や、自身の経験をどのように活かしたいかなどを具体的に記述することで、企業への関心が本物であることを示せます。
文章の内容や言葉遣いからは、その人の人柄がにじみ出るものです。
誤字脱字がなく、丁寧な言葉で書かれたメールは、仕事においても誠実で真摯に取り組む人物であるという印象を与えます。
メールという手軽な手段でありながら、自己PRの機会として有効に活用できます。
理由3:採用担当者の記憶に残りやすくなり、好印象を与えられるため
採用担当者は、日々多くの候補者と面談を行っているため、一人ひとりの印象が薄れてしまうことも少なくありません。
そのような状況で、面談後に心のこもったお礼メールが届けば、他の候補者との差別化を図ることができます。
特に、面談の内容に具体的に触れた感想が書かれていると、「自社に本当に関心を持ってくれている」と受け取られ、記憶に残りやすくなります。
ポジティブな印象とともに名前を覚えてもらうことで、その後の選考プロセスにおいても有利に働く可能性が高まります。
【基本構成】カジュアル面談のお礼メールに盛り込むべき6つの要素
カジュアル面談のお礼メールを作成する際は、決まった基本構成に沿って書くと、要点がまとまり読みやすくなります。
ビジネスメールのマナーを押さえた構成は、採用担当者に内容をスムーズに伝える上で不可欠です。
件名、宛名、挨拶、本文、結び、署名の6つの要素を漏れなく含めることで、丁寧で分かりやすいメールが完成します。
この構成は一種のテンプレとして活用できるため、初めてお礼メールを書く人でも安心して作成に取り組めるでしょう。
件名:用件と氏名が一目でわかるように記載する
採用担当者は毎日多くのメールを処理しているため、件名を見ただけで「誰から」「何の用件で」来たメールなのかが瞬時にわかるように記載することが重要です。
具体的で分かりやすい件名にすることで、他のメールに埋もれて見落とされるリスクを減らせます。
例えば、「〇月〇日のカジュアル面談のお礼(〇〇大学氏名)」や「カジュアル面談の御礼/氏名」のように、用件と自分の名前を簡潔に記載します。
このように配慮された件名は、相手の時間を尊重する姿勢の表れともなり、ビジネスマナーを心得ているという評価にもつながります。
宛名:会社名・部署名・担当者名を正確に書く
宛名は、メールの冒頭で相手を指定する重要な部分であり、正確性が求められます。
会社名は「株式会社」と正式名称で記載しましょう。
部署名や担当者の氏名も、面談時にもらった名刺などを確認し、一字一句間違えないように入力します。
もし担当者の部署名や氏名が不明な場合は、「採用ご担当者様」としても問題ありません。
宛名を正確に書くことは、ビジネスマナーの基本であり、相手への敬意を示す第一歩です。
送信前に必ず見直し、間違いがないかを確認する習慣をつけてください。
挨拶:面談の機会をいただいたことへのお礼を述べる
メール本文の書き出しは、面談の機会を設けてくれたことへの感謝の言葉から始めます。
時候の挨拶などは省略し、「お世話になっております。本日カジュアル面談の機会をいただきました、〇〇大学の〇〇です。」といったように、自己紹介と本題を簡潔に述べましょう。
続けて、「本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。」と感謝の意を明確に伝えます。
この最初の挨拶で、丁寧な姿勢を示すことが、その後の本文をスムーズに読んでもらうための導入となります。
本文:面談で心に残ったことや今後の意気込みを伝える
本文は、お礼メールの中で最も重要な部分であり、自身の個性や熱意を伝える絶好の機会です。
単に感謝を述べるだけでなく、面談で特に印象に残った話や、それを通じて企業への理解がどのように深まったかを具体的に記述します。
例えば、担当者の話した事業内容や企業文化に関するエピソードに触れ、それに共感した点などを述べると、真剣に話を聞いていた姿勢が伝わります。
さらに、面談を経て入社意欲が高まったことや、今後の選考へ進みたいという前向きな気持ちを伝えることで、効果的な自己アピールができます。
結びの言葉:今後の活躍を祈る言葉や返信不要の旨を添える
本文を書き終えたら、結びの言葉でメールを締めくくります。
「末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」といったように、相手企業の発展を願う一文を入れるのが一般的です。
これに加えて、「ご多忙と存じますので、ご返信には及びません。」という一文を添えることも重要です。
この気遣いの一言があることで、採用担当者が返信する手間を省くことができ、相手への配慮ができる人物であるという好印象を与えられます。
ビジネスメールにおける締め方のマナーとして覚えておくと良いでしょう。
署名:自身の氏名や大学名、連絡先を明記する
メールの最後には、自分が何者であるかを明確にするための署名を必ず記載します。
署名には、氏名、大学名・学部・学科、そして電話番号やメールアドレスといった連絡先を正確に含めます。
これにより、採用担当者がメールの内容を確認した後、すぐに連絡を取りたいと思った場合でもスムーズに対応できます。
署名はビジネスメールの基本マナーであり、記載がないと相手に不便をかける可能性があります。
あらかじめメールソフトの署名設定機能でテンプレートを作成しておくと、記載漏れを防ぐことができて便利です。
採用担当者に好印象を与える!お礼メール作成で意識したい3つのポイント
お礼メールの基本構成を押さえるだけでなく、さらに採用担当者に良い印象を残すためには、いくつかのポイントを意識することが効果的です。
メールを送るタイミングや内容の具体性、そして細部への配慮が、他の候補者との差別化につながります。
企業側の担当者がどのようなメールを受け取ると「この人と一緒に働きたい」と感じるかを想像しながら作成することが、好印象を与える鍵となります。
以下の3つのポイントを実践し、丁寧で心のこもったお礼メールを目指しましょう。
ポイント1:面談当日、もしくは翌日の午前中までに送信する
お礼メールは、面談の記憶が新しいうちに送るのが最も効果的です。
理想的なタイミングは、面談当日の就業時間内、もしくは遅くとも翌日の午前中です。
時間が経つほど面談の印象は薄れてしまうため、迅速に送ることで、感謝の気持ちや入社意欲の強さを伝えられます。
いつ送るか迷った場合は、できるだけ早く行動に移すことを心がけてください。
ただし、深夜や早朝の送信は相手の迷惑になる可能性があるため、企業の就業時間内に着信するよう、送信予約機能を活用するなどの配慮も必要です。
ポイント2:定型文だけでなく、面談内容を踏まえた具体的な感想を盛り込む
テンプレートをそのまま利用したような当たり障りのない内容では、採用担当者の心には響きません。
お礼メールで差をつけるためには、自分の言葉で具体的な感想を述べることが不可欠です。
面談の中で特に印象的だった話、共感した企業の価値観、新たに発見した事業の魅力など、固有名詞や具体的なエピソードを交えて記述しましょう。
これにより、「しっかりと話を聞き、自社について深く理解しようとしてくれている」という姿勢が伝わり、入社への本気度が高いと評価されます。
ポイント3:誤字脱字や敬語の間違いがないか送信前に必ず見直す
誤字脱字や敬語の誤用は、注意力やビジネスマナーに対する評価を下げてしまう原因になります。
どれだけ内容が素晴らしくても、基本的なミスがあると「仕事においてもケアレスミスが多いのではないか」という懸念を抱かれかねません。
メールを作成したら、すぐに送信ボタンを押すのではなく、必ず声に出して読み返すなどして、文章に違和感がないかを確認しましょう。
特に、会社名や担当者名の間違いは大変失礼にあたるため、細心の注意を払ってチェックする習慣をつけてください。
【状況別】そのまま使えるカジュアル面談のお礼メール例文3選
カジュアル面談後の状況は、選考に進みたい、辞退したい、もう少し考えたいなど、人によってさまざまです。
ここでは、それぞれの状況に応じたお礼メールの書き方を、具体的な例文を交えて解説します。
紹介する例文はあくまで一例であり、これを基に自分の言葉で面談の感想や気持ちを付け加えることで、より気持ちの伝わるメールになります。
特に中途採用の場合は、職務経験と結びつけた内容を盛り込むと効果的です。
自身の状況に合わせて適切にカスタマイズして活用してください。
例文1:選考への参加を前向きに希望する場合
選考への参加を希望する場合は、面談への感謝とともに、その意欲をストレートに伝えることが重要です。
面談を通じて企業のどのような点に魅力を感じ、入社意欲が高まったのかを具体的に記述します。
例えば、「〇〇という事業ビジョンのお話に深く共感し、ぜひ貴社の一員として貢献したいという思いが強くなりました」のように、心に響いたポイントを挙げましょう。
そして、「今後の選考にもぜひ参加させていただきたく存じます」と、次のステップに進みたい意思を明確に示します。
前向きで熱意のある姿勢は、採用担当者にポジティブな印象を与えます。
例文2:選考を丁寧に辞退したい場合
面談の結果、選考を辞退することにした場合でも、時間を割いてくれたことへの感謝を伝えるのが社会人としてのマナーです。
メールの冒頭で、まずは面談の機会をいただいたことへのお礼を述べます。
その上で、「慎重に検討を重ねました結果、今回は選考を辞退させていただきたく存じます」と、辞退の意思を丁寧に伝えます。
辞退の理由を詳細に説明する必要はありません。
「諸般の事情により」といった表現で十分です。
誠実な対応を心がけることで、企業との良好な関係を保つことができ、将来的なキャリアで再び接点を持つ可能性も残せます。
例文3:選考に進むかじっくり検討したい場合
面談後、すぐには結論が出せず、選考に進むかどうかを検討したい場合もあるでしょう。
その際は、正直にその旨を伝えることが大切です。
まず、面談の機会を設けてくれたことへの感謝を述べ、非常に有意義な時間であったことを伝えます。
その上で、「お話を伺い、貴社への理解を深めることができましたが、自身のキャリアについて改めて考える時間をいただきたく存じます」といった形で、検討中であることを正直に、かつ丁寧に伝えます。
いつ頃までに返答できるか目安を示せると、より誠実な印象を与えられます。
送信前にチェック!カジュアル面談のお礼メールで避けたいNG例
良かれと思って送ったお礼メールが、かえってマイナスの印象を与えてしまうケースも存在します。
採用担当者に「配慮が足りない」「ビジネスマナーが身についていない」と思われないよう、送信前には必ず内容をチェックすることが重要です。
ここでは、カジュアル面談のお礼メールで特に注意したいNG例を3つ紹介します。
これらのポイントを確認し、自身のメールが当てはまっていないか、最終確認の項目として活用してください。
NG例1:どの企業にも送れるような抽象的な内容になっている
本日は貴重なお話をありがとうございました。貴社の事業内容に大変魅力を感じました。といった、どの企業にも当てはまるような抽象的な文章だけでは、採用担当者の心に響きません。
このような内容は、テンプレートを使い回しているだけだと見なされ、入社意欲が低いと判断される可能性があります。
その企業ならではの魅力や、面談で聞いた具体的な話に触れることで、自社のために書かれたメールであることが伝わり、熱意を効果的にアピールできます。
必ず、その面談でしか書けないオリジナルの内容を盛り込みましょう。
NG例2:面談で話した雑談や個人的な話がメインになっている
カジュアル面談の和やかな雰囲気から、趣味や出身地などの雑談で盛り上がることもあるかもしれません。
しかし、お礼メールはあくまでビジネス文書です。
面談で話した雑談や個人的なエピソードばかりをメールに書いてしまうと、公私の区別ができない、ビジネスマナーに欠ける人物という印象を与えかねません。
親しみを込めたつもりが、馴れ馴れしいと受け取られるリスクもあります。
本文の中心は、あくまで企業の事業や仕事に関する内容とし、雑談に触れる場合はごく簡潔に留めるのが賢明です。
NG例3:改行が少なく、長文で読みにくいメールになっている
伝えたいことが多いあまり、文章が長くなり、改行のないメールを送ってしまうのは避けるべきです。
特にスマートフォンでメールを確認する採用担当者も多いため、文字が詰まった長文メールは非常に読みにくく、内容が伝わる前に読むのをやめられてしまう可能性もあります。
伝えたい要点は簡潔にまとめ、3〜4行に一度は改行を入れる、話題が変わる部分で段落を分けるなど、読みやすさを意識したレイアウトを心がけてください。
相手への配慮が感じられる読みやすいメールは、それだけで好印象を与えます。
カジュアル面談のお礼メールに関するよくある質問
カジュアル面談のお礼メールを作成する上で、細かな疑問や判断に迷う場面が出てくることもあります。
担当者の名前がわからない場合や、複数の担当者がいた場合の対応など、具体的なシチュエーションでどう振る舞うべきかを知っておくと、よりスムーズで適切な対応が可能です。
ここでは、多くの就職・転職活動者が抱きがちな質問とその回答をまとめました。
これらのQ&Aを参考に、自信を持ってメールを送付しましょう。
Q1. 担当者の氏名や部署がわからない場合はどうすれば良い?
面談時に名刺をもらえなかったり、担当者の名前を失念してしまったりした場合、宛名の書き方に迷うことがあります。
そのような場合は、無理に個人名を記載せず、「株式会社〇〇採用ご担当者様」や「人事部採用ご担当者様」といった形で、部署名や役職で記載するのが最も無難な対処法です。
もし面談の調整をしてくれた担当者が別にいるのであれば、その方宛にメールを送り、面談担当者への謝意を伝えてもらうようお願いする形も丁寧な方法です。
不明なまま憶測で名前を書くことは避けましょう。
Q2. 担当者が複数いた場合、メールは全員に送るべき?
面談の担当者が複数名いた場合、全員の連絡先を知っているのであれば、連名で一通のメールを送るのが基本です。
宛名には役職が上の方から順に名前を記載し、TO(宛先)に主担当者を、CCにその他の方々を入れます。
もし代表者1名の連絡先しかわからない場合は、その方宛にメールを送り、本文中に「〇〇様、〇〇様にも、くれぐれもよろしくお伝えください」といった一文を添えましょう。
この一言があるだけで、同席した全員への配慮を示すことができ、丁寧な印象を与えます。
Q3. 企業からお礼メールに返信が来たら、さらに返信は必要?
お礼メールに対して企業側から返信が来た場合、そのメールに「ご返信には及びません」といった記載があれば、そこでやり取りを終えるのがマナーです。
特に記載がない場合は、メールをいただいたことへのお礼として、簡潔に返信するのが丁寧な対応とされます。
ただし、その際も「お忙しいと存じますので、本メールへのご返信は不要です」と一言添え、こちらからやり取りを締めくくる気遣いを見せましょう。
メールの往復が何度も続くと相手の負担になるため、簡潔に終わらせることが肝心です。
まとめ
カジュアル面談後のお礼メールは、面談の機会を設けてくれた企業への感謝を示すとともに、入社意欲や人柄をアピールする重要なコミュニケーションツールです。
面談の記憶が新しいうちに、当日か翌日の午前中までに送付することが効果的です。
メールを作成する際は、定型文に頼るのではなく、面談で心に残った具体的なエピソードや感想を自分の言葉で盛り込むことで、他の候補者との差別化が図れます。
送信前には誤字脱字や敬語の誤りがないかを必ず確認し、ビジネスマナーを守った丁寧な対応を心がけてください。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む