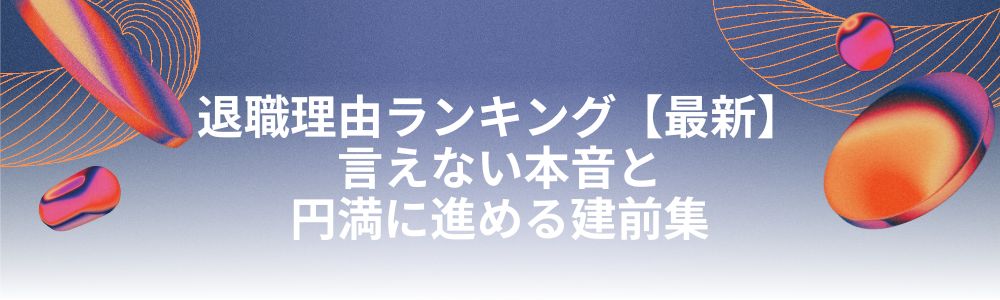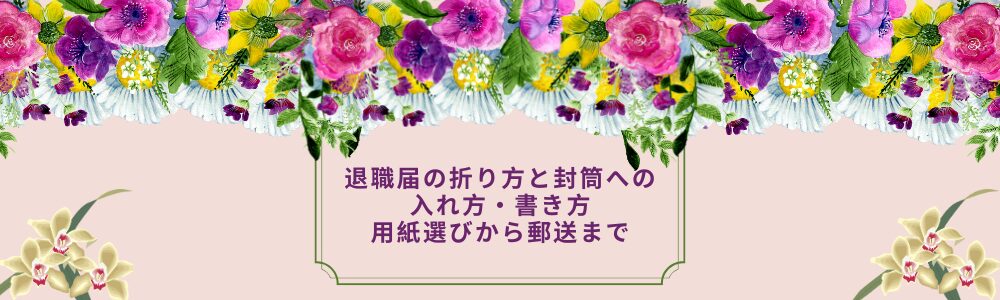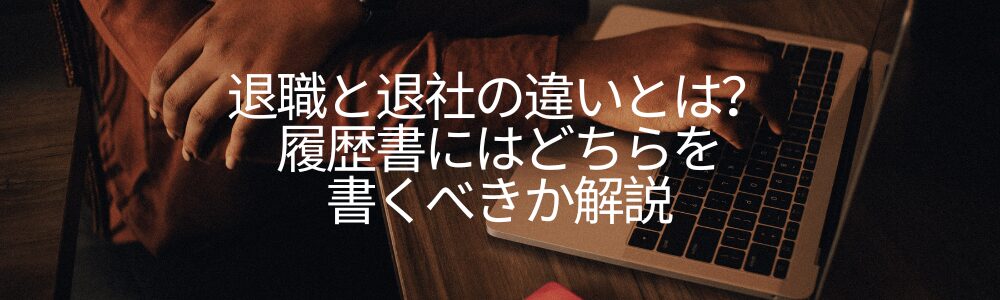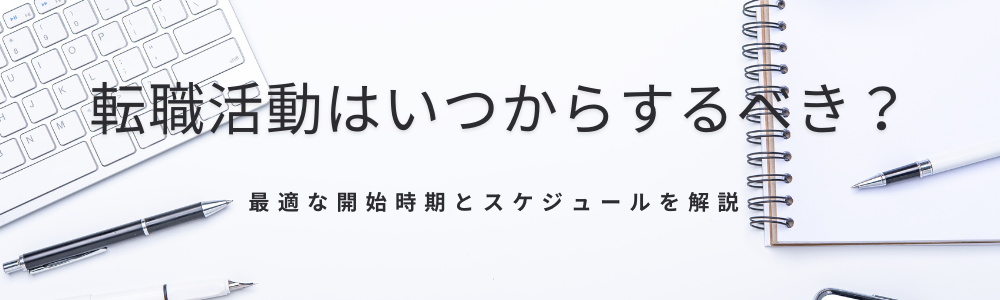

転職活動はいつからするべき?最適な開始時期とスケジュールを解説
転職を考え始めたとき、「いつから活動を始めるべきか」は多くの人が悩むポイントです。
転職活動は、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要するため、やみくもに始めるのではなく、いつから始めるかを希望する入社時期から逆算して計画的に進めることが成功の鍵となります。
求人が増える時期や自身のキャリアプランを考慮し、最適なタイミングを見極めることで、納得のいく転職を実現しやすくなります。
転職活動にかかる期間は平均3〜6ヶ月が目安
転職活動にかかる期間は、自己分析や情報収集といった準備段階から、応募、選考、内定、そして退職手続きを経て新しい会社に入社するまで、平均して3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。
もちろん、この期間は個人の状況や希望する業界、職種によって変動します。
すぐに内定が出る場合もあれば、納得のいく企業と出会うまで半年以上かかるケースも少なくありません。
焦らずじっくり取り組むためにも、ある程度の期間を見越して計画を立てることが重要です。
転職活動の始め方|入社希望時期から逆算した5ステップ
転職活動は、収入が途絶えるリスクを避けるため、可能な限り在職中に進めるのが一般的です。
希望する入社時期から逆算し、各ステップに必要な期間を考慮してスケジュールを立てましょう。
例えば、半年後に入社したい場合、今すぐ活動開始の準備に取り掛かる必要があります。
全体の流れを把握し、計画的に行動することで、焦らず着実に転職活動を進めることが可能になります。
具体的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:自己分析とキャリアの棚卸し(1週間〜1ヶ月)
転職活動で最初に行うべきことは、自己分析とキャリアの棚卸しです。
これまでの業務経験を通じて得たスキルや知識、実績を具体的に書き出し、自分の強みや弱みを客観的に把握します。
同時に、どのような仕事にやりがいを感じるのか、将来どのようなキャリアを築きたいのかといった価値観を明確にすることも重要です。
この作業を丁寧に行うことで、企業選びの軸が定まり、応募書類や面接で一貫性のあるアピールをするための土台ができます。
転職の目的を明確にするためにも、この最初のステップを疎かにしないようにしましょう。
ステップ2:求人情報の収集と応募書類の作成(1週間〜1ヶ月)
自己分析で明確になった自身の強みや希望条件を基に、具体的な求人情報を収集します。
転職サイトや企業の採用ページ、転職エージェントなど、複数の情報源を活用して、業界や職種の動向を把握しながら選択肢を広げましょう。
正社員だけでなく、派遣や契約社員といった雇用形態も視野に入れると、キャリアの可能性が広がることがあります。
同時に、これまでの経歴をまとめた職務経歴書と履歴書を作成します。
応募する企業に合わせて内容を調整できるよう、基本となるフォーマットを準備しておくと効率的です。
本格的な就職活動の基盤となります。
ステップ3:求人への応募と選考(1ヶ月〜2ヶ月)
興味のある求人が見つかったら、作成した応募書類を送付してエントリーします。
書類選考を通過すると、面接へと進むのが一般的な流れです。
面接は、一次、二次、最終と複数回行われることが多く、すべての選考プロセスが完了するまでには1ヶ月から2ヶ月程度かかることも珍しくありません。
選考期間が長引くことや、不採用となる可能性も考慮し、複数の企業に並行して応募を進めるのが効率的です。
それぞれの企業の選考スケジュールを管理しながら、面接対策をしっかりと行い、本番に臨むことが求められます。
ステップ4:内定獲得から承諾までの手続き(1週間〜2週間)
最終面接を通過すると、企業から内定の連絡があります。
内定通知を受けたら、まず労働条件通知書で給与や勤務地、休日、残業時間といった条件を詳細に確認することが不可欠です。
提示された内容に不明な点や交渉したい項目があれば、この段階で確認や相談を行います。
内定を承諾するかどうかの回答期限は、一般的に1週間程度とされています。
複数の企業から内定を得た場合は、それぞれの条件や自身のキャリアプランを慎重に比較検討し、最終的な入社先を決定します。
焦らず、納得のいく決断を下しましょう。
ステップ5:現職の退職交渉と業務引継ぎ(1ヶ月〜2ヶ月)
転職先への入社を承諾したら、現在の職場に退職の意思を伝えます。
法律上は退職日の2週間前までに伝えればよいとされていますが、円満退職のためには、会社の就業規則に定められた期間(多くは1ヶ月以上前)に従うのが一般的です。
直属の上司に、まずは口頭で退職の意思と希望退職日を伝えましょう。
退職が承認されたら、後任者への業務引継ぎを計画的に進めます。
引継ぎ資料の作成や、関係各所への挨拶なども含め、最終出社日まで責任を持って業務を遂行することが、社会人としてのマナーです。
【求人が多い】転職活動におすすめの時期は年2回
転職活動を始めるタイミングとして、企業の求人数が増加する時期を狙うのも有効な戦略です。
一般的に、1月から3月と7月から9月の年2回、採用市場が活発化する傾向にあります。
この時期は、企業の採用計画に基づいて多くのポジションが募集されるため、希望に合う求人が見つかる可能性が高まります。
自身の準備状況と市場の動向を照らし合わせ、戦略的に活動を開始することで、より多くの選択肢の中から転職先を検討できます。
1月〜3月:年度末に向けた増員や欠員補充が活発化する時期
1月から3月は、4月からの新年度に向けて企業の採用活動が最も活発になる時期です。
多くの企業が新年度の事業計画に基づいて増員を図るほか、年度末での退職者による欠員を補充する必要があるため、求人数が大幅に増加します。
様々な業界・職種で募集が行われるため、転職希望者にとっては選択肢が広がる大きなチャンスとなります。
ただし、同時に応募者も増えるため、競争が激しくなる傾向があります。
他の候補者との差別化を図るためにも、自己分析や企業研究といった事前準備を念入りに行い、自身の強みを的確にアピールすることが求められます。
7月〜9月:下半期に向けた採用計画が本格化する時期
7月から9月も、転職市場が活発になる時期の一つです。
多くの企業では10月から下半期が始まるため、それに向けた組織体制の強化や事業拡大に伴う増員募集が増加します。
また、夏のボーナスを受け取ってから退職する人が増えるため、その欠員補充を目的とした求人も出てきます。
上半期の業績を踏まえて、急遽採用計画が変更されることもあります。
1月から3月の時期ほどではありませんが、この期間も多様な求人が市場に出回るため、転職を考えている人にとっては積極的に活動しやすいタイミングと言えるでしょう。
転職活動を始める際に注意したい時期
求人が増える時期がある一方で、企業の採用活動が一時的に落ち着く、あるいは選考スピードが遅くなりがちな時期も存在します。
具体的には、新年度の対応で忙しい4月・5月や、年末年始で企業活動がスローダウンする11月・12月が挙げられます。
これらの時期に活動することが一概に悪いわけではありませんが、一般的な傾向として知っておくことで、より効率的な転職活動のスケジュールを組むことが可能になります。
4月・5月:新卒採用や組織再編で採用担当者が多忙な傾向
4月は多くの企業で新卒社員が入社する時期であり、人事・採用担当者は入社式や新人研修の対応に追われます。
また、新年度に伴う組織再編や異動も重なるため、部署全体が多忙を極める傾向にあります。
こうした背景から、中途採用に関する業務の優先順位が下がり、書類選考や面接の日程調整に通常より時間がかかることがあります。
5月もその影響が続く場合や、大型連休を挟むことで選考プロセスが停滞しがちです。
この時期は、すぐに結果が出なくても焦らず、情報収集や自己分析に時間を充てるのが賢明かもしれません。
11月〜12月:年末年始で企業の採用活動が落ち着く傾向
11月の後半から12月にかけては、多くの企業が年末年始の繁忙期や長期休暇に向けて業務を調整するため、採用活動が落ち着く傾向にあります。
採用担当者や面接官も通常業務が忙しくなり、面接の日程調整が難しくなったり、選考結果の連絡が遅れたりすることが増えます。
また、選考プロセスが年をまたいでしまうケースも少なくありません。
この時期に転職活動を進める場合は、選考に時間がかかることをあらかじめ想定しておく必要があります。
一方で、ライバルが少ないこの時期を狙うという考え方もありますが、年明けの活発な時期に向けて準備を整える期間と捉えるのも良いでしょう。
あなたはいつから始めるべき?転職を考えるきっかけ別のタイミング
求人が多い時期に合わせて動くことも一つの方法ですが、転職の最適なタイミングは人それぞれ異なります。
「スキルアップが見込めない」「正当に評価されていない」など、現状に対する具体的な課題意識が芽生えたときこそが、行動を起こすきっかけとなります。
自身のキャリアやライフプランと向き合い、主体的に動くことが、後悔のない転職につながります。
ここでは、転職を考えるきっかけ別に、活動を始めるタイミングについて解説します。
今の仕事でスキルアップが見込めないと感じたとき
日々の業務がルーティン化し、新しい知識やスキルの習得機会がない、あるいは成長している実感を得られないと感じたときは、転職を考える一つのタイミングです。
自身のキャリアプランを考えた際に、現在の職場で目標とする姿に近づけないと判断した場合、より挑戦的な環境や専門性を高められる職場を探す必要が出てきます。
まずは現職で部署異動を希望したり、新たな役割を担えないか上司に相談したりするのも一つの手です。
それでも状況が変わらないようであれば、自身の市場価値を確かめる意味でも、外部の求人情報に目を向けてみるのが良いでしょう。
給与や評価制度に不満を感じ始めたとき
自身の業務成果や貢献度が、給与や昇進といった評価に適切に反映されていないと感じる場合、転職が解決策の一つとなります。
特に、保育士などの専門職では、業務の責任や負担に対して待遇が見合わないと感じ、より良い条件を求めて職場を変えるケースも少なくありません。
ただし、一時的な感情で行動するのは避けるべきです。
まずは業界の給与水準や自身のスキルに見合った市場価値を客観的に調査し、現職での昇給交渉の余地がないかを確認しましょう。
その上で、より正当な評価を得られる企業への転職を検討するのが賢明な判断です。
会社の将来性や経営方針に疑問を抱いたとき
所属している会社の業績が悪化したり、事業の方向性が大きく変わったりして、将来性に不安を感じたときも転職を検討するタイミングです。
経営陣が打ち出す方針に共感できず、仕事へのモチベーションが維持できなくなった場合も同様です。
会社の状況は個人の力で変えることが難しいため、自身のキャリアを守るという観点から、新たな環境を探すことが有効な選択肢となります。
すぐに転職活動を始めなくとも、業界の動向を注視し、情報収集を開始することで、いざという時に迅速に行動できるよう備えておくことが重要です。
ライフステージの変化があったとき(結婚・出産など)
結婚や出産、子育て、家族の介護など、ライフステージの変化は働き方を見直す大きなきっかけとなります。
例えば、産後や育休中に復職後のキャリアについて考え、これまでと同じように働くことが難しいと感じた場合、より柔軟な勤務時間やリモートワークが可能な企業への転職を検討するのも一つの選択です。
将来のライフプランを見据え、プライベートと仕事を両立できる環境を求めることは、長期的なキャリア形成において非常に重要です。
家族との時間を大切にしながら、自身のキャリアも継続していけるような働き方を探してみましょう。
より良い労働環境を求めているとき
慢性的な長時間労働、休日出勤の多さ、ハラスメントが横行している、あるいは職場の人間関係に深刻なストレスを感じているなど、労働環境に問題がある場合は、自身の心身の健康を守るために転職を検討すべきです。
我慢を続けても状況が改善する見込みが薄いのであれば、より健全な環境で働ける場所を探すことが最優先されます。
ワークライフバランスを保ち、安心して業務に集中できる職場に移ることで、仕事のパフォーマンスが向上し、結果としてキャリアにも良い影響を与えることが期待できます。
【年代別】転職活動を始めるタイミングの考え方
転職活動では、年代によって企業から期待される役割やスキルが異なります。
そのため、自身の年齢やキャリアステージに合わせた戦略を立てることが成功の鍵となります。
例えば、ポテンシャルが重視される第二新卒を含む20代と、即戦力としての実績が求められる30代、マネジメント能力が問われる40代以降とでは、アピールすべきポイントや活動の進め方が大きく変わってきます。
ここでは、年代別の転職活動の考え方について解説します。
20代:ポテンシャルを武器にキャリアチェンジも視野に入れる
20代の転職では、これまでの経験や実績以上に、今後の成長可能性、いわゆるポテンシャルや学習意欲が重視される傾向にあります。
特に社会人経験の浅い入社1年目などの場合は、基本的なビジネスマナーや仕事へのスタンスが評価の対象となります。
経験が少ない分、未経験の業界や職種へのキャリアチェンジに挑戦しやすいのがこの年代の強みです。
これまでの経験を振り返りつつも、将来どのようなキャリアを築きたいかを明確にし、その実現に向けた熱意や意欲をアピールすることが、転職成功の鍵となります。
30代:即戦力としてのスキルや実績をアピールする
30代の中途採用では、企業は即戦力となる人材を求める傾向が強まります。
そのため、これまでのキャリアで培ってきた専門的なスキルや、具体的な業務実績を明確にアピールすることが不可欠です。
自分がその企業に入社したら、どのような形で貢献できるのかを、過去の経験に基づいて具体的に説明する必要があります。
リーダーやマネジメントの経験があれば、それは大きな強みとなります。
自身のスキルや経験を客観的に棚卸しし、応募先企業が求める人物像と合致する部分を的確に伝える戦略が求められます。
40代以降:マネジメント経験や専門性を活かす
40代以降の転職では、高度な専門性や、チームや組織を率いてきたマネジメント経験が求められます。
これまでのキャリアでどのような課題を解決し、組織に貢献してきたのか、具体的な実績を交えて説得力のある説明ができなければなりません。
求人数は若年層に比べて限られてくるため、自身の市場価値を正確に把握し、これまでの経験を最大限に活かせるポジションを戦略的に探す必要があります。
豊富な正社員経験を通じて培った知見や人脈も、大きな武器となり得ます。
転職活動を始める前に押さえておきたい3つの注意点
転職活動を成功に導くためには、勢いで行動するのではなく、いくつかの重要なポイントを事前に押さえておく必要があります。
なぜ転職したいのかという目的を明確にすること、現職を辞めるタイミングを見極めること、そして利用できるサービスを賢く活用すること。
これらの準備と思慮深さが、後悔のない転職につながります。
ここでは、活動を始める前に特に注意したい3つの点について解説します。
なぜ転職したいのか目的を明確にする
転職活動を始めるにあたり、最も重要なのは「なぜ転職したいのか」という目的を明確にすることです。
「給与が低い」「人間関係が悪い」といった現状への不満を洗い出すだけでなく、転職によって何を実現したいのか、どのような働き方をしたいのかというポジティブな目標を設定することが肝心です。
目的が曖昧なまま活動を進めると、企業選びの軸がぶれてしまい、目先の条件だけで転職先を決めて後悔する可能性があります。
自身のキャリアプランと向き合い、転職の軸をしっかりと定めることが、成功への第一歩となります。
退職の意思は内定を獲得してから伝える
在職しながら転職活動を行う場合、現在の職場に退職の意思を伝えるタイミングは非常に重要です。
原則として、転職先から正式な内定通知を受け、労働条件などを確認して入社を承諾した後に、現職の上司に退職を申し出るようにしましょう。
先に退職の意思を伝えてしまうと、もし転職活動が長引いた場合に収入が途絶え、焦りから不本意な転職先を選んでしまうリスクが生じます。
また、会社から強い引き留めにあったり、退職日までの期間を気まずい雰囲気で過ごしたりすることにもなりかねません。
円満退職のためにも、手順とタイミングは慎重に守るべきです。
転職エージェントを有効活用して効率化を図る
在職中の転職活動は、時間的な制約の中で情報収集や面接日程の調整を行う必要があり、一人で進めるのは大変です。
そこで有効活用したいのが、転職エージェントです。
キャリアの相談から非公開求人の紹介、応募書類の添削、面接対策、さらには企業との条件交渉まで、転職活動のあらゆるプロセスを無料でサポートしてくれます。
いつから活動を始めるべきか迷っている段階でも、専門のキャリアアドバイザーに相談することで、客観的なアドバイスを得られます。
効率的に活動を進めるためにも、積極的に利用を検討すると良いでしょう。
まとめ
転職活動をいつから始めるべきかについて、決まった正解はありません。
企業の求人が増える1月~3月や7月~9月といった市場の動向と、自身のキャリアプランや転職を考えるきっかけとなった個人のタイミングを総合的に判断することが重要です。
一般的に活動期間は3~6ヶ月を見込むため、希望する入社時期から逆算して計画的に活動開始の準備を進める必要があります。
転職の目的を明確にし、自己分析を徹底した上で、必要に応じて転職エージェントなどの外部サービスも活用しながら、自身のキャリアにとって最善のタイミングを見極めてください。
転職活動を始めるベストなタイミングは、「転職で何を目指すか」によって異なります。一般的には、4月入社を目指す場合は半年前の10月頃から準備をスタートするのが理想です。平均すると、内定獲得までに3〜6ヵ月ほどかかるため、スムーズな転職をするには早めの行動がポイントとなります。特に中途採用市場では、企業の採用ターンが年度や繁忙期と連動しており、年度末や夏季休暇前などは求人が増える傾向があります。マイナビやリクナビNEXT、エン転職、dodaなどの求人サイトを定期的にチェックし、募集動向を見ることで、自分に合ったタイミングを見極めることができます。転職活動を早めにやるメリットは、応募先を比較検討できる余裕が生まれ、面接準備や書類作成も丁寧に進められる点です。一方で、在職中の多忙な時期に始めると、面接日程の調整や手続きが難しくなるデメリットもあります。休暇や育休明けなど、自分の生活リズムに合わせて適切な時期を決めることが大切です。転職活動の全体の流れとしては、情報収集→自己分析→書類作成→応募→面接→内定→退職・入社手続きの順で進みます。コンサルティング業界や専門職など、選考期間が長い業種もあるため、余裕を持ったスケジュールを組むのがおすすめです。まとめると、「転職活動は早すぎず遅すぎず」、平均3〜6ヵ月前を目安に準備を始め、目指す入社時期から逆算して動くのが最も適切といえるでしょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む