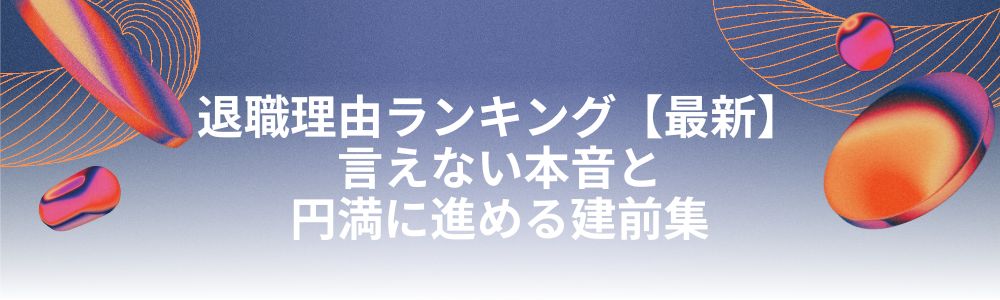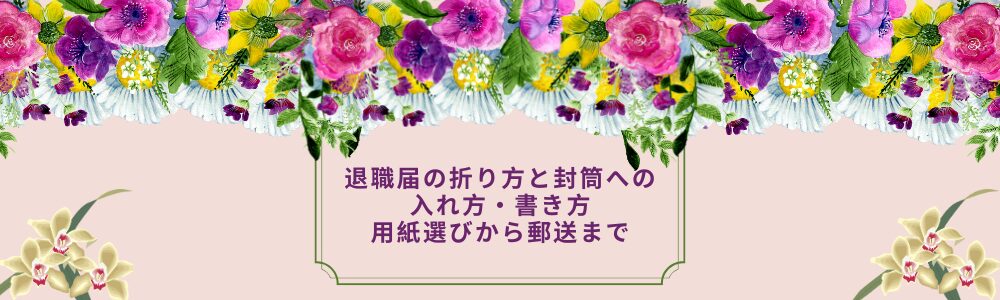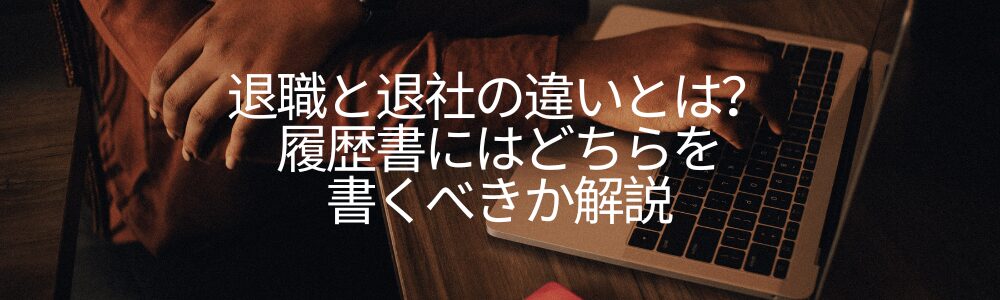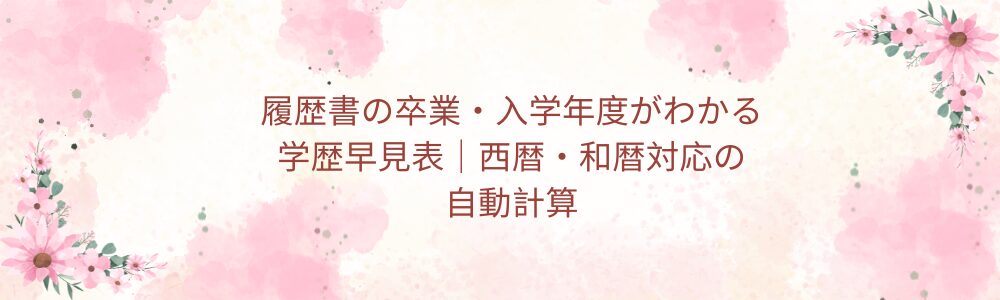

履歴書の卒業・入学年度がわかる学歴早見表|西暦・和暦対応の自動計算
履歴書を作成する際に多くの人が迷うのが、「入学・卒業年度をどう記入すればいいのか」という点です。
「いつ入学したか忘れてしまった」「卒業した年の西暦や和暦が分からない」といった悩みは珍しくありません。
この記事では、生まれ年や年齢から簡単に卒業年度を確認できる卒業年度早見表を紹介します。
正確な情報を把握しておくことで、履歴書の学歴欄をスムーズに記入できます。
この早見表を活用して、誤りのない履歴書を完成させましょう。
生年月日を入力するだけ!入学・卒業年度の自動計算ツール
自身の生年月日と最終学歴を入力すると、小学校から大学院までの入学・卒業年度が自動で計算されるツールです。
浪人や留年を経験した場合でも、その年数を入力すれば対応した年度が算出されます。
早見表と合わせて活用することで、履歴書の学歴欄をいつからでも正確に、かつ効率的に作成できます。
卒業がいつだったか忘れてしまった場合に、手軽に確認できる便利な機能です。
【生まれ年別】入学・卒業年度がひと目でわかる学歴早見表
自身の生まれ年から、各学歴の入学・卒業年度を一覧で確認できる早見表です。
小学校から大学院まで、浪人や留年がない場合の標準的な卒業年を記載しています。
西暦と和暦の両方に対応しているため、履歴書のフォーマットに合わせて転記が可能です。
自身の生まれ年が含まれる項目を参照し、学歴欄の作成に役立ててください。
2000年(平成12年)~生まれの学歴
2000年以降に生まれた世代は、平成後期から令和にかけて学生時代を過ごしています。
例えば、2005年生まれの場合、小学校入学は2012年、中学校入学は2018年です。
高校卒業は2024年3月となります。
この世代は、学歴を記入する際に平成から令和への元号の切り替わりをまたぐことが多く、特に注意が必要です。
例えば、大学の入学が平成31年4月でも、卒業が令和5年3月というケースが該当します。
早見表を利用して、平成25年や2017年といった特定の年の出来事と照らし合わせながら、正確な情報を記入しましょう。
1990年(平成2年)~1999年(平成11年)生まれの学歴
1990年代生まれの世代は、学生時代のほとんどを平成の期間で過ごしています。
例えば、1995年(平成7年)生まれの場合、高校入学が2011年(平成23年)、大学入学が2014年(平成26年)です。
この年代は、履歴書を記入する際に和暦表記で迷うことは比較的少ないかもしれませんが、西暦と混同しないように注意を払う必要があります。
平成8年や平成9年生まれなど、自身の生まれ年を基準に、小学校から最終学歴までの流れを一度書き出してみると、間違いを防げます。
特に転職活動で久しぶりに履歴書を作成する場合、卒業から年数が経過しているため、早見表での確認が有効です。
1980年(昭和55年)~1989年(平成元年)生まれの学歴
1980年代生まれの世代は、昭和から平成へと元号が変わる時期に学生時代を送っています。
例えば、1981年(昭和56年)生まれの場合、小学校入学は1988年(昭和63年)4月となり、在学中に平成へと改元されました。
このように、入学時と卒業時で元号が異なるケースが発生するため、履歴書作成時には西暦と和暦の対応を正確に確認することが重要です。
1980年(昭和55年)生まれは、高校卒業が1999年(平成11年)3月です。
特に昭和生まれの場合、和暦の計算が複雑に感じられることもあるため、西暦で統一して記入するのも一つの方法です。
1970年(昭和45年)~1979年(昭和54年)生まれの学歴
1970年代生まれの世代は、学生時代の多くを昭和の期間で過ごしています。
例えば、1977年(昭和52年)生まれの場合、小学校入学が1984年(昭和59年)、中学校入学が1990年(平成2年)となり、中学校以降の学歴は平成で記載します。
この世代も、学歴の途中で昭和から平成への改元を経験しているため、和暦で記入する際は注意が必要です。
1979年(昭和54年)生まれの場合、大学卒業は2002年(平成14年)3月となります。
卒業から時間が経過していることも多いため、記憶に頼るだけでなく、卒業証明書や卒業アルバムなどで正確な年月日を確認し、早見表と照らし合わせるのが確実です。
履歴書の学歴欄を作成する前に押さえるべき基本ルール
履歴書の学歴欄は、単に入学・卒業の事実を並べるだけでなく、採用担当者に分かりやすく伝えるための基本的な書き方のルールが存在します。
表記の統一や正しい元号の使い方、どこから学歴を記載するかなど、細かな点に配慮することで、丁寧で正確な印象を与えられます。
特に卒業月は、特別な事情がない限り学校教育法に基づき3月と記載するのが一般的です。
西暦か和暦のどちらかに表記を統一する
履歴書を作成する際、学歴や職歴欄の日付表記は西暦か和暦のどちらかに統一するのが基本です。
例えば、学歴を和暦で書いたにもかかわらず、職歴を西暦で記載すると、採用担当者が時系列を把握しにくくなります。
どちらの表記法を選ぶかは個人の自由ですが、一般的に外資系企業やIT業界では西暦が好まれる傾向にあります。
一方、官公庁や歴史の長い国内企業では和暦がなじみ深い場合もあります。
応募する企業の文化に合わせて選択するのも良いですが、最も重要なのは履歴書全体で表記を統一することです。
生年月日や資格取得年月日なども含め、一貫性を持たせましょう。
「H」や「R」など元号のアルファベット表記は避ける
履歴書は公的な書類であるため、元号をアルファベットで省略して表記するのは避けるべきです。
「H31年」や「R5年」といった書き方は、ビジネスマナーに欠けると判断される可能性があります。
必ず「平成31年」「令和5年」のように、漢字で正式に記載します。
これは学歴欄に限らず、職歴や資格欄など、履歴書内のすべての元号表記に共通するルールです。
細かい部分ですが、書類作成における丁寧さや正確さを示す上で重要なポイントとなります。
採用担当者にマイナスの印象を与えないよう、正式名称での記述を徹底しましょう。
令和1年は「元年」と記載するのが正しい書き方
元号が切り替わった初めの年は、「1年」ではなく「元年」と表記するのが正式な書き方です。
例えば、2019年5月1日から始まった令和の場合、履歴書には「令和元年」と記載します。
同様に、昭和や平成の初めの年も「昭和元年」「平成元年」と書きます。
なお、2019年は4月30日までが平成31年であったため、同年内の日付を記載する際は注意が必要です。
例えば、2019年3月の卒業であれば「平成31年3月」となりますが、同年5月以降の出来事については「令和元年」を使用します。
このように、元号をまたぐ年の学歴や職歴を記入する際は、月日を正確に確認しましょう。
義務教育は省略し高校入学から書くのが一般的
履歴書の学歴欄は、いつから書くかという明確な決まりはありませんが、一般的には高等学校の入学から記載します。
小学校や中学校は義務教育課程にあたり、卒業していることが前提となるため、通常は記載を省略します。
最終学歴が中学校卒業の場合は、中学の卒業年月を記載した上で、その後の職歴を記述します。
学歴をいつから書くか迷った場合は、高校入学から書き始めるのが無難です。
小学校や中学校の経歴を書かないことで、採用担当者が学歴の要点を把握しやすくなり、読みやすい履歴書になります。
中途退学した経歴も年月と合わせて明記する
大学や高校を中途退学(中退)した場合、その経歴も学歴欄に正確に記載する必要があります。
入学した年月日を記載した次の行に、中退した年月日と「中途退学」と明記します。
日付の年数は正確に、年月まで記載するのが基本です。
中退の事実はネガティブに捉えられるのではないかと懸念する人もいますが、記載しないと学歴に空白期間が生まれ、経歴詐称を疑われる可能性があります。
家庭の事情や経済的な理由、あるいは新たな目標のためなど、やむを得ない理由がある場合は、備考欄や自己PR欄で簡潔に補足説明することも可能です。
正直に事実を伝えることが信頼につながります。
履歴書の学歴欄でよくある疑問を解消
履歴書の学歴欄を作成していると、浪人や留年、卒業見込みの場合など、書き方に迷うケースが出てきます。
また、最終学歴の定義や、アルバイト経験を学歴に含めるべきかといった疑問も生じやすい点です。
ここでは、そのような個別の状況に応じた正しい書き方や考え方を解説し、学歴欄に関する悩みを解消します。
浪人や留年した場合の書き方は?
浪人や留年をした場合でも、その事実を履歴書に直接記載する必要はありません。
学歴欄には、入学と卒業の年月を事実通りに書くだけで問題ありません。
例えば、1年浪人して大学に入学した場合、高校卒業から大学入学までの間に1年間の空白期間ができますが、これが浪人期間を示唆します。
留年した場合も同様で、入学から卒業までの期間が標準年数より長くなることで表現されます。
採用担当者は卒業までの年数を見て状況を理解するため、あえて「浪人」「留年」と書く必要はなく、事実を時系列に沿って正確に記入することが重要です。
面接で質問された際に、その期間の経験を前向きに説明できるよう準備しておくと良いでしょう。
卒業見込みの場合はどのように記載すれば良い?
在学中の学生が就職活動で履歴書を提出する場合、卒業予定の年月を記載し、学校名の後に「卒業見込み」と書き添えます。
例えば、大学4年生であれば、「令和◯年3月◯◯大学◯◯学部卒業見込み」と記載します。
これは、高校や専門学校に在学中の場合も同様です。
卒業が確定していない段階で「卒業」と記載してしまうと、経歴詐称とみなされる恐れがあるため、必ず「卒業見込み」とします。
すでに卒業単位をすべて取得している場合でも、卒業式を迎えるまではこの表記を使用するのが適切です。
卒業年月は、特別な事情がなければ3月と記載します。
学部や学科名が変わったときはどう書く?
在学中に所属していた学部や学科の名称が、組織改編などによって変更された場合、履歴書には在籍時の正式名称を記載するのが基本です。
卒業証明書に記載されている学部・学科名をそのまま転記するのが最も正確です。
もし、現在の名称を補足したい場合は、在籍時の名称の後に括弧書きで「(現:◯◯学部)」のように書き加えることも可能です。
これにより、採用担当者が現在の大学の情報を確認する際に分かりやすくなります。
ただし、補足は必須ではありません。
まずは卒業証明書に記載された、自身が卒業した時点での正式名称を正しく書くことを優先しましょう。
まとめ
履歴書の学歴欄は、自身の経歴を正確に伝えるための重要な項目です。
入学・卒業年度が分からなくなった場合は、この記事で紹介した自動計算ツールや早見表を活用することで、西暦・和暦の両方で簡単に確認できます。
また、学歴を記載する際は、表記の統一や正しい元号の使用など、基本的なルールを守ることが大切ですす。
中退や浪人といった特殊なケースでも、事実を正直に記載することが信頼につながります。
マイナビなどが提供している履歴書のテンプレートなども参考にしつつ、採用担当者にとって分かりやすく、丁寧な書類作成を心掛けましょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む