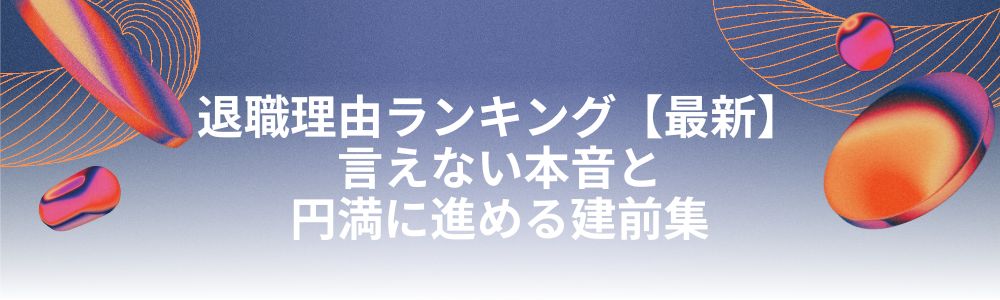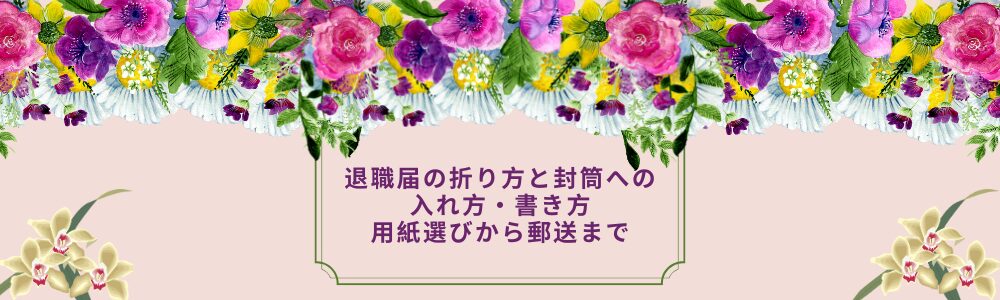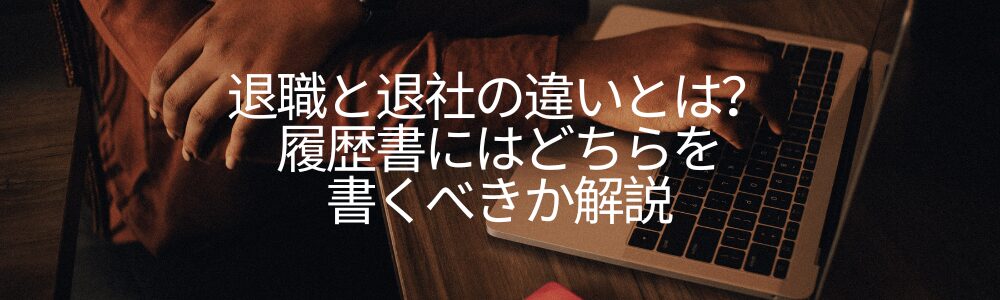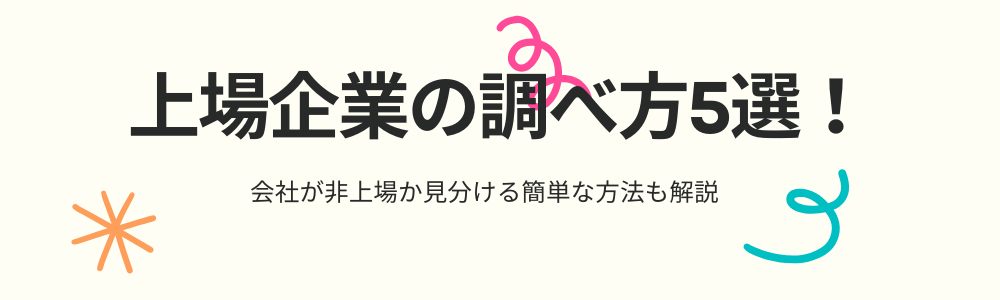

上場企業の調べ方5選!会社が非上場か見分ける簡単な方法も解説
就職や転職活動において、応募先企業が上場しているかどうかは気になる情報の一つです。
上場企業の調べ方には、公式サイトの確認や証券取引所の情報検索など、いくつかの簡単な調べる方法があります。
この記事では、誰でもできる上場企業を調べるための具体的な探し方を解説します。
また、上場企業と非上場企業の違い、それぞれの企業で働くメリット・デメリットについても掘り下げて解説するので、自分に合った会社選びの参考にしてください。
まずは基本から!「上場企業」と「非上場企業」の違いとは
上場企業と非上場企業を分ける最も大きな違いは、その会社の株式が証券取引所で誰でも売買できる状態にあるかどうかです。
上場企業は厳しい審査基準をクリアして株式を公開しており、社会的な信用度が高いと評価されます。
一方、非上場企業は株式を公開しておらず、経営の自由度が高いという特徴があります。
ここでは、それぞれの企業の定義と具体的な違いについて詳しく見ていきます。
証券取引所で株式が売買できるのが「上場企業」
上場企業とは、株式会社が発行する株式を、東京証券取引所などの金融商品取引所で一般の投資家が自由に売買できるように公開している会社のことです。
企業が上場するためには、事業の継続性や収益性、コーポレート・ガバナンスの体制など、証券取引所が定める厳しい審査基準をクリアしなければなりません。
このため、上場しているという事実自体が、社会的な信用の高さを証明する一因となります。
また、上場企業は株主や投資家保護の観点から、経営や財務に関する情報を定期的に開示する義務を負っており、透明性の高い経営が求められます。
株式を自由に売買できないのが「非上場企業」
非上場企業とは、株式を証券取引所に公開しておらず、一般の投資家が市場で自由に株式を売買できない会社を指します。
日本に存在する株式会社の大多数がこの非上場企業に該当し、株式は創業者一族や経営陣、特定の取引先などが保有しているケースが一般的です。
上場していないため、IR情報などの開示義務がなく、外部から経営情報を詳しく調べる方法が限られます。
ただし、非上場だからといって経営規模が小さい、あるいは業績が悪いとは限りません。
独自の技術力を持つ優良企業や、あえて上場を選ばずに自由な経営を維持する大企業も数多く存在します。
そのため、非上場企業について調べるには、公式サイト以外の調べ方が求められます。
【簡単】上場企業かどうかを調べる5つの方法
気になる企業が上場しているか確認したい場合、専門的な知識がなくても簡単に調べることが可能です。
企業の公式ウェブサイトで投資家向けの情報を探したり、証券取引所のデータベースで検索したりする方法は、誰でもすぐに実践できます。
ここでは、信頼性が高く、比較的容易に上場企業かどうかを判断できる具体的な5つの方法を解説します。
これらの方法を知っておけば、企業研究を効率的に進めることができるでしょう。
方法1:企業の公式サイトで「IR情報」を確認する
最も手軽で基本的な確認方法は、対象企業の公式サイトを訪れることです。
上場企業は、株主や投資家に向けて経営状況や財務状況といった情報を公開する義務があります。
そのため、公式サイトには必ず「IR情報」「株主・投資家の皆様へ」といったセクションが設けられています。
このページには、決算短信や有価証券報告書、株価情報などが掲載されています。
もし企業の公式サイトにIR情報の項目が存在し、情報が定期的に更新されていれば、その会社は上場企業であると判断できます。
逆に、この項目が見当たらない場合は、非上場企業である可能性が高いと言えます。
方法2:証券取引所の公式サイトで検索する
日本取引所グループ(JPX)のウェブサイトを利用すれば、国内の上場企業を正確に検索できます。
JPXのサイト内には「上場会社情報検索サービス」があり、会社名や証券コードを入力することで、上場の有無や上場している市場区分(プライム、スタンダード、グロース)などを確認することが可能です。
このデータベースに掲載されている情報は公的で信頼性が非常に高いため、最も確実な調べ方の一つです。
海外の企業に関しても、ニューヨーク証券取引所など、その国を代表する証券取引所の公式サイトで同様に検索することで、上場の事実を確認できます。
方法3:証券会社のウェブサイトで銘柄を検索する
証券会社のウェブサイトや株式取引アプリも、上場企業を調べる上で有効なツールです。
多くのネット証券では、口座を開設していなくても、株式の銘柄検索機能を利用できます。
調べたい会社の名前を入力して検索し、株価やチャート、関連ニュースなどの情報が表示されれば、その会社は上場していると判断できます。
証券会社のツールは、リアルタイムの株価情報や詳細な企業データも併せて確認できるため、企業分析をさらに深めたい場合にも役立ちます。
手軽にアクセスできるため、スマートフォンなどから素早く確認したいときに便利な方法です。
方法4:書籍やWeb版の「会社四季報」で調べる
東洋経済新報社が発行する「会社四季報」は、国内の全上場企業に関する情報を網羅したデータブックです。
企業の業績、財務内容、株主構成、役員情報などがコンパクトにまとめられており、上場企業の情報を調べる際の定番ツールとして広く利用されています。
書店で冊子版を購入できるほか、「会社四季報オンライン」などのWebサービスでも情報を検索することが可能です。
四季報に掲載されている企業はすべて上場企業であるため、掲載の有無で簡単に判別できます。
企業の事業内容や将来性を深く理解するための情報源としても非常に有用です。
方法5:新聞の株式欄で株価を探す
日本経済新聞をはじめとする経済紙の株式欄(株価表)を確認するのも、古典的ですが有効な方法の一つです。
株式欄には、証券取引所に上場している主要企業の株価が毎日掲載されています。
調べたい企業の名前がこの欄にあれば、その企業は上場していると判断できます。
ただし、紙面の都合上、すべての上場企業の株価が掲載されているわけではないため、この方法で見つからないからといって非上場であるとは断定できません。
あくまで、知名度の高い企業を調べる際の一つの目安として活用するとよいでしょう。
新聞社のウェブサイトの電子版でも同様の情報を確認できます。
企業はなぜ上場する?主な3つのメリット
企業が多額のコストと労力をかけてまで上場を目指すのには、明確な理由があります。
上場によって企業は、株式市場を通じて幅広い投資家から直接資金を調達できるようになり、事業拡大や新規投資の選択肢が大きく広がります。
また、上場企業というステータスは社会的な信用を高め、ビジネスや人材採用において有利に働きます。
ここでは、企業が上場することで得られる代表的な3つのメリットについて解説します。
社会的な信用度が格段に向上する
上場するためには、証券取引所が定める厳しい審査基準を満たす必要があります。
この審査では、企業の収益性や財産の状況、事業の継続性、内部管理体制の有効性などが厳しく評価されます。
このプロセスをクリアしたという事実自体が、その企業が健全な経営を行っていることの証明となり、社会的な信用度を飛躍的に向上させます。
信用が高まることで、金融機関からの融資が受けやすくなったり、大手企業との取引が有利に進んだりするなど、事業活動全般において大きなメリットが生まれます。
また、企業の知名度も向上し、ブランドイメージの強化にもつながります。
幅広い投資家から資金を調達できる
上場の最大のメリットの一つは、資金調達の手段が多様化し、その規模が格段に大きくなることです。
株式を市場に公開することで、企業は不特定多数の投資家から直接、大規模な資金を調達することが可能になります。
これを「直接金融」と呼びます。
銀行からの借入(間接金融)と異なり、返済義務のない自己資本を増強できるため、より健全な財務基盤を構築できます。
調達した資金は、新規事業への投資、設備増強、研究開発、M&Aなどに活用でき、企業の持続的な成長を加速させる原動力となります。
優秀な人材が集まりやすくなる
上場企業であることは、採用活動においても大きな強みとなります。
社会的な信用度や知名度が高いため、求職者に対して安心感や魅力を与えやすく、優秀な人材からの応募が集まりやすくなります。
特に新卒採用やキャリア採用において、企業の安定性や将来性を重視する求職者にとって、上場企業は魅力的な選択肢です。
また、ストックオプション制度(自社の株式をあらかじめ決められた価格で購入できる権利)を導入することで、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の確保・定着につなげることも可能です。
これは、従業員が会社の成長を自身の利益として実感できる有効なインセンティブとなります。
上場する際に伴う3つのデメリット
上場は企業に多くのメリットをもたらす一方で、相応のデメリットや責任も伴います。
上場を維持するためには、監査法人への報酬や証券取引所への年間上場料など、継続的に高額なコストが発生します。
また、株式が市場で自由に売買されるようになることで、経営陣の意に沿わない株主による買収のリスクにもさらされます。
ここでは、企業が上場する際に考慮すべき主な3つのデメリットについて解説します。
上場の維持に高額なコストが発生する
上場企業であり続けるためには、多岐にわたるコストが継続的に発生します。
まず、証券取引所に支払う年間上場料が必要です。
さらに、財務諸表の信頼性を担保するために、公認会計士または監査法人による監査が義務付けられており、その監査報酬も支払わなければなりません。
加えて、株主総会の運営費用、有価証券報告書などの開示資料の作成費用、株主名簿の管理を委託する信託銀行への手数料など、様々な維持コストが毎年かかります。
これらの金銭的な負担は、特に企業規模がまだ小さい場合、経営を圧迫する要因となる可能性があります。
敵対的買収の標的になる可能性がある
株式を公開するということは、市場を通じて誰でもその会社の株主になれることを意味します。
これにより、企業の経営権を奪うことを目的とした「敵対的買収(TOB)」の標的になるリスクが生じます。
会社の経営方針に反対する投資家や、競合他社などが市場で株式を大量に買い集めることで、経営陣が望まない形で経営権を握られてしまう可能性があるのです。
このような事態を防ぐため、企業は買収防衛策を導入するなどの対策を講じる必要がありますが、その対策自体にもコストや手間がかかります。
経営の自由度が制限されるケースがある
上場企業は、創業者や経営陣だけのものではなく、多くの株主のものであるという考え方(株主主権)に基づいた経営が求められます。
そのため、経営者は常に株主の利益を意識した意思決定を行う必要があり、短期的な業績向上へのプレッシャーにさらされることになります。
株主の意向に反するような、長期的視点に立った大胆な投資や経営判断が難しくなる場合があります。
また、重要な経営判断を行う際には株主総会の承認が必要になるなど、非上場企業に比べて意思決定のプロセスが複雑化し、経営の自由度が制限されると感じるケースがあります。
就職・転職の参考に!上場企業で働くメリット
就職先や転職先を選ぶ際、企業が上場していることは多くの人にとって魅力的な要素となります。
上場企業は一般的に経営が安定しており、給与や福利厚生といった待遇面で優れている傾向があります。
また、社会的な信用度が高いため、住宅ローンを組む際など、個人のライフプランにおいても有利に働くことがあります。
ここでは、上場企業で働くことによって得られる具体的なメリットについて、働く人の視点から解説します。
安定した経営基盤と高い給与水準が期待できる
上場企業は厳しい審査を通過しているため、経営基盤が安定している会社が多いです。
事業規模が大きく、継続的な収益を上げる仕組みが構築されているため、倒産のリスクが比較的低いと言えます。
これにより、従業員は長期的なキャリアプランを立てやすく、安心して働くことが可能です。
また、利益を社員に還元する体力があるため、給与水準も日本の平均と比較して高い傾向にあります。
安定した収入は生活の基盤となるため、経済的な安心感を重視する人にとって、これは大きなメリットです。
充実した福利厚生を受けられることが多い
多くの大手上場企業は、優秀な人材を確保し、長く働いてもらうために、福利厚生の充実に力を入れています。
法律で定められた社会保険などの法定福利はもちろんのこと、住宅手当や家族手当、退職金制度、財形貯蓄、社員持株会といった法定外福利が手厚いケースが珍しくありません。
その他にも、人間ドックの費用補助や保養施設の利用、自己啓発支援制度など、社員の健康やプライベート、キャリアアップをサポートする多様な制度が整っています。
こうした充実した福利厚生は、働く上での満足度を高め、生活の質を向上させることにつながります。
ローン審査などで社会的信用を得やすい
上場企業に正規雇用で勤めているという事実は、個人の社会的な信用度を高める要素となります。
企業の安定性や収入の継続性が高く評価されるため、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンといった金融機関からの融資審査において、有利に働くことが一般的です。
また、クレジットカードの作成や賃貸物件の契約時にも、審査がスムーズに進む傾向があります。
これは、将来のライフイベントを見据えた際に大きな安心材料となり、人生設計を立てやすくするメリットと言えるでしょう。
働く前に知っておきたい上場企業のデメリット
上場企業で働くことには多くのメリットがある一方で、その特性ゆえのデメリットも存在します。
株主をはじめとする多くのステークホルダーへの責任を負うため、社内ルールやコンプライアンスが非常に厳格であり、個人の裁量が制限される場面も少なくありません。
こうした側面を理解せずに就職・転職すると、入社後にギャップを感じる可能性があります。
ここでは、働く人が知っておくべき上場企業のデメリットについて解説します。
厳格な社内ルールやコンプライアンスが求められる
上場企業は社会的な責任が大きく、株主や投資家など多くの人の監視下に置かれています。
そのため、不祥事を防ぎ、企業価値を守るために、コンプライアンス(法令遵守)体制が非常に厳格に整備されています。
業務の進め方や情報の取り扱い、経費の精算に至るまで、細かく定められた社内ルールに従うことが全社員に求められます。
こうした環境は、人によっては堅苦しく、手続きが煩雑で窮屈に感じられる可能性があります。
自由な発想や迅速な行動を重視する人にとっては、働きにくさを感じる一因となるかもしれません。
業務における裁量権が比較的小さい傾向にある
上場企業は組織の規模が大きいことが多く、業務が機能ごとに細分化されているのが一般的です。
そのため、従業員一人ひとりが担当する業務範囲は限定的になりがちで、若手のうちから大きな裁量権を持って仕事を進める機会は少ない傾向にあります。
意思決定には複数の部署や上司の承認が必要となるなど、稟議プロセスが複雑で時間がかかることも珍しくありません。
仕事の全体像を把握しにくかったり、自分の判断で物事を動かす実感が得にくかったりすることから、成長のスピードが遅いと感じる人もいるでしょう。
まとめ
応募を検討している企業が上場しているか調べるには、会社の公式サイトでIR情報の有無を確認する方法や、日本取引所グループ(JPX)のウェブサイトで検索する方法など、複数の簡単な手段が存在します。
上場企業は、経営の安定性や充実した福利厚生といった働く上でのメリットがある一方、厳格な社内ルールや裁量権の小ささといった側面も持ち合わせています。
企業選びの際は、上場・非上場という情報だけでなく、事業内容や社風、働く人にとってのメリット・デメリットを総合的に理解し、自分自身の価値観やキャリアプランに合うかどうかを見極めることが重要です。
上場企業を調べる際には、インターネット上の無料ツールや公式情報源を活用するのが最も手軽で正確です。
たとえば、**「EDINET」や「金融庁の有価証券報告書検索システム」**では、上場企業の財務情報や純資産、配当、株主構成などが公開されています。求人サイトやナビ媒体(リクナビ、マイナビなど)にも企業情報が掲載されていますが、信頼性の高い情報を得るなら公的なデータベースや証券取引所のサイトで確認しましょう。上場企業は「有価証券報告書」を提出しているため、企業名で検索するとすぐに見つかります。
一方、非上場企業かどうか見分ける方法も簡単です。まず、証券取引所の検索結果に該当がない場合や、会社HPに「IR情報」「株主還元」「決算報告」などの項目がない場合は、非上場の可能性が高いです。さらに、国会図書館や地域の図書館では『会社年鑑』『日本会社録』などの冊子で企業の業種や資産情報を確認できます。税理士事務所や会計士によるリサーチ、レファレンス協同データベースも有効な手段です。
実際に企業をリサーチする際は、「どの業種に属するか」「資産・純資産の推移」「株の保有状況」「配当実績」などを総合的に見ることが重要です。海外企業の場合は「Bloomberg」「Morningstar」などの英語サイトも参考になります。企業承継やM&Aを検討している場合には、税務や資産評価の観点からも専門家の診断を受けると安心です。
このように、上場・非上場の見分け方は、インターネット検索+公的情報源+専門家のサポートの3ステップで効率的に確認できます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む