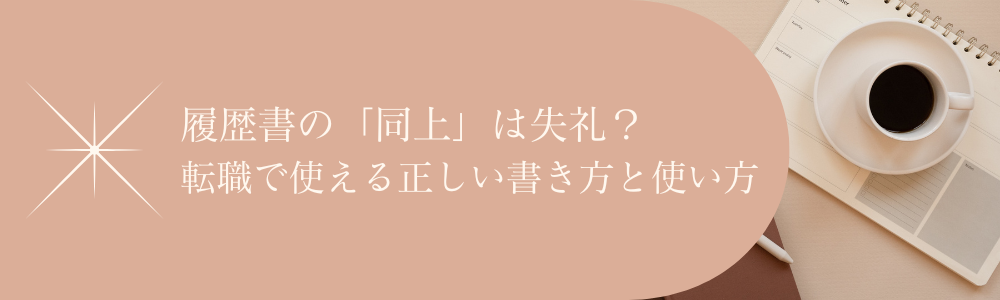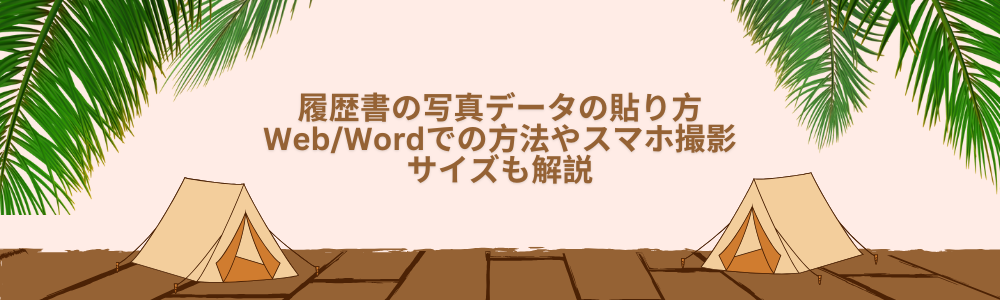業界研究のやり方と企業一覧|就活サイトの効果的な使い方【27卒・28卒】
27卒・28卒就活を始めたばかりの学生にとって、業界研究は自分に合った企業を見つけるための第一歩です。
しかし、業界研究の具体的なやり方がわからず、何から手をつければ良いか悩む人も少なくありません。
この記事では、27卒・28卒の就職活動に不可欠な業界研究の目的から具体的な進め方、さらには主要な業界の一覧とそれぞれの特徴までを網羅的に解説します。
正しい手順を理解し、効率的に情報を集めることで、納得のいく企業選びを実現させましょう。
そもそも業界研究とは?就活で必要とされる3つの理由
業界研究とは、世の中にどのような産業分野が存在し、それぞれがどのようなビジネスモデルで成り立っているのかを調べる活動です。
就職活動における業界研究の目的は、単に業界を知ることだけではありません。
自身のキャリアプランを明確にし、説得力のある志望動機を形成するための重要なプロセスであり、入社後のミスマッチを防ぐという大きなメリットも存在します。
この研究を通じて、社会の構造や経済の動きを理解し、自分の適性や興味に合った就職先を見つけることが可能になります。
理由1:自分に合った業界を見つけるため
世の中には多種多様な業界が存在し、それぞれの業界で事業内容や働き方、求められるスキルは大きく異なります。
自己分析で自分の強みや価値観を理解しても、それをどの業界で活かせるのかを把握しなければ、最適な就職先は見つかりません。
業界研究を通じて、これまで知らなかった業界の魅力に気づいたり、イメージと実際との違いを発見したりすることが可能です。
適性診断ツールなどを活用しつつ、自分の興味や適性と各業界の特徴を照らし合わせることで、働く意欲を高く保てる自分に合ったフィールドを発見できます。
理由2:説得力のある志望動機を作成するため
説得力のある志望動機を作成するには、「なぜこの業界でなければならないのか」という問いに明確な根拠を持って答える必要があります。
業界研究を通して、その業界が社会で果たす役割やビジネスモデル、将来の展望などを深く理解することが不可欠です。
業界全体の動向や課題を把握した上で、その中でなぜ特定の企業を志望するのかを語ることで、志望動機の深みと説得力が増します。
企業の魅力に対する理解を深めるだけでなく、業界構造の中でのその企業の位置づけを説明できるようになるため、他の就活生との差別化が図れます。
理由3:入社後のミスマッチを防ぐため
入社後のミスマッチは早期離職や転職の大きな原因となります。
業界の将来性や働きがい、社風などを事前に何もわからないまま入社してしまうと、「思っていた仕事と違った」「会社の雰囲気が合わない」といったギャップが生じやすくなります。
業界研究を徹底的に行うことで、その業界で働くことのやりがいだけでなく、厳しさや課題についても事前に把握できます。
理想と現実のギャップを最小限に抑え、入社後も意欲的に働き続けるためには、表面的な情報だけでなく、業界のリアルな姿を理解しておくことが重要です。
就活を成功に導く業界研究の具体的な進め方4ステップ
業界研究を効果的に行うためには、やみくもに情報を集めるのではなく、体系的な手順に沿って進めることが重要です。
まずは自己分析で自身の軸を定め、そこから視野を広げて様々な業界をリサーチし、最終的に志望企業を絞り込むという流れが一般的です。
この進め方を実践することで、膨大な情報の中から自分に必要なものを効率的に見つけ出し、納得感のある企業選びにつなげられます。
ここでは、業界研究の具体的な4つのステップを解説します。
ステップ1:自己分析で自分の軸を明確にする
業界研究を始める前に、まずは自己分析を行いましょう。
自分の興味・関心、得意なこと、価値観などを深く掘り下げることで、「どのような仕事にやりがいを感じるか」「どのような環境で働きたいか」といった就職活動の軸が明確になります。
この軸が定まっていないと、数ある業界の中からどれを調べるべきか判断できません。
過去の経験を振り返り、モチベーションの源泉を探ったり、友人や家族といった第三者の意見を聞いたりして、自分なりの判断基準を確立させることが、効率的な業界研究の第一歩となります。
ステップ2:様々な業界を広く浅くリサーチする
自己分析で定めた軸を参考にしつつも、初めは先入観を持たずに様々な業界を広く浅くリサーチすることをおすすめします。
自分の知らない業界や、今まで興味がなかった業界の中にも、実は適性に合った場所が見つかる可能性があるからです。
就活サイトの業界一覧ページや、業界地図といった書籍を活用し、どのような業界が存在するのか全体像を掴むことから始めましょう。
この段階では、各業界のビジネスモデルや市場規模などを大まかに把握するwebでのサーチで十分です。
視野を広げることを意識して情報を集めてみてください。
ステップ3:興味のある業界を3〜5つに絞り込んで深掘りする
広く浅くリサーチを進める中で、自分の就活の軸と照らし合わせて興味を持った業界や、魅力を感じた業界を3〜5つ程度に絞り込みます。
次に、その絞り込んだ業界について、より深く掘り下げていきましょう。
具体的には、業界の歴史、市場規模の推移、主要な企業の動向、現在抱えている課題、そして将来性などを詳しく調査します。
業界団体のウェブサイトや専門誌、ニュース記事などを活用して、より専門的で客観的な情報を収集することで、業界に対する理解度が一気に高まります。
ステップ4:業界内の企業を比較し志望企業を絞り込む
特定の業界について深く理解できたら、次はその業界に属する複数の企業を比較検討するステップに移ります。
同じ業界内でも、企業によって強みや事業内容、社風、働き方などは大きく異なります。
各社のウェブサイトや採用ページ、IR情報などを読み込み、事業内容、業績、福利厚生、平均年収などを比較しましょう。
株価の動向をチェックすることも、企業の安定性や将来性を測る一つの指標になります。
これらの情報を総合的に判断し、自分の軸に最も合致する企業をいくつかピックアップして、エントリーする志望企業を絞り込んでいきます。
業界研究はいつから始めるべき?27卒・28卒におすすめのスケジュール
27卒・28卒の就職活動において、業界研究をいつから始めるべきか悩む学生は多いでしょう。
結論から言うと、大学3年生(2025年)の4月〜5月頃から少しずつ始め、夏休みのインターンシップ選考が本格化する前に基礎を固めておくのが理想的です。
早期から動くことで、自己分析と並行しながらじっくりと業界知識を深められ、余裕を持って本選考(2026年)に臨むことが可能になります。
もちろん、このスケジュールはあくまで目安であり、28卒の学生が今から始めても早すぎることはありません。
効率的な情報収集!業界研究に役立つ6つの方法
業界研究を効率的に進めるためには、情報収集の方法を知り、それらを組み合わせて活用することが重要です。
就活サイトや書籍といった定番のツールから、説明会やOB・OG訪問といったリアルな情報を得られる機会まで、多様なアプローチが存在します。
特に近年では、オンラインで手軽に利用できる無料のサービスやアプリも充実しており、時間や場所を選ばずに情報を集めることが可能です。
ここでは、業界研究におすすめの具体的な方法を6つ紹介します。
方法1:就活サイトの業界研究ページを活用する
多くの就活サイトには、業界研究に特化したページが用意されています。
キャリタス就活などのサイトでは、各業界のビジネスモデルや市場規模、最新動向、代表的な企業などがコンパクトにまとめられており、初心者でも全体像を掴みやすいのが特徴です。
ネット環境さえあればいつでもどこでも手軽に情報収集を始められるため、最初のステップとして最適です。
リクルートやレバレジーズなどが運営する複数の就活サイトを併用することで、より多角的な視点から情報を得ることができ、知識の偏りを防げます。
方法2:業界団体の公式サイトで最新情報を得る
各業界には、その業界全体の発展を目的とした「業界団体」が存在します。
これらの公式サイトでは、業界に関する統計データや市場動向、法改正の影響といった、信頼性の高い一次情報が公開されていることが多いです。
例えば、日本自動車工業会や電子情報技術産業協会(JEITA)など、自分が興味を持つ業界の団体を調べてみましょう。
官公庁が発表する白書とあわせて参照することで、就活サイトだけでは得られない専門的かつ客観的な情報を得られ、より深い業界理解につながります。
方法3:四季報や業界地図で全体像を掴む
『就職四季報』や『業界地図』といった書籍は、業界研究の定番ツールです。
特に『業界地図』は、業界ごとの勢力図や企業間の関係性が図や表を用いてわかりやすく整理されており、複雑な業界構造を視覚的に理解するのに役立ちます。
『就職四季報』では、各企業の業績や採用実績、平均勤続年数、有給取得日数といった詳細なデータが項目ごとに掲載されているため、企業比較を行う際に非常に便利です。
どちらの書籍も、業界の全体像を俯瞰的に掴む上で強力な味方となります。
方法4:説明会やインターンシップでリアルな声を聞く
企業が主催する説明会やインターンシップは、Web上の情報だけでは得られない「生の情報」に触れる絶好の機会です。
現場で働く社員の方から直接、仕事内容ややりがい、社風について聞くことで、その業界や企業で働くイメージを具体的にできます。
特にインターンでは、業務の一部を体験できるため、自分との相性を確かめる上で非常に有益です。
最近ではオンライン形式のイベントも増えていますが、対面式の合同説明会に参加し、複数の企業を一度に比較検討するのも効率的です。
参加する際の服装は、企業の指示に従いましょう。
方法5:新聞やニュースで社会の動向を追う
新聞や経済ニュースは、社会の動きと業界の動向を結びつけて理解するための重要な情報源です。
日々のニュースに目を通す習慣をつけることで、新しい技術の登場や法改正、国際情勢の変化などが各業界にどのような影響を与えているのかをリアルタイムで把握できます。
最近では、新聞社の電子版やニュースアプリ、さらには経済ニュースを分かりやすく解説するYouTubeチャンネルなども充実しています。
興味のある業界に関連する記事をクリッピングしたり、キーワードで検索したりして、継続的に情報を追うことが大切です。
方法6:OB・OG訪問で現場の社員に質問する
OB・OG訪問は、興味のある企業で実際に働く大学の先輩から、本音の情報を聞ける貴重な機会です。
企業の公式な説明会では聞きにくいような、仕事の具体的なやりがいや苦労、職場の雰囲気、キャリアパスといったリアルな話を聞き出せます。
事前に企業や業界についてしっかり調べた上で、的確な質問を用意していくことが、有意義な時間にするための鍵です。
大学のキャリアセンターや、OB・OG訪問専用のマッチングサービスを通じて依頼できる場合があるので、積極的に活用してみましょう。
【ジャンル別】全9業界のビジネスモデルと特徴を一覧で紹介
世の中には無数の企業が存在しますが、それらは事業内容によっていくつかの業界に分類できます。
ここでは、就職活動で特に人気の高い9つの業界をピックアップし、それぞれのビジネスモデルや特徴、代表的な企業を簡潔に紹介します。
各業界の概要を掴むことで、自分の興味や適性がどの分野にあるのかを考えるきっかけになります。
まずは大枠を理解し、興味を持った業界からさらに深掘りしていくと良いでしょう。
メーカー業界(自動車・食品・化粧品など)
メーカー業界は、自社の工場で製品を企画、開発、製造し、販売する企業群の総称です。
その領域は非常に幅広く、トヨタやホンダなどの自動車、キリンやサントリー、味の素といった食品、化粧品、ソニーや富士通などの電機、旭化成のような化学・素材まで多岐にわたります。
ビジネスモデルは、作った製品を消費者に直接販売するBtoCと、他の企業に部品や素材として販売するBtoBに大別されます。
日本のものづくりを支える根幹的な産業であり、研究開発から製造、営業、マーケティングまで多様な職種が存在するのが特徴です。
商社業界(総合商社・専門商社など)
商社業界は、国内外の企業間で商品やサービスを仲介するトレーディングを主な事業とする企業群です。
カップラーメンから航空機まで、あらゆる商材を取り扱う「総合商社」と、鉄鋼や化学製品、食品といった特定の分野に特化した「専門商社」に分かれます。
近年では、トレーディングで得た利益や情報を元に、有望な企業や資源開発プロジェクトに投資する事業投資にも力を入れています。
グローバルな舞台でダイナミックなビジネスを手掛けたい学生から根強い人気を誇る業界です。
金融業界(銀行・証券・保険など)
金融業界は「お金」を商品として扱い、企業や個人の経済活動を支える役割を担っています。
個人や企業から預かったお金を貸し出す銀行、企業の株式や債券の売買を仲介する証券、万が一のリスクに備える保険が代表的です。
その他にも、クレジットカード、リース、投資信託など、多様なビジネスモデルが存在します。
社会の血液ともいえるお金を循環させる重要なインフラであり、経済に関する深い知識と高い倫理観が求められる業界です。
IT・通信業界(ソフトウェア・通信キャリアなど)
IT・通信業界は、情報技術や通信インフラを通じて社会に様々なサービスを提供する、成長著しい業界です。
ソフトバンクなどの通信キャリア、企業のシステム開発を担うSIer(NECなど)、業務効率化を図るソフトウェア開発、Webサービスやアプリ開発、ITコンサルティング(アクセンチュアなど)まで、事業領域は非常に広範にわたります。
技術革新のスピードが速く、常に新しいサービスが生まれるダイナミックな環境が特徴で、変化に対応できる柔軟性や学習意欲が求められます。
広告・マスコミ業界(広告代理店・テレビ・出版など)
広告・マスコミ業界は、情報を多くの人々に伝える役割を担っています。
新聞、テレビ、出版、ラジオといった媒体を通じて情報を発信する「マスコミ」と、企業の商品やサービスの販売促進を支援する「広告」の二つの領域に大別されます。
広告代理店は、クライアント企業のマーケティング戦略立案から広告制作、メディアへの出稿までをトータルで手掛けます。
近年はインターネット広告の市場が急速に拡大しており、デジタル領域の知識やスキルがますます重要になっています。
不動産・建設業界(デベロッパー・ゼネコンなど)
不動産・建設業界は、人々の生活や経済活動の舞台となる「建物」や「街」を創り、提供する業界です。
大規模な都市開発や街づくりを手掛ける「デベロッパー」、オフィスビルやマンションなどの企画・販売・仲介・管理を行う「不動産」、そして実際に建物を建築する「建設(ゼネコン)」など、様々な役割を担う企業で構成されています。
近年では、既存の建物を改修するリフォーム事業や、中古物件の流通なども市場を拡大しており、社会のニーズに合わせて多様なビジネスが展開されています。
インフラ・交通業界(電力・ガス・鉄道など)
インフラ・交通業界は、電力、ガス、水道、鉄道、航空、道路といった、社会生活に不可欠な基盤を提供する役割を担っています。
エネルギー供給や運輸サービスを通じて人々の暮らしを支える公共性の高い事業が多く、景気の変動を受けにくい安定性が特徴です。
ANAのような航空会社や鉄道会社、電力・ガス会社、石油元売り会社、日本郵船などの海運会社がこの業界に含まれます。
近年は、エネルギーの自由化や脱炭素化、自動運転技術の開発など、大きな変革期を迎えている分野でもあります。
小売・サービス業界(百貨店・ホテル・人材など)
小売・サービス業界は、消費者に直接商品やサービスを提供する、非常に幅広い分野を網羅する業界です。
百貨店やスーパー、コンビニエンスストアなどの「小売業」から、ホテルや旅行(HISなど)、レジャー施設、飲食、人材派遣、教育(英語学習など)、福祉・介護まで、その事業は多岐にわたります。
人々のライフスタイルや価値観の変化をダイレクトに受けるため、常に新しいニーズを捉え、魅力的な商品やサービスを提供し続けることが求められます。
多様なビジネスが存在するため、自分の興味関心に合った企業を見つけやすい業界ともいえます。
教育業界(塾・資格・学校教育機関(幼稚園から大学まで)
教育業界は、人々の成長や学びを支援するサービスを提供する業界です。
幼稚園から大学までの学校教育機関はもちろん、民間企業が運営する学習塾や予備校、資格取得スクール、英会話教室、幼児教育、社会人向けの研修サービスなども含まれます。
少子化の影響が懸念される一方で、グローバル化に対応するための語学教育や、IT人材育成、社会人の学び直し(リカレント教育)といった新たな需要も生まれています。
近年は、ICTを活用した「EdTech(エドテック)」と呼ばれる新しい教育サービスの開発も活発です。
やりがちだけどNG!業界研究で陥りやすい失敗と注意点
業界研究は就職活動の成否を分ける重要なプロセスですが、やり方を間違えると時間と労力を無駄にしてしまう可能性があります。
多くの学生が陥りがちな失敗パターンを事前に把握し、注意点を意識しながら進めることで、より効果的で質の高い研究が可能になります。
ここでは、業界研究で特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
これらの点を念頭に置き、客観的で深い分析を心掛けましょう。
注意点1:1つの情報源だけを鵜呑みにしない
特定の就活サイトや一冊の書籍など、単一の情報源だけに頼った業界研究は非常に危険です。
情報には発信者の意図や立場が反映されるため、内容が偏っていたり、情報が古かったりする可能性があります。
必ず複数の情報源を比較検討し、多角的な視点から業界を分析するよう心掛けましょう。
就活サイト、企業の公式発表、新聞記事、業界団体のレポート、さらにはシンクタンクが発表する調査報告など、性質の異なる情報を組み合わせることで、より客観的で信頼性の高い業界像を掴むことが可能になります。
注意点2:企業の知名度やイメージだけで判断しない
テレビCMなどで馴染みのあるBtoC企業は知名度が高く、華やかなイメージを抱きがちです。
しかし、世の中には一般消費者には知られていなくても、特定の分野で世界トップクラスのシェアを誇る優良なBtoB企業が数多く存在します。
知名度や漠然としたイメージだけで業界や企業を絞り込んでしまうと、自分に合った優良企業を見逃すことにつながりかねません。
例えば、コンサル業界なども人気ですが、その実態を詳しく調べずに判断するのは避けるべきです。
先入観を捨て、企業の事業内容や社会での役割を正しく理解することが重要です。
注意点3:業界の将来性やリスクも確認する
業界研究では、現状の市場規模や動向だけでなく、その業界が将来どのように変化していくのか、どのようなリスクを抱えているのかという視点も不可欠です。
AIやDXの進展、グローバル化、環境問題、少子高齢化といった社会全体の大きな変化が、各業界に与える影響は計り知れません。
例えば、製薬業界は新薬開発による大きな成長が期待される一方、開発費の高騰や成功確率の低下といったリスクも抱えています。
業界の明るい側面だけでなく、課題やリスクについても目を向け、長期的な視点でキャリアを考えましょう。
業界研究に関するよくある質問Q&A
業界研究を進めていると、「業界と業種の違いは?」「ノートは作った方がいい?」といった素朴な疑問が浮かんでくることがあります。
ここでは、多くの就活生が抱きがちな質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
基本的な用語の定義を正確に理解することは、効率的な情報収集と深い企業分析の土台となります。
例えば、営業という職種を希望する場合でも、どの業界でその仕事をするかによって内容は大きく変わってきます。
Q1.「業界」と「業種」は何が違うの?
「業界」と「業種」は似ていますが、使われる文脈が異なります。
「業界」は、企業が生産する製品や提供するサービスの種類によって分類したもので、例えば「自動車業界」や「IT業界」のように、慣習的に使われる区分です。
一方、「業種」は、総務省が定めた日本標準産業分類に基づいた公的な分類を指すことが多く、「製造業」「情報通信業」といったより大きな括りになります。
就職活動においては、一般的に「業界」という言葉が頻繁に使われます。
職種はまた別の概念です。
Q2.「業界」と「職種」の違いは?
「業界」が企業の事業内容による分類(どのようなビジネスを行っているか)であるのに対し、「職種」は個人が担当する仕事内容による分類(どのような仕事をするか)です。
例えば、「IT業界」という大きな括りの中に、「営業」「エンジニア」「マーケティング」「人事」といった様々な職種が存在します。
自分が「何をしたいか(職種)」と「どのフィールドでそれをしたいか(業界)」を掛け合わせて考えることで、志望企業がより具体的に見えてきます。
公務員の場合は、民間企業のような業界という括りはありません。
Q3.業界研究ノートは作った方が良い?
業界研究ノートの作成は必須ではありませんが、作ることを強く推奨します。
調べた情報をノートやシートにまとめておくことで、知識が整理され、後から見返した際に比較検討しやすくなるからです。
決まったフォーマットはないため、自分が使いやすいテンプレートを作成すると良いでしょう。
例えば、業界ごとに「市場規模」「ビジネスモデル」「主要企業」「将来性」「課題」といった項目を設けるのがおすすめです。
手書きのノートでも、PC上のファイルでも構いません。
自分なりの方法で情報を一元管理することが大切です。
研究成果をアピール!ES・面接で差がつく志望動機の伝え方
業界研究の最終的な目的は、そこで得た知識や自分なりの考察を、エントリーシート(ES)や面接で効果的にアピールし、内定を獲得することにあります。
ただ単に調べた情報を羅列するだけでは、他の就活生との差別化は図れません。
重要なのは、業界の動向や課題を深く理解した上で、「なぜこの業界なのか」「その中でなぜこの企業なのか」「入社後、自分はどのように貢献できるのか」という一連のストーリーを論理的に伝えることです。
具体的な数字や事実を交えながら、自分自身の言葉で語ることで、志望度の高さと企業への深い理解を示すことができます。
まとめ
本記事では、業界研究の目的から具体的な進め方、情報収集の方法、主要な業界の解説まで、網羅的に説明しました。
このまとめとして、業界研究は自分に合った企業を見つけ、納得のいくキャリアを歩むための土台となる、就職活動において極めて重要なプロセスであることを再度強調します。
自己分析を基点として、広い視野で業界を捉え、徐々に深掘りしていくという手順を踏むことが成功の鍵です。
様々な情報源を活用しながら、自分なりの視点で業界を分析し、自信を持って選考に臨んでください。
就活を始めるうえで欠かせないのが「業界研究」です。業界研究とは、企業や職種の特徴・働き方・将来性を知るための情報収集のこと。リクナビやマイナビなどのナビサイトを活用すれば、住宅・医療・海運・鉄鋼・スーパー・メガバンク・旅行・AI・財務など、多様な業界の概要や企業一覧を簡単に比較できます。特に2024〜2025年卒の学生は、インターン情報や合同説明会、セミナーなどのイベントが増えており、動画やYouTubeを使った企業紹介も主流になっています。
まずは、ナビサイトの「業界マップ」機能で全体像を把握し、自分の興味分野を絞り込みましょう。わからない点やめんどくさいと感じる部分も、テンプレート化された業界研究シートやフォーマットを使えば整理がしやすくなります。さらに、企業セミナーやオンラインイベントに参加し、実際の社員の話を聞くことで「公式サイトや求人票では見えないリアルな事情」を知ることができます。
また、AI技術やデジタル分野の発展により、企業の変化も早くなっています。転職市場での評価や今後の成長性を見据えて、業界の将来トレンドも意識しておくことがポイントです。YouTubeでの業界紹介動画や就活エージェントの解説も、理解を深める助けになります。
総じて、業界研究は「自分に合った企業を見つける地図づくり」。2025年卒以降の学生も、情報をうまく組み合わせて、自分だけのキャリアマップを描いていきましょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む