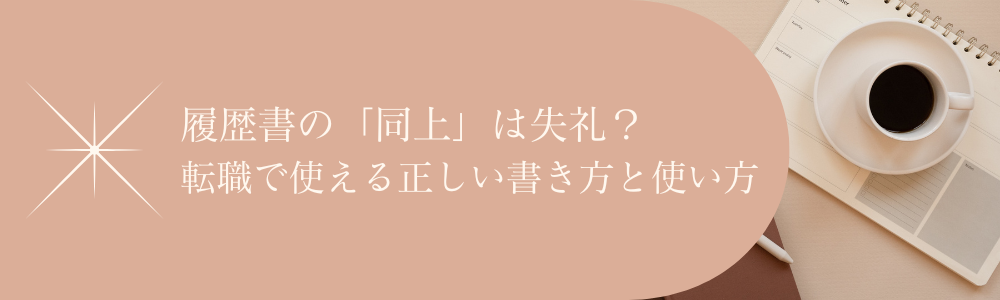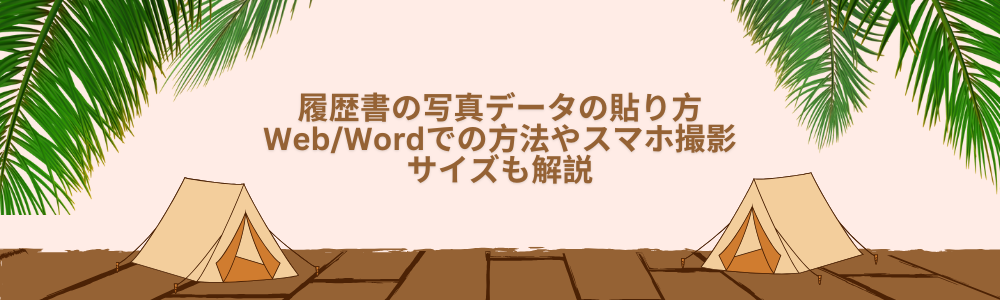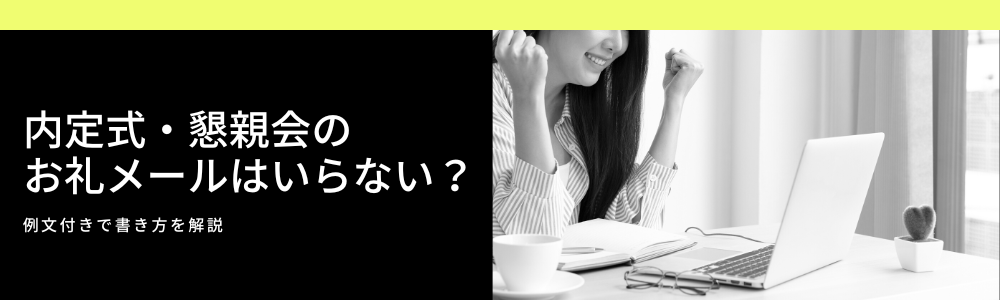

内定式・懇親会のお礼メールはいらない?例文付きで書き方を解説
内定式や懇親会が終わった後、「お礼のメールは送るべきか」と悩む方は少なくありません。
就活の一環として、内定式のお礼を伝えることは必須ではありませんが、感謝の気持ちや入社意欲を示す良い機会となります。
このメールの一手間が、社会人としての丁寧な印象を与え、就職後の円滑な人間関係の構築につながることもあります。
この記事では、内定式のお礼メールの必要性から、基本構成、相手別の例文、送信時のマナーまで、分かりやすく解説します。
内定式のお礼メールは送るべき?評価への影響は?
内定式のお礼メールを送るかどうかは、個人の判断に委ねられます。
送らなかったからといって、内定が取り消されるようなことはありません。
面接とは異なり、お礼メールの有無が直接的な評価に影響することは考えにくいです。
しかし、メールを送ることで、企業に対して感謝の気持ちや入社への高い意欲を改めて示すことができます。
採用担当者の記憶に残り、丁寧で誠実な人柄というポジティブな印象を与える可能性があります。
入社前から良好な関係を築くきっかけにもなるため、送っておくのが賢明です。
【基本構成】内定式のお礼メールに盛り込むべき5つの要素
内定式のお礼メールを作成する際は、ビジネスメールの基本構成を押さえることが重要です。
構成要素は主に「件名」「宛名」「本文」「結びの言葉」「署名」の5つです。
この型に沿って作成すれば、要点が分かりやすく、相手に失礼のない丁寧なメールになります。
それぞれの項目で記載すべき内容を理解し、感謝の気持ちと入社意欲がしっかりと伝わるように心がけましょう。
企業側が内容を把握しやすく、もし返信が必要な場合でもスムーズに対応できるような配慮が求められます。
①件名|大学名と氏名、用件が一目でわかるように記載する
メールの件名は、受信者が多くのメールの中から内容を瞬時に把握するための重要な要素です。
採用担当者は日々大量のメールを処理しているため、「【内定式のお礼】〇〇大学氏名」のように、用件と送信者が一目でわかるように記載します。
具体的な件名を付けることで、メールが見落とされたり、後回しにされたりするのを防げます。
件名だけで誰から何の連絡かが明確に伝わるように、大学名と氏名を必ず含めるのがマナーです。
分かりやすい件名は、相手への配慮を示す第一歩となります。
②宛名|会社名・部署名・氏名は省略せず正式名称で書く
宛名はメールの冒頭で相手への敬意を示す部分であり正確さが求められます。
会社名は「株式会社」と正式名称で記載してください。
部署名や役職担当者の氏名も間違いがないように名刺や企業のウェブサイトで確認してから入力します。
もし担当者名が分からない場合は「人事部採用ご担当者様」のように記載しても問題ありません。
複数名に宛てる際は役職が上の方から順に名前を並べるのがビジネスマナーです。
正確な宛名は社会人としての基本姿勢を示すことにもなります。
③本文|内定式への感謝と具体的な感想を伝える
本文の冒頭では、まず内定式を開催していただいたことへの感謝の気持ちを述べます。
単に「ありがとうございました」と伝えるだけでなく、内定式で特に印象に残ったことを具体的に盛り込むと、より気持ちが伝わります。
例えば、社長の祝辞や先輩社員との懇談会での話、同期入社の仲間と交流できた喜びなど、自身の言葉で感想を綴ることで、オリジナリティのある内容になります。
ありがとうという感謝の心を、具体的なエピソードを交えて表現することで、入社意欲の高さを効果的にアピールできます。
④結びの言葉|入社後の意気込みや抱負を述べる
メールの結びでは、内定式を経て高まった入社への意欲や、今後の抱負を簡潔に伝えます。
「貴社の一員として貢献できるよう、精一杯努力してまいります」といった前向きな姿勢を示すことで、企業側にポジティブな印象を残せます。
最後に、「今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」のように、指導を仰ぐ言葉で締めくくるのが一般的です。
改めて感謝の言葉を添えることで、文章全体が丁寧な印象でまとまります。
これからよろしくお願いしますという謙虚な気持ちを表現しましょう。
⑤署名|連絡先を明記し、誰からのメールか分かりやすくする
メールの末尾には、誰が送信したのかを明確にするために必ず署名を記載します。
署名には、氏名、大学名、学部・学科名、そして連絡先である電話番号とメールアドレスを明記するのが基本です。
大学の先生にレポートを提出するメールと同様に、自身の所属と連絡先を正確に伝えることは社会人としてのマナーです。
企業側が返信や連絡をしたい場合に、署名を見ればすぐに情報が分かるため、相手の手間を省く配慮にもなります。
あらかじめメールソフトの署名機能に登録しておくと、入力漏れを防げて便利です。
【相手別】すぐに使える内定式のお礼メール例文3選
内定式のお礼メールは、送る相手によって内容や言葉遣いを調整することが望ましいです。
例えば、採用活動全般でお世話になった採用担当者、経営トップである社長や役員、親しく話ができた先輩社員では、それぞれに適した表現が異なります。
ここでは、送る相手を3つのパターンに分け、それぞれの状況ですぐに使えるお礼メールの例文を紹介します。
基本の構成は同じですが、相手との関係性を考慮した文面を作成する際の参考にしてください。
例文1:採用担当者・人事部宛ての基本的なお礼メール
採用担当者や人事部宛てのお礼メールは、最も標準的な形式です。
まずは内定式を滞りなく開催してくれたことへの感謝を伝えます。
次に、式典の内容や同期となる内定者と交流できたことへの感想を述べ、入社への期待感が高まったことを示します。
本文では、「〇〇様のお話をお伺いし、貴社で働くことへの期待がより一層高まりました」のように、具体的なエピソードを交えると良い印象を与えられます。
結びには、入社後の抱負を簡潔に記し、今後の指導をお願いする言葉で締めくくります。
丁寧でありながら堅苦しくなりすぎない、バランスの取れた文面を心がけます。
例文2:社長や役員と話した場合の丁寧なお礼メール
内定式や懇親会で社長や役員と直接話す機会があった場合は、個別にお礼メールを送るとより丁寧な印象になります。
宛名は「代表取締役社長〇〇様」のように、役職と氏名を正確に記載し、採用担当者宛てよりも一層かしこまった言葉遣いを意識します。
本文では、内定式に参加できたことへの感謝に加え、社長から直接聞いた言葉で特に感銘を受けた点や、それによって自身の考えがどう変化したかを具体的に記述します。
自身の入社後の目標と、企業の発展にどう貢献したいかという熱意を伝えることで、記憶に残りやすくなります。
例文3:懇親会でお世話になった先輩社員宛てのお礼メール
内定式後に行われた懇親会などで、親身に相談に乗ってくれたり、有益なアドバイスをくれたりした先輩社員がいる場合は、個別にお礼メールを送ることをお勧めします。
社長や役員宛てのような堅い表現は避けつつも、ビジネスメールとしての礼儀はわきまえましょう。
懇親会で話した具体的な内容に触れ、「〇〇様から伺ったプロジェクトのお話に大変感銘を受けました」のように、感謝の気持ちを伝えます。
最後に「入社後、ご一緒できることを楽しみにしております」といった言葉を添えると、良好な関係を築くきっかけになります。
お礼メールで失敗しないために!送信前に確認したい4つのマナー
お礼メールは、感謝の気持ちを伝えるためのものですが、ビジネスマナーが守られていないと、かえってマイナスの印象を与えかねません。
内定式後にせっかくメールを送るのであれば、内容だけでなく形式面でも相手に配慮することが重要です。
ここでは、送信タイミングや誤字脱字のチェック、送信形式など、メールを送る前に必ず確認しておきたい4つのマナーを解説します。
業務に関する具体的な質問などは、お礼メールに含めず、改めて別の機会に連絡するのが適切です。
送信のタイミングは内定式の当日か翌日の午前中がベスト
お礼メールは、内定式での記憶や感謝の気持ちが鮮明なうちに送るのが効果的です。
最適なタイミングは、内定式当日の業務時間内、または翌日の午前中です。
時間が経過しすぎると、儀礼的な印象が強まってしまいます。
企業の担当者の勤務時間を考慮し、深夜や早朝の送信は避けるのが社会人としてのマナーです。
スマートフォンの予約送信機能を活用するなどして、相手が業務を開始する時間帯に届くように調整すると良いでしょう。
迅速な対応は、仕事に対する意欲や姿勢の表れと受け取られることもあります。
誤字脱字や敬語の間違いがないか声に出して読み返す
作成したメールは送信前に必ず全体を注意深く読み返しましょう。
特に宛先となる企業名や部署名、担当者の氏名に間違いがあると大変失礼にあたります。
誤字脱字や敬語の誤用がないかも入念に確認が必要です。
黙読では見逃しやすい細かなミスも一度声に出して読んでみることで不自然な表現や文章のリズムの悪さに気づきやすくなります。
時間をかけて作成したメールもたった一つのミスで印象が損なわれる可能性があるため最終チェックは怠らないようにしましょう。
パソコン・スマホどちらでも読みやすいテキスト形式で送る
ビジネスメールは、受信者の環境に依存しないテキスト形式で送るのが基本です。
文字の装飾や画像の挿入が可能なHTML形式は、相手のメーラーによっては正しく表示されない、あるいはセキュリティ上の理由から敬遠されることがあります。
そのため、誰でも確実に内容を確認できるテキスト形式を選びましょう。
また、スマートフォンでの閲覧も想定し、一文を短くしたり、段落ごとに一行空けたりするなど、読みやすいレイアウトを心がけることも大切です。
相手がスムーズに読め、もし返信が必要な場合でも負担にならないように配慮します。
複数名に送る際は一人ひとり個別で送信する
お礼を伝えたい相手が複数名いる場合でも、CC機能などを使って一斉送信するのは避けましょう。
一斉送信は効率的ですが、受け手にとっては「大勢の中の一人」として扱われたと感じさせ、事務的な印象を与えてしまいます。
採用担当者、社長、先輩社員など、お礼を伝えたい相手には、それぞれ個別にメールを送るのが最も丁寧な方法です。
手間はかかりますが、一人ひとりに宛てて内容を少し変えることで、感謝の気持ちがより深く伝わります。
特に役職者に対しては、必ず個別で送信するように心がけてください。
まとめ
内定式のお礼メールは義務ではありませんが、送ることで入社意欲や感謝を伝え、好印象を残す機会となります。
メールを作成する際は、基本構成とマナーを守り、相手に合わせた丁寧な言葉遣いを心がけることが重要です。
内定式の当日は、必要な持ち物の確認だけでなく、誰とどのような話をしたかを簡単にメモしておくと、後でメールを書く際に具体的なエピソードを盛り込みやすくなります。
この記事で紹介したポイントや例文を参考に、心のこもったお礼メールを作成し、社会人としての第一歩を良い形でスタートさせましょう。
内定式や懇親会に参加した後、「お礼メールはいらないの?」と悩む就活生は多いでしょう。結論から言えば、形式的に必須ではありませんが、印象を良くするためには送るのがおすすめです。社会人としてのマナーや自己PRの場としても活用でき、リクナビやナビサイトでも「好印象を残すポイント」として紹介されています。
■お礼メールを送る理由とタイミング
お礼メールを送る目的は、感謝の気持ちを伝えると同時に、改めて入社への意欲をアピールすることです。送るタイミングは当日~翌日中が理想。時間が経つと印象が薄れるため、早めに準備しておきましょう。
また、誤字脱字や宛先ミス、アドレス間違いは人事担当者への印象を下げる原因になります。送信前には必ず確認するのがポイントです。
■お礼メールの書き方のコツ
書く内容は簡潔に、感謝と今後への意気込みを中心にまとめます。以下の流れで書くと分かりやすいです。
件名:「内定式(または懇親会)へのお礼/○○大学○○」
冒頭:人事担当者の名前+「お世話になっております」
本文:感想や印象に残った点、今後への抱負を1~2文で
結び:「今後ともよろしくお願いいたします」で締めくくる
■お礼メールの例文
件名:内定式へのお礼(○○大学 ○○)
○○株式会社 人事部 ○○様
お世話になっております。○○大学の○○です。
本日は内定式に参加させていただき、誠にありがとうございました。社員の皆さまの温かい雰囲気に触れ、入社への意欲がより一層高まりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
○○大学 ○○(電話番号/メールアドレス)
■まとめ
お礼メールは「いらない」と考える人もいますが、感謝と誠実さを伝える絶好のチャンスです。形式的な一文でも構いません。丁寧な書き方とタイミングを意識し、就活の締めくくりとして好印象を残しましょう。コラムや就活サイト「リクナビ」「マイナビ」でも監修付きの例文一覧が紹介されているので、参考にして自分らしいメールをまとめてみてください。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む