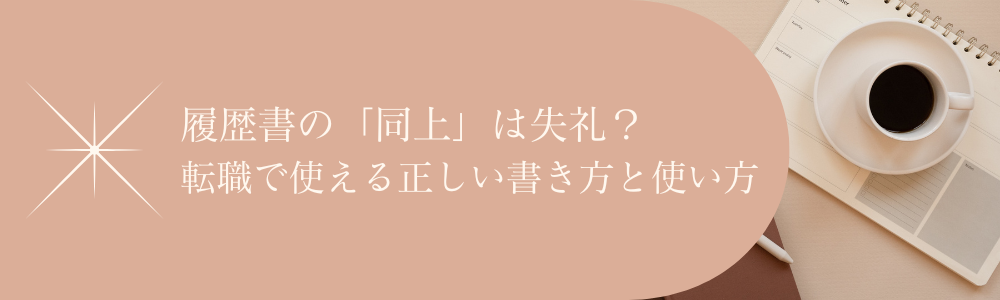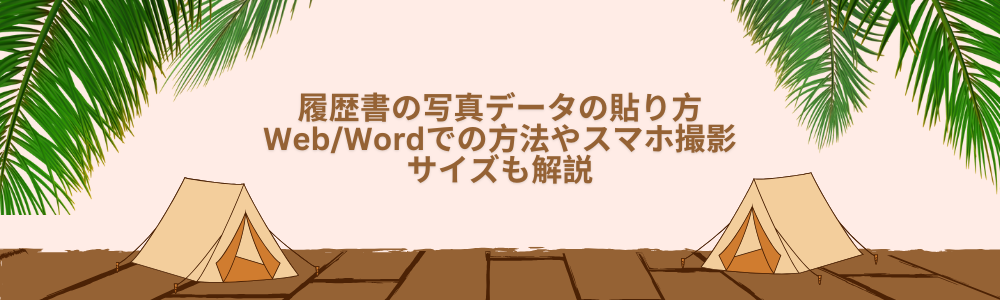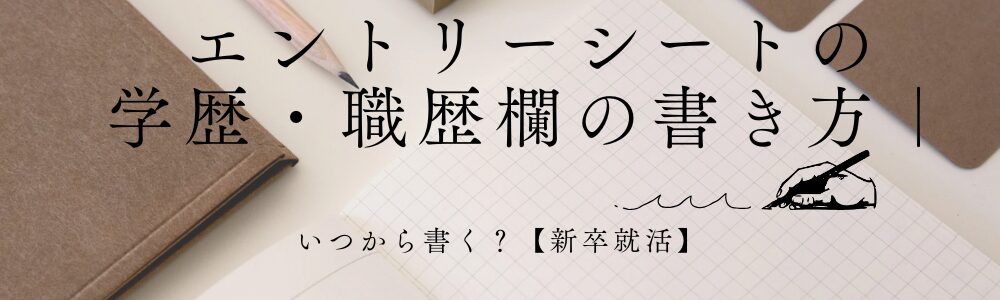

エントリーシートの学歴・職歴欄の書き方|いつから書く?【新卒就活】
エントリーシートの学歴欄は、就活で最初に企業へ提出する重要書類の一部です。
新卒の就活では、自身の経歴を正確に伝えるための書き方の基本ルールを理解しておく必要があります。
エントリーシートで学歴をいつから書くべきか、職歴はどう扱うかなど、多くの学生が疑問に思う点を網羅的に解説します。
この基本的な項目で評価を落とさないよう、正しい書き方をマスターすることが求められます。
エントリーシートの学歴はいつから書く?中学校卒業からが基本
エントリーシートの学歴をいつから書くかについて、明確な決まりはないものの、一般的には中学校卒業から記載するのが基本です。
義務教育である中学の卒業年月と、高校以降の入学・卒業年月を時系列で記入します。
企業によっては「高校卒業から」と指定される場合もあるため、提出先の指示を必ず確認することが重要です。
学歴欄は応募者の経歴を簡潔に伝える役割を担っており、指定がない限り、中学校卒業から書くのが無難な対応といえます。
【見本付き】エントリーシート学歴欄の基本的な書き方5ステップ
エントリーシートの学歴欄は、履歴書と同様に基本的な書き方のルールが存在します。
Webエントリーシートの場合でも、これらのルールは共通して適用されます。
学歴・職歴欄は、採用担当者が応募者の経歴を最初に確認する重要な項目なため、正確かつ丁寧な記入が求められます。
ここでは、具体的な見本を交えながら、学歴欄を完成させるための5つのステップを解説します。
この手順に沿って作成すれば、誰でも間違いのない学歴欄を仕上げることが可能です。
ステップ1:1行目の中央に「学歴」と記載する
まず、学歴・職歴欄の1行目中央に「学歴」と明記します。
この記載は、ここから学歴に関する情報が始まることを示すための見出しの役割を果たします。
学歴と職歴を同じ欄に記入する場合、学歴を先に書き、その後に職歴を続けるのが一般的です。
そのため、最初に「学歴」と記載し、学歴情報をすべて書き終えた後、1行空けてから中央に「職歴」と記載する流れとなります。
手書き、PC入力のどちらの場合でもこのルールは共通です。
文字の大きさやフォントは、本文と合わせるか、やや目立つように調整すると見やすくなります。
この最初のステップを忘れると全体の体裁が整わないため、必ず記載するように心掛けましょう。
ステップ2:年号は西暦か和暦のどちらかに統一する
学歴を記入する際の年号は、西暦(例:2023年)か和暦(例:令和5年)のどちらかに必ず統一します。
エントリーシート全体で表記が統一されていることが重要であり、学歴欄だけではなく、提出日や生年月日などの他の項目とも揃える必要があります。
どちらを使用するかは企業の指定がなければ任意ですが、外資系企業やIT業界では西暦が好まれる傾向にあります。
入学・卒業年が不明な場合は、自動計算ツールなどを活用して正確な情報を確認してください。
年号の計算ミスや表記の混在は、注意力が不足しているという印象を与えかねないため、提出前には必ず全体を見直して、表記が統一されているかを確認することが求められます。
ステップ3:学校名・学部・学科名は省略せず正式名称で記入する
学校名や学部・学科名は、絶対に省略せずに正式名称で記入してください。
「〇〇高校」ではなく「〇〇県立〇〇高等学校」のように、都道府県名や「高等学校」まで正確に記載することが基本です。
大学名についても同様で、「〇〇大学」が正式名称であればその通りに記入します。
また、「私立」の場合は学校名の前に「私立」と記載しましょう。
「〇〇学部〇〇学科」のように、学部と学科の間にはスペースを一つ入れると見やすくなります。
専攻やコースがある場合も、それらを省略せずに記入してください。
正式名称を正確に書くことは、ビジネスマナーの基本であり、丁寧な書類作成ができる人材であることを示すことにもなります。
ステップ4:在学中の場合は「卒業見込み」と明記する
新卒の就活生は、大学や専門学校に在学中であるため、最終学歴の卒業年月を記入した後に「卒業見込み」と明記します。
例えば、「〇〇大学〇〇学部〇〇学科卒業見込み」のように記載してください。
これにより、採用担当者は応募者が卒業予定であることを正確に把握できます。
大学院生の場合は、「修士課程修了見込み」や「博士課程単位取得後退学見込み」など、自身の状況に合わせて正確な表現を用いましょう。
すでに卒業している場合は「卒業」と記載します。
この「卒業見込み」の記載がないと、経歴が不明確になり、選考で不利になる可能性もあるため、忘れずに記入することが重要です。
ステップ5:学歴を書き終えたら次の行に「以上」と記載する
すべての学歴を記入し終えたら、最後の行の右端に「以上」と記載します。
この「以上」は、学歴の記載がここで終わりであることを示すための締めくくりの言葉です。
学歴を書き終えた直後の行に書くのがルールで、左寄せや中央寄せではなく、必ず右寄せで記入してください。
職歴も記入する場合は、学歴を書き終えて「以上」を記載し、その後一行空けて「職歴」の見出しを立て、職歴を記入した後に再度「以上」と記載します。
このルールは、手書きでもPC作成でも同様です。
些細な点に見えるかもしれませんが、正式な書類作成におけるマナーの一つとして認識し、忘れずに記入するように心掛けましょう。
【新卒向け】エントリーシート職歴欄の書き方
新卒の就活生にとって、職歴欄の書き方は悩むポイントの一つです。
正社員としての就業経験がない場合、どのように記載すればよいのか迷うことが多いでしょう。
原則として、新卒の場合は職歴がないため、その旨を明記するのが基本となります。
ただし、長期インターンなど、アピールにつながる経験がある場合は、書き方を工夫することも考えられます。
ここでは、新卒向けの職歴欄の基本的な書き方と、アルバイトやインターン経験の扱いについて解説します。
職歴がない場合は「なし」と記入する
新卒の就活生で正社員としての就業経験がない場合、職歴欄には「なし」と記入するのが一般的です。
学歴を書き終え、右端に「以上」と記載した後、一行空けて中央に「職歴」と見出しを書き、その下の行に「なし」と記入します。
最後に、その次の行の右端に「以上」と記載して締めくくってください。
空欄のまま提出するのは、記入漏れと判断される可能性があるため避けるべきです。
アルバイト経験は職歴には含まれないため、ここに記載する必要はありません。
「なし」と明確に記載することで、職歴がないことを正確に伝え、同時に書類作成のルールを理解していることを示せます。
これが新卒における最も基本的で正しい職歴欄の書き方です。
アピールしたいアルバイト経験は自己PR欄に書くのがおすすめ
アルバイト経験を職歴欄に記載するかどうかは、状況によって判断が異なります。一般的には、正社員としての経歴を記載する欄ですが、以下のような場合はアルバイト経験を職歴欄に記載することが推奨されます。
* 正社員としての就業経験がない、または少ない場合
* 応募する企業の業務内容と関連性が高く、自身の強みとしてアピールできる経験がある場合
* 長期にわたる勤務経験がある場合(3ヶ月以上が目安)
* アルバイト経験を記載しないと長い空白期間ができてしまう場合
* 企業から記入の指示があった場合
職歴欄にアルバイト経験を記載する際は、会社名を正式名称で記入し、その横に「(アルバイト)」と雇用形態を明記することが重要です。また、担当していた業務内容を簡潔に記載し、入社年月と退職年月を明記します。
自己PR欄やガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の欄では、応募する企業に関連性の高い経験や、リーダー経験、売上向上に貢献した実績、専門的なスキルを習得した経験などを具体的に記述することで、自身の能力を効果的に伝えられます。職務経歴書には、履歴書に書ききれない詳細な業務内容や、そこで得た経験・スキルを詳しく記述すると良いでしょう。
【パターン別】迷いやすい学歴の書き方Q&A
就活生の経歴は多様であり、浪人や留年、留学、中退など、学歴欄の書き方に迷うケースは少なくありません。
これらの経歴をどのように書けば、採用担当者に正確かつ正直に伝えられるのか、多くの学生が疑問を抱いています。
ここでは、パターン別に迷いやすい学歴の書き方について、具体的なQ&A形式で解説します。
自身の経歴を正しく、そして不利にならないように表現するためのポイントを押さえることが重要です。
浪人や留年した場合はどう書く?
浪人や留年をした場合、その事実をエントリーシートの学歴欄に直接記載する必要はありません。
高校卒業と大学入学の間に1年以上の空白期間があれば、採用担当者は浪人したことを理解します。
同様に、入学から卒業までの期間が標準年数より長ければ留年したことが分かります。
そのため、学歴は事実を時系列に沿って淡々と記入すれば問題ありません。
例えば、高校卒業が2022年3月で大学入学が2023年4月であれば、浪人期間があったと判断されます。
面接で空白期間について質問された際に、その理由をポジティブに説明できるように準備しておくことが重要です。
予備校名などを記載する必要はなく、事実をそのまま書くのが基本となります。
休学期間がある場合はどう書く?
休学した経験がある場合、学歴欄にその事実を明記することが望ましいです。
休学の期間と理由を簡潔に記載することで、採用担当者に経歴の空白期間について誤解を与えずに済みます。
書き方としては、大学名の行の下に「〇〇年〇月〜〇〇年〇月〇〇のため休学」のように一行で簡潔にまとめるのが一般的です。
休学理由が病気療養や経済的な事情であっても、正直に記載するのが基本ですが、詳細まで書く必要はありません。
「一身上の都合により休学」とすることも可能です。
留学やボランティアなど、ポジティブな理由での休学であれば、アピール材料にもなり得ます。
面接で質問される可能性を想定し、理由を具体的に説明できるように準備しておくことも求められます。
大学を中退した場合はどう書く?
大学を中退した場合、その事実を学歴欄に正確に記載する必要があります。
隠したり偽ったりすると、経歴詐称とみなされる可能性があるため注意が必要です。
書き方としては、「〇〇大学〇〇学部〇〇学科中途退学」と記入します。
中退した年月も正確に記載してください。
「中退」という言葉の代わりに「中途退学」と書くのがより丁寧な表現となります。
中退理由については、学歴欄に詳しく書く必要はありませんが、面接で質問されることを想定しておくべきです。
その際は、ネガティブな印象を与えないよう、前向きな理由や学びを伝えられるように準備することが重要です。
例えば、新たな目標ができて別の道に進むことを決めた、などと説明できると良いでしょう。
転校・編入した場合はどう書く?
転校や編入の経験がある場合も、その経歴を時系列に沿って学歴欄に明記します。
まず、入学した学校名と入学年月を記載し、その次の行に転校または編入した学校名を記入してください。
転校の場合は「〇〇高等学校へ転入学」のように記載します。
大学への編入であれば、「〇〇大学〇〇学部〇〇学科3年次編入学」のように、何年次に編入したかを明記するとより丁寧です。
最終的に卒業(または卒業見込み)の学校が最終学歴となるため、その情報を最後に記載します。
転校や編入は、自身のキャリアプランや学びたい分野を追求した結果であることが多く、ポジティブな行動として評価される可能性もあります。
経歴を分かりやすく正確に伝えることが重要です。
留学経験がある場合はどう書く?
留学経験は、語学力や異文化適応能力を示すアピールポイントになるため、学歴欄に積極的に記載したいものです。
留学期間が1年以上の長期留学の場合は、学歴として正式に記載するのが一般的です。
大学の在学中に留学した場合は、「〇〇大学在学中、〇〇大学へ交換留学(〇〇年〇月〜〇〇年〇月)」のように、留学先の大学名、国名、留学期間を明記します。
休学して留学した場合は、休学の事実と合わせて記載してください。
1年未満の短期留学や語学研修の場合は、学歴欄ではなく自己PRや特技欄などでアピールするのが適切です。
留学経験を記載することで、グローバルな視野や行動力を示すことが可能になります。
在学中や卒業後に学校名が変更された場合はどう書く?
在学中や卒業後に、通っていた学校の名称が変更された場合、学歴欄には在学当時の正式名称を記入するのが基本です。
その上で、現在の学校名を括弧書きで併記すると、採用担当者にとって分かりやすくなります。
例えば、「〇〇大学(現:△△大学)〇〇学部卒業」のように記載します。
これにより、経歴の事実を正確に伝えつつ、現在の正式名称も示すことができます。
現在の名称のみを記載すると、卒業証明書などと相違が生まれる可能性があるため避けるべきです。
学校名の変更は応募者本人の経歴とは直接関係ないですが、採用担当者が経歴を確認する際に混乱しないよう、配慮した書き方をすることが求められます。
企業はエントリーシートの学歴欄で何を見ている?
企業がエントリーシートの学歴欄を確認する際、単に最終学歴の学校名を見ているだけではありません。
採用担当者は、学歴情報から応募者の基礎的な能力や人となり、書類作成能力などを多角的に判断しようとしています。
学歴欄は、自己PRや志望動機と同様に、自身を評価してもらうための重要な項目です。
ここでは、企業が学歴欄を通じて具体的にどのような点を確認しているのか、その3つの視点を解説します。
応募者の基礎的な学力や専門分野を確認している
企業は学歴欄を通して、応募者がどのような教育を受けてきたか、つまり基礎的な学力レベルや専門分野を把握しようとしています。
特に、研究職や専門職など、特定の知識やスキルが求められる職種では、学部や学科、専攻が重視される傾向にあります。
どのような分野を学んできたかは、応募者の興味・関心や思考の特性を理解する手がかりにもなります。
また、卒業した学校のレベルから、一定の地頭や論理的思考力、学習意欲などを推測することもあります。
ただし、学歴だけで合否が決まるわけではなく、あくまで人物評価の一つの要素として捉えられています。
自身の学びが、応募企業の事業内容とどう結びつくかを意識することが重要です。
経歴に嘘や間違いがないかチェックしている
採用担当者は、学歴欄に記載された内容が正確であるかを確認しています。
入学・卒業年月に矛盾がないか、学校名や学部名が正式名称で書かれているかなど、細部までチェックされます。
もし虚偽の記載が発覚すれば、経歴詐称とみなされ、内定取り消しや、入社後であれば懲戒解雇の対象となる可能性もあります。
意図的でなくても、単純な記入ミスが多ければ、注意力散漫な人物という印象を与えかねません。
卒業証明書の提出を求められた際に、エントリーシートの記載内容と相違がないように、正確な情報を記入することが絶対条件です。
信頼性の高い人物であることを示すためにも、経歴は正直かつ正確に記載する必要があります。
指示通りに書類を作成できるか判断している
エントリーシートの学歴欄は、応募者が指示通りに、かつ丁寧に書類を作成できるかという基本的なビジネススキルを判断する材料にもなっています。
例えば、「西暦で記入」「高校卒業から記載」といった企業からの指定を守れているか、誤字脱字がなく、全体のフォーマットが整っているかなどが評価の対象となります。
学歴欄のような定型的な項目でさえ正確に書けない場合、入社後も仕事でミスを多発するのではないか、と懸念される可能性があります。
丁寧な書類作成は、仕事に対する真摯な姿勢を示すことにもなります。
細部にまで気を配り、誰が見ても分かりやすい書類を作成する能力は、社会人として必須のスキルと見なされています。
エントリーシートの学歴欄でよくある疑問を解決
エントリーシートの学歴欄を作成していると、書き方の基本ルールだけでは解決できない細かな疑問が生じることがあります。
例えば、書き間違えた場合の訂正方法や、学校名が長くて一行に収まらない場合の対処法など、具体的な状況に応じた対応が求められます。
ここでは、就活生が学歴欄の作成で抱きがちな、よくある疑問とその解決策を解説します。
これらのポイントを押さえることで、より完成度の高いエントリーシートを目指せます。
書き間違えた場合は二重線で訂正する?最初から書き直す?
手書きのエントリーシートで書き間違えた場合、修正テープや修正液の使用は避けるべきです。
公的な書類では、修正の痕跡が残るものはマナー違反とされます。
もし間違えた箇所が小さなものであれば、二重線を引いて訂正印を押すのが正式な訂正方法です。
しかし、エントリーシートは企業への第一印象を決める重要な書類であり、訂正跡があると見栄えが悪く、丁寧さに欠ける印象を与えかねません。
そのため、時間に余裕があれば、新しい用紙に最初から書き直すのが最も望ましい対応です。
PCで作成している場合は、該当箇所を修正するだけで済みます。
提出前に複数回見直しを行い、そもそもミスをしないように心掛けることが重要です。
学校名が長くて1行に収まらないときの対処法
学校名や学部・学科名が非常に長く、指定された欄の一行に収まりきらない場合があります。
その際は、無理に小さな文字で詰め込むのではなく、二行に分けて書くのが適切な対処法です。
一行で書くのが基本ですが、読みにくくなってしまっては本末転倒になります。
二行に分ける際は、学校法人名や学部名など、意味の区切りが良いところで改行すると、すっきりと見やすいレイアウトになります。
例えば、「学校法人〇〇学園△△大学」や「〇〇学部△△学科国際コミュニケーション専攻」のように、名称の切れ目で改行しましょう。
採用担当者が読みやすいように配慮することが最も重要であり、レイアウトを工夫することで、丁寧な印象を与えられます。
予備校に通っていた期間は学歴に含めるべきか
浪人期間中に通っていた予備校は、一般的には学校教育法で定められた正規の学校ではないため、学歴には含まれないとされています。ただし、予備校の中には学校教育法第82条または第83条に基づいて認可設置された専修学校や各種学校に該当する場合もあり、その際は正規の学校として扱われます。
したがって、エントリーシートの学歴欄に記載するのは、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院など、正規の学歴に該当するものです。予備校に通っていた事実を記載する際には、それが正規の学歴として認められるかどうかを確認することが重要です。もし正規の学歴ではない予備校名を記載してしまうと、学歴の定義を正しく理解していないと判断される可能性があります。
浪人期間については、高校卒業と大学入学の年月を見れば採用担当者には伝わるため、予備校名を書かなくても問題ありません。学歴欄には、決められたルールに従って、正規の学歴のみを正確に記入するように心掛けましょう。
まとめ
エントリーシートの学歴欄は、就職活動における基本中の基本であり、応募者の経歴と人柄を伝える最初のステップです。
中学校卒業から記載するのが一般的であり、年号の統一、正式名称の使用、卒業見込みの明記といったルールを守ることが重要となります。
新卒の場合、職歴は「なし」と記入し、アピールしたい経験は自己PR欄で述べるのが適切です。
浪人や留学といった個別の事情も、ルールに沿って正確に記載すれば問題ありません。
企業は学歴から基礎能力や誠実さ、書類作成能力を見ているため、丁寧な作成を心掛ける必要があります。
これらの基本は、将来の転職活動で職務経歴書を作成する際にも役立つ知識となるため、今のうちにしっかりと身につけておくことが求められます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む