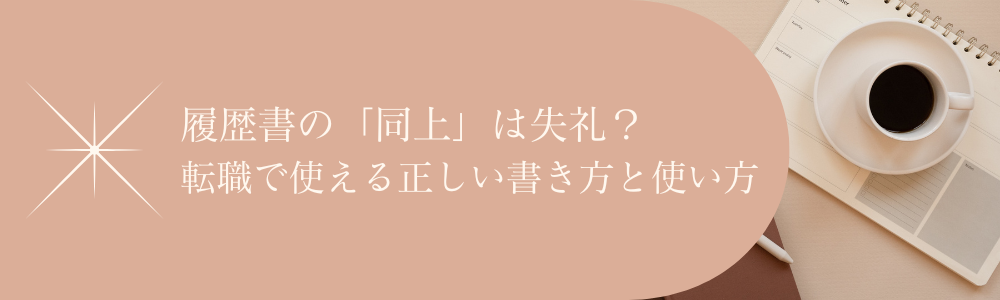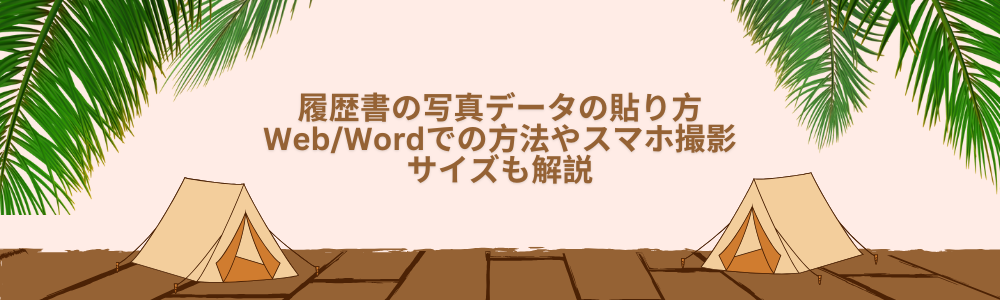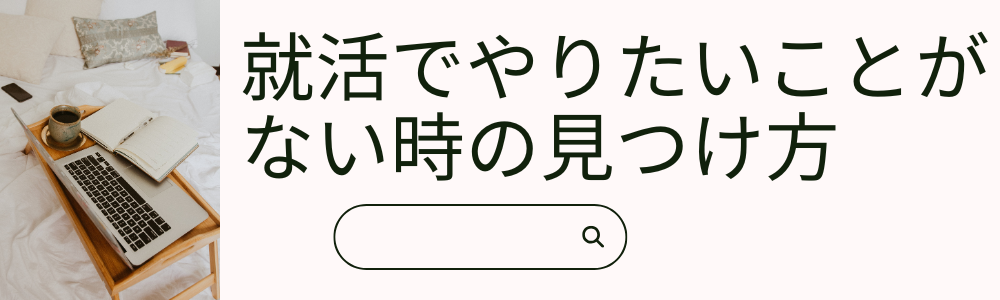

就活でやりたいことがない時の見つけ方|ES・面接で使える回答例文も紹介
就職活動(就活)を進める中で、「やりたいことがない」という思いに直面し、明確な答えが見つからずに悩む学生は少なくありません。
周囲の友人が具体的に就活で目標を語るのを聞いて、焦りを感じることもあるでしょう。
しかし、就活のときに「やりたいことがない」と感じるのは、決して特別なことではありません。
企業がその質問をする意図から、自分と向き合い、やりたいことを見つけるための具体的な5つのステップまでを詳しく解説します。
さらに、どうしてもやりたいことがない場合の企業選びの軸や、エントリーシート・就活面接で使える回答例文も紹介するので、自分らしいキャリアを歩むための見つけ方のヒントとして活用してください。
そもそも企業が就活で「やりたいこと」を質問する3つの理由
多くの企業の面接で、「入社後にやりたいことは何ですか?」という質問がされます。
この問いに対して、単に学生の将来の夢や希望を聞いているわけではありません。
企業側には、採用活動における重要な判断材料として、この質問を活用する明確な意図が存在します。
その背景にある理由を理解することで、より的を射た回答を準備することが可能になります。
ここでは、企業がこの質問を通して確認しようとしている、主な3つの理由について掘り下げていきます。
入社後のミスマッチを防ぎたいから
企業が「やりたいこと」を質問する最も大きな理由の一つは、入社後のミスマッチを未然に防ぐためです。
企業は多大な時間とコストをかけて採用活動を行っており、採用した人材には長く活躍してほしいと願っています。
学生が抱くキャリアプランや仕事に対する価値観と、企業の事業内容や社風、求める人物像が大きく異なっている場合、入社後に「思っていた仕事と違った」と感じ、早期離職につながる可能性が高まります。
例えば、学生が「若いうちから裁量権を持って新しい事業を立ち上げたい」というビジョンを持っている一方で、企業側が求めているのが、既存の事業を着実に運用していく堅実な人材であった場合、両者の間には明らかなミスマッチが生じます。
このような事態を避けるため、企業は学生の「やりたいこと」を聞き、それが自社の環境で実現可能なのか、そして自社の方向性と一致しているのかを慎重に見極めています。
したがって、学生側は企業理念や事業内容を深く理解した上で、自身のやりたいこととどう結びつくのかを具体的に示すことが求められます。
自社への志望度の高さを確認したいから
やりたいことは、その学生がどれだけ自社に対して強い入社意欲を持っているか、つまり志望度の高さを測るための重要な指標となります。
多くの学生が複数の企業にエントリーしている中で、採用担当者はなぜ数ある企業の中から自社を選んだのかという点を特に重視しています。
もし回答がどの企業にも当てはまるような抽象的な内容であれば、この学生は誰にでも同じことを言っているのではないかという印象を与えかねません。
志望度の高さをアピールするためには、その企業ならではの強みや特徴を踏まえた上で、この会社でしか実現できないことを具体的に語る必要があります。
例えば、競合他社と比較した上での事業の優位性や、特定のプロジェクト、独自の企業文化などに触れ、そこで自分の能力をどのように活かして貢献したいかを論理的に説明することが有効です。
面接の場で熱意を伝えるためには、徹底した企業研究に基づいた、具体的で説得力のある回答が不可欠です。
仕事への熱意やポテンシャルを測りたいから
新卒採用は、現時点でのスキルや経験だけでなく、将来的な成長可能性、すなわちポテンシャルを重視する「ポテンシャル採用」が基本です。
企業は「やりたいこと」という質問を通して、学生が仕事に対してどれほどの熱意を持ち、入社後にどのように成長していきたいと考えているのか、その意欲や伸びしろを評価しようとしています。
具体的な目標を掲げ、その実現に向けて努力する姿勢は、たとえ困難な業務に直面しても、前向きに乗り越えていける人材であることの証となります。
面接の場では、たとえ未経験の分野であっても、「新しい知識を積極的に学びたい」「失敗を恐れずに挑戦したい」といった高い学習意欲やチャレンジ精神を示すことが好意的に受け止められます。
明確なビジョンを持っている学生に対して、企業側も具体的なキャリアパスを提示しやすく、長期的な視点で育成計画を立てることが可能です。
自分の強みを活かしてどのように貢献し、将来的にはどのような人材に成長していきたいのかを伝えることで、仕事への熱意とポテンシャルを効果的にアピールできます。
「やりたいこと」がないでも大丈夫!自分と向き合う5つのステップ
就職活動中に「やりたいことがわからない」と焦りを感じるかもしれませんが、それは自分自身を深く見つめ直すための貴重な機会です。
多くの学生が同様の悩みを抱えながら、自分なりの答えを見つけ出しています。
大切なのは、漠然とした不安を抱えたまま立ち止まるのではなく、思考を整理し、具体的な行動に移していくことです。
ここでは、自己分析を深め、自分だけのキャリアの軸を築くための「やりたいことの見つけ方」を、具体的な5つのステップに分けて紹介します。
これらのステップを踏むことで、納得のいくキャリア選択への第一歩を踏み出せるでしょう。
ステップ1:過去の経験を振り返り、モチベーションの源泉を探る
やりたいことを見つけるための最初のステップは、自分自身の過去を丁寧に振り返り、何に心を動かされてきたのかを探ることです。
これまでの人生における様々な経験、例えば学業、部活動、サークル、アルバイト、趣味など、あらゆる場面を思い出し、どのような時に喜び、達成感、悔しさ、充実感を覚えたかを具体的に書き出してみましょう。
その際、「モチベーショングラフ」を作成するのも有効な手法です。
横軸に時間(幼少期から現在まで)、縦軸にモチベーションの高低を設定し、人生の出来事を曲線で結んでいきます。
グラフの曲線が大きく上がった時や下がった時の出来事に着目し、「なぜその時にモチベーションが上がったのか」「どのような状況で、誰と関わっていたのか」を深く掘り下げて分析します。
そこから、「チームで目標を達成することに喜びを感じる」「誰かの役に立つことで満足感を得る」「新しい知識を学ぶのが好き」といった、自分を突き動かす共通の価値観やモチベーションの源泉が見えてきます。
この自己分析こそが、自分に合った仕事の方向性を探る上で最も重要な土台となり、効果的なやりたいことの見つけ方につながります。
ステップ2:「Will・Can・Must」のフレームワークで思考を整理する
「やりたいことがわからない」という漠然とした状態から抜け出すためには、「Will・Can・Must」というフレームワークを用いて思考を整理することが非常に有効です。
これは、キャリアを考える上での3つの重要な要素を洗い出し、それらの重なり合う部分から自分の目指すべき方向性を見出すためのツールです。
まず、「Will(やりたいこと・なりたい姿)」、「Can(できること・得意なこと)」、「Must(やるべきこと・求められる役割)」の3つの円を紙に描き、それぞれに該当する内容を書き出していきます。
「Will」には、仕事に限らず、人生で成し遂げたい夢や理想のライフスタイルなどを自由に記述します。
「Can」には、資格や語学力といったスキルだけでなく、コミュニケーション能力や継続力といった性格的な強みも含めます。
「Must」には、企業や社会から期待される役割や責任を考えます。
初めから3つの円が綺麗に重なる必要はありません。
まずはそれぞれの要素を可視化することが重要です。
このフレームワークを使うことで、自分自身の現在地と目指す方向性を客観的に把握し、今後何をすべきか(例:Canを増やすために資格を取る、Mustの中からWillに近い仕事を探す)が明確になります。
ステップ3:「やりたくないこと」を書き出して選択肢を絞り込む
やりたいことがない人にとって、「やりたいこと」を無理に探し出すのは苦痛を伴う場合があります。
そのような時は、視点を変えて「やりたくないこと」や「避けたいこと」を明確にすることから始めてみるのが効果的です。
このアプローチは、消去法によって自分に合った選択肢を絞り込んでいく作業です。
例えば、「毎日同じことの繰り返しは避けたい」「個人で黙々と進める作業より、チームで協力する仕事が良い」「厳しいノルマに追われる営業は向いていない」「転勤が多い働き方はしたくない」といったように、仕事内容、人間関係、労働環境、企業文化などの観点から、自分がどうしても受け入れられない条件を具体的にリストアップします。
その際、なぜそれをやりたくないのかという理由も併せて考えてみると、自分が仕事に求める本質的な価値観がより鮮明になります。
この「やりたくないことリスト」は、企業選びの際のフィルターとして機能し、膨大な求人情報の中から自分に合わない企業を効率的に除外する手助けとなります。
結果として、ストレスなく自分らしく働ける環境を見つけやすくなるでしょう。
ステップ4:インターンシップやOB・OG訪問でリアルな仕事に触れる
自己分析やWebサイトでの情報収集だけでは、仕事の具体的なイメージを掴むことには限界があります。
机上で考えた「やりたいこと」が、実際の現場と乖離している可能性も少なくありません。
そこで重要になるのが、インターンシップやOB・OG訪問を通じて、社会人と直接関わり、リアルな仕事に触れる機会を持つことです。
インターンシップに参加すれば、実際の業務を体験することで、その仕事の面白さや難しさ、職場の雰囲気、社員の方々の働き方を肌で感じることができます。
一方、OB・OG訪問では、特定の企業や業界で働く先輩から、Webサイトには書かれていない仕事のやりがいや苦労、キャリアパス、業界の裏話といった本音を聞き出すことが可能です。
これらの一次情報は、自分の適性を見極め、キャリアの方向性を定める上で非常に貴重な判断材料となります。
これまで全く視野に入れていなかった業界や職種に興味を持つきっかけになったり、逆に憧れていた仕事が自分には向いていないと気づいたりすることもあるでしょう。
このような実践的な経験こそが、納得感のあるやりたいことの見つけ方につながります。
ステップ5:新卒の就職活動はとりあえず、体験してみる。就職先の探し方(就職サイト紹介)
やりたいことが明確に定まっていなくても、まずは就職活動というプロセスに身を投じてみること自体に大きな価値があります。
企業説明会に参加したり、エントリーシートを作成したり、面接を受けたりする一連の活動を通じて、否が応でも自分自身や社会と向き合うことになり、その中で思考が整理され、興味の方向性が見えてくることは少なくありません。
新卒の就職活動は、様々な業界や企業について、フラットな立場で知ることができる人生で一度きりの貴重な機会です。
最初から選択肢を狭めすぎず、少しでも興味を引かれた企業の情報を積極的に集めてみましょう。
情報収集には、就職サイトの活用が不可欠です。
「リクナビ」や「マイナビ」といった大手総合サイトは掲載企業数が圧倒的に多く、幅広い選択肢から検討できます。
また、企業からオファーが届く「OfferBox」のような逆求人型サイトに登録すれば、自分では見つけられなかった優良企業と出会える可能性も広がります。
まずは行動を起こし、多くの情報に触れる中で、自分の心の動きに耳を傾けてみることが重要です。
やりたいことが見つからない人が企業を選ぶ際の3つの軸
就職活動において「やりたいこと」が明確に見つからない場合でも、立ち止まってしまう必要はありません。
無理に理想の「やりたいこと」をこじつけるよりも、視点を変えて自分なりの企業選びの軸を確立することが、後悔のない選択につながります。
やりたいことがない人でも、自分に合った環境を見つけ、納得のいくキャリアをスタートさせることは十分に可能です。
ここでは、企業選びの具体的な判断基準となる3つの軸を提案します。
これらの軸を参考にすることで、漠然とした企業選びから一歩踏み出し、自信を持って就職活動を進められるようになるでしょう。
「できること」や「得意なこと」を活かせる仕事から探す
やりたいことが見つからない時に最も現実的で有効なアプローチの一つが、自分の「できること(スキル)」や「得意なこと(特性)」を基準に仕事を探すことです。
これまでの経験で培ってきた能力や、他人から「上手だね」と褒められた長所を活かせる環境であれば、入社後もスムーズに業務に適応しやすく、早い段階で成果を出すことが期待できます。
例えば、ゼミや研究で培った論理的思考力や分析力が得意ならコンサルタントやマーケティング職、アルバイトの接客経験で磨いたコミュニケーション能力に自信があるなら営業職や販売職などが考えられます。
得意なことを仕事にすると、成果が出やすいために周囲からの評価も得られ、それが自信となって仕事へのモチベーションを高めるという好循環が生まれます。
その結果、当初は「できるから」という理由で始めた仕事が、次第に「やりがいのある仕事」、つまり「やりたいこと」へと変わっていくケースも少なくありません。
自己分析を通じて自分の強みを客観的に把握し、その強みがどのような職種で求められているのかをリサーチすることから始めてみましょう。
興味のある業界や事業内容から企業をリサーチする
明確に「この職種に就きたい」という希望がなくても、「なんとなく気になる」というレベルの興味を起点に企業を探していくのも有効な方法です。
やりたいことが見つからないと感じている人でも、日常生活の中で関心を持つ分野や、社会的な意義を感じるテーマはあるはずです。
例えば、普段からよく利用するアプリやサービスを提供しているIT業界、好きな食品や化粧品を製造しているメーカー、あるいは環境問題や地域活性化といった社会課題の解決に取り組む企業など、少しでも心が動かされる分野があれば、そこから深掘りしてみましょう。
業界地図や企業のウェブサイト、ニュース記事などを通じて、その業界のビジネスモデルや将来性、主要な企業について調べていくうちに、具体的な仕事内容や企業の魅力に気づくことがあります。
最初は漠然とした興味でも、情報収集を重ねることで、その業界で働くことへの解像度が高まり、結果として自分のキャリアの方向性を見出すきっかけになる可能性があります。
働きがいや労働環境など「理想の働き方」を基準にする
やりたいことがない人にとって、「どのような働き方をしたいか」「どのような環境で過ごしたいか」という価値観は、企業を選ぶ上で非常に重要な軸となります。
これは、仕事の「What(何をやるか)」よりも、「How(どう働くか)」や「Where(どこで働くか)」を優先するアプローチです。
まずは、自分が理想とする働き方を具体的にイメージし、リストアップしてみましょう。
例えば、「プライベートの時間を確保できるワークライフバランスを重視したい」「若いうちから裁量権を持って挑戦できる環境が良い」「安定した企業で長く安心して働きたい」「尊敬できる仲間とチームで協力しながら働きたい」など、自分にとって譲れない条件を明確にします。
その上で、福利厚生、勤務地、残業時間、研修制度、社風といった具体的な条件を比較検討し、自分の価値観に合致する企業を探していきます。
仕事内容は時代や組織の状況によって変化する可能性がありますが、自分に合った労働環境や企業文化は、長期的なキャリア満足度を支える重要な基盤となります。
適正診断や就活サイトに登録してみる
自分一人で自己分析を進めても、客観的な視点が欠けてしまい、考えが堂々巡りになってしまうことがあります。そのような時は、第三者の視点や客観的なツールを活用するのが有効です。多くの就職サイトが無料で提供している適性診断ツールは、いくつかの質問に答えるだけで、自分の性格特性、価値観、向いている仕事の傾向などを科学的に分析してくれます。
リクナビの「リクナビ診断」やマイナビの「適職診断MATCHplus」などが有名で、これらの診断結果は、自分では気づかなかった強みや意外な職種との相性を発見するきっかけとなります。ただし、診断結果はあくまで参考情報であり、それ自体を鵜呑みにするのではなく、自己理解を深めるための一つの材料として活用する姿勢が重要です。また、様々なタイプの就活サイトに登録し、多くの企業情報に触れることも視野を広げる上で役立ちます。特に、自分のプロフィールに興味を持った企業からアプローチがあるスカウト型のサイトに詳細な情報を登録しておけば、思いがけない優良企業との出会いが生まれる可能性もあります。
ES・面接で「やりたいこと」を聞かれた時の答え方と例文
自己分析や企業研究を通じて、自分なりの「やりたいこと」や「企業選びの軸」が見えてきたら、次はその考えを選考の場で採用担当者に効果的に伝える準備が必要です。
単に「〇〇がしたいです」と願望を述べるだけでは、相手を納得させることはできません。
ここでは、自分の考えを論理的かつ具体的に伝え、説得力を持たせるための回答の構成要素を解説します。
さらに、様々な状況に応じてすぐに使える回答例文や、評価を下げてしまうNG例も紹介するので、面接で自信を持って受け答えができるよう、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
回答に説得力を持たせるための3つの構成要素
面接で「やりたいこと」を伝える際に、回答に説得力を持たせるためには、以下の3つの構成要素を意識して話を組み立てることが重要です。
1つ目は「結論(What)」です。まず最初に、入社後に何を成し遂げたいのかを簡潔かつ明確に述べます。結論から話すことで、聞き手である面接官は話の全体像を把握しやすくなります。
2つ目は「理由(Why)」です。なぜそれをやりたいと考えるようになったのか、その背景にある自分自身の経験や価値観を具体的に説明します。特に、過去の具体的なエピソード(原体験)を交えて語ることで、話に深みと独自性が生まれ、単なる思いつきではない、一貫した考えであることが伝わります。
3つ目は「入社後の貢献(How)」です。その「やりたいこと」を実現するプロセスを通じて、企業に対してどのように貢献できるのかを具体的に示します。企業の事業内容や強み、今後のビジョンなどを踏まえた上で、自分のスキルや強みをどう活かせるのかを語ることで、入社意欲の高さと将来性をアピールできます。この3つの要素を盛り込むことで、論理的で一貫性のある、説得力の高い回答が完成します。
【状況別】すぐに使える就活での回答例文3選
ここでは、企業選びの軸に応じて応用できる具体的な回答例文を3つの状況別に紹介します。
「できること」を軸にする場合の例文
私の強みであるデータ分析力を活かし、貴社のマーケティング部門で顧客の購買行動に基づいた販売戦略の立案に貢献したいと考えています。
大学のゼミでは、統計学を用いて飲食店の来店客データ分析を行い、客単価を10%向上させる施策を提案した経験があります。
この経験で培った分析力と提案力を活かし、貴社の膨大な顧客データを分析することで、新たな顧客層の開拓や既存顧客の満足度向上に貢献したいです。
「興味」を軸にする場合の例文
私は、IT技術を用いて教育格差という社会課題を解決したいという強い思いがあり、業界のリーディングカンパニーとして革新的な教育プラットフォームを展開されている貴社を志望しています。
学生時代に教育ボランティアとして活動する中で、地域による学習環境の差を痛感しました。
貴社の持つ高い技術力と豊富なコンテンツを、まだ届いていない地域の子どもたちに届ける事業に携わり、持続可能な社会の実現に貢献したいです。
「働き方」を軸にする場合の例文
私は、多様なバックグラウンドを持つメンバーと協力し、一つの目標を達成することに大きなやりがいを感じます。
学生時代の〇〇というチームプロジェクトで、意見の対立を乗り越え、全員が納得する形で目標を達成できた経験は、私の大きな自信となっています。
個人の成果だけでなく、チーム全体の成功を重視する貴社の社風に強く惹かれており、私の強みである傾聴力と調整力を活かして、チームの潤滑油のような存在として大きな成果に貢献したいです。
評価を下げてしまうNGな回答例と改善ポイント
意欲を伝えようとするあまり、かえって評価を下げてしまう回答をしてしまうケースがあります。
ここでは、よくあるNGな回答例とその改善ポイントを解説します。
NG例:漠然としていて具体性がない
「社会に貢献できる仕事がしたいです。」
この回答は意欲は感じられますが、どの企業でも言える内容であり、なぜこの会社なのかが全く伝わりません。
【改善ポイント】
「貴社の再生可能エネルギー事業に携わり、クリーンなエネルギーを普及させることで、持続可能な社会の実現に貢献したいです。」のように、企業の具体的な事業内容と結びつけ、どのように貢献したいのかを明確に述べることが重要です。
NG例:受け身で学習意欲のみをアピールする
「充実した研修制度を活用して、様々なことを学び、成長したいです。」
成長意欲は大切ですが、企業は学校ではありません。
会社に貢献する姿勢が見えないと、「教えてもらう」ことだけを期待している受け身な人材だと判断されかねません。
【改善ポイント】
「貴社の充実した研修制度で〇〇の専門知識をいち早く習得し、△△の分野で即戦力として貢献できるようになりたいです。」と、学んだことをどう仕事に活かすかまで言及し、主体的な姿勢を示すことが求められます。
まとめ
就職活動の過程で「やりたいことがない」と感じるのは、決して特別なことでも、ネガティブなことでもありません。
多くの学生が通る道であり、むしろ自分自身と深く向き合う良い機会と捉えることができます。
もしやりたいことが見つからない状態であっても、焦る必要は全くありません。
「できること」や「興味のあること」、「理想の働き方」といった多角的な視点から企業選びの軸を設定することが可能です。
自己分析を丁寧に行い、インターンシップやOB・OG訪問などを通じて社会との接点を持つことで、行動する中で少しずつ自分の進むべき方向性が見えてくるものです。
企業側も、完成された答えよりも、学生が真剣に自分のキャリアについて考え、努力する姿勢やそのポテンシャルを評価します。
この記事で紹介した考え方や方法を参考に、自分なりの言葉で考えをまとめ、自信を持って就職活動に臨んでください。
社会経験の少ない学生が、限られた情報の中で業界や企業を選ぶのは当然難しいことです。
まず大切なのは、「やりたいことがない=ダメ」ではないという理解です。就職活動(活動)では、“やりたいこと”よりも“興味を持てること”や“自分の強みを活かせそうな場”を探すことが出発点になります。自己分析ツールや性格診断を使って自分の価値観や得意なことを整理し、アルバイトやインターンシップなどの体験を通じて「合う」「合わない」を検証してみましょう。
また、「とりあえず応募」は迷走の原因にもなりますが、複数の企業や業界を見て“比較する”こと自体はアリです。例えばリクナビなどの就活サイトで興味が少しでもある企業をピックアップし、仕事内容や社員の話を聞くことで理解が深まります。自分の軸(価値観・優先順位)を整理することが、最終的にマッチする企業選びのポイントになります。
面接では「やりたいことがわからない」と答えるより、「現場で経験を積み、自分のキャリアを考えたい」「社会人として成長できる環境に魅力を感じる」と前向きに表現すると好印象です。就活エージェントやキャリアセンターに相談するのも有効な方法です。
「やりたいことがない」時期は、人生の方向性を考える貴重なプロセス。焦らず、多くの情報に触れ、体験し、考えることで、自分に合った“働く道”が見えてきます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む