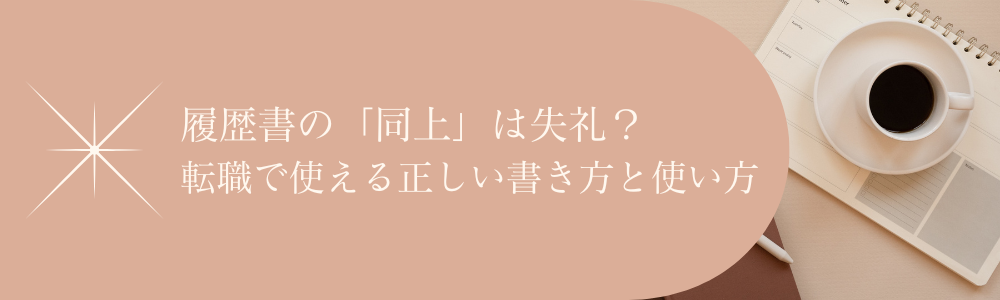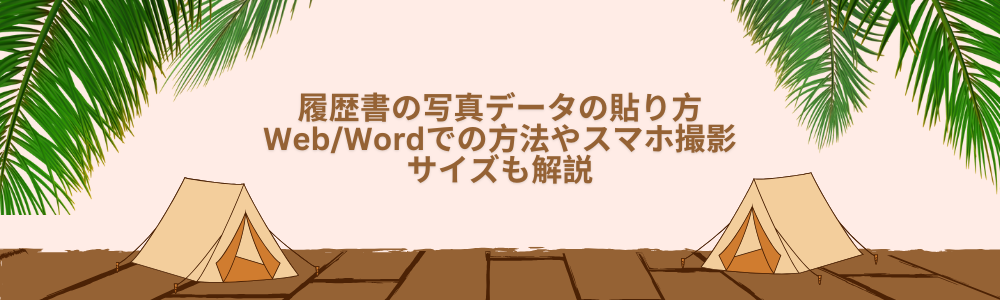大学生の就活はいつから始める?【27卒・28年卒・29年卒向け】スケジュールとやるべきこと
大学生の就活はいつから始めるべきか、多くの大学生が悩む問題です。
近年、就職活動の早期化が進んでおり、27卒以降の大学生も早めの準備が求められます。
しかし、ただ早く就活を始めれば良いというわけではありません。
本記事では、最新の動向を踏まえつつ、学年別の具体的ないつから始めるか就活スケジュールと、それぞれの段階でやるべきことを網羅的に解説します。
全体像を把握し、いつから計画的に行動を起こすのが良いか参考にしてください。
大学生の就活はいつから始めるべき?近年の早期化傾向を解説
大学生の就活の時期は年々早まる傾向にあります。
かつては大学3年生の3月に広報活動が解禁され、4年生の6月から選考が始まるのが一般的でした。
しかし現在、このルールは形骸化しつつあり、多くの企業が大学3年生の夏に参加するインターンシップを事実上の選考プロセスとして活用しています。
26卒の就活でもその傾向は顕著で、インターンシップ経由の早期選考で内定を得る学生が増加しました。
この流れは今後も続くと予想されるため、就職活動が本格的に始まるのは大学3年生の春から夏と捉え、それ以前から準備を進める意識が重要です。
【27卒向け】大学3年生から卒業までの就活全体スケジュールはいつから、いつまで?
27卒学生の就職活動は、大学3年生の春から本格的に始動します。
一般的な流れとしては、まずサマーインターンシップへの参加を目指し、自己分析や業界研究を進めます。
秋以降は秋冬インターンシップに参加しつつ、本選考に向けた準備を具体化させていきます。
そして大学3年の3月には企業説明会が本格化し、エントリーシートの提出が開始。
大学4年生の6月頃から面接などの選考がピークを迎え、内々定を獲得し、10月の正式な内定へと進みます。
このスケジュールを念頭に置き、計画的に行動することが求められます。
大学3年生(4月〜8月):サマーインターンシップの情報収集と応募
大学3年生の4月頃から、多くの就活情報サイトがオープンし、夏のインターンシップ情報が公開され始めます。
この時期は、まずどのような業界や企業があるのかを幅広く調べ、興味のある分野を見つけることが重要です。
サマーインターンシップは、企業を深く知る絶好の機会であり、選考に直結することも少なくありません。
人気企業のインターンシップは選考倍率が高いため、エントリーシートの準備やWebテスト対策が必須です。
6月頃にはエントリー受付が本格化するため、余裕を持って準備を進める必要があります。
就職活動のスタートダッシュを切るためにも、広報活動が解禁される翌年3月を待たずに行動を開始することが求められます。
大学3年生(9月〜2月):秋冬インターンシップ参加と自己分析の深化
夏のインターンシップが終わる9月以降は、その経験を振り返り、自己分析をさらに深める時期です。
サマーインターンシップで感じたことや学んだことを整理し、自分の強みや興味の方向性をより明確にしていきます。
また、この時期には秋冬インターンシップの募集も始まります。
夏に参加できなかった業界や、さらに理解を深めたい企業のインターンシップに参加することで、視野を広げることが可能です。
一部の企業では、インターンシップ参加者を対象とした早期選考が始まることもあります。
大学4年次の本格的な選考を見据え、面接の練習を始めるなど、より実践的な準備を進めていくことが有効です。
大学3年生(3月〜):企業説明会への参加とエントリーシートの提出開始
大学3年生の3月1日からは、経団連の指針に沿って多くの企業で広報活動が解禁され、就職活動が本格化します。
この時期になると、企業の採用サイトがオープンし、単独の企業説明会や複数の企業が集まる合同説明会が全国各地で頻繁に開催されます。
同時に、本選考へのエントリーシート提出も開始されるため、学生は非常に多忙な日々を送ることになります。
説明会に参加して企業の情報を集めながら、自己分析や企業研究の成果をエントリーシートに落とし込む作業が求められます。
複数の企業の選考を同時に進めることになるため、緻密なスケジュール管理が不可欠です。
大学4年生(6月〜):面接や筆記試験など本格的な選考がスタート
大学4年生の6月1日以降は、企業の採用選考活動が公式に解禁され、面接や筆記試験が本格的に始まります。
エントリーシートによる書類選考を通過した学生は、グループディスカッションや複数回の個人面接などに臨むことになります。
ただし、これはあくまで経団連の指針であり、実際にはこれより早い段階で選考を進め、内々定を出す企業も少なくありません。
特にインターンシップ経由の早期選考は一般的になっています。
そのため、大学1年生や2年生といった早い段階からキャリアについて考え、準備を進めてきた学生が有利になる傾向があります。
6月を待つのではなく、常に選考を意識した準備を継続することが重要です。
大学4年(10月〜):内々定の獲得と承諾
大学4年生の10月1日は、多くの企業で正式な内定式が行われる日です。
この日までに、学生は企業から通知される「内々定」を承諾するかどうかを決定する必要があります。
内々定とは、企業と学生の間で交わされる「10月1日以降に内定を出す」という約束のことです。
複数の企業から内々定を得た場合は、これまでの就職活動で深めてきた自己分析や企業研究を基に、自分にとって最適な一社を慎重に選び、入社の意思を伝えます。
入社承諾書を提出した後は、内定者懇親会や研修などのイベントに参加し、社会人になるための準備を進めていくことになります。
自分に合ったやり方で企業を選び抜くことが大切です。
【28卒・29卒向け】大学1・2年生から始められる就活準備
就職活動の早期化が進む中、28卒や29卒の大学1・2年生も、早い段階からキャリアを意識することが有益です。
本格的な選考対策をする必要はありませんが、低学年のうちから自己分析の基礎となる経験を積んだり、社会への理解を深めたりすることは、将来の選択肢を広げます。
例えば、学業やサークル活動に主体的に取り組む、興味のある分野のニュースに触れるなど、日々の大学生活の中に準備のヒントは隠されています。
5月からキャリアイベントの情報を探し始めるなど、少しずつ行動を起こすことが、大学3年生になった時の大きなアドバンテージになります。
自分の興味や得意なことを見つける自己分析
大学1・2年生の段階で行う自己分析は、就活のためだけでなく、充実した大学生活を送るためにも重要です。
この時期は、履修する授業やサークル活動、アルバイトなど、様々な選択肢の中から自分で決断する機会が増えます。
それらの経験を通して、自分がどのようなことに興味を持ち、何が得意で何が苦手なのかを意識的に考えることが自己分析の第一歩です。
将来やりたいことがわからないと感じていても、過去の経験を振り返り、自分が熱中できたことや達成感を得られた瞬間を書き出してみるのが有効です。
こうした日々の積み重ねが、後のキャリア選択における自分の軸を形成していきます。
社会にはどんな仕事があるのかを知る業界研究
低学年のうちから社会に目を向けることは、将来の可能性を広げる上で非常に有効です。
特定の期間に限定せず、継続的に業界研究を行うことを推奨します。
普段利用しているサービスや商品が、どの業界のどのような企業によって提供されているのかを調べてみるだけでも、社会の仕組みへの理解が深まります。
スマートフォン一つをとっても、通信、メーカー、ソフトウェア、広告など多くの業界が関わっています。
業界地図などの書籍を読んでみたり、気になる企業のウェブサイトを覗いてみたりすることで、これまで知らなかった仕事の存在に気づくことができます。
いつまでという期限を設けず、知的好奇心を持って様々な業界に触れることが大切です。
ガクチカとして語れる経験を大学生活で積む
就職活動で頻繁に問われる「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」は、大学3年生になってから急に作れるものではありません。
大学1・2年生の時間をどう過ごすかが、ガクチカの中身を大きく左右します。
学業で高い成績を目指す、部活動やサークルで目標達成に向けて仲間と協力する、アルバイトで責任ある役割を担う、ボランティアや留学に挑戦するなど、何でも構いません。
重要なのは、自ら目標を設定し、課題解決のために試行錯誤した経験です。
主体的に行動し、その過程で何を考え、どう成長したのかを自分の言葉で語れるように、日々の活動に目的意識を持って取り組むことが、説得力のあるエピソードにつながります。
低学年向け仕事体験やオープン・カンパニーに参加する
近年、企業は大学1・2年生を対象としたキャリアイベントを積極的に開催しています。
これらは「オープン・カンパニー」や業界研究セミナーといった名称で実施され、選考とは切り離された形で、学生が企業や社会について知る機会を提供することを目的としています。
内容は、企業説明や職場見学、若手社員との座談会など様々です。
これらのイベントに参加することで、働くことの具体的なイメージを掴み、社会人から直接話を聞くことで自分のキャリア観を醸成できます。
学業や課外活動と両立しながら、気軽に参加して視野を広げる良い機会として活用することが推奨されます。
本格的な就活開始前にやっておきたい7つの準備リスト
就職活動が本格化する大学3年生の春を迎える前に、計画的に準備を進めておくことで、その後の活動をスムーズに進めることができます。
自己分析や業界研究といった基本的な準備はもちろん、筆記試験対策やOB・OG訪問など、やるべきことは多岐にわたります。
ここでは、本格的な就活シーズンが始まる前に着手しておきたい7つの準備項目を紹介します。
これらを一つひとつ着実にこなしていくことが、納得のいく企業選びと内定獲得への近道となります。
「自分」という人間を深く知るための自己分析
自己分析は、就職活動におけるすべての土台となります。
自分の過去の経験を時系列で振り返る自分史や、モチベーションの源泉を探るモチベーショングラフを作成することで、自分の価値観、強み、弱みを客観的に把握します。
なぜその大学・学部を選んだのか、どんな活動に熱中してきたのかを深掘りし、自分の行動原理を言語化することが重要です。
この作業を通じて明確になった「自分の軸」は、業界・企業選びの基準となり、エントリーシートや面接で語る自己PRや志望動機の根幹を形成します。
時間をかけて丁寧に行い、自分という人間を深く理解することが、ミスマッチのない就職につながります。
「社会」の仕組みを理解するための業界研究
自己分析で自分の興味や適性がある程度見えてきたら、次は社会に目を向けて業界研究を行います。
世の中には、メーカー、商社、金融、IT、サービスなど多種多様な業界が存在し、それぞれが異なるビジネスモデルで成り立っています。
まずは業界地図などを活用して、どのような業界があるのか全体像を掴むのが有効です。
その上で、興味を持った業界について、市場規模や成長性、将来の動向、主要な企業などを詳しく調べていきます。
一つの業界だけでなく、その周辺業界や関連性の薄い業界にも目を向けることで、より広い視野で自分のキャリアを考えることが可能になります。
「働きたい会社」を見つけるための企業研究
業界研究で興味のある分野が絞れてきたら、次はその中の個別の企業について調べる企業研究に進みます。
同じ業界に属していても、企業によって事業内容、強み、社風、企業理念は大きく異なります。
企業の採用ホームページやIR情報、中期経営計画などを読み込み、その企業が何を目指しているのか、社会にどのような価値を提供しているのかを理解します。
競合他社と比較し、その企業ならではの特徴や魅力を自分なりに分析することが重要です。
インターンシップや説明会に参加して、実際に働く社員の雰囲気を感じることも、自分に合う企業を見極める上で欠かせないプロセスです。
「やりたい仕事」を具体的にする職種研究
企業研究と並行して職種研究も行う必要があります。
「総合職」として一括で採用される場合でも、企業内には営業、マーケティング、企画、人事、経理、研究開発など、様々な仕事が存在します。
それぞれの職種がどのような役割を担い、どのようなスキルが求められ、どのようなキャリアパスを歩むのかを理解することが大切です。
自分の強みや興味が、どの職種で最も活かせるのかを考えることで、入社後の働く姿をより具体的にイメージできます。
職種への理解を深めることは、エントリーシートや面接で「入社後に何をしたいか」を明確に伝えるためにも不可欠です。
エントリーシート(ES)で伝えるエピソードを整理する
エントリーシートや面接で必ず問われる「自己PR」や「学生時代に力を入れたこと」に備え、事前に伝えるエピソードを整理しておきます。
自己分析で見つけ出した自分の強みや特性を、具体的な行動経験によって裏付けられるように準備することが重要です。
例えば「リーダーシップがある」という強みを伝えたいなら、サークル活動などで目標達成のために周囲をどのように巻き込み、困難をどう乗り越えたのかを詳細に語れるようにします。
STARメソッド(状況、課題、行動、結果)を意識してエピソードを構造化すると、相手に伝わりやすくなります。
複数のエピソードを用意し、企業の求める人物像に合わせて使い分けられると理想的です。
SPIや玉手箱などのWebテスト・筆記試験対策
多くの企業が選考の初期段階でSPIや玉手箱といったWebテストや筆記試験を実施します。
この試験を通過できなければ面接に進むことすらできません。
内容は言語(国語)、非言語(数学)、性格検査が中心ですが企業によっては英語や構造把握力検査などが加わることもあります。
問題の形式には独特の傾向があるため事前の対策が結果を大きく左右します。
まずは市販の対策本を一冊購入し繰り返し解いて問題形式に慣れることが基本です。
特に非言語分野は解法のパターンを覚えることで時間内に解答できる問題が増えるため早期から計画的に学習を進めることが不可欠です。
社会人の先輩からリアルな話を聞くOB・OG訪問
OB・OG訪問は、企業のウェブサイトや説明会では得られない、現場のリアルな情報を得るための貴重な機会です。
大学のキャリアセンターや、ゼミ・研究室のつながりを利用して、興味のある企業で働く先輩社員を紹介してもらい、話を聞きます。
仕事の具体的な内容や一日の流れ、やりがい、大変なこと、職場の雰囲気など、実際に働いているからこそ語れる生の声は、企業理解を深め、志望動機をより具体的にする上で非常に役立ちます。
また、社会人と一対一で話す経験は、面接の良い練習にもなります。
事前に質問事項をしっかり準備し、主体的な姿勢で臨むことが求められます。
就活を早くから始める3つのメリット
就職活動を早期に始めることには、多くのメリットが存在します。
時間に余裕が生まれることで、一つひとつの準備にじっくりと取り組むことができ、結果として選考を有利に進められる可能性が高まります。
ここでは、早くから行動を起こすことで得られる代表的な3つのメリットについて具体的に解説します。
これらの利点を理解し、計画的なスタートを切ることが、納得のいく就活につながります。
余裕を持って自己分析や企業研究に取り組める
就職活動を早く始める最大のメリットは、自己分析や企業研究といった準備に十分な時間を確保できることです。
就活が本格化すると、説明会への参加やエントリーシートの提出、面接対策などで多忙を極め、自分自身と向き合ったり、業界を深く掘り下げたりする時間が取りにくくなります。
早期から着手すれば、何度も自己分析を繰り返して自分の軸を確立したり、これまで知らなかった業界や企業にまで視野を広げたりすることが可能です。
この時間的な余裕が精神的な安定にもつながり、焦らずに自分に合った企業をじっくりと見極めることができるようになります。
インターンシップ参加で企業への理解が深まる
早期から就活を意識することで、インターンシップに参加できる機会が増えます。
特にサマーインターンシップは、大学3年生の夏に実施されるため、早い段階からの情報収集と準備が不可欠です。
インターンシップは、企業のオフィスで実際の業務に近い内容を体験できる貴重な機会であり、ウェブサイトや説明会だけでは分からない社内の雰囲気や文化を肌で感じられます。
社員の方々と直接交流することで、仕事のやりがいや厳しさについてリアルな話を聞くこともできます。
こうした経験を通じて企業への理解が深まることは、入社後のミスマッチを防ぎ、説得力のある志望動機を作成する上で大きなアドバンテージとなります。
早期選考で早い時期に内定を得られる可能性がある
近年、多くの企業がインターンシップ参加者などを対象とした早期選考を実施しています。
早くから就職活動を始め、インターンシップで高い評価を得ることで、通常の選考スケジュールよりも早い段階で選考に進み、内々定を獲得できる可能性があります。
早い時期に一つ内々定を持っていると、「まだ持ち駒がある」という精神的な安心感が生まれます。
その後の就職活動では、プレッシャーから解放され、より挑戦的な気持ちで本当に自分が行きたい企業の選考に臨むことができるようになります。
この精神的な余裕は、面接でのパフォーマンスにも良い影響を与えることがあります。
就活のスタートがいつからか知らずに出遅れた場合に起こりうるデメリット
就職活動の開始が遅れると、デメリットが生じる可能性があります。
準備期間が短くなることで、精神的な焦りが生まれたり、機会を逃してしまったりすることも考えられます。
ここでは、就活のスタートが出遅れることによって起こりうる3つのデメリットを解説します。
これらのリスクを理解し、早めの行動を心掛けることが重要です。
準備不足のまま選考に臨むことになり焦ってしまう
就活のスタートが遅れると、自己分析や企業研究が不十分なまま選考に臨まざるを得ない状況に陥りがちです。
自分の強みや志望動機を明確に言語化できていないため、エントリーシートの内容が薄くなったり、面接で説得力のある回答ができなかったりします。
選考に落ち続けると、「何が悪いのかわからない」という状態になり、さらに焦りが募ります。
この焦りが冷静な判断力を奪い、自己分析や企業研究に集中できなくなるという悪循環を引き起こすことも少なくありません。
十分な準備期間を確保できないことが、精神的な負担を増大させる大きな要因となります。
志望企業のインターンシップや本選考を逃す恐れがある
就職活動の早期化に伴い、企業の情報公開やエントリーの締め切りも早まっています。
特に、人気企業のサマーインターンシップは大学3年生の春から初夏にかけて募集が締め切られることがほとんどです。
のんびりしていると、気づいた時には応募期間が終わっていたという事態になりかねません。
また、本選考においても、企業によっては採用予定人数に達した段階で募集を終了することがあります。
スタートが遅れることは、こうした貴重な機会を失うリスクを直接的に高めます。
志望度の高い企業への挑戦権を確保するためにも、早期からの情報収集は不可欠です。
周囲が内定を獲得し始めると精神的に追い込まれやすい
大学4年生の春から夏にかけて、友人や知人がSNSなどで内定獲得を報告し始める時期が来ます。
就活のスタートが遅れ、まだ内定がない状況でこうした情報に触れると、「自分だけが取り残されている」という強い焦りや劣等感を感じやすくなります。
周囲と比較してしまうことで精神的に追い込まれ、本来の自分のペースを見失ってしまうことも少なくありません。
このプレッシャーから、本心では納得していない企業に妥協して就活を終えてしまうケースも見られます。
自分の軸を保ちながら活動を続けるためにも、周囲の状況に惑わされないだけの準備と自信が必要です。
大学生の就活に関するよくある疑問
就職活動には、多くの学生が共通して抱く疑問や不安があります。
就活をいつ終えるべきか、準備が遅れてしまった場合の対処法、あるいはやりたいことが見つからない時の考え方など、悩みは多岐にわたります。
ここでは、そうした大学生の就活に関するよくある疑問を取り上げ、それぞれの問いに対する考え方や具体的な対処法を解説します。
正しい知識を得ることで、不要な不安を解消し、前向きに就活に取り組むことができます。
一般的な就活はいつから始まり、いつ終わるもの?
就職活動の開始時期と終了時期は、学生一人ひとりによって大きく異なります。
経団連のルールに則れば、正式な内定が出るのは大学4年生の10月1日ですが、それより前に内々定を得て活動を終える学生が多数派です。
特に早期選考ルートに乗った場合、大学4年生の春頃に就活を終えるケースも珍しくありません。
一方で、秋以降も採用活動を継続している企業は多く、自分の納得がいくまで卒業間際まで活動を続ける学生もいます。
したがって、「いつまでに終わらせなければならない」という決まりはありません。
自分が心から入社したいと思える企業から内定を得られた時が、その人にとっての就活のゴールです。
大学3年生でまだ何もしていないのは手遅れ?
大学3年生の夏や秋の時点で何も準備をしていなくても、決して手遅れではありません。
実際に、多くの学生がその時期から本格的に就職活動をスタートさせます。
重要なのは、出遅れたという事実に焦るのではなく、今から何をすべきかを冷静に考えて行動に移すことです。
まずは自己分析や業界研究といった基本から着実に始め、秋冬のインターンシップや説明会に積極的に参加しましょう。
残された時間を有効に使うために、計画を立てて効率的に準備を進めることが挽回の鍵となります。
周りと比較せず、自分のペースでやるべきことを一つひとつこなしていく姿勢が求められます。
企業説明会には何社くらい参加すればいい?
企業説明会に何社参加すべきかという明確な基準や正解はありません。
重要なのは参加した社の数ではなく、その経験を通じてどれだけ視野を広げ、企業理解を深められたかという質です。
就活序盤は、業界を絞らずに合同説明会などを活用して、できるだけ多くの企業に触れることをおすすめしますめ。
様々な企業の話を聞く中で、自分の興味の方向性や企業選びの軸が徐々に明確になっていきます。
その後、興味を持った企業の個別説明会に参加し、より詳細な情報を得るという段階的な進め方が効率的です。
数を目標にするのではなく、一つひとつの説明会で何を得たいのか目的意識を持つことが大切です。
特にやりたいことが見つからない時の対処法は?
就職活動を始めても「特にやりたいことが見つからない」と悩む学生は少なくありません。
その場合、まず「やりたいこと」ではなく「やりたくないこと」をリストアップし、消去法で選択肢を絞っていくアプローチが有効です。
また、「好き」を仕事にするのではなく、「できること」や「得意なこと」を軸に仕事を探すのも一つの方法です。
自己分析を通して自分の強みを把握し、その強みが活かせる業界や職種を検討してみましょう。
インターンシップやOB・OG訪問で社会人と接点を持ち、働くことの解像度を上げていく中で、興味が湧いてくることもあります。
最初から完璧な答えを求めず、行動しながら探していく姿勢が重要です。
まとめ
大学生の就職活動は、近年の早期化傾向により、大学3年生になる前から準備を意識することが重要になっています。
特に27卒以降の学生は、大学3年生の夏に行われるインターンシップが実質的な選考のスタート地点となることを念頭に置き、計画的に行動する必要があります。
低学年のうちから自己分析の基礎となる経験を積み、社会への理解を深めておくことが、後の活動を有利に進める上で有効です。
就活の準備には、自己分析、業界・企業研究、筆記試験対策、OB・OG訪問など多岐にわたる項目が含まれます。
出遅れたと感じた場合でも焦る必要はなく、今やるべきことを着実にこなしていくことが、納得のいくキャリア選択につながります。
大学生の就活は「いつから始める?」という質問は、毎年Yahoo!知恵袋などでも多く見られる定番テーマです。一般的に、26卒・27卒・28卒と年次が進むにつれ、就活の「早期化」が進んでいます。経団連のルールが事実上なくなったことで、リクナビやOfferBoxなどのオファー型サービスを活用した早期インターン参加や企業登録が重要になっています。特に理系学生は研究や実験との両立を考え、文系よりも早めに動く傾向が多いです。
スケジュールとしては、2026年卒は3年生の夏からインターンが始まり、秋冬インターンで志望業界を絞り込み、2027卒はさらに前倒しで2年生から動く学生も増加。政府や大学のガイドライン上では「3月解禁・6月選考開始」とされていますが、外資系・ベンチャー企業では年中採用活動を実施しているのが実情です。マスコミや日系大手企業は依然としてルールに沿った動きを見せる一方、中小やスタートアップは独自のスケジュールを持ち、就活サイトや合同説明会、Webテスト準備などが並行して進みます。
就活を成功させるポイントは「早めの行動と記録」。エントリーや面接で話すガクチカ(学生時代頑張ったこと)は、早期インターンや課外活動を通じて磨かれるため、大学2年・3年のうちから体験を積むことがカギです。リクナビやOfferBoxへの登録を済ませ、気になる企業をチェックし、オファーを受け取る準備を整えましょう。早めのスタートが、理想の企業との出会いにつながります。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む