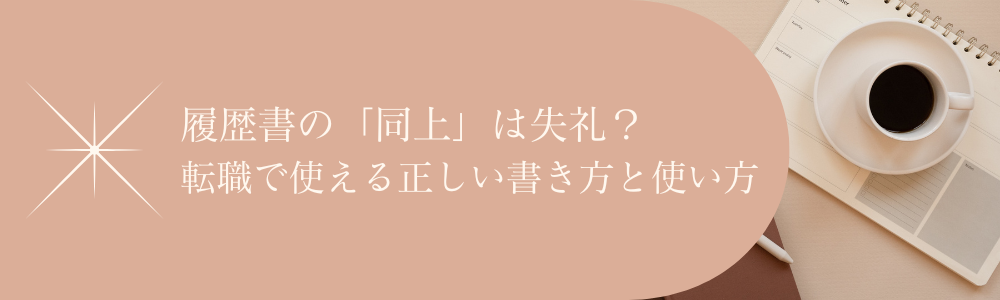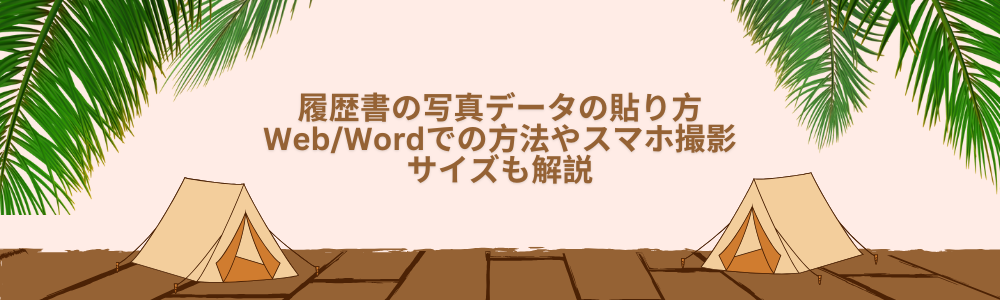会社説明会の質問例69選!好印象な聞き方とマナー、浮かばない時の対策
就活における会社説明会の質問は、企業へのアピールとミスマッチ防止の重要な機会です。
この記事では、新卒の就活生向けに、会社説明会で使えるおすすめの質問集例文を一覧で提供します。
カテゴリ別の豊富な例に加え、好印象を与える聞き方のマナーや、質問が浮かばない時の対策も解説するので、ぜひ参考にしてください。
会社説明会で質問することが企業へのアピールにつながる理由
会社説明会で質問することは、他の就活生と差をつける絶好の機会です。
ただ受け身で説明を聞くだけでなく、能動的に疑問点を解消しようとする姿勢は、企業側にとって魅力的に映ります。
鋭い質問をすることで、入社意欲の高さや企業研究の深さを示せば、選考を有利に進める一歩となり得ます。
企業への理解を深め、自分自身をアピールする有益な場として、質疑応答の時間を最大限に活用しましょう。
深い企業理解度を示せるチャンスになる
事前に企業のウェブサイトや公開情報を読み込んだ上で、さらに一歩踏み込んだ質問をすることで、企業への関心の高さと深い理解度をアピールできます。
例えば、中期経営計画を読んだ上で「中期経営計画に記載のあった〇〇という戦略について、新入社員はどのように貢献できるとお考えでしょうか」と尋ねることで、御社の将来性まで見据えていることを示せます。
表面的な情報だけでなく、事業の核心に迫るような問いかけは、他の学生との差別化を図る上で効果的です。
入社意欲の高さを採用担当者に伝えられる
具体的で的確な質問は、その企業で働きたいという熱意の表れとして人事担当者に伝わります。
自身のキャリアプランや身につけたいスキルと、企業の事業内容や求める人物像を結びつけた質問は、単なる志望動機の説明以上に説得力を持ちます。
例えば、「将来〇〇の分野で専門性を高めたいと考えているのですが、貴社にはどのようなキャリアパスがありますか」といった質問は、入社後の活躍イメージを具体的に持っていることの証明となり、志望度の高さを効果的に示せます。
入社後のミスマッチを防ぐ貴重な機会になる
会社説明会は、就職後のミスマッチを避けるために、自分が本当に聞きたい内容を確認できる貴重な場です。
ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない、社風や社員の働きがい、キャリアパスの実際など、リアルな情報を直接聞ける機会は多くありません。
ここで疑問点を解消しておくことで、入社後に「思っていたのと違った」と感じるリスクを減らせます。
自身の価値観や働き方の希望と企業文化が合っているかを見極めるためにも、積極的に質問をすることが求められます。
【カテゴリ別】会社説明会で使える質問例70選
ここでは、会社説明会で実際に使える質問をカテゴリ別に一覧で紹介します。
仕事内容から働き方、選考に関することまで、様々な角度からの質問リストを用意しました。
これらのよくある質問を参考に、自分が本当に知りたいことは何かを考え、質問を準備する際のたたき台として活用してください。
自分なりの言葉でアレンジを加えることで、より印象に残る質問になります。
仕事内容や事業に関する会社説明会での質問例
企業の事業内容や入社後に担当する仕事について深く理解するための質問は、働くイメージを具体化させます。
仕事のやりがいといったポジティブな側面だけでなく、課題や弱みについても尋ねることで、多角的な企業研究が可能です。
営業、IT、SE、エンジニアといった職種ごとの具体的な業務内容に踏み込むと、より志望度の高さが伝わるでしょう。
1:入社後の具体的な業務内容について教えてください
入社後の業務内容を尋ねる際は、配属先によって仕事がどう変わるのか、あるいはチームでどのような役割を担うのかといった視点を加えると、より深い回答が期待できます。
単に仕事内容を問うだけでなく、「若手社員は、どのような業務から担当することが多いのでしょうか」のように対象を絞ることで、自身のキャリアのスタート地点をより鮮明にイメージできます。
説明会で複数の職種が紹介された場合は、自分が最も関心のある職種について具体的に質問するのも有効です。
2:社員の方が感じる仕事のやりがいや魅力は何ですか
企業のウェブサイトやパンフレットには書かれていない、現場で働く社員の生の声を聞き出すための質問です。
この質問を通して、どのような点に価値を置いて仕事をしている人が多いのか、企業の文化や風土を垣間見ることができます。
可能であれば、「説明会に登壇されている〇〇様が、最も仕事のやりがいを感じたエピソードを教えていただけますか」のように、特定の社員に問いかけると、よりパーソナルで具体的な回答を得やすくなり、共感できるポイントが見つかるかもしれません。
3:業務で求められるスキルや資格はありますか
この質問は、入社後の活躍に向けて今から準備できることはないか、という前向きな姿勢を示すことにつながります。
特に専門職を志望する場合、必須となるスキルや歓迎される資格について具体的に聞いておくことで、自己研鑽の方向性が明確になります。
「〇〇という資格の取得を考えているのですが、業務に活かせる場面はありますか」といった形で、自身の学習意欲と関連付けて質問すると、より主体性をアピールできるでしょう。
4:仕事で困難に直面した際の乗り越え方について伺いたいです
仕事の成功体験だけでなく、困難な状況にどう対処するのかを尋ねることで、企業のカルチャーやサポート体制をより深く理解できます。
特に、先輩社員が後輩をどのようにフォローするのか、チームとしてどのように課題解決に取り組むのかといった点に注目すると、組織の風通しの良さや団結力を推し量れます。
個人の力だけでなく、周囲と協力しながら困難を乗り越えていく姿勢を重視する企業かどうかを見極めるための、重要な質問となります。
5:1日の業務スケジュールはどのような流れですか
入社後の働き方を具体的にイメージするために有効な質問です。
単にテンプレ的なタイムスケジュールを聞くだけでなく、「日によって業務の流れは大きく変わりますか」や「チームでのミーティングはどのくらいの頻度で行われますか」といった補足の問いを投げかけると、よりリアルな働き方が見えてきます。
外勤や内勤の割合、他部署との連携の頻度など、職種による特徴も合わせて確認しておくと、自分に合った働き方ができるかどうかの判断材料になります。
6:閑散期や繁忙期はいつ頃になりますか
業務の繁閑を知ることは、年間の働き方のリズムを理解する上で重要です。
繁忙期にはどのような業務が集中するのか、残業時間はどの程度になるのかを把握することで、ワークライフバランスを考える参考になります。
また、ノルマが設定されている職種であれば、繁忙期と目標達成のプレッシャーがどう関連するのかも気になるところです。
「繁忙期を乗り越えるために、チームで工夫していることはありますか」と付け加えることで、協力体制についても探ることができます。
7:貴社のサービスが持つ独自の強みは何だとお考えですか
競合他社と比較した際の企業の優位性や独自性を尋ねる質問は、深い企業分析を行っていることを示すのに効果的です。
事前に自分なりに分析した企業の強みを述べた上で、「私は貴社の〇〇という点に強みがあると考えているのですが、社員の皆様はどのようにお考えですか」と問いかけることで、一方的な質問ではなく、対話形式で企業理解を深めようとする姿勢が伝わります。
企業の自己認識と外部からの見え方の違いを知る良い機会にもなります。
8:今後の事業展開で特に注力していく分野はありますか
企業の将来性や成長戦略に対する関心の高さを示す質問です。
特に、社長や経営層が発信するメッセージ、中期経営計画などを踏まえた上で、「社長が〇〇の分野に注力するとお話しされていましたが、その背景や具体的な戦略について、もう少し詳しく教えていただけますか」と尋ねると、情報を深く読み解いていることが伝わります。
自身の将来のキャリアプランと企業の成長方向が一致しているかを確認する上でも、重要な問いかけとなるでしょう。
活躍する人材や評価に関する会社説明会での質問例
どのような人材が評価され、活躍しているのかを知ることは、自身がその企業で成長できるかを判断する上で欠かせません。
企業が求める人材像と自身の強みが合致しているかを確認することで、入社後のキャリアを具体的に描けます。
評価制度の透明性や内容について質問することは、働く上でのモチベーションにも関わる重要なポイントです。
1:貴社で高い評価を受けている社員の方に共通する特徴は何ですか
この質問は、企業がどのような価値観や行動指針を重視しているのかを具体的に理解するために役立ちます。
単に「主体性」や「協調性」といった抽象的な言葉ではなく、「若いうちから積極的に新しいプロジェクトを提案する人が評価される」といった具体的な人物像を聞き出すことが目的です。
得られた回答から、自分がその環境で輝けるかどうか、また目指すべき社員像を明確にイメージできるようになります。
企業の求める人材と自分の特性が合っているかを見極める指標になります。
2:若手社員に期待されている役割について教えてください
入社後、自身がどのようなことを期待され、どのような貢献を求められるのかを把握するための質問です。
若手社員に対して、まずは着実に業務を覚えることを求めるのか、あるいは早い段階から新しいアイデアを出すことを期待するのか、企業によってそのスタンスは異なります。
この質問を通じて、企業の育成方針や若手への期待度を知ることができ、自分の成長意欲や挑戦したい気持ちと企業の環境がマッチしているかを確認する手がかりになります。
3:成果を出すために最も重要だと考えられていることは何ですか
この質問は、企業の評価基準の根底にある価値観を探るためのものです。
例えば、個人の業績を重視するのか、チーム全体の成果を優先するのか、あるいはプロセスを評価する文化があるのかなど、成果に対する考え方は企業によって様々です。
回答から、その企業で働く上でどのような行動や思考が求められるのかを深く理解できます。
自分の仕事に対する価値観と企業の文化が合致しているかを見極めることで、入社後の満足度にも影響を与えるでしょう。
4:入社までに習得しておくべき知識やスキルがあれば教えてください
この質問は、入社意欲の高さと、学生のうちから準備を怠らない主体的な姿勢をアピールするのに効果的です。
具体的なスキルや知識を聞くことで、入社後のスタートダッシュをスムーズにするための準備ができます。
もし特定のスキルを挙げられた場合は、「そのスキルを習得するために、おすすめの書籍や学習方法はありますか」とさらに踏み込んで尋ねると、より熱意が伝わります。
企業側も、学習意欲の高い学生に対して好印象を抱く傾向にあります。
職場の雰囲気や社風に関する会社説明会での質問例
職場の雰囲気や社風は、働きやすさや仕事への満足度に直結する重要な要素です。
ウェブサイトだけでは分からない、実際の職場の人間関係やコミュニケーションの取り方を知ることで、自分に合った環境かどうかを判断できます。
社員同士の交流や上司との関係性など、リアルな雰囲気について質問することは、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。
1:部署内やチームでのコミュニケーションはどのように取っていますか
チームワークを重視する姿勢を示すとともに、職場のコミュニケーションスタイルを知るための質問です。
定例会議の頻度や、チャットツールなどのITツールの活用度、あるいは雑談が生まれやすい雰囲気があるかなど、具体的なコミュニケーション手段について尋ねることで、職場の風通しの良さが想像できます。
自分がどのような環境で能力を発揮しやすいかを考えながら、企業のコミュニケーション文化が自分に合っているかを見極めることが重要です。
2:上司や先輩社員との関わり方について教えてください
若手社員が成長していく上で、上司や先輩との関係性は非常に重要です。
メンター制度のように、新入社員をサポートする仕組みが整っているか、あるいは業務で困った際に気軽に相談できる雰囲気があるかなどを確認しましょう。
「1on1ミーティングのような、上司と一対一で話す機会は定期的に設けられていますか」といった具体的な質問をすることで、企業が社員の成長やキャリアにどれだけ向き合っているかの姿勢を伺い知ることができます。
3:他部署の社員と交流する機会はありますか
組織の風通しの良さや、部門間の連携がスムーズに行われているかを探るための質問です。
社内イベントや部活動、あるいは部門横断型のプロジェクトなど、他部署との交流を促進する具体的な取り組みについて尋ねてみましょう。
こうした機会が多ければ、多様な知識や価値観に触れることができ、自身の視野を広げることにもつながります。
組織全体としての一体感や、社員同士のつながりを大切にする社風があるかどうかを見極める一つの指標になります。
4:社員の皆さんが仕事のモチベーションを維持する方法を教えてください
この質問は、社員がどのようなことにやりがいを感じ、仕事への意欲を保っているのか、その源泉を探るためのものです。
企業の理念への共感、顧客からの感謝、あるいは自己成長の実感など、モチベーションの源は人それぞれです。
登壇している社員個人の価値観に触れることで、企業の魅力や働く人々の姿勢をより深く理解できます。
「〇〇様が仕事で最もワクワクする瞬間はどのような時ですか」のように個人に焦点を当てて尋ねると、より本音に近い回答が期待できます。
5:社内の交流を深めるためのイベントなどは開催されますか
社員同士のつながりを大切にする社風があるかを知るための質問です。飲み会や社員旅行といった伝統的なイベントだけでなく、部活動やサークル活動、ファミリーデーなど、企業独自のユニークな取り組みについて聞いてみるのも良いでしょう。こうしたイベントの有無や参加率から、社員同士の仲の良さや、仕事以外でのコミュニケーションを重視する文化があるかを推測できます。自分がどのような環境を好むかと照らし合わせて、社風がマッチするかを判断する材料になります。
6:社員の意見が経営や現場に反映される機会はありますか
風通しの良い職場かを判断する質問です。
「現場の声が新しい制度やサービス開発に生かされた事例はありますか」と具体的に尋ねると、企業文化がより明確に見えます。
7 :上司との定期的な面談やフィードバック制度はありますか
社員の成長支援体制を探る質問です。
1on1ミーティングやキャリア面談の有無は、社員を大切にする企業ほど充実しています。
8:社員が働きやすいと感じる理由を教えてください
社員目線のリアルな環境を知ることができる質問です。
制度面だけでなく、心理的安全性や人間関係の側面を探ることができます。
9:女性社員や育児中の社員の活躍事例はありますか
ダイバーシティ推進の取り組みを探る質問です。
女性管理職比率や育休復帰後の支援制度の運用状況なども併せて確認できます。
10:働き方改革として実施している取り組みがあれば教えてください
リモートワーク、時短勤務、フレックス制度など、柔軟な働き方を支援しているかを把握する質問です。
「制度だけでなく、実際にどの程度利用されているか」を聞くことで、実効性を確認できます。
11:チーム内で意見の違いが出たとき、どのように解決していますか
チームワークやコミュニケーションの質を探る質問です。
対話重視なのか、リーダー判断なのかなど、組織文化の特徴が見えてきます。
12:入社後すぐに相談できる先輩や上司はいますか
フォロー体制の有無を確認する質問です。
メンター制度やOJT担当の存在は、新入社員にとって安心材料になります。
13:社内で感謝や称賛を伝える仕組みはありますか
社員同士の関係性やモチベーション維持施策を知るための質問です。
「サンクスカード」や「表彰制度」がある企業も多く、文化の成熟度を測る指標になります。
14:上司との距離感はどのような雰囲気ですか
上下関係のフラットさや心理的安全性を探る質問です。
自由に意見を言える環境かどうかを見極めるポイントになります。
15:新入社員が職場に早く馴染むために工夫していることはありますか
新人受け入れ文化を探る質問です。
オンボーディングやチームビルディングの工夫から、企業の人材育成姿勢を感じ取れます。
キャリアパスや成長環境に関する質問例
入社後のキャリアプランを真剣に考えていることを示し、自己成長への意欲をアピールするカテゴリです。
研修制度やスキルアップ支援、キャリアアップのモデルケースなどを質問することで、企業が社員の成長をどれだけサポートしてくれる環境なのかを判断できます。
自身の目指す将来像と、企業が提供できるキャリアパスが合致しているかを見極めることが重要です。
1:新入社員が早期に活躍するための研修制度について教えてください
入社後の教育体制について具体的に知るための質問です。
新人研修の内容や期間、OJT(On-the-JobTraining)の進め方、メンター制度の有無など、新入社員をどのように育成していくのかを確認しましょう。
「研修期間終了後も、継続的にスキルアップを支援するプログラムはありますか」と付け加えることで、長期的な視点で人材育成を考えている企業かどうかを見極めることができます。
成長意欲の高い姿勢をアピールすることにもつながります。
2:若手社員が裁量を持って働ける機会はありますか
早い段階から責任のある仕事を任せてもらえる環境か、挑戦を奨励する社風があるかを知るための質問です。
若手社員がプロジェクトの主要メンバーとして関わった事例や、新規事業の提案が採用されたケースなどを具体的に尋ねることで、企業の挑戦に対する姿勢が分かります。
「入社何年目くらいから、大きな裁量を与えられることが多いのでしょうか」と聞くことで、キャリアアップのスピード感を把握する手がかりにもなり、自身の成長意欲と企業の環境が合っているかを判断できます。
3:〇〇職でのキャリアモデルについて具体的に教えてください
自身のキャリアプランを具体的に描けていることを示し、入社後の姿を真剣に考えていることをアピールする質問です。
特定の職種におけるキャリアパスの例を尋ねることで、将来的にどのようなポジションを目指せるのか、どのようなスキルを身につけられるのかを把握できます。
「〇〇職で活躍されている方が、どのようなキャリアを経て現在のポジションに就かれたのか、具体的な事例を教えていただけますか」と尋ねると、より現実的なキャリアイメージを持つことができます。
4:社員のスキルアップを支援する制度はありますか
自己成長意欲の高さを示し、企業が社員の能力開発にどれだけ投資しているかを知るための質問です。
資格取得支援制度や外部研修への参加費補助、eラーニングの導入など、具体的な支援制度について尋ねましょう。
これらの制度が実際にどの程度利用されているのか、利用した社員の声なども合わせて聞けると、制度が形骸化していないかどうかも判断できます。
主体的に学び続ける姿勢は、どの企業においても高く評価される要素です。
5:希望する部署への異動は可能でしょうか
長期的な視点でキャリアを築いていきたいという意思表示になる質問です。
社内公募制度や自己申告制度など、キャリアの方向性を自分で選択できる仕組みがあるかを確認しましょう。
異動の頻度や実現のしやすさ、また、どのような経験やスキルがあれば希望が通りやすいのかを具体的に尋ねることで、キャリアプランの柔軟性を判断できます。
入社後のキャリアアップやキャリアチェンジの可能性を探る上で、重要な情報となります。
6:昇進や昇格はどのような基準で決まりますか
透明性や公正さを確認する質問です。
成果主義か、プロセス重視かによって評価文化が異なります。
7:キャリア面談はどのくらいの頻度で実施されていますか
キャリア支援体制を探る質問です。
自分の成長目標を上司と共有する機会が多い企業ほど、長期的に活躍しやすい環境といえます。
8:自己申告制度や社内公募制度はありますか
自分の希望を伝えられる仕組みがあるかを確認できます。
主体的にキャリアを築きたい学生にとって重要なポイントです。
9:挑戦したいことを提案できる仕組みはありますか
社内起案制度や新規事業提案制度の有無を尋ねることで、社員の自主性を尊重する文化を確認できます。
10:どのような社員が長く活躍されていますか
定着している人材の特徴を知ることで、自分との相性を判断できます。
「どのような理由で長く働いている方が多いのか」を聞くと、企業の強みが浮かび上がります。
働き方や福利厚生に関する会社説明会での質問例
ワークライフバランスを重視する現代において、働き方や福利厚生に関する情報は企業選びの重要な判断基準です。
残業時間や休暇制度、リモートワークの導入状況などを確認することで、自分らしい働き方が実現できるかを見極めます。
ただし、待遇面だけに質問が偏らないよう、他のカテゴリの質問とバランスを取ることが大切です。
1:月平均の残業時間はどのくらいですか
ワークライフバランスを考える上で、残業時間は重要な指標の一つです。
部署や職種による違いや、繁忙期の残業時間についても合わせて確認すると、より実態に近い情報を得られます。
また、「残業を減らすために、会社としてどのような取り組みをされていますか」と質問することで、企業の働き方改革への意識の高さを測ることも可能です。
休日出勤の有無やその際の代休制度についても、併せて聞いておくと良いでしょう。
2:有給休暇の平均取得日数を教えてください
制度として有給休暇が存在するだけでなく、実際に社員が休暇を取得しやすい雰囲気があるかどうかが重要です。
平均取得日数や取得率を尋ねることで、職場の働きやすさを推し量ることができます。
「連休や夏季休暇と合わせて、長期の休みを取得することは可能ですか」といった質問を付け加えると、プライベートとの両立を真剣に考えていることが伝わります。
休暇の取りやすさは、心身の健康を維持し、長く働き続けるための大切な要素です。
3:育児休業や介護休業を取得している社員の割合はどの程度ですか
ライフステージの変化に対応できる、長期的に働きやすい環境か見極める質問です。
男女別の取得率や復職後の働き方の事例について尋ねることで、企業の子育てや介護へのサポート体制が分かります。
これらの制度が実際に活用されているかは、社員を大切にする文化があるかの指標になります。
将来のライフプランを見据えた際に、安心して働き続けられる企業か判断する上で重要であり、企業の離職率とも関連する可能性があります。
4:転勤の頻度や可能性について教えてください
将来のライフプランを考える上で、転勤の有無や勤務地の情報は非常に重要です。
全国展開している企業の場合、転勤の可能性やその頻度、期間、また勤務地の希望がある程度考慮されるのかを具体的に確認しておく必要があります。
「キャリアアップに伴って転勤するケースが多いのでしょうか」といった形で、転勤の目的や背景を尋ねると、企業の意図も理解しやすくなります。
自身のキャリアプランと照らし合わせ、許容できる範囲かどうかを判断しましょう。
5:社員の健康をサポートする独自の制度はありますか
法定の福利厚生だけでなく、企業が独自に設けている健康支援制度について尋ねることで、社員を大切にする姿勢を伺い知ることができます。
例えば、人間ドックの費用補助、フィットネスクラブの割引、メンタルヘルス相談窓口の設置など、具体的な取り組みについて質問してみましょう。
社員の心身の健康を第一に考える企業は、働きがいのある職場である可能性が高いです。
企業の健康経営への意識を知る良い機会になります。
採用や選考プロセスに関する会社説明会での質問例
選考を有利に進めるために、企業がどのような点を重視しているのかを知ることは不可欠です。
面接での評価ポイントや、求める人物像について直接尋ねることで、今後の選考対策に役立てることができます。
選考について質問する際は、選考の公平性を損なわない範囲で、自身の準備に活かせる情報を得ることを目的としましょう。
1:採用選考において最も重視しているポイントは何ですか
今後の面接対策を立てる上で非常に重要な質問です。企業が候補者のスキル、経験、人柄のうち、何を最も重視しているのかを直接確認することで、自己PRの方向性を定めることができます。
「エントリーシートや面接など、各選考段階で特に注目している点は異なりますか」と深掘りすると、より具体的な対策が可能になります。
この質問から得られた回答をもとに、自分の強みを効果的にアピールする準備を進めましょう。
2:面接では候補者のどのような点に注目していますか
面接官がどのような視点で候補者を評価しているかを知るための質問です。
論理的思考力、コミュニケーション能力、仕事への熱意など、企業によって注目するポイントは異なります。
面接でどのような内容が質問されるのかを予測し、効果的な準備をするためのヒントが得られます。
「過去の経験について深掘りする質問が多いのでしょうか、それとも未来のビジョンについて尋ねられることが多いのでしょうか」など、質問の傾向を尋ねるのも有効です。
3:内定者向けのインターンシップや研修はありますか
内定後のフォロー体制や、入社までの期間をどのように過ごせばよいかを知るための質問です。
内定者向けのイベントや研修があれば、入社前に同期と交流を深めたり、必要なスキルを学んだりする良い機会になります。
企業の採用人数によっては、手厚いフォローが難しい場合もあるため、その規模感も合わせて考慮すると良いでしょう。
入社までの期間も成長の機会と捉えている、という意欲的な姿勢を示すことにもつながります。
企業理念やビジョンに関する会社説明会での質問例
企業理念やビジョンを理解することは、企業がどのような価値観を持ち、どのような社会的使命を果たそうとしているかを把握するために欠かせません。
経営陣や社員がその理念をどのように日々の業務に反映しているのかを知ることで、自分の価値観との一致度を確認できます。
理念が実際の経営や現場にどのように生きているかを探る視点で質問するのが効果的です。
1:企業理念が社員の行動にどのように反映されているか教えてください
企業理念が単なるスローガンではなく、実際の行動指針や評価基準として機能しているかを見極める質問です。
経営方針や日常業務の中で理念がどう活用されているのかを聞くことで、理念浸透度の高さを知ることができます。
「理念を体現している社員の具体的なエピソードはありますか」と掘り下げると、企業文化をよりリアルに理解できます。
2:経営者が最も大切にしている価値観を教えてください
トップの価値観を知ることは、企業の方向性を理解する上で非常に重要です。
社長や経営層が語る価値観が現場レベルに浸透しているかを確認することで、企業の一体感を測ることができます。
「経営者が社員に対してよく伝えている言葉や考え方はありますか」といった質問も有効です。
3:今後の中長期的なビジョンや目標について教えてください
企業の将来性や成長性に関心を持っていることを示せる質問です。
特に「5年後・10年後にどのような会社になりたいと考えていますか」といった問いは、経営方針の方向性を探ることにつながります。
自分がその成長の中でどのように貢献できるかを考えるための材料にもなります。
4:企業理念と実際の事業戦略にはどのような関係がありますか
理念と戦略が一致している企業は、持続的な成長を遂げやすい傾向にあります。
「理念をどのように事業方針に落とし込んでいるか」を尋ねることで、理念経営の実践度を把握できます。
特に社会課題解決型の企業では、この質問によって企業の本気度を見極められます。
5:社会に対してどのような価値を提供したいと考えていますか
企業の社会的使命やパーパス(存在意義)を探る質問です。
「利益だけでなく、どのような形で社会に貢献していくことを目指しているか」を尋ねることで、企業の社会的責任意識の深さを確認できます。
特にSDGsやサステナビリティに注力している企業には効果的です。
経営・業界動向に関する会社説明会での質問例
企業の立ち位置や業界の動向を理解することで、自身のキャリア選択に説得力を持たせることができます。
競合との比較や今後の市場変化への対応を尋ねることで、企業の安定性や将来性を把握することが可能です。
1:競合他社と比べて、特に強みだと感じる部分はどこですか
企業研究を深めている姿勢を示す質問です。
「〇〇という点で御社が強みを持っていると感じましたが、社員の皆様はどのように感じていますか」と自分の考えを交えて聞くと、より印象的になります。
2:業界の中で直面している課題や変化にはどのように対応していますか
企業が環境変化にどのように柔軟に対応しているかを確認できます。
課題への向き合い方から、組織の危機管理能力や柔軟性を知ることができます。
特にDX化や人材不足など、業界共通の課題を踏まえて質問すると効果的です。
3 :新しい市場や海外展開への取り組みはありますか
グローバル展開や新規分野進出に関する質問は、企業の成長戦略への理解を示すものです。
自分が将来的に関わりたい領域がある場合、その展開方向が一致しているか確認できます。
4:今後の業界全体のトレンドをどのように見ていますか
業界分析力をアピールできる質問です。
「AI技術の進化や環境変化に対して、どのような影響があるとお考えですか」といった形で時代背景を交えると、深い関心が伝わります。
5:御社が今後注目している技術・分野はありますか
変化に対応し続ける企業かどうかを見極める質問です。
イノベーションを重視する企業であれば、研究開発や新技術導入の方針を知る良い機会になります。
選考・採用活動に関する質問例
企業理解を深めつつ、今後の選考対策にも活用できる質問群です。
相手に誠実な印象を与えるため、「受かるため」ではなく「理解を深めたい」という姿勢を意識しましょう。
1:エントリーシートで特に重視しているポイントはありますか
書類選考を突破するための重要な質問です。志望動機・経験・自己PRのどれを重視しているかを把握できます。
2:面接では学生のどのような点を見ていますか
具体的な評価基準を知ることで、効果的な自己PRを準備できます。
3:グループワークや筆記試験などがある場合、どのような目的で実施されていますか
選考意図を理解する質問で、企業が重視する能力(協調性・論理力・創造性)を読み取れます。
4:面接官の方はどのような立場の方が担当されることが多いですか
質問内容の傾向を知ることで、回答準備の方向性が定まります。
5:選考で印象に残る学生にはどのような特徴がありますか
印象に残る学生像を知ることで、自分の見せ方を磨くヒントが得られます。
6:採用人数や配属の目安を教えてください
組織規模や競争率を把握する質問で、現実的な入社後のイメージ形成に役立ちます。
7:入社後に活躍している社員の共通点を教えてください
企業が大切にしている行動特性や姿勢を把握できます。
8:内定者フォローはどのように行われていますか
入社前からサポート体制が整っているかを確認する質問です。
9:オンライン面接と対面面接で評価の観点は異なりますか
最近の採用トレンドを踏まえた現代的な質問です。
10:説明会参加者にはどのような行動を期待されていますか
受け身ではなく主体的な姿勢を示す質問で、印象アップにつながります。
11:学生に今のうちに意識してほしいことは何ですか
採用担当者のリアルなアドバイスを引き出せます。成長意欲の高さを印象付ける質問です。
12:入社前に準備しておくと良いことはありますか
入社意欲を示す質問で、今後の準備にも直結します。
13:御社の選考プロセスで重視される“人柄”とはどのようなものですか
抽象的な“人柄重視”を具体化する質問です。
14:最終的に内定を出す決め手はどのような点ですか
本質的な採用基準を知るための質問です。企業が求める人物像の最終ラインを把握できます。
採用担当者に響く!会社説明会でのオリジナル質問の考え方3ステップ
他の就活生と差がつくオリジナルの質問は、深い企業研究と自己分析から生まれます。
用意された質問例をただ使うのではなく、自分ならではの視点を加えることで、採用担当者の記憶に残りやすくなります。
ここでは、自分だけの質問を組み立てるための具体的なやり方を3つのステップで紹介します。
説明会で聞いた内容をメモしながら、質問を練り上げていきましょう。
ステップ1:企業の公式サイトや採用サイトを徹底的に読み込む
まずは、企業の公式サイト、採用サイト、中期経営計画、IR情報などを隅々まで読み込み、基本的な情報を完全に把握します。
社長メッセージや社員インタビューからは企業の価値観や文化を、事業内容や財務状況からは企業の現状と将来性を読み取ることができます。
この段階で得た情報が、質問の土台となります。
調べれば分かることを質問してしまう事態を避けるためにも、この情報収集のステップは不可欠です。
ステップ2:会社説明会で深掘りしたい疑問点をリストアップする
ステップ1で収集した情報をもとに、さらに知りたいこと、疑問に思ったこと、矛盾を感じたことなどを全て書き出します。
例えば、「企業の理念として『挑戦』を掲げているが、実際の事業では安定志向に感じる。
若手の挑戦を後押しする具体的な制度はあるのだろうか」といった、自分なりの考察から生まれる疑問が理想的です。
この段階では質より量を意識し、些細なことでもリストアップしていくことで、質問の種を見つけ出します。
ステップ3:自分の経験や強みと関連付けて質問を組み立てる
リストアップした疑問点と、自身の経験や強みを結びつけて、質問を完成させます。
例えば、「学生時代に〇〇という挑戦で△△という成果を出した経験があり、貴社の『挑戦』という理念に強く共感しています。
社員の皆様が、仕事の中で『挑戦して良かった』と感じた具体的なエピソードがあればお聞かせください」といった形です。
自分の言葉で語ることで、単なる情報収集ではなく、自己アピールを兼ねた質の高い質問になります。
これは避けたい!会社説明会でのNG質問リスト
会社説明会での質問はアピールの機会ですが、内容によってはかえって評価を下げてしまう可能性があります。
準備不足や意欲の低さを感じさせるNG質問は、絶対にしないように注意が必要です。
ここでは、就活生が陥りがちなNG質問の典型的なパターンを紹介します。
これらのリストを参考に、自分の用意した質問が不適切でないかを事前にチェックしておきましょう。
企業の公式サイトや採用パンフレットで確認できる内容
御社の設立はいつですかどのような事業を行っていますかなど、企業の公式サイトや採用パンフレットを読めばすぐに分かるような基本的な情報を尋ねることは、企業研究が不十分であることの証明になってしまいます。
これは、企業への関心が低い、あるいは準備を怠っているという印象を与えかねません。
質疑応答は、公開情報だけでは分からない、より深い情報を得るための貴重な機会であるという認識を持つことが重要です。
給与や休日など待遇面のみに偏った内容
給与、福利厚生、休日、残業時間といった待遇面の情報は、働く上で確かに重要です。
しかし、質疑応答の時間にこれらの質問ばかりを繰り返すと、「仕事内容よりも条件面しか見ていない」という印象を与えてしまう可能性があります。
特に最初の質問者である場合や、一人で何度も質問する機会がある場合は注意が必要です。
待遇に関する質問は、仕事内容やキャリアに関する質問とバランスを取りながら、1つか2つに留めるのが賢明です。
「はい」「いいえ」だけで終わってしまう内容
研修制度はありますか海外勤務の可能性はありますかなどはいかいいえの一言で回答が終わってしまうクローズドクエスチョンは会話が広がらず深い情報を引き出すことができません
これではせっかくの質疑応答の機会を活かせません
研修制度はどのような目的で具体的にどのようなプログラムが組まれているのでしょうかのように5W1Hいつどこで誰が何をなぜどのようにを意識したオープンクエスチョンを心がけることが求められます
会社説明会ですでに解説された内容の内容
説明会のプレゼンテーション中にすでに説明があった内容について再度質問することは、「人の話をきちんと聞いていない」というマイナスの印象を与えてしまいます。
これは、社会人として基本的な傾聴力に欠けると判断されかねない、非常にリスクの高い行為です。
説明会中は重要なポイントをメモに取り、話の内容を正確に理解するよう努めましょう。
もし聞き逃してしまった場合は、正直に断りを入れるか、他の学生の質問で同様の内容が出ないか様子を見るのが無難です。
好印象を与える会社説明会での質問の仕方と守るべきマナー
会社説明会では、質問の内容だけでなく、質問の仕方も評価の対象となります。
適切なマナーやルールを守り、ハキハキとした聞き方を心がけることで、採用担当者に好印象を与えられます。
社会人としての基礎的なコミュニケーション能力を示すためにも、ここで紹介する立ち居振る舞いや話し方を押さえておきましょう。
最初に大学名と氏名をはっきりと名乗る
質問をする際は、挙手をして指名された後、その場に立ち上がり、まず「〇〇大学の〇〇と申します」と大学名と氏名をはっきりと名乗るのがマナーです。
これは、自分が何者であるかを明確に伝え、相手への敬意を示すための基本的な作法です。
簡単な前置きとして、「本日は貴重なお話をありがとうございました」といった感謝の言葉を添えると、より丁寧な印象になります。
名前を覚えてもらうきっかけにもなるため、最初の自己紹介は省略せずに必ず行いましょう。
質問は要点をまとめて簡潔に伝える
質問をする際は、背景説明が長くなりすぎないよう注意し、何が聞きたいのか要点を簡潔にまとめて伝えることが重要です。
結論から先に述べる「PREP法(Point,Reason,Example,Point)」を意識すると、分かりやすい言い方になります。
例えば、「1点質問がございます。〇〇についてですが、~」というように、まず質問のテーマを明確に示してから詳細を話すと、相手は内容を理解しやすくなります。
他の参加者の時間も考慮し、1分程度で話し終えるのが理想的です。
聞き取りやすい声の大きさでハキハキと話す
特に広い会場での対面の説明会では、後ろの席まで届くよう、普段より少し大きめの声でハキハキと話すことを意識しましょう。
小さな声や早口では、内容が聞き取れず、自信がないような印象を与えてしまいます。
背筋を伸ばし、堂々とした態度で話すことで、熱意や誠実さが伝わりやすくなります。
マイクが用意されている場合は、口元に適切に近づけて使用し、自分の声が会場全体にしっかりと届いているかを確認しながら話すことが求められます。
回答をいただいた後には感謝の言葉を述べる
質問への回答をいただいた後は、必ず「お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。よく分かりました」といったお礼の言葉を述べましょう。
これは、時間を使って答えてくれた相手への敬意を示す基本的なマナーです。
感謝の意を示すことで、コミュニケーションが円滑になり、丁寧で謙虚な人柄を印象付けることができます。
質疑応答の最後には、改めて「本日は誠にありがとうございました」と全体への感謝を伝えて締めくくると、より好印象です。
他の学生がした質問と同じ内容は繰り返さない
他の学生が質問している間も、自分の準備に集中するのではなく、その内容にしっかりと耳を傾けましょう。
自分がしようと思っていた質問が先に出てしまった場合は、同じ内容を繰り返すのは避けるべきです。
これは、周囲の状況を把握できていない、あるいは話を聞いていないという印象を与えます。
その場合は、その回答をさらに深掘りする質問を考えたり、別の角度から問いかけたりするなど、臨機応変な対応力が求められます。
Web会社説明会で気をつけたい3つのポイント
オンライン形式のWeb説明会は、対面とは異なる注意点が存在します。
通信環境や画面越しの見え方など、Webならではのマナーを理解しておくことが重要です。
チャット機能を使って質問する場合もあれば、音声で直接質問する場合もあります。
どのような形式であっても、スムーズなコミュニケーションを心がけ、良い印象を与えるためのポイントを押さえておきましょう。
背景や身だしなみを整えてカメラをオンにする
オンライン説明会では、カメラをオンにして参加するのが基本マナーです。
背景には、余計なものが映り込まないよう、壁やカーテンの前を選ぶか、無地のバーチャル背景を設定しましょう。
服装は、対面の説明会と同様にスーツやオフィスカジュアルなど、場にふさわしい身だしなみを整えます。
画面に映る自分の姿が、企業の採用担当者にとっての第一印象となるため、清潔感のある姿で参加することが求められます。
通信環境が安定した静かな場所で参加する
音声が途切れたり、映像が止まったりすると、スムーズな質疑応答の妨げになります。
事前に通信速度を確認し、Wi-Fi環境が安定した場所で参加しましょう。
有線LAN接続が利用できる場合は、そちらの方がより安定します。
また、家族の声やペットの鳴き声、外部の騒音などが入らない静かな環境を確保することも重要です。
マイク付きイヤホンを使用すると、自分の声をクリアに届け、周囲の雑音を拾いにくくなるため効果的です。
対面よりも少し大きめなリアクションを心がける
画面越しでは、表情や感情が伝わりにくいため、対面の時よりも意識的にリアクションを大きくすることが大切です。
説明を聞きながら頷いたり、興味深い点では少し身を乗り出したりするなど、視覚的な反応を示すことで、熱心に参加している姿勢が伝わります。
自分が質問する際だけでなく、他の学生が質問している時も、真剣に耳を傾けていることを態度で示しましょう。
こうした小さな工夫が、オンラインでのコミュニケーションを円滑にします。
どうしても会社説明会での質問が思いつかない時の対処法
説明会も終盤に差し掛かり、「最後に何か質問はありますか」と問いかけられた際、何も質問が浮かばないという状況は誰にでも起こり得ます。
無理にありきたりの質問をするよりも、別の方法で意欲を示す方が賢明な場合もあります。
質問する時になって焦らないよう、事前にいくつかの対処法を知っておくことで、落ち着いて対応できるようになります。
他の参加者の質疑応答に集中してヒントを得る
自分が質問できない状況でも、他の参加者の質問とそれに対する企業の回答に注意深く耳を傾けましょう。
そのやり取りの中から、新たな疑問が生まれたり、自分が聞きたかった内容のヒントが見つかったりすることがあります。
また、他の学生がどのような点に関心を持っているかを知ることは、企業研究を多角的に進める上でも役立ちます。
傾聴の姿勢を保つこと自体が、学習意欲の表れとして評価される可能性もあります。
説明会で最も印象に残った点について感想を述べる
質問が思いつかない場合、無理に質問を探すのではなく、「本日の説明会で〇〇というお話が特に印象に残りました」と感想を述べるのも一つの方法です。
具体的にどの部分に感銘を受けたのか、そしてそれが自分の価値観や企業選びの軸とどう結びつくのかを伝えることで、企業への理解度と入社意欲を十分にアピールできます。
質問という形式にこだわらず、自分の言葉で熱意を伝えることが重要です。
社員個人の経験談や価値観について尋ねてみる
一般的な事業内容や制度についての質問が思い浮かばない場合は、登壇している社員個人に焦点を当てた質問をしてみましょう。
「〇〇様がこの会社に入社を決めた一番の理由は何ですか」や「仕事をする上で最も大切にされている価値観について教えてください」といった質問です。
個人の経験に基づいた回答は、企業のリアルな姿を映し出すと同時に、その社員の人柄に触れる良い機会にもなります。
相手への関心を示すことで、コミュニケーションが深まります。
まとめ
会社説明会での質問は、就職活動において企業理解を深め、自身をアピールするための重要な機会です。
本記事で紹介した回答例や質問集を参考に、自分なりの質問を準備することが成功の鍵となります。
質問する際には、内容だけでなく、マナーや答え方も意識しましょう。
説明会後には、お礼のメールを送ることで、さらに丁寧な印象を残せます。
これらのノウハウは、新卒の就活だけでなく、将来の転職活動にも通じるものですので、ぜひ実践してみてください。
会社説明会は、新卒や転職を問わず、企業と学生・求職者の出会いの場です。最近ではオンラインやZoomを使った形式も増えており、リモートワークを取り入れている企業も多く見られます。会場で行う合同説明会や個別説明会など、開催の仕方によって聞き方や立ち振る舞いのやり方も変わるため、自分に合ったスタイルを選ぶことが大切です。
説明会では、まず前置きとして自己紹介を行い、大学名や名前をしっかり名乗ることが基本です。そのうえで、志望動機や職場の雰囲気、福利厚生などについて人事や先輩社員に質問し、企業側への理解を深めていきます。特に座談会のような形式では、先輩やOB・OGのリアルな話を聞ける貴重な機会となるでしょう。
質問の聞き方にもコツがあります。たとえば「どんな仕事をしていますか?」ではなく、「営業職で活躍されている方の一日の流れを教えてください」といった具体的な例文を用意しておくと印象が良くなります。質問が思いつかないときは、知恵袋やリクナビなどのサイトで質問一覧を参考にするのもおすすめです。
また、説明会では服装やメールでのお礼など、細かなマナーも印象を左右します。企業によってスーツ指定かオフィスカジュアルかが異なるため、事前に確認しておきましょう。終了後には、「本日は貴重なお時間をありがとうございました」とお礼のメールを送ると、誠実な印象を残せます。質問の際に「配属先について教えてください」や「選考についてどのような流れですか」と尋ねるのも前向きです。
業界別に見ると、不動産、銀行、薬局、ITなどさまざまな業種で説明会が行われています。営業職を志望する場合は、それぞれの業界で求められるスキルや考え方を理解しておくことが大切です。サービス業なら「お客様の満足度を高める力」、銀行や不動産では「信頼を築く力」、薬局では「正確性や対応力」など、評価のポイントが異なります。
説明会で感じた印象と入社後の現実にギャップが生まれないよう、先輩やOB訪問で補足情報を得るのも効果的です。実際に働く人から、配属先や管理体制、働き方などを聞くと理解が深まります。自分の弱みを正直に話し、それをどう改善しているかを伝えると、より好印象になります。
当日は緊張してもうまく話せなくても大丈夫です。何も行動しないより、挑戦することに意味があります。大学低学年のうちから説明会に参加することで、社会の仕組みや職業への興味が広がり、将来の準備にもつながります。
説明会の後は、得た情報を徹底的に整理して志望動機に反映しましょう。最近はオンライン選考やWeb面接が増えているため、メールのやり取りや提出期限にも注意が必要です。準備の仕方次第で結果は大きく変わります。
会社説明会は単なる情報収集の場ではなく、自分と企業が逆に「選び合う」場でもあります。思いつかないことがあっても、座談会やOB訪問などで一歩踏み出せば、きっと新しい発見があります。やり方を磨き、積極的に行動すれば、あなたのキャリアはより面白い方向に広がっていくはずです。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む