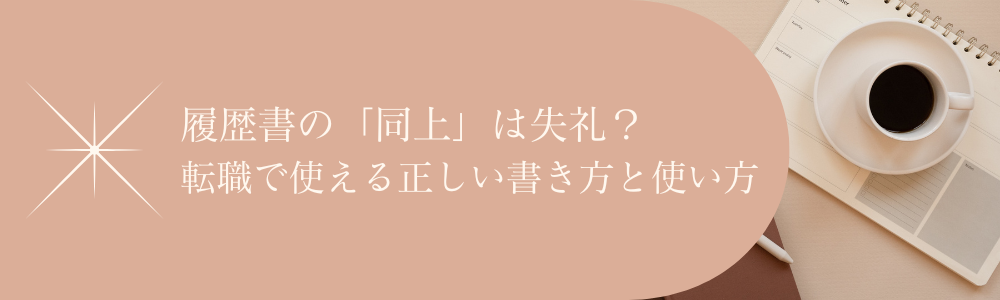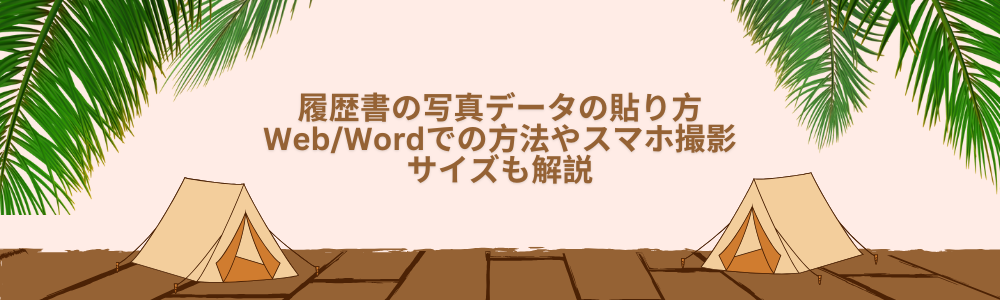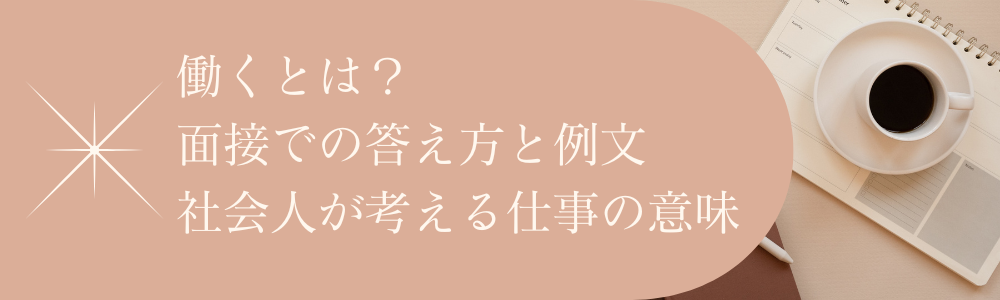

働くとは?面接での答え方と例文|社会人が考える仕事の意味
「働くとは」という問いは、就職活動の面接で頻繁に聞かれる質問の一つです。
この質問には明確な正解がなく、自身の仕事に対する価値観が問われます。
この記事では、社会人が考える仕事の意味を様々な角度から解説し、面接で効果的に伝えるための答え方や具体的な例文を紹介します。
自分なりの「働くとは」を見つけ、自信を持って面接に臨むための準備を整えましょう。
そもそも「働くとは」どういう意味?社会人が考える8つの目的
そもそも働くとはどういうことかという問いは、時に哲学的な領域にも及びます。
働くことは何か、働くとは何ですか、という疑問に対して、社会人は多様な目的を持っています。
それは単に収入を得るためだけでなく、自己実現や社会貢献といった、より高次な欲求を満たすための手段でもあります。
ここでは、多くの社会人が働く目的として掲げる代表的な8つの意味を解説します。
社会に貢献し、誰かの役に立つため
仕事を通じて社会貢献を果たし、人の役に立つことを働く目的とする考え方があります。
自分の業務が社会の一部を支え、他者の生活を豊かにしているという実感は、大きなやりがいにつながるでしょう。
直接的に顧客の笑顔を見たり、感謝の言葉を受け取ったりする経験は、貢献している感覚を強くします。
また、これまで社会から受けてきた恩を、今度は自分が働くことで恩返ししたいという動機も、人の役に立つことを重視する姿勢の表れです。
社会の一員として、誰かのために自分の能力や時間を使うことに価値を見出す人は少なくありません。
スキルを身につけて自己成長を実感するため
働くことを通じて新たなスキルや知識を習得し、自己成長を実感することに意義を見出す人も多くいます。
企業が提供する研修制度を活用したり、日々の業務で課題解決に取り組んだりする中で、自身の能力が高まっていく過程は大きな喜びとなります。
昨日までできなかったことができるようになる、あるいは専門的な知識が深まることで、自分の成長を客観的に認識できます。
周囲から「すごい」と評価されるような専門性を身につけることは、自信を持つことにもつながり、働く上での強力なモチベーションとなるのです。
自分の夢や目標を実現させるため
働くことを、自分の夢や個人的な目標を達成するための手段と捉える考え方もあります。
例えば、起業するための資金や経験を得る、あるいは趣味や好きなことを仕事にするなど、働くこと自体が自己実現のプロセスとなります。
仕事内容そのものにやりがいや生きがいを感じ、情熱を注ぎ込める場合、仕事は単なる労働ではなく、人生を懸けて取り組むべきテーマになるのです。
このように、個人の夢と仕事が直結している状態は、非常に高いモチベーションを維持することを可能にします。
経済的な安定を手に入れ、豊かな生活を送るため
働くことの最も基本的な目的は、お金を得て経済的な基盤を築くことです。
安定した収入は、衣食住といった生活の基本を満たす上で不可欠であり、その必要性は誰もが認めるところでしょう。
また、自分自身だけでなく、将来的に家族を扶養するためにも経済力は重要になります。
趣味や自己投資など、人生を豊かにするための活動にもお金は必要です。
このように、経済的な安定を確保し、安心した生活を送ることは、多くの人にとって働く上での根源的な動機となっています。
社会的な信用や地位を得るため
定職に就いて働くことは、社会的な信用を得る上で重要な要素です。
安定した職業に就いているという事実は、ローンを組む際や賃貸契約を結ぶ際など、様々な場面で信用の証となります。
また、組織の中で経験を積み、昇進していくことで、より大きな責任を伴う地位を得ることも可能です。
働く人として社会的な役割を担い、責任を果たすことは、自己肯定感を高めるとともに、社会の一員としての自覚を促します。
こうした社会的な信認や地位も、働く目的の一つと考えることができます。
多くの人と関わり、つながりを築くため
職場は多様な背景を持つ人々が集まるコミュニティです。
仕事を通じて同僚や上司、取引先など多くの人と関わり、社会的なつながりを築くことに価値を見出す人もいます。
一人では成し遂げられない大きな目標に向かってチームで協力し、コミュニケーションを取りながら共に働く経験は人間的な成長を促します。
こうした人との関わりの中で新たな視点を得たり、信頼関係を築いたりすることは、人生を豊かにする重要な要素であり、働くことの大きな魅力の一つです。
困難を乗り越えることで達成感を得るため
仕事には高い目標や予期せぬトラブルなど様々な困難が伴います。
しかしそうした困難な課題に真摯に向き合い試行錯誤の末に乗り越えた時に得られる達成感は何物にも代えがたい喜びとなります。
働くと自分の限界に挑戦するような場面に直面することもありますがその経験が自信となり次への挑戦意欲をかき立てます。
このプロセスを繰り返すことで精神的な強さや問題解決能力が養われるのです。
この達成感こそが働くよろこびであると感じる人は少なくありません。
生きがいを見つけ、人生を充実させるため
働くことは、人生に目的や意味を与え、生きがいを見つけるための重要な手段となり得ます。
子供の頃や小学生の時に抱いた夢を仕事として実現する人もいれば、仕事を通じて新たな目標を見つける人もいるでしょう。
もし働くことが無意味だと感じたり、ただ暇を潰すためだけの行為になったりすれば、人生の充実感は得られにくいかもしれません。
しかし、仕事に目標を持ち、打ち込める何かを見つけることで、日々の生活に張り合いが生まれ、人生全体がより豊かなものになるのです。
面接で「働くとは?」と質問される理由
面接で「あなたにとって仕事とは何ですか」と問われるのには、明確な理由があります。
面接官は、この質問を通して応募者の価値観や仕事への姿勢、将来性などを見極めようとしています。
なぜこの質問が重要なのか、その背景にある3つの主な理由を理解することで、より的確な回答を準備することが可能になります。
応募者の価値観が企業文化と合っているか確認したい
企業は、応募者が持つ仕事に対する価値観が、自社の企業文化や理念と一致しているかを確認しようとしています。
例えば、チームワークを重視する企業に対して、個人での成果を最優先する価値観を述べた場合、入社後のミスマッチが懸念されます。
就職活動においては、企業の風土や大切にしている価値観を事前に理解し、自身の考えと合致する部分を伝えることが重要です。
長期的に活躍してもらうためにも、企業と応募者の価値観のマッチ度は採用の重要な判断基準となります。
仕事への意欲や熱意の度合いを測りたい
この質問は、応募者が仕事に対してどれほどの意欲や熱意を持っているかを測るための指標にもなります。
働くことに対する自分なりの哲学や明確な目的を持っている応募者は、入社後も主体的に業務に取り組み、困難な状況でも前向きに努力できると期待されるでしょう。
逆に、曖昧で表面的な回答しかできない場合、仕事への真剣度が低いと判断される可能性があります。
自身の言葉で、情熱を持って働くことへの思いを語ることが、高い評価につながります。
入社後の活躍イメージや将来性を知りたい
応募者の回答から、面接官は入社後にその人物がどのように成長し、会社に貢献してくれるかを具体的にイメージしようとしています。
例えば、「働くことは自己成長の機会」と答えた応募者であれば、入社後も積極的にスキルアップに励む姿が想像できます。
特に、3年後、5年後といった中長期的な視点で、どのようなキャリアを築き、会社の中でどのような役割を果たしていきたいかという将来性まで示せると、計画性や向上心のある人材として高く評価される可能性が高まります。
面接官に響く「働くとは」の答え方3ステップ
「働くとは」という抽象的な問いに対して、自身の考えを分かりやすく、かつ説得力を持って伝えるためには、話の構成を意識することが重要です。
ここでは、誰でも簡単に実践できる、面接官に響く答え方を3つのステップに分けて解説します。
このフレームワークに沿って回答を組み立てることで、論理的で一貫性のあるメッセージを伝えることが可能になります。
【ステップ1】まず結論として「私にとって働くとは〇〇です」と定義する
最初に、自分自身の言葉で「私にとって働くとは〇〇です」と結論を明確に定義します。
例えば、「私にとって働くとは、自己成長を実現するプロセスです」や「社会とのつながりを築き、貢献することです」のように、一文で端的に考えを述べます。
これにより、話の要点が明確になり、面接官はこれから話される内容を理解しやすくなります。
この最初の定義が、回答全体の軸となるため、自分の価値観を最もよく表す言葉を選ぶことが重要です。
【ステップ2】その考えに至った具体的なエピソードを伝える
次に、ステップ1で定義した考えを持つに至った背景として、具体的なエピソードを話します。
自身の経験に基づいた話は、回答に説得力と独自性を与えます。
例えば、アルバイトでの経験、学業での研究、サークル活動など、どのような場面でその価値観が形成されたのかを具体的に説明することが重要です。
働くとは何かを考えるきっかけとなった出来事を交えて話すことで、単なる理想論ではなく、実体験に裏打ちされた深い考えであることを示すことができます。
【ステップ3】入社後にどのように貢献したいかを述べる
最後に、自身の「働くとは」という考え方が、入社後どのように企業の発展に貢献できるのかを具体的に述べます。
自分の価値観や強みが、応募企業の事業内容や理念、求める人物像とどのように合致しているかを結びつけて説明します。
例えば、「自己成長を追求する姿勢で、貴社の新しい技術をいち早く習得し、事業拡大に貢献したいです」といった形で、仕事への意欲と将来性をアピールします。
これにより、入社後の活躍イメージを面接官に持たせることができます。
【目的別】面接で使える「働くとは」の回答例文5選
ここからは、解説した答え方の3ステップを踏まえ、面接で実際に使える「働くとは」の回答例文を5つの目的別に紹介します。
これらの例文を参考に、自分の経験や価値観に基づいたオリジナルの回答を作成してみてください。
自身の言葉で語ることが最も重要ですが、構成や表現の参考にすることで、より伝わりやすい回答を準備できるはずです。
例文1:「働くとは」「社会貢献」をアピールする場合
私にとって働くとは、「社会を構成する一員としての責任を果たし、人々の生活を豊かにすること」です。
大学時代のボランティア活動で、地域の高齢者施設を訪問した際、私の些細な手伝いに対して「ありがとう、助かったよ」と涙ながらに感謝された経験があります。
この時、自分の行動が誰かの役に立ち、笑顔を生むことに大きな喜びを感じ、社会に貢献することの尊さを実感しました。
この経験から、人々の生活に不可欠なインフラを支える貴社の一員として、社会への責任を果たしながら、より多くの人々の快適な暮らしに貢献していきたいと考えております。
例文2:「働くとは」「自己成長」をアピールする場合
私にとって働くとは、「新たな知識やスキルを習得し、自身の可能性を広げ続けるための挑戦の場」です。
大学のゼミで、未経験だったプログラミングを用いた研究プロジェクトに取り組んだ際、最初は多くの壁にぶつかりましたが、粘り強く学習を続けた結果、最終的にシステムを完成させることができました。
この過程で、困難を乗り越えることで自分が成長できるという大きな手応えを感じました。
常に最先端の技術を取り入れ、社員の成長を支援する貴社の環境であれば、私も常に挑戦を続け、自身の成長を通じて企業の発展に貢献できると確信しております。
例文3:「働くとは」「自己実現」をアピールする場合
私にとって働くとは、「自身の夢や目標を実現するためのプロセス」です。
私は幼い頃から、人々の創造性を刺激し、新しいアイデアを生み出す手助けをしたいという夢を持っていました。
大学ではマーケティングを専攻し、消費者の潜在的なニーズを掘り起こし、革新的な商品を企画する面白さに魅了されました。
人々の生活をより豊かにするというビジョンを掲げ、独創的な製品開発に力を入れる貴社でなら、私の夢を実現できると強く感じています。
私の強みである企画力を活かし、世の中をあっと言わせるような新しい価値を創造したいです。
例文4:「働くとは」「人との関わり」をアピールする場合
私にとって働くとは、「多様な価値観を持つ人々と協力し、一つの目標を達成していくこと」です。
学生時代に所属していたオーケストラでは、100人以上のメンバーがそれぞれの役割を果たし、心を一つにして一つの音楽を創り上げていました。
意見がぶつかることもありましたが、対話を重ねて互いを理解し、より良い演奏を目指す過程に大きなやりがいを感じました。
この経験から、チームで協力することの重要性と素晴らしさを学びました。
チームワークを重視し、社員一丸となって事業に取り組む貴社の一員として、周囲と協調しながら大きな成果を出すことに貢献したいです。
例文5:「働くとは」「安定した生活」を伝えたい場合
私にとって働くとは、「経済的な基盤を築き、社会人としての責任を果たすこと」です。
新卒として社会に出るにあたり、まずは自立した生活を送り、将来にわたって安定した基盤を築くことが重要だと考えています。
経済的な安定は、精神的な余裕を生み、仕事に集中して取り組むための土台となると信じています。
また、安定した環境で腰を据えて働くことで、長期的な視点を持ってスキルを磨き、着実に会社へ貢献していくことができると考えております。
貴社で真摯に業務に取り組み、責任ある社会人として着実に成長していきたいです。
「働くとは」の答えが思いつかない時の考え方
就職活動を進める中で、「働くとは」という問いに自分なりの答えがすぐに見つからないと感じる人もいるでしょう。
この問いは自己の価値観の核心に触れるものであるため、深く考える時間が必要です。
もし答えが思いつかない場合は、焦らずに自分自身と向き合うためのアプローチを試してみることが大切です。
ここでは、考えを整理し、自分なりの答えを見つけるための3つの方法を紹介します。
自己分析で自分の価値観や強みを深掘りする
まずは、自己分析を通じて自分自身を深く理解することから始めましょう。
過去の経験を振り返り、どのような時に喜びや達成感を感じたか、何に対して情熱を注いできたかを書き出してみてください。
自分の強みや弱み、大切にしている価値観が明確になることで、仕事に何を求めるのかが見えてきます。
これまでの学生生活やアルバイト経験などを総合的に見つめ直す作業は、自分だけの「働く意味」を発見するための重要なステップとなります。
自分の理想の将来像から仕事の目的を考える
5年後、10年後、あるいはそれ以上の未来で、自分がどのような人間になっていたいか、どのような生活を送っていたいかという理想の将来像を思い描いてみましょう。
そこから逆算して、その理想を実現するためには仕事を通じて何を得る必要があるのかを考えます。
例えば、専門知識を身につけたい、経済的な豊かさが欲しい、社会的に認められたいなど、具体的な目的が見えてくるはずです。
理想のキャリアやライフスタイルという魅力的なゴールを設定することで、働くことの目的が明確になります。
身近な社会人に働く理由を聞いて参考にする
自分一人で考え込まず、両親や大学の先輩、OB・OGなど、身近で働く社会人に「なぜ働くのか」「仕事のやりがいは何か」を直接聞いてみるのも有効な方法です。
他者の多様な仕事観や働く理由に触れることで、これまで気づかなかった新たな視点や価値観を発見できることがあります。
様々な人の意見を参考にすることで、自分の考えを客観的に見つめ直し、より多角的な視点から自分自身の「働くとは」という問いに対する答えを構築していくことができるでしょう。
まとめ
「働くとは」という問いに対する答えは一つではなく、個人の価値観や経験によって様々です。
本記事では、社会人が考える働く目的や、面接で評価される答え方のポイント、具体的な例文などを紹介しました。
このまとめとして重要なのは、自分自身の言葉で、実体験に基づいた説得力のある回答を準備することです。
自己分析を深め、将来のビジョンを描きながら、自分なりの仕事観を確立し、自信を持って面接に臨んでください。
就活の面接で「働くとは?」と問われるのは、単に収入やお金を得るためではなく、学生がどのように仕事の意義や目的を考えているかを探るためです。
中学生や高校生の授業や動画で学んできた「人とのつながり」や「教育の大切さ」は、社会に出ても変わらず、正社員や公務員、株式会社や店などあらゆる組織で必要とされます。働くことは、自己成長や自立を促す場であり、社会貢献を通じて自分のキャリアを築き、将来の自己実現へとつなげる大切な機会です。
仕事は単なる収入源ではなく、生き生きと自分の能力を活かし、社会に役立つ場としての価値を持ちます。学生が面接で答える際には、「働くとは自己成長と社会貢献の間にあるもの」「将来に向けて学べる場であり、人や社会の役に立つこと」といった表現を簡単にわかりやすく伝えることが重要です。リクナビや教育labの解説にもあるように、面接官はあなたが持つ価値観や視点を知りたいと考えているため、自己の力をどう活かし、社会にどのように貢献していきたいかを示すことが評価につながります。
つまり「働く」とは、収入を得ることだけではなく、自己の成長や社会貢献を実現するための場であり、人生を通して意義ややりがいを持ち続けることだと考えることができます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む