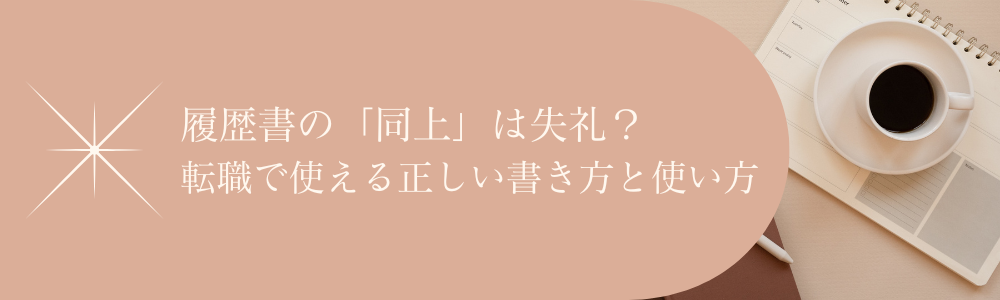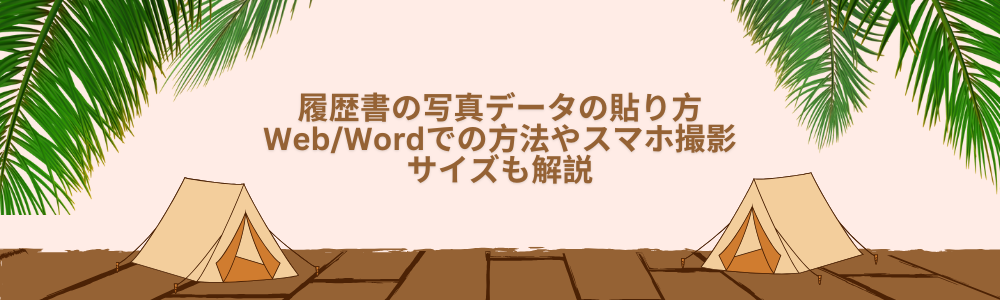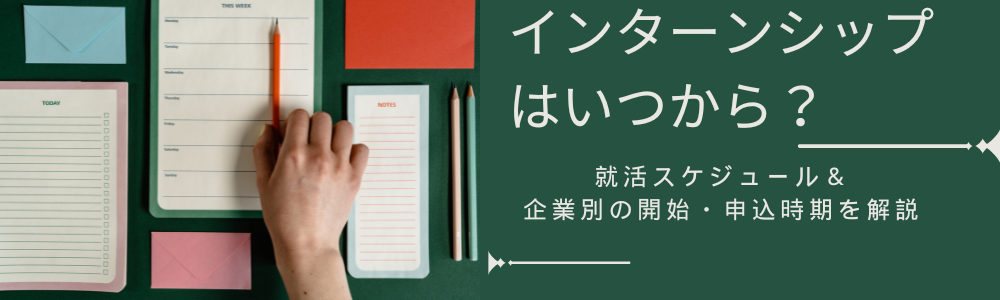

インターンシップはいつから?就活スケジュールと企業別の開始・申込時期を解説
インターンシップはいつから始めれば良いのだろうと悩む学生は少なくありません。
就活の早期化が進む中で、いつからインターンシップは企業理解を深め、自身のキャリアを考える上で重要な機会となっています。
この記事では、一般的にはいつからインターンシップを開始するか申し込みのタイミングを解説します。
学年別にやるべきことや、参加までの具体的な準備ステップも紹介するので、計画的に就活を進めるための参考にしてください。
インターンシップへの参加は大学3年生の夏からが主流
多くの大学生にとって、インターンシップへの本格的な参加は大学3年生の夏から始まります。
この時期に開催されるインターンシップは「サマーインターン」や「サマーインターンシップ」と呼ばれ、夏季休暇を利用して多くの企業がプログラムを実施します。
そのため、就職活動を意識し始めた3年生が最初に経験する機会となることが主流です。
この夏の経験を通じて、業界研究や自己分析を深め、その後の就職活動の軸を定めていく学生が多数を占めます。
そもそもインターンシップとは?目的や種類を理解しよう
インターンシップとは、学生が一定期間企業で就業体験を行う制度です。
その目的は、仕事内容や企業文化への理解を深めること、自身の適性を見極めること、実践的なスキルを習得することなど多岐にわたります。
形式も様々で、企業説明会に近い1day仕事体験から、グループワーク中心のもの、社員と同様の業務に取り組む長期的なものまで存在します。
インターンシップとは何か、その定義や種類を正しく理解し、自分の目的に合った形式を選ぶことが重要です。
【年間スケジュール】インターンシップの開催時期はいつから?申し込みのタイミング
インターンシップの開催時期は、主に夏と秋冬の二つに大別されます。
いつからインターンに参加するかを考える上で、この年間スケジュールと申し込みのタイミングを把握しておくことが不可欠です。
夏のインターンシップは大学3年生の夏休み期間、秋冬はそれ以降から本選考が始まる前までの期間に集中します。
それぞれの時期で企業側の目的やプログラム内容が異なるため、いつごろ、どのインターンシップに参加するのか計画を立てる必要があります。
夏インターンシップ:7月〜9月開催|情報収集は4月頃から
夏のインターンシップは、主に大学3年生の7月から9月にかけて開催されます。
特に8月インターンシップは多くの企業が実施するため、学生の参加も集中する時期です。
このインターンシップに参加するためには、早い段階からの準備が求められます。
多くの企業では4月から5月にかけて情報の公開とエントリーの受付を開始するため、この時期には自己分析や業界研究をある程度進めておくことが理想的です。
幅広い業界のプログラムが開催されるため、視野を広げる良い機会になります。
秋冬インターンシップ:10月〜2月開催|本選考に直結しやすい
秋から冬にかけて開催される秋冬インターンシップは、10月から翌年の2月頃まで続きます。
夏インターンシップが業界理解を深める目的であるのに対し、秋冬はより実践的な内容や、本選考に直結するプログラムが増える傾向にあります。
情報公開や募集は9月から順次始まり、3月の本選考開始を目前に控えた1月頃まで行われます。
夏のインターンシップでの経験を踏まえ、志望業界を絞り込んだ学生が多く参加するため、より選考を意識した対策が求められます。
【学年別】インターンシップに向けていつから何をすべきか
インターンシップへの準備は、大学の学年によって取り組むべき内容が異なります。
低学年のうちからキャリアについて考え始めることで、余裕を持って就職活動に臨めます。
大学1・2年生は自己分析や情報収集といった基礎固め、3年生は本格的な応募と参加、4年生・大学院生は内定獲得を見据えた活動が中心となります。
自分の学年に応じて、いつから何をすべきかを理解し、計画的に行動を起こしていくことが、納得のいくキャリア選択につながります。
大学1・2年生:自己分析や業界研究から始めよう
大学1年2年生や短大生は、本格的な選考に参加する前に、まずは自己分析や業界研究から始めるのがおすすめです。
自分が何に興味があり、どのような仕事に関心を持つのかを探るため、様々な分野の本を読んだり、社会人の話を聞く機会を設けたりすると良いでしょう。
学年不問で参加できる短期のイベントやセミナーも開催されているため、気軽に参加して社会との接点を持つことも有効です。
焦ってインターンシップに応募するのではなく、自分の視野を広げる期間と捉えましょう。
大学3年生:夏・秋冬に向けて本格的に準備を開始
大学3年生は、夏のインターンシップを最初の目標として、本格的な準備を始める時期です。
自己分析や業界研究をさらに深め、エントリーシートの作成や筆記試験対策に着手する必要があります。
理系学生であれば専門性を活かせるインターン、公務員志望者向けのプログラム、看護学生対象の病院インターンなど、目指す進路に合わせた多様な選択肢があります。
夏と秋冬のインターンシップに積極的に参加し、経験を積むことで、自身のキャリアプランを具体化させていきましょう。
大学4年生・大学院生:内定獲得を意識したインターンシップを選ぼう
大学4年生や大学院生の場合、インターンシップへの参加は内定獲得を強く意識したものとなります。
この時期に募集されるインターンシップは、本選考の一部として位置づけられていたり、参加後に早期選考ルートへ案内されたりするケースが少なくありません。
これまでの就職活動で得た知見を活かし、志望度の高い企業のプログラムに絞って応募することが効果的です。
自身のスキルや経験が、その企業でどのように貢献できるかを明確にアピールする準備が求められます。
インターンシップ参加までに準備すべき5つのこと
インターンシップへの参加を実りあるものにするためには、事前の準備が欠かせません。
目的を明確にすることから始まり、情報収集、書類作成、筆記試験対策、面接練習と、計画的に進めるべきステップが存在します。
これらの準備を一つひとつ丁寧に行うことで、選考を通過しやすくなるだけでなく、参加した際の学びの質も大きく向上します。
明確な意図を持って臨むための準備を進めましょう。
ステップ1:なぜ参加したいのか目的を明確にする
まず初めに、なぜインターンシップに行きたいのか、その目的を自分の中で明確にすることが重要です。
「周りが参加しているから」といった理由でとりあえず行くのではなく、「特定の業界のビジネスモデルを理解したい」「営業職の仕事を体験してみたい」「企業の風土を肌で感じたい」など、具体的な目標を設定します。
目的がはっきりしていれば、応募する企業を選ぶ際の基準が定まり、エントリーシートや面接で伝えるべき内容も具体的になります。
ステップ2:興味のある業界や企業の情報収集を行う
自己分析を通じて見えてきた興味・関心を軸に、業界や企業の情報収集を進めます。
企業のウェブサイトや就職情報サイトはもちろん、業界地図やニュース、OB・OG訪問など、様々な情報源を活用して多角的に調べることが大切です。
この際、知名度の高い大企業だけでなく、独自の技術を持つBtoB企業や、地域に貢献する優良な中小企業、急成長中のベンチャー企業などにも目を向けてみましょう。
自分の価値観に合う企業を見つけるため、区別なく幅広く情報を集める姿勢が求められます。
ステップ3:応募に必要なエントリーシート(ES)を作成する
インターンシップへの応募には、エントリーシート(ES)の提出が必須となる場合がほとんどです。
ESでは、志望動機や自己PR、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)などが問われます。
企業は、応募者が自社に興味を持ち、目的意識を持って参加しようとしているかを見ています。
設問の意図を正確に読み取り、自身の経験と結びつけながら、なぜその企業のインターンシップに参加したいのかを論理的に記述する必要があります。
エントリー前に完成させるのではなく、余裕を持って準備を進めましょう。
ステップ4:WEBテストやSPIの対策を進めておく
多くの企業が、インターンシップの選考過程でWEBテストやSPIなどの適性検査を実施します。
これらは言語能力や計算能力、論理的思考力を測るもので、対策なしで高得点を取るのは容易ではありません。
市販の対策本を繰り返し解いたり、模擬試験サービスを利用したりして、問題形式に慣れておくことが重要です。
応募の申し込み期限が迫ってから慌てて対策を始めるのではなく、大学の授業などと並行して、計画的に学習を進めておくことが選考通過の鍵となります。
ステップ5:面接で自分をアピールできるよう練習する
書類選考やWEBテストを通過すると、面接が実施されます。
面接では、エントリーシートに書いた内容を基に、より深く人物像を理解するための質疑応答が行われます。
自信を持って自分をアピールできるよう、事前の練習が不可欠です。
キャリアセンターの職員や友人、家族に協力してもらい、模擬面接を経験しておきましょう。
結論から簡潔に話すことや、具体的なエピソードを交えて説得力を持たせることなど、効果的なコミュニケーションスキルを身につけることが求められます。
「もう出遅れたかも…」と不安な人が今からできること
夏のインターンシップに応募しそびれたり、選考に通過しなかったりして、「出遅れたかもしれない」と不安を感じる人もいるでしょう。
しかし、焦る必要は全くありません。
インターンシップの機会は秋冬にも豊富にありますし、企業によっては通年で募集している場合もあります。
また、フルタイムでの就業体験だけでなく、1dayの仕事体験や会社説明会、業界研究セミナーなど、参加のハードルが低いイベントも多数開催されています。
今からできることに目を向け、積極的に情報収集と行動を続けましょう。
インターンシップの開始時期に関するよくある質問
インターンシップの準備を進める中では、様々な疑問や不安が生じるものです。
例えば、「何社くらい応募すれば良いのか」「参加しないと不利になるのか」といった質問は、多くの学生が抱く共通の悩みです。
ここでは、インターンシップの開始時期や参加方法に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
これらの情報を参考に、自分自身の状況と照らし合わせながら、就職活動に関する疑問を解消していってください。
Q. 何社くらい応募すればいい?
応募すべき社数に明確な正解はなく、平均応募社数を気にする必要もありません。
大切なのは、数ではなく質です。
1社ずつ丁寧に企業研究を行い、質の高いエントリーシートを作成することが選考通過につながります。
ただし、応募数が0社では比較検討ができず、視野が狭まってしまう可能性があります。
また、選考に慣れるという意味でも、少しでも興味を持った企業が複数あれば、積極的に応募してみるのが良いでしょう。
結果的に数社から参加の機会を得られれば、比較を通じて自分に合う企業を見つけやすくなります。
Q. 参加しないと就職活動で不利になる?
インターンシップに参加しなかったからといって、直ちに就職活動で不利になるわけではありません。
しかし、参加することで得られるメリットは大きいのが実情です。
業界や企業への理解が深まったり、入社後のミスマッチを防げたりするほか、早期選考の対象となる可能性もあります。
もし参加が難しい場合は、その分、業界研究セミナーやOB・OG訪問、企業説明会などに積極的に足を運び、情報収集を徹底する必要があります。
インターンシップ以外の活動で、企業への熱意や理解度を示すことが重要です。
Q. 短期と長期はそれぞれいつから始めるべき?
インターンシップの期間は様々ですが、短期と長期で始めるべきタイミングは異なります。
1日や5日程度の短期インターンシップは、主に大学3年生の夏休みや春休みといった長期休暇中に集中して開催されます。
一方、数ヶ月以上にわたる長期インターンシップは、企業が通年で募集していることが多く、学年を問わずいつでも挑戦が可能です。
2日以上や5日以上といった実務に近い経験を積みたい場合、時間に余裕のある大学1・2年生のうちから長期インターンを始める学生も増えています。
まとめ
インターンシップは大学3年生の夏から本格化しますが、それ以前の低学年から自己分析や業界研究を始めることで、よりスムーズに就職活動へ移行できます。
年間スケジュールを把握し、夏と秋冬の各時期の特性を理解した上で、自身の目的に合ったプログラムを選びましょう。
事前の準備を計画的に行い、大手企業だけでなく中小・ベンチャー企業にも視野を広げることが、有意義な経験を得るための鍵となります。
焦らず、自分のペースでキャリア形成に向けた一歩を踏み出すことが大切です。
インターンはいつから始めるべきか迷う大学生は多いですが、実際には大学2年の夏頃から情報収集を始め、大学3年の夏休みが参加のピークとなります。
27卒(2027年卒業予定)の学生は2025年夏から本格化し、2026卒や2025卒はすでに動いているため注意が必要です。
大学生や大学院生、専門学校生では予定や学校の仕組みに違いがあり、薬学生など資格系は実習との調整がポイントになります。
探し方はリクナビなどの就活サイト、学校のキャリアセンター、先輩や知恵袋の体験談を活用するのがベスト。
インターンは夏・秋・冬・春と年間を通じて開催されますが、特に選考直結型は締め切りが早いため、予約は早めに行うのが安心です。
服装は紺色や白など清潔感のある落ち着いた色を選ぶとよく、短期のワンデーインターンから挑戦する学生も増えています。
早めの準備が内定への近道になるので、計画的に参加していきましょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む