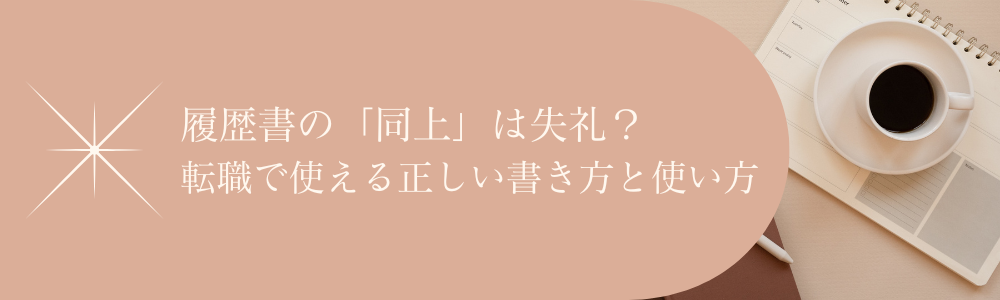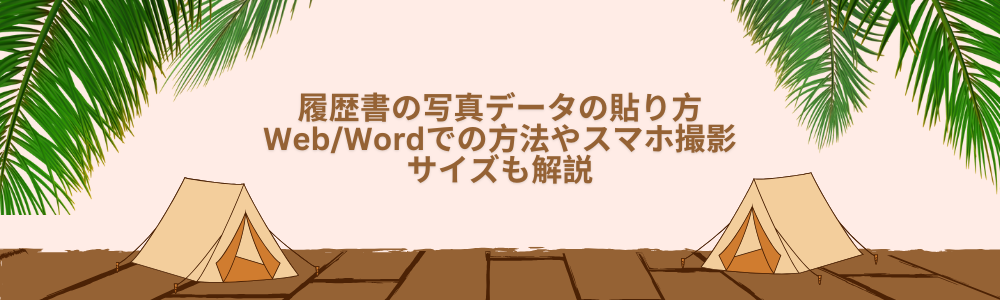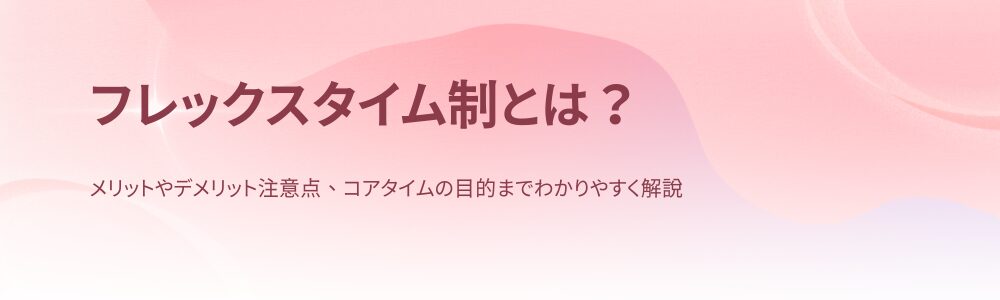

フレックスタイム制とは?メリットやデメリット注意点、コアタイムの目的までわかりやすく解説
フレックスタイム制とは、定められた総労働時間の範囲内で、日々の始業時間や終業時間を労働者が自由に決定できる制度です。
この制度の目的は、柔軟な働き方を実現し、ワークライフバランスの向上や生産性の向上を図ることにあります。
この記事では、就職活動中の学生に向けて、フレックス制の仕組みやメリット・デメリットについて、わかりやすい解説を提供します。
フレックスタイム制とは出社・退社の時間を自由に決められる制度
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業時刻と終業時刻を自主的に決定できる制度です。
この制度のもとでは、毎日の出社時間や退社時間が固定されておらず、個人の都合に合わせて勤務時間を調整できます。
ただし、多くの企業では、全従業員が必ずオフィスにいなければならない時間帯(コアタイム)を設けています。
この柔軟な勤務形態の説明として、ワークライフバランスの実現を目指す企業で導入が進んでいます。
固定時間制や裁量労働制との違いとは
フレックスタイム制と固定時間制の最も大きな違いは、始業・終業時刻を労働者自身が決められる点です。
固定時間制では、会社が定めた「9時から18時まで」といった時間に拘束されます。
一方、裁量労働制との違いは、労働時間の実績を管理するかどうかにあります。
裁量労働制は、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた時間分を働いたとみなす制度で、業務の進め方自体を労働者の裁量に委ねます。
これに対し、フレックスタイム制は、働く時間帯の自由度は高いものの、清算期間内での総労働時間を満たす必要があり、実労働時間に基づいて給与が計算される点で異なります。
フレックスタイム制の仕組みを構成する4つの基本要素とは
フレックスタイム制を正しく理解するためには、いくつかの基本的な用語を知っておく必要があります。
この制度は、主に「コアタイム」「フレキシブルタイム」「清算期間」「総労働時間」という4つの要素で構成されています。
これらの仕組みをわかりやすい形で把握することで、企業ごとの制度の違いや特徴を比較検討しやすくなります。
就職活動で企業の働き方について調べる際に、これらの用語の意味を理解していると、より深く企業研究を進めることが可能です。
必ず出勤すべき時間帯「コアタイム」
コアタイムとは、フレックスタイム制が導入されている企業において、全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯のことです。
例えば「10時から15時まで」のように設定され、この時間帯には会議や打ち合わせ、チームでの共同作業などが集中して行われる傾向にあります。
コアタイムを設ける目的は、従業員間の円滑なコミュニケーションを確保し、業務の連携に支障が出ないようにすることです。
企業によっては、このコアタイムを設定せず、すべての勤務時間を従業員の裁量に委ねる「スーパーフレックスタイム制」を採用している場合もあります。
働く時間を自由に選べる「フレキシブルタイム」
フレキシブルタイムとは、フレックスタイム制において、労働者が自身の裁量で始業および終業の時刻を自由に選択できる時間帯を指します。
通常、1日の勤務時間帯の中で、コアタイムの前後に設定されることが多く、「7時から10時まで」と「15時から20時まで」のように、始業時間帯と終業時間帯に分けて設けられます。
このフレキシブルタイムをどのように活用するかで、働き方の自由度が大きく変わります。
例えば、朝の時間を有効活用するために早く出社したり、夕方のプライベートな用事のために早めに退勤したりするなど、柔軟な働き方を実現するためにフレックス制を活用できます。
労働時間を計算する単位期間「清算期間」
清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が働くべき総労働時間を算定するための単位となる期間のことです。
この期間内で、定められた総労働時間を満たすように日々の勤務時間を調整します。
以前は清算期間の上限は1ヶ月でしたが、法改正により最長で3ヶ月まで設定可能になりました。
例えば、清算期間が1ヶ月の場合、その月単位で総労働時間を満たせばよく、ある週は長く働き、別の週は短く働くといった柔軟な働き方ができます。
企業は、この期間を労使協定で定める必要があり、給与計算もこの期間を基準に行われます。
清算期間内に働くべき合計時間「総労働時間」
総労働時間とは、清算期間内において労働者が勤務すべきと定められた合計時間のことです。
この時間は、一般的に「1日の標準労働時間×その清算期間における所定労働日数」で算出されます。
労働者は、この総労働時間の範囲内で日々の労働時間を調整し、期間の終わりで過不足がないように働きます。
例えば、ある日に長く働いた分、別の日に早く帰ることで調整が可能です。
総労働時間を超えて働いた場合は時間外労働(残業)となり、割増賃金が支払われます。
逆に満たなかった場合は、賃金控除の対象となることがあります。
フレックスタイム制を運用する上で、この時間の管理が基本となります。
コアタイムがない「スーパーフレックスタイム制」とは?
スーパーフレックスタイム制とは、フレックスタイム制の一種で、必ず勤務しなければならない時間帯である「コアタイム」を設けない制度のことです。
この制度では、フレキシブルタイムのみで構成されるため、労働者は規定の総労働時間を満たす限り、日々の始業・終業時刻を完全に自由に決められます。
例えば、特定の日に集中的に働き、別の日は短時間勤務にするなど、最も自由度の高い働き方が可能になります。
ただし、完全に自由というわけではなく、会議への出席やチームとの連携など、業務上の必要性に応じた時間調整は求められます。
スーパーフレックス制度は、特に個人の裁量が大きい職種で導入されています。
フレックスタイム制で働く3つのメリットとは
フレックスタイム制は、労働者にとって多くのメリットをもたらす働き方です。
日々の始業・終業時刻を自分で決められるため、プライベートの予定と仕事の調整がしやすくなります。
また、通勤ラッシュを避けて出勤できるため、通勤に伴うストレスが軽減される点も大きな利点です。
さらに、業務の繁閑に合わせて労働時間を配分できるため、生産性の向上も期待できます。
これらのメリットは、就職活動において企業を選ぶ際の重要な判断材料の一つとなり得ます。
仕事とプライベートの両立がしやすくなる
フレックスタイム制の最大のメリットは、仕事とプライベートの調和、すなわちワークライフバランスを実現しやすくなる点です。
始業・終業時間を自由に調整できるため、育児や介護、通院といった家庭の事情や、自己啓発のための通学、趣味の時間確保など、個人のライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。
例えば、平日の日中にしか開いていない役所や銀行での手続きを済ませるために、一時的に仕事を抜けて後でその分を補うといった柔軟な対応もできます。
このように、個人の裁量で時間を管理できるため、充実した私生活を送りながら、仕事にも集中しやすい環境が整います。
通勤ラッシュを避けてストレスなく出勤できる
都市部で働く多くの人にとって、満員電車での通勤は大きなストレス要因です。
フレックスタイム制を活用すれば、朝夕の通勤ラッシュのピーク時間を避けて出退勤することが可能になります。
例えば、早朝に出勤して夕方早く帰宅したり、ラッシュが過ぎた後の時間帯に出勤したりすることで、心身の負担を大幅に軽減できます。
通勤時間が快適になるだけでなく、空いた電車内で読書や勉強をするなど、時間を有効に使うこともできます。
このストレス軽減は、日々の仕事へのモチベーションや集中力の維持にも良い影響を与えるでしょう。
自分のペースで働けるため生産性が向上する
フレックスタイム制では、日々の業務量や自身のコンディションに合わせて労働時間を調整できるため、生産性の向上が期待できます。
例えば、重要なミーティングや集中力が必要な作業がある日は長めに働き、比較的業務が落ち着いている日は早めに退勤するといった、メリハリのある働き方が可能です。
また、個人の集中力が最も高まる時間帯に重要なタスクを割り当てることで、効率的に仕事を進めることができます。
このように、労働時間を画一的に管理するのではなく、個人の裁量に任せることで、より質の高い成果を生み出しやすくなります。
知っておきたいフレックスタイム制の3つのデメリットとは
フレックスタイム制は多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
導入している企業へ就職を検討する際は、良い面だけでなく、課題となりうる点も理解しておくことが重要です。
主なデメリットとして、社員間のコミュニケーションが取りにくくなる可能性、労働者自身に求められる高度な自己管理能力、そして勤務時間外に連絡が来る可能性などが挙げられます。
これらの点を踏まえ、自分に合った働き方かどうかを判断する必要があります。
コミュニケーション不足で業務に支障が出る場合がある
フレックスタイム制では、従業員ごとに出社・退社時間が異なるため、オフィスに全員が揃う時間が限られます。
これにより、対面でのコミュニケーション機会が減少し、業務上の連携に支障をきたす可能性があります。
例えば、簡単な相談や確認をしたい時に相手が不在であったり、情報共有にタイムラグが生じたりすることが考えられます。
この問題を解決するため、多くの会社では、定期的なミーティングの設定やチャットツールの活用、情報共有ルールの徹底など、コミュニケーションを円滑にするための工夫を凝らしています。
高度な自己管理能力が求められる
フレックスタイム制は、労働時間の管理を個人の裁量に大きく委ねる制度です。
この自由度の高さはメリットである反面、労働者には高度な自己管理能力が求められます。
計画的に業務を進め、清算期間内に定められた総労働時間を満たす責任は個人にあります。
自己管理が苦手な場合、つい仕事を後回しにしてしまったり、逆に働きすぎてしまったりするリスクも考えられます。
企業側も勤怠管理システムで労働時間を把握していますが、日々のスケジュール管理や業務の進捗管理は、自分自身でしっかりと行う意識が必要です。
時間外でも仕事の連絡が来る可能性がある
フレックスタイム制では、同僚や上司と自分の勤務時間帯がずれることが頻繁に起こります。
そのため、自分がすでに業務を終えて退勤した後でも、まだ働いている他の社員から仕事に関するメールやチャットが届く可能性があります。
すぐに返信する必要はないとしても、業務時間外に連絡が来ること自体が精神的な負担になることもあります。
このような事態を避けるため、チーム内でお互いの勤務時間を共有したり、緊急時以外の時間外連絡に関するルールを設けたりするなどの対策が求められます。
フレックスタイム制における残業代や勤怠のルールとは
フレックスタイム制は働き方の自由度が高い制度ですが、勤怠管理や残業代の計算については独自のルールが定められています。
一般的な固定時間制とは異なり、1日の労働時間が8時間を超えてもすぐには残業扱いになりません。
ここでは、フレックスタイム制における残業時間の考え方や、コアタイムに遅刻・早退した場合の基本的な扱いについて解説します。
就職後に戸惑わないよう、これらのルールを事前に理解しておくことが大切です。
残業時間は総労働時間を超えた分で計算される
フレックスタイム制における時間外労働(残業)は、1日単位ではなく、清算期間全体で計算されるのが特徴です。
具体的には、清算期間内に定められた「総労働時間」を超えて働いた時間が、残業として扱われます。
例えば、ある日に10時間働いたとしても、別の日に6時間勤務するなどして、清算期間の終わりで総労働時間を超えていなければ、残業代は発生しません。
総労働時間を超えた時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた分については、法律上の時間外労働となり、割増賃金の支払い要件を満たします。
コアタイムに遅刻・早退した場合の扱いは?
フレックスタイム制であっても、全従業員が必ず勤務すべき時間帯として定められているコアタイムには、遅刻や早退の概念が存在します。
コアタイムに遅刻したり早退したりした場合の扱いは、企業の就業規則によって異なります。
一般的には、固定時間制と同様に遅刻・早退と見なされ、その時間分が給与から控除されたり、人事評価に影響したりすることがあります。
ただし、企業によっては、遅れた時間分を同期間内のフレキシブルタイムで補うことを認めている場合もあります。
やむを得ない理由でコアタイムに遅刻・早退する際は、事前に上司の許可を得るのが基本的なルールです。
フレックスタイム制が導入されやすい業界・職種とは
フレックスタイム制は、個人の裁量で業務を進めやすい業界や職種で導入が進んでいます。
代表的なのは、エンジニアやデザイナー、プログラマーなどが属するIT・Web業界です。
成果物の質が重視され、時間や場所の柔軟性が高い業務と相性が良いためです。
また、広告・出版業界のクリエイティブ職や、企業の企画・マーケティング職、研究開発職なども、個人のペースで仕事を進める場面が多いため、導入されやすい傾向にあります。
一方で、工場勤務や店舗での接客業など、チーム全員が同時に稼働する必要がある業種では、導入が難しいのが実情です。
企業選びの際には、志望する業界や職種の特性も考慮するとよいでしょう。
フレックスタイム制を導入するために企業が行うこと
企業がフレックスタイム制を導入するには、制度を開始すると宣言するだけでは不十分で、法律に基づいた正式な手続きを踏む必要があります。
具体的には、就業規則への規定と、労使協定の締結という2つのステップが不可欠です。
これらの手続きは、制度を適法に運用し、労働者を保護するための重要なプロセスです。
就活生が直接関わることではありませんが、こうした背景を知っておくことで、その会社が法令を遵守し、しっかりとした労務管理を行っているかを判断する一つの材料になります。
就業規則への規定
企業がフレックスタイム制を導入するための第一歩は、就業規則にその旨を明記することです。
就業規則とは、賃金や労働時間、服務規律など、その会社で働く上での基本的なルールを定めたものです。
フレックスタイム制を導入する場合、労働基準法の定めに従い、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」という内容を就業規則に記載しなければなりません。
この規定がなければ、制度を有効に運用することができません。
したがって、就業規則への記載は、フレックスタイム制導入の法的根拠となります。
労働者と使用者間での労使協定の締結
就業規則への規定とあわせて、企業は労働者の代表との間で労使協定を締結する必要があります。
この労使協定では、フレックスタイム制の具体的な運用ルールを定めます。
具体的には、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヶ月や3ヶ月など)、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、そしてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合にはその時間帯などを書面で協定します。
この協定があって初めて、企業は労働者に対してフレックスタイム制の適用が可能になります。
これらの要件を満たすことで、適正な制度運用が担保されます。
フレックスタイム制と時差出勤違いとは
フレックスタイム制と時差出勤は、どちらも出勤時間を調整できる働き方ですが、その仕組みには明確な違いがあります。
最大の違いは、日々の始業・終業時刻を誰が決めるかという点です。
フレックスタイム制では、労働者自身が日々の始業・終業時刻を自由に決定できます。
一方、時差出勤は、会社が「8時~17時」「9時~18時」「10時~19時」といった複数の勤務時間パターンをあらかじめ設定し、労働者はその中から選択、あるいは会社から指定されたパターンで勤務する制度です。
また、時差出勤では1日の実働時間が固定されていますが、フレックスタイム制では日によって労働時間を長くしたり短くしたりと調整が可能です。
フレックスタイム制とはまとめ
フレックスタイム制は、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を自主的に決められる柔軟な勤務制度です。
ワークライフバランスの向上や生産性の向上といったメリットがある一方で、コミュニケーション不足や高度な自己管理が求められるといった側面も持ち合わせています。
また、コアタイムや清算期間といった独自の仕組みや、残業時間の計算方法など、正しく理解しておくべきルールも存在します。
企業によって制度の詳細は異なるため、就職活動でフレックス制を導入している企業を検討する際は、その運用実態まで確認することが望ましいです。
フレックスタイム制(flex time、英語では fl とも表記)は、働く時間を自分である程度調整できる制度です。フルに「好きな時間に出社・退社してよい」わけではありませんが、会社が決めた清算期間内で所定の労働時間を満たせばよいため、ライフスタイルに合わせやすい働き方です。
例えば、朝ゆっくり準備して遅めに出勤したり、予定がある日は早く帰ったりといった調整ができます。求人サイトのリクナビなどでも「フレックスタイムあり」と書かれている職場があり、柔軟な働き方を求める学生や転職希望者には役立つ知識です。
また、派遣や人材紹介のサービスでもこの制度を導入している会社は多く、面接で「フレックスタイムの概要を説明してください」と聞かれるケースもあります。その際の例文としては「フレックスタイムとは、出退勤時間を調整できる制度で、職場の事情やスタッフの生活リズムに合わせられる仕組みです」と答えるとわかりやすいでしょう。
注意点として、制度があっても「コアタイム」と呼ばれる必ず出勤しないといけない時間帯がある場合もあります。また、残業や延長勤務についても会社ごとにルールが異なりますので、求人や面接の場でしっかり確認してみることが大切です。
ちなみに「flex」という言葉は、英語のスラングでは「自慢する」という意味でも使われます。働き方の制度としてのフレックスタイムと混同しないようにしておきましょう。
タッチオンタイムのような勤怠管理システムを使うと、出退勤の記録や申請がスムーズにできるため、企業・スタッフ双方にとって便利です。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む