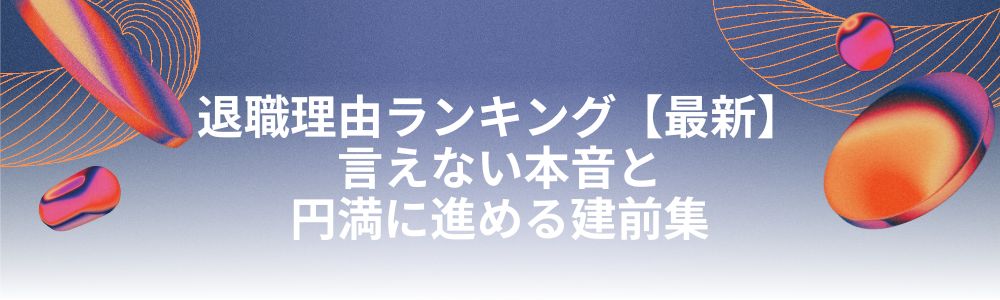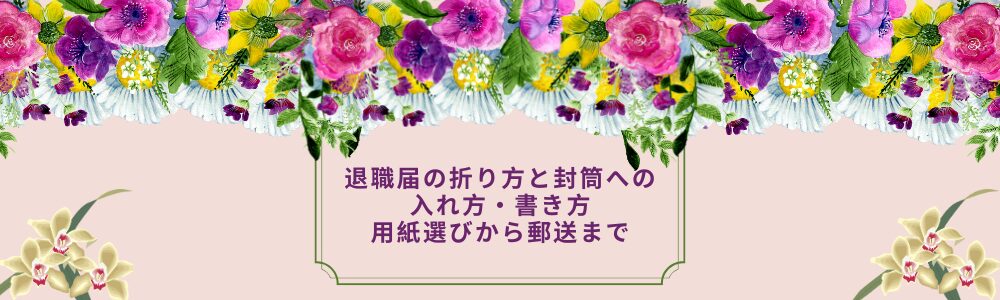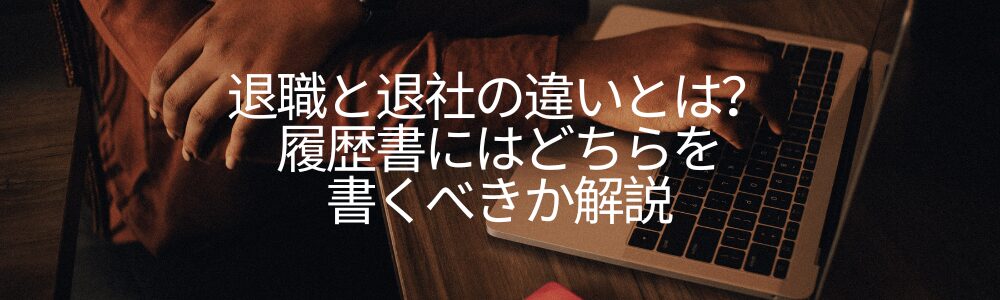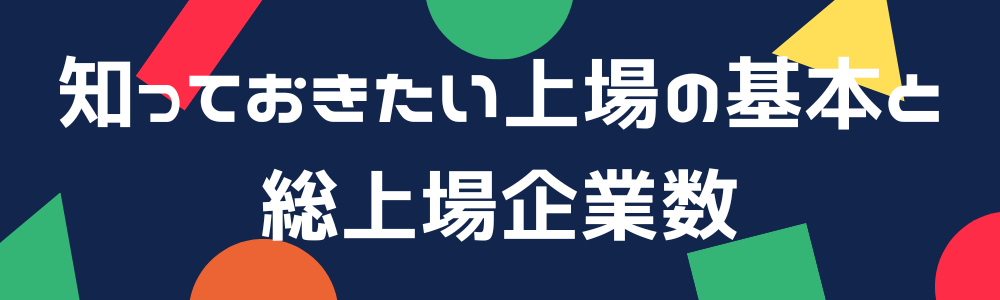

知っておきたい上場の基本と総上場企業数
日本の上場企業数は何社?市場別の割合や推移もわかりやすく解説
日本の最新の上場企業数は約4,000社です。
この企業数は、日本の全法人の中から見るとごくわずかな割合に過ぎません。
企業が上場する市場はプライム、スタンダード、グロースなどに分かれており、市場別にその数や特徴は異なります。
この記事では、日本の全上場企業数や市場別の内訳、上場するメリット・デメリットについて解説します。
そもそも上場企業とは?基本的な意味をわかりやすく解説
上場企業とは、証券取引所が設ける審査基準をクリアし、自社の株式が取引所で売買されることを認められている会社のことです。
投資家は誰でもその会社の株式を売買できます。
一方、株式の売買が特定の株主に限定されているのが非上場企業です。
上場する企業は、株式を発行して市場から広く資金を調達することを目的の一つとしています。
このように、株式の公開状況が上場しているのか非上場なのかの大きな違いです。
【2024年最新】日本に上場企業は全部で何社ある?
2024年6月時点での国内の全上場企業数は3,939社です。
この数字は2023年末の3,924社から微増しており、年間を通じて新規上場や上場廃止によって変動します。
例えば、2023年には96社が新規上場し、一方で経営破綻や完全子会社化などを理由に49社が上場廃止となりました。
このように、全上場企業数は常に変化しているため、最新の情報を確認することが重要です。
東京証券取引所の市場区分ごとの企業数
日本には東京証券取引所(東証)のほか、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所が存在します。
その中でも国内上場企業の9割以上が東証に上場しており、中心的な役割を担っています。
東証は2022年4月に市場区分を再編し、現在は「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つで構成されています。
各市場はそれぞれ異なるコンセプトや上場基準を持っており、上場している銘柄の性質も異なります。
そのため、東証の市場区分ごとの企業数を見ることで、日本経済の構造や動向をより深く理解できます。
プライム市場に上場している企業数
プライム市場は、グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場です。
高いガバナンス水準が求められ、日本を代表する大企業が多く含まれます。
2024年6月時点でのプライム上場企業数は1,651社です。
これは東証全体の約4割を占めています。
業種としては、製造業、情報・通信業、卸売業、銀行業、建設業など、幅広い分野のリーディングカンパニーが名を連ねています。
企業の時価総額が大きく、安定した経営基盤を持つ企業が中心となる市場区分です。
スタンダード市場に上場している企業数
スタンダード市場は、国内経済を支える中核企業向けの市場です。
公開市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業が上場しています。
2024年6月時点でのスタンダード市場の上場企業数は1,654社で、プライム市場とほぼ同等の規模を誇ります。
プライム市場ほどの厳しい基準はないものの、安定した事業基盤を持つ優良企業が多く、幅広い業種の企業が含まれているのが特徴です。
グロース市場に上場している企業数
グロース市場は高い成長可能性を有する企業向けの市場です。
事業実績の観点ではまだ途上にある新興企業が多く、将来性を見越した投資家からの資金供給を促すことを目的としています。
2024年6月時点での上場企業数は634社です。
新規株式公開(IPO)を目指す企業の多くが、まずこのグロース市場への上場を選択します。
そのためIT関連やバイオテクノロジーなど、新しいビジネスモデルを持つ企業が数多く含まれています。
リスクは高いものの、将来の大きな成長が期待される企業が集まる市場です。
日本の全法人の中で上場している会社の割合
日本には約300万社の法人が存在しますが、その中で上場している会社は約4,000社であり、割合にすると全体のわずか0.1%程度です。
この数字からも、上場がいかに厳しい基準をクリアした企業であるかがわかります。
本社所在地の都道府県別ランキングを見ると、東京都に約半数が集中しており、次いで大阪府、神奈川県、愛知県と続きます。
一方で、北海道や福岡県、宮城県といった地方中核都市にも多くの有力企業が存在します。
兵庫県、京都府、埼玉県、千葉県、静岡県、広島県なども上位に位置する一方、和歌山県、佐賀県、高知県、青森県、秋田県、山形県、宮崎県など、上場企業数が一桁の県もあり、地域による偏りが見られます。
新潟県、石川県、岡山県、熊本県、長野県、茨城県、三重県、滋賀県、香川県、愛媛県、大分県、山口県、福井県、山梨県、栃木県、沖縄県などでも、地域経済を牽引する企業が上場を果たしています。
企業が株式上場を目指す4つのメリット
上場は企業にとって大きな目標の一つですが、その過程では厳しい審査や多大なコストが伴います。
それでもなお多くの企業が上場を目指すのは、それを上回る経営上のメリットが存在するためです。
具体的には、社会的信用の向上、資金調達方法の多様化、優秀な人材の確保、そして社内管理体制の強化といった点が挙げられます。
これらのメリットは、企業の持続的な成長を実現するための重要な基盤となります。
企業の社会的信用度が格段に向上する
上場するためには、証券取引所が定める収益性や財産の健全性、コーポレート・ガバナンスなどに関する厳しい審査基準をクリアしなければなりません。
この審査を通過したという事実そのものが、企業の信頼性を客観的に証明するものとなります。
その結果、企業の社会的信用度は格段に向上し、新たな取引先との契約がスムーズに進んだり、金融機関から有利な条件で融資を受けやすくなったりします。
また、企業の製品やサービスに対する顧客からの信頼も高まり、ブランドイメージの向上にも寄与するなど、事業活動のあらゆる面で好影響が期待できます。
資金調達の選択肢が広がり経営の安定化につながる
非上場企業の場合、資金調達の方法は主に金融機関からの借入れや経営者による出資に限られます。
しかし、上場を果たすと、株式市場を通じて不特定多数の投資家から直接資金を調達する「公募増資」が可能になります。
これにより、大規模な設備投資や新規事業の立ち上げ、M&Aといった成長戦略に必要な資金を、返済義務のない自己資本として確保できます。
また、株式を発行するだけでなく、社債の発行など多様な手段を選べるようになるため、財務戦略の自由度が高まります。
資金調達の選択肢が広がることは、経営基盤の安定化とさらなる事業拡大を後押しする大きな要因です。
知名度アップにより優秀な人材が集まりやすくなる
上場すると、企業の株価や業績が日々報道されるようになり、メディアへの露出機会が格段に増えます。
これにより企業の知名度が全国的に高まり、採用活動において大きなアドバンテージとなります。
知名度の向上は、企業の製品やサービスだけでなく、働く場所としての魅力も高めるため、より多くの求職者の目に留まるようになります。
特に、安定性や将来性を重視する優秀な求職者にとって、上場しているという事実は安心材料となり、応募への動機付けとなります。
優秀な能力を持つ者の確保は企業の成長に不可欠であり、採用競争力の強化は上場がもたらす重要なメリットの一つです。
厳しい審査基準により社内管理体制が強化される
上場審査の過程では、企業の内部管理体制が厳しく問われます。
具体的には、適切な会計処理、法令遵守(コンプライアンス)の徹底、内部統制システムの構築などが求められます。
この準備プロセスを通じて、社内の業務フローが見直され、経営の透明性が高まります。
それまで経営者個人の判断に依存しがちだった部分も、明確なルールや権限に基づいて運営されるようになり、組織的な経営体制へと移行します。
上場後も、四半期ごとの決算開示や適時開示が義務付けられるため、常に高い水準の管理体制を維持しなくてはなりません。
結果として、不正や不祥事のリスクが低減し、企業の持続的な成長を支える強固な基盤が築かれます。
株式上場にともなう3つのデメリット
株式上場は多くのメリットをもたらす一方で、企業にとっては新たな責任やリスクを背負うことにもなります。
株式が市場で自由に売買されるようになるため、経営の自由度が一定程度制約されるほか、上場を維持するためのコストも発生します。
具体的には、敵対的買収のリスク、株主に対する情報開示の義務、そして上場維持費用の発生などが主なデメリットとして挙げられます。
これらの点を理解しておくことは、上場という選択肢を多角的に捉える上で不可欠です。
常に敵対的買収のリスクにさらされる
株式を上場すると、その株式は市場を通じて誰でも自由に購入できるようになります。
これは、経営陣が意図しない相手に株式を買い占められ、経営権を奪われる「敵対的買収」のリスクに常にさらされることを意味します。
株価が企業の実質的な価値に比べて割安な状態にある場合などは、特にその標的となりやすい傾向があります。
経営陣は、安定した株主を確保したり、買収防衛策を導入したりするなど、常に経営権の維持に注意を払わなければなりません。
株主の利益を最大化しつつ、望まない買収から会社を守るという、非上場時にはなかった経営課題に直面することになります。
株主に対して経営状況を開示する義務が発生する
上場企業には、投資家保護の観点から、自社の経営状況を詳細に開示する義務(ディスクロージャー)が課せられます。
具体的には、四半期ごとの決算短信や年間の有価証券報告書の提出が法律で義務付けられており、業績や財務状況、事業のリスクなどを公表しなくてはなりません。
また、株価に大きな影響を与える重要事実が発生した際には、速やかに情報を開示する「適時開示」も求められます。
これにより経営の透明性は高まりますが、一方で重要な経営情報が競合他社に知られるリスクも生じます。
さらに、株主からは常に短期的な業績向上が期待されるため、長期的な視点での経営判断が難しくなるというプレッシャーにさらされる側面もあります。
上場を維持するために高額な費用が必要になる
上場を維持するためには、継続的に高額な費用が発生します。
まず、証券取引所に支払う年間上場料が必要です。
これに加えて、財務諸表の信頼性を担保するための監査法人への監査報酬、株主名簿を管理する信託銀行への手数料、株主総会の運営費用などが毎年かかります。
さらに、投資家向けに情報を発信するIR活動にも人件費や資料作成費といったコストを要します。
これらの費用は企業の規模にもよりますが、年間で数千万円から数億円に上ることも少なくありません。
こうした維持コストが、特に業績が不安定な時期には経営の大きな負担となる可能性があります。
上場企業で働く従業員から見たメリット
企業の視点だけでなく、そこで働く従業員の視点から見ても、上場企業には多くのメリットがあります。
上場企業は社会的な責任が大きく、コンプライアンス遵守が求められるため、社員が働きやすい環境が整備されている傾向にあります。
特に、福利厚生の充実度や経営の安定性は、非上場企業と比較した場合の大きな魅力と言えるでしょう。
上場企業の社員として働くことは、キャリアだけでなく生活の安定にも寄与する可能性があります。
福利厚生や社内制度が充実している傾向にある
上場企業は、優秀な人材を確保し定着させるため、福利厚生や社内制度の充実に力を入れていることが多くあります。
住宅手当や家族手当といった金銭的な補助に加え、充実した退職金制度や企業年金、社員持株会などが整備されていることも少なくありません。
また、コンプライアンス意識の高さから、労働時間管理が徹底され、長時間労働の是正や有給休暇の取得促進にも積極的です。
育児や介護と仕事の両立を支援する制度、スキルアップのための研修制度などが整っている場合も多く、従業員が長期的に安心してキャリアを築ける環境が提供されています。
経営が安定しており倒産のリスクが低い
上場している企業は、厳しい審査基準をクリアしているため、事業の継続性や収益性において一定の評価を得ています。
強固な経営基盤を持ち、社会的信用も高いため、事業運営が安定している傾向にあります。
また、株式市場からの資金調達が可能なため、非上場企業に比べて財務体力が強いことも特徴です。
これにより、景気の変動や突発的な経営危機に対する耐性が比較的高く、倒産のリスクは低いと言えます。
従業員にとっては、会社の将来に対する不安が少なく、長期的な視点で自身の生活設計やキャリアプランを立てやすいという大きな安心感を得られます。
上場企業で働く従業員から見たデメリット
安定性や充実した制度といったメリットがある一方で、上場企業で働くことにはデメリットと感じられる側面も存在します。
特に、組織規模の大きさや、株主をはじめとする多くのステークホルダーへの配慮が求められる企業体質から生じる課題が挙げられます。
具体的には、意思決定のプロセスが複雑化しスピードが遅くなることや、個々の従業員に与えられる裁量が小さくなる可能性などが考えられます。
これらは、仕事の進め方や働きがいにも影響を与える要素です。
意思決定のスピードが遅くなる場合がある
上場企業は組織が大きく、多くの部署や役職者が存在するため、一つの物事を決定するのに複雑な手続きが必要となる場合があります。
企画の提案から承認まで、直属の上司、部長、役員といった複数の階層での決裁(稟議)を経なければならず、時間がかかりがちです。
また、株主への説明責任が伴うため、重要な意思決定は慎重に行われ、多様なリスクを検討するプロセスが挟まれます。
こうした構造的な要因から、市場の変化に迅速に対応すべき場面でも、意思決定のスピードが遅くなることがあります。
結果として、ビジネスチャンスを逃したり、現場の業務が停滞したりする可能性も否定できません。
個人の裁量が小さくなる可能性がある
大企業である上場企業では、業務が細かく分業化されていることが一般的です。
そのため、従業員一人ひとりが担当する業務範囲は限定的になりがちです。
また、業務の進め方についても、社内規定やマニュアルが整備されており、定められた手順に沿って仕事を進めることが求められます。
これは業務の標準化や品質維持には貢献しますが、一方で個人の裁量で仕事を進める余地は小さくなります。
自分のアイデアを自由に試したり、部署を横断して幅広い業務を経験したりする機会が限られるため、人によっては「組織の歯車の一つ」であると感じ、仕事のやりがいを見出しにくくなる可能性があります。
まとめ
日本の上場企業数は約4,000社であり、これは全法人数のごく一部です。
上場には社会的信用の向上や資金調達の多様化といったメリットがある一方、買収リスクや情報開示義務などのデメリットも存在します。
また、従業員にとっては安定性や福利厚生の充実が魅力ですが、意思決定の遅さや裁量の小ささを感じる場合もあります。
世界の状況に目を向けると、上場企業数は国によって大きく異なり、最も多いのはインド、次いで米国、中国と続きます。
タイのような新興国市場も活発です。
各証券取引所のウェブサイトでは上場企業の一覧が公開されており、個別の企業情報を確認できます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部ルーチンワークとは?意味や仕事内容、向いている人、効率化のコツを解説
ルーチンワークとは、決まった手順で繰り返し行う定型業務を指し、その意味を理解することは自身のキャリアを考える上で重要です。 この記事では、ルーチンワーク… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む