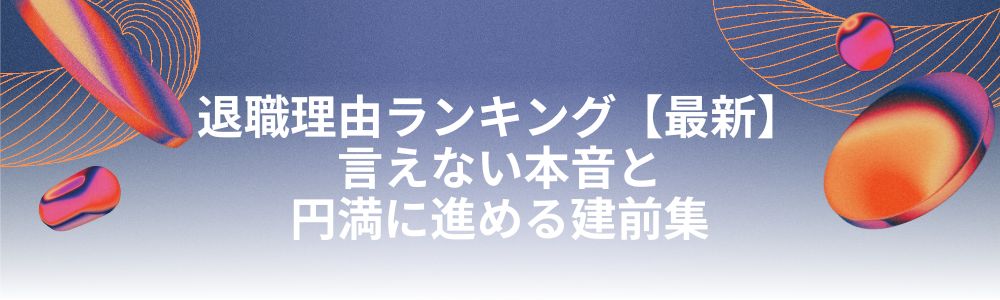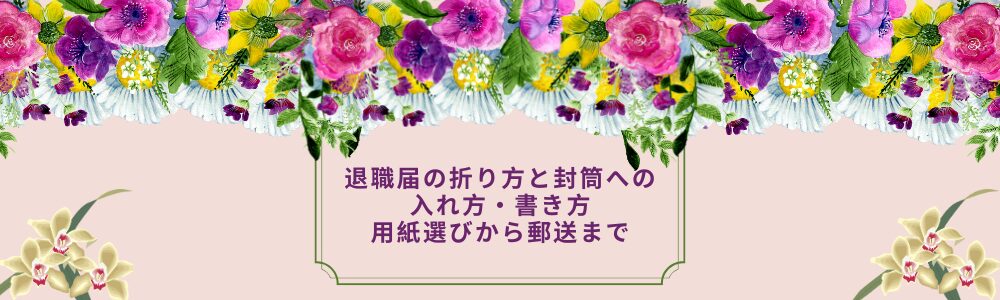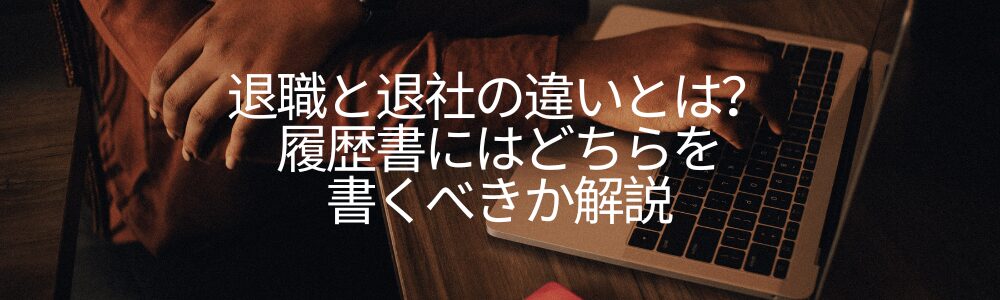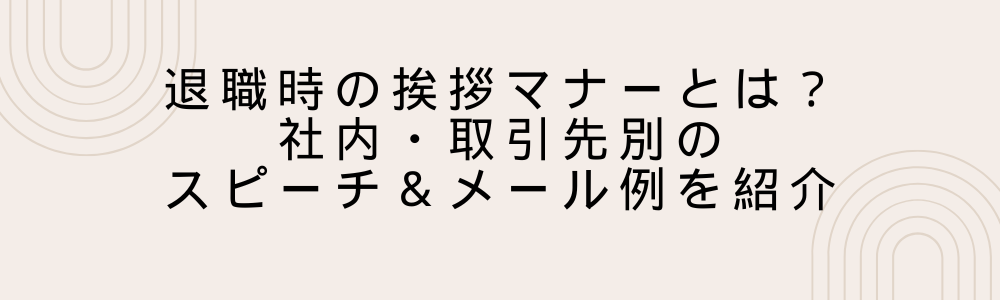

退職時の挨拶マナーとは?社内・取引先別のスピーチ&メール例を紹介
退職時には、これまでお世話になった社内外の関係者へ感謝を伝える「退職のご挨拶」が欠かせません。
挨拶の方法は、朝礼などで行うスピーチや、関係者へ送信するメールなど多岐にわたります。
円満退職を実現するためには、状況や相手に応じた適切な方法を選ぶ必要があります。
この記事では、社内向けや取引先向けの挨拶について、具体的な例文を交えながら、退職時のマナーや段取りを解説します。
退職の挨拶でまず押さえるべき基本マナー
円満な退職を実現するためには、挨拶の内容だけでなく、タイミングや伝え方といった事前の段取りが重要です。
社会人としての基本である報告・連絡・相談、いわゆる「報・連・相」を最後まで徹底する姿勢が、良好な人間関係を保つ鍵となります。
退職を伝える際は、まず直属の上司に報告し、その後の流れについて相談します。
挨拶の場では、会社の不満やネガティブな退職理由は避け、感謝の気持ちを伝えることに終始するのが基本的なマナーです。
誰にいつ伝える?退職挨拶の適切なタイミングと順番
退職の意向を最初に伝える相手は直属の上司です。
就業規則を確認し、定められた期間内にアポイントを取って直接報告します。
正式な退職日が決定した後、上司と相談の上で他の社員へ公表するタイミングを決めます。
一般的に、最終出社日の1〜2週間前に周知されることが多いです。
引き継ぎが必要な部署のメンバーには、業務に支障が出ないよう少し早めに伝える配慮も求められます。
社外への挨拶は後任者の紹介も兼ねるため、最終出社日の2〜3週間前が適切な時期となります。
スピーチとメールで共通する感謝を伝える構成要素
退職の挨拶文を作成する際は、まず退職の報告と最終出社日を明確に伝えます。
次に、これまでの業務でお世話になったことへの感謝の言葉を、具体的なエピソードを交えながら述べると気持ちが伝わりやすくなります。
続けて、新しい道へ進む前向きな姿勢や今後の抱負を簡潔に示し、最後に会社のさらなる発展と、在籍する社員の活躍を祈る言葉で締めくくるのが一般的です。
この構成はスピーチとメールのどちらでも応用できる、挨拶文の基本形です。
退職理由は「一身上の都合」と簡潔に伝えるのが基本
退職の挨拶で、具体的な退職理由を詳細に説明する必要はありません。
特に、会社への不満や人間関係のトラブルといったネガティブな内容は、聞いている人を不快にさせる恐れがあるため避けるべきです。
自己都合で退職する場合、理由は「一身上の都合」という表現を用いるのが最も無難であり、社会的なマナーとされています。
もし詳しく尋ねられた場合でも、「新しい分野に挑戦するため」といった前向きな表現に留め、余計な憶測を呼ばないよう配慮することが、円満な退職につながります。
【社内向け】状況別の退職挨拶スピーチ例文
最終出社日には、朝礼や終礼の場で全社員に向けた退職のスピーチを求められる機会が多くあります。
限られた時間の中で、これまでの感謝の気持ちと今後の抱負を伝えることが、良い印象を残すための鍵です。
こうした公の場でのスピーチは、個別に挨拶ができなかった人へ気持ちを伝える最後の機会にもなります。
ここでは、朝礼や送別会、オンライン会議といった、さまざまな状況に応じたスピーチの例文とポイントを紹介します。
朝礼や終礼で好印象を残す社内でのスピーチのポイント
朝礼や終礼でのスピーチは、他の社員の業務時間を割いて行われるため、1〜3分程度で手短にまとめるのがマナーです。
まず退職の報告と最終出社日を明確に伝え、続いて部署全体や会社全体への感謝を述べます。
特定の個人名ではなく、全体への感謝を示すのが無難です。
思い出深いエピソードを一つだけ簡潔に盛り込むと、より気持ちが伝わります。
最後に会社の発展を祈る言葉で締め、ネガティブな内容は避け、明るくはきはきと話すことを心がけると良い印象を残せるでしょう。
社内で全員の前で話す場合の挨拶とスピーチ基本例文
皆様、お忙しいところ、少しお時間をいただき恐縮です。
私事ではございますが、本日をもちまして退職することになりました。
入社してから〇年間、至らない点も多々あったかと存じますが、皆様の温かいご指導とご協力のおかげで、多くのことを学び、成長することができました。
特に、〇〇のプロジェクトでは、チーム一丸となって目標を達成できたことが心に残っております。
ここで得た貴重な経験を、今後の人生でも活かしていきたいと考えております。
最後になりましたが、皆様の今後のご健勝と、会社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
長い間、本当にありがとうございました。
送別会で求められた時の一言スピーチ例文
送別会でのスピーチは、朝礼などよりも少しくだけた雰囲気で話すことが可能です。
最初に、会を開いてくれたことへの感謝を伝えます。
「本日は、私のためにこのような会を開いていただき、誠にありがとうございます」と切り出しましょう。
仕事の思い出に加え、飲み会や社員旅行といったプライベートなエピソードに触れるのも良いです。
ただし、長くなりすぎないように配慮し、謙虚な姿勢を忘れないようにします。
お世話になった方々への感謝を改めて伝え、場を盛り上げる言葉で締めくくると好印象です。
社内でのオンライン会議で気をつけたいこと
リモートワークが中心の職場では、オンライン会議で挨拶の機会が設けられることもあります。
対面と異なり表情や声のトーンが伝わりにくいため、いつもより明るく、はっきりとした口調で話すことを意識しましょう。
視線をカメラに向けることで、参加者一人ひとりに語りかけているような印象を与えられます。
事前に上司に相談して挨拶の時間を確保してもらい、簡潔に話せるよう内容を準備しておきます。
挨拶後にチャット機能で個人宛にメッセージを送るなど、丁寧なフォローを入れるのも良い方法です。
【社内向け】送る相手別の退職挨拶メール例文
退職の挨拶は、直接会うのが難しい相手や、改めて感謝を伝えたい相手に対してメールで行うのが一般的です。
スピーチと違って文章として残るため、言葉遣いや内容にはより一層の配慮が必要です。
一斉送信メールはマナーを守りつつ簡潔に、個別のメールでは具体的なエピソードを交えて感謝の気持ちを伝えます。
ここでは、送信相手や状況に応じたメールの書き方を、手紙のように気持ちが伝わる例文とともに紹介します。
一斉送信メールで失敗しないための退職挨拶の書き方マナー
社内向けの退職挨拶メールを一斉送信する際は、送信タイミングが重要です。
業務の妨げにならないよう、始業直後や休憩時間を避け、最終出社日の業務が落ち着いた夕方頃に送るのが望ましいです。
宛先は、情報保護の観点からBCCに全員のアドレスを入れ、TOには自分のアドレスを指定するのがマナーです。
これにより、受信者同士のアドレスが見えないように配慮できます。
件名は「退職のご挨拶(氏名)」のように、誰から何のメールかが一目でわかるものにします。
社外秘の情報は記載しないよう注意が必要です。
社内全体へ送るメールの基本例文
件名:退職のご挨拶(〇〇部氏名)
本文:
皆様
お疲れ様です。〇〇部の〇〇です。
この度、一身上の都合により、本日〇月〇日をもちまして退職することになりました。本来であれば直接ご挨拶に伺うべきところ、メールでのご連絡となり失礼いたします。
入社以来、〇年間にわたり、皆様には大変お世話になりました。至らない点も多々ありましたが、温かくご指導いただき、心より感謝しております。最終の日まで皆様と共に働くことができ、多くのことを学ばせていただきました。
最後になりましたが、皆様の今後のご健勝と、会社の益々のご発展をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
特にお世話になった上司へ送る個別メールの例文
特にお世話になった上司には、一斉送信メールとは別に個別で感謝の気持ちを伝えると、より心がこもります。
可能であれば、メールを送る前に直接挨拶を済ませておくのが丁寧です。
メールには、一斉送信の文面には書けなかった具体的な指導への感謝や、心に残っているエピソードを盛り込むと良いでしょう。
「〇〇部長には、新人時代から粘り強くご指導いただき、本当にありがとうございました。
特に〇〇の案件で壁にぶつかった際、いただいたアドバイスのおかげで乗り越えられました」といった具体的な言葉を入れることで、オリジナルのメッセージになります。
今後も付き合いのある同僚へ送る個別メールの例文
退職後もプライベートで交流を続けたい同僚には、よりパーソナルな内容のメールを送ります。
今後の連絡のために、個人の携帯電話番号やSNSアカウントなどを記載し、「今後とも変わらずお付き合いいただけると嬉しいです」と一言添えるのがポイントです。
共にプロジェクトを乗り越えた思い出や、ランチを共にした楽しい時間など、親しい間柄ならではのエピソードを交えると気持ちが伝わります。
最終日の挨拶回りの際にお菓子を渡しながら直接感謝を伝え、その上で改めてメールを送る形も丁寧な印象を与えます。
【社外・取引先向け】退職挨拶の進め方と例文
社外の取引先への退職挨拶は、自社の都合で担当者が変わることへのお詫びと、円滑な引き継ぎを約束する目的で行います。
社内向けとは異なる配慮が必要で、タイミングや伝え方を誤ると会社の信用問題に発展する可能性もあります。
そのため、挨拶の進め方は必ず上司に確認してから行動に移すことが重要です。
ここでは、取引先への退職報告の適切な時期や方法、後任者と訪問する際のポイント、そしてメールで連絡する場合の例文について解説します。
取引先への退職報告は最終出社日の2〜3週間前が目安
取引先への退職報告は、後任者への引き継ぎ期間を十分に確保するため、最終出社日の2〜3週間前に行うのが一般的です。
報告が早すぎると取引先に不安を与え、遅すぎると引き継ぎが不十分になる恐れがあります。
まずは上司に、退職の事実を取引先に伝えて良いかを確認し、許可を得てから連絡を開始します。
挨拶の順番は、業務上の関わりが深い相手や、特にお世話になった取引先から優先的に進めるのが基本です。
後任者が決まっている場合は、必ず同行して挨拶に伺います。
後任者と訪問して直接挨拶する際のポイント
取引先へは、後任者と共に訪問し、直接挨拶するのが最も丁寧な方法です。
訪問時には、まず退職の報告とこれまでの感謝を伝えます。
退職理由は社内向けと同様に「一身上の都合」とし、詳細を話す必要はありません。
次に後任者を紹介し、引き継ぎが問題なく進んでいることを具体的に説明して、取引先の不安を解消します。
自分の在職中に後任者がスムーズに業務を開始できるよう、全面的にサポートする姿勢を示すことが信頼維持につながります。
今後の連絡は後任者宛てにお願いする旨を明確に伝えましょう。
訪問が難しい場合に送る退職報告メールの例文
遠方の取引先やスケジュールの都合で直接訪問できない場合は、メールで退職の挨拶と後任者の紹介を行います。
件名は「退職のご挨拶と後任担当のご紹介(株式会社〇〇氏名)」のように、用件が明確にわかるようにしましょう。
本文では、退職日と後任者の氏名、連絡先を明記し、引き継ぎが滞りなく完了していることを伝えます。
後任者のメールアドレスをCCに入れ、後任者からも一言挨拶を添えてもらうと、より丁寧な印象になります。
本来は直接伺うべきところをメールでの挨拶になったことへのお詫びを一言添えるのがマナーです。
最終出社日をスムーズに終えるためのチェックリスト
最終出社日は、挨拶回りや私物の整理などで想像以上に慌ただしくなるものです。
円満に退職し、気持ちよく最後の一日を終えるためには、事前にやるべきことをリスト化し、計画的に行動することが求められます。
万全の準備をしておくことで、感謝の気持ちを伝えることに集中でき、心残りのない最終日を過ごせます。
ここでは、業務の引き継ぎの最終確認から備品の返却、挨拶回りまで、最終日をスムーズに過ごすためのチェック項目を解説します。
業務の引き継ぎ漏れがないか最終確認を行う
最終出社日には、後任者や関係者と共に、引き継ぎ内容に漏れがないかを最終確認します。
作成した引き継ぎ資料を再度見直し、口頭での補足が必要な点がないか確認しましょう。
担当業務の進捗状況、関係者の連絡先リスト、ファイルの保管場所などを改めて共有し、後任者が翌日から一人で業務を進められる状態を整えます。
自分にしかわからない業務の進め方や注意点などがあれば、このタイミングで全て伝えきることが重要です。
退職後の緊急連絡先についても上司と相談しておきます。
パソコンのデータ整理や備品の返却を忘れずに行う
最終日には、会社から貸与された備品を全て返却します。
健康保険被保険者証、社員証、名刺、社章、業務用携帯電話、PCなどが主な返却物です。
事前に総務部などに返却すべきものを確認し、リスト化しておくと漏れがありません。
使用していたパソコン内のデータは、業務に必要なファイルを共有フォルダへ移動させ、個人的なファイルは完全に削除します。
ブラウザの閲覧履歴やパスワードの消去も忘れずに行い、私物も計画的に持ち帰るようにしましょう。
お世話になった人への個別の挨拶回りも計画的に
最終日には、お世話になった上司や同僚、他部署の関係者へ直接挨拶に回る時間を確保します。
相手の業務の妨げにならないよう、昼休みや業務が比較的落ち着いている時間帯を見計らって訪問するのがマナーです。
感謝の気持ちを伝えるために個包装で日持ちのする菓子折りを持参すると、より丁寧な印象になります。
どうしても会えなかった人のためには、デスクに一言添えたメッセージカードと菓子を置いておくなどの配慮も有効です。
全員に挨拶できるよう、事前に回る順番を決めておくとスムーズに進みます。
まとめ
退職時の挨拶は、お世話になった方々へ感謝を伝え、良好な関係を維持したまま次のステップへ進むための重要な区切りとなります。
挨拶の基本は、適切なタイミングと順番を守り、感謝の気持ちを中心に伝えることです。
スピーチやメールといった手段を状況や相手に応じて使い分け、最後まで誠実な対応を心がけます。
業務の引き継ぎや備品の返却といった最終日の手続きも計画的に進めることで、気持ちの良い最終日を迎え、円満な退職が実現できます。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む