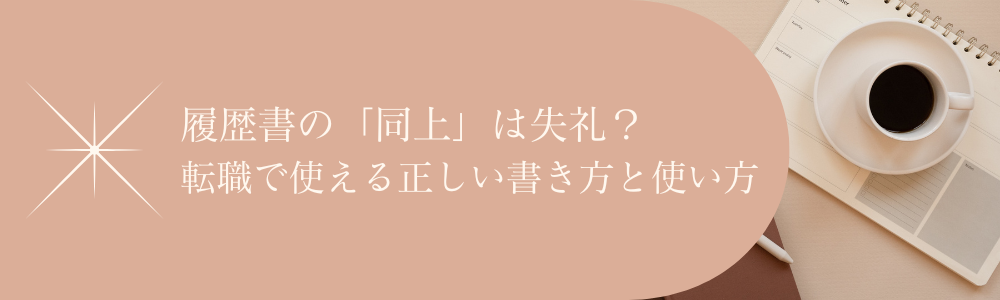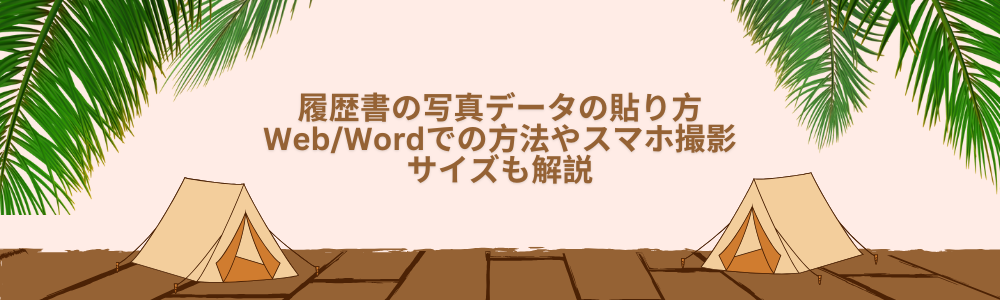ガクチカとは?就活で使える例文と自己PRとの違いを解説
ガクチカとは何か、その意味や就活における重要性について解説します。
多くの企業がエントリーシートや面接で質問するガクチカは、自己PRとの違いを正しく理解し、効果的な書き方をマスターすることが内定獲得の鍵となります。
この記事では、ガクチカとはなにか、採用担当者に評価されるの構成やテーマ別の例文、エピソードが見つからない場合の対処法まで、就活生の悩みに応える情報を網羅的に紹介します。
ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略称
ガクチカとは、「学生時代に力を入れたこと」を指す就活用語であり、その略称です。
この質問は、エントリーシートや面接の場で頻繁に問われる定番の項目の一つで、その意味を正しく理解しておく必要があります。
企業側は、学生がどのような経験に対して情熱を注ぎ、その過程で何を学び、どのように成長したのかを知ろうとしています。
単に活動内容を報告するのではなく、直面した課題や目標達成に向けた自身の考え、具体的な行動を伝えることが求められます。
このエピソードを通じて、人柄や潜在的な能力、入社後の活躍可能性などを評価されるため、就職活動における極めて重要なアピール要素と言えます。
企業が就活でガクチカを質問する3つの意図
企業がESや面接でガクチカを質問する目的を理解することは、的確なアピールをする上で不可欠です。
この質問には、学生の能力や人柄を多角的に評価し、自社のニーズと合致するかどうかを見極めたいという企業の意図が隠されています。
単なる経験の有無ではなく、その経験に対する向き合い方や思考プロセスを知ることで、書類上だけではわからない学生の素顔を把握しようとしています。
質問の背景にある意図を把握し、それに沿った内容を準備することが重要です。
学生の価値観や人柄を知るため
企業は学生がどのような物事に興味を持ち、何に対してやりがいを感じるのかという価値観や人柄を、ガクチカのエピソードから深く理解しようとしています。
学生が力を注いだと語る内容やその動機には、その人の個性やモチベーションの源泉が色濃く反映されます。
例えば、困難な状況に直面した際に、どのように考え、どう乗り越えようと行動したかというプロセスは、その学生の課題解決における姿勢や思考の特性を明らかにするものです。
企業はこれらの情報をもとに、自社の組織風土や価値観に合う人物か、チームの一員として協調できるかといった点を判断しています。
自社との相性を見極めるため
ガクチカで語られるエピソードは、企業が自社との相性、すなわちカルチャーフィットを見極めるための重要な判断材料となります。
学生が持つ強みや価値観が、企業の社風や行動指針、求める人物像とどれだけ合致しているかを確認しています。
例えば、チームワークを重んじる企業に対して、個人で黙々と研究に打ち込んだ経験よりも、サークル活動などで仲間と協力して目標を達成した経験を話す方が、相性の良さを伝えやすい場合があります。
企業にとって、相性の良い人材を採用することは、入社後の早期活躍や定着率の向上といったメリットに直結するため、この点を慎重に評価しています。
入社後の活躍イメージを掴むため
企業はガクチカを通じて、学生が過去の経験で発揮した能力やスキルを、入社後にどのように活かして活躍してくれるのか、その具体的なイメージを掴もうとしています。
学生時代に取り組んだ課題解決のプロセスは、社会人として仕事上の困難に直面した際の対応力を予測する指標となります。
目標達成に向けて主体的に行動した経験や、その過程で得た学びは、入社後の成長ポテンシャルを示すものです。
自身の経験から得たスキルが、志望企業のどのような業務で再現性をもって発揮できるのかを具体的に示すことで、採用担当者に入社後の貢献度を強く印象づけられます。
ガクチカとは?自己PRの決定的な違いを解説
就職活動において、ガクチカと自己PRは頻繁に問われる項目ですが、両者はアピールすべきポイントが明確に異なります。
この違いを正確に理解せずに回答すると、質問の意図からずれた内容になり、評価を下げてしまう可能性があります。
ガクチカと自己PR、それぞれの役割を把握し、適切に使い分けることで、自身の魅力をより効果的かつ多角的に伝えることができます。
それぞれの定義と、何を伝えるべきかを正しく整理しておきましょう。
ガクチカとは「経験のプロセス」を伝えるもの
ガクチカで最も重視されるのは、結果そのものよりも、目標や課題に対して「どのような思考と行動で取り組んだか」という過程(プロセス)です。
例えば、「サークルの新入生歓迎イベントを成功させた」という結果だけを伝えるのではなく、企画段階でどのような課題があり、それを解決するために何を考え、どんな工夫を凝らして行動したのかを具体的に説明することが求められます。
このプロセスを通じて、物事に対する向き合い方、課題発見能力、計画性、実行力といったポテンシャルを企業は見ています。
経験から何を学び、どのように成長できたのかを自身の言葉で語ることで、説得力が増します。
自己PRは「自身の強み」を伝えるもの
自己PRは、ガクチカとは異なり、自身の持つ能力や人柄といった「強み」そのものを直接的にアピールする場です。
まず結論として「私の強みは〇〇です」と明確に提示し、その強みがどのようなものかを簡潔に説明します。
そして、その強みが発揮された具体的なエピソードを根拠として添えることで、主張に説得力を持たせます。
最終的に、その強みを活かして入社後にどのように企業へ貢献できるのかを伝える構成が一般的です。
ガクチカで語る経験が、自己PRで述べた強みを裏付ける内容になっていると、人物像に一貫性が生まれ、より高い評価を得やすくなります。
ガクチカに高校時代のエピソードはあり?なし?
ガクチカで話すエピソードは、原則として大学時代の経験を用いるのが一般的です。
企業は応募者の「今」に最も近い姿、つまり大学生活を通じて培われた価値観や能力を知りたいと考えているため、高校時代の経験では情報が古いと判断される可能性があります。
ただし、高校時代の経験が現在の自分の強みや大学での取り組みに直接的かつ強く結びついている場合は、例外的に用いることも可能です。
その際には、その経験が大学での活動にどう影響を与えたのか、一貫性のあるストーリーとして明確に説明する必要があります。
ガクチカの文字数はどれくらいがよい
エントリーシートで求められるガクチカの文字数は、企業によって様々ですが、300文字から400文字程度で設定されている場合が多いです。
文字数が指定されている場合は、その8割から9割以上を埋めるのが望ましいとされています。
文字数が少なすぎると、意欲が低いと見なされる可能性があります。
特に指定がない場合でも、300~400字程度を目安に内容をまとめておくと、多くの企業に対応しやすくなります。
また、面接では1分程度で簡潔に話せるように、この文字数で要点を整理して話す練習をしておくと良いでしょう。
採用担当者に響くガクチカ作成の3つのコツ
数多くのエントリーシートに目を通す採用担当者の心に響くガクチカを作成するためには、いくつかのコツを押さえる必要があります。
単に経験を羅列するのではなく、企業の視点を意識し、自身の魅力を効果的に伝える工夫が求められます。
ここで紹介する3つのポイントを実践することで、他の学生と差別化された、説得力のあるガクチカを作成することが可能になります。
自身の経験を最大限に活かすための準備を行いましょう。企業が望んでいる人物像とガクチカが合致していれば特別にな事を書く必要はありません。
企業の求める人物像と自分の強みを合致させる
ガクチカを作成する上で最初のステップは、志望する企業や人事がどのような人材を求めているのか、その「求める人物像」や「社風」を正確に把握することです。
企業の採用サイトや説明会、OB・OG訪問、写真や動画などを通じて情報を収集し、自社のビジネスモデルや社風に合った人物像を理解します。
その上で、自身の数ある経験の中から、その人物像に合致する強みが発揮されたエピソードを選択します。
例えば、挑戦意欲を重視する企業には、主体的に新しいことに取り組んだ経験をアピールするなど、企業側のニーズと自身の経験を戦略的に結びつける視点が不可欠です。多くの企業は就活の学生に即戦力を望んでいることは少なく、素直さやまじめさ、社風になじめるかなどを見ていることが多いです。
あまりすごい自分に見せるようなガクチカより等身大のガクチカでも大丈夫です。
具体的な数字を用いて客観的な事実を伝える
エピソードの説得力を格段に高めるためには、具体的な数字を用いて定量的に示すことが極めて有効です。
「サークル活動を頑張った」という曖昧な表現ではなく、「100人規模のイベントを企画し、前年比120%の参加者を集めた」というように、具体的な数を入れることで、取り組みの規模感や成果が客観的に伝わります。
数字を用いることで、採用担当者は状況を具体的にイメージしやすくなり、自身の貢献度を正確に評価できます。
売上や人数、期間、割合など、エピソードに関連する数字を洗い出し、積極的に活用することが重要です。
但し人事に刺さるように無理に大きな数字を出す必要はなく、誠実さや謙虚さも大事になりますので、相手に伝える為に数字を用いることを心がけましょう。
行動から得られた学びや再現性をアピールする
ガクチカでは、経験した事実を述べるだけでなく、その行動を通じて何を得たのかという「学び」や実行した理由を明確に言語化することが重要です。
そして、その学びや身につけたスキルが入社後、企業の業務においてどのように活かせるのか、つまり「再現性」や「利用価値」を示すことで、採用担当者は学生の将来性を評価します。
例えば、アルバイトでの経験から「相手の立場に立ってニーズを先読みする力」を学んだのであれば、それが営業職として顧客にどう貢献できるかを具体的に結びつけます。過去の経験を未来の貢献につなげる視点が、入社意欲の高さを示すことにもなります。
選考についてはアルバイトや学生時代のすごい実績より、おそらく失敗に向き合う姿勢やキャリアや仕事に対する姿勢や考え方もアピールになります。
誰でも魅力的なガクチカが書ける基本構成(フレームワークとは)
ガクチカを初めて書く人でも、分かりやすく説得力のある文章を作成するために役立つのが、基本となる構成です。
この型に沿って情報を整理することで、伝えたい内容が明確になり、読み手である採用担当者がスムーズに理解できるようになります。
ここで紹介する5つのステップを意識して組み立てることで、自身の経験を論理的かつ魅力的にアピールするガクチカを完成させることが可能です。
結論:何に力を入れたのかを最初に示す
ガクチカを書き始める際は、まず「私が学生時代に最も力を入れたことは〇〇です」というように、結論から簡潔に述べます。
文章の冒頭で主題を明確にすることで、採用担当者は話の全体像をすぐに把握でき、その後の内容に集中しやすくなります。
多くのエントリーシートに目を通す人事担当者にとって、要点が分かりやすい文章は高く評価されます。
アピールしたい項目は1つに絞り、これから何について語るのかを端的に示すことが、相手の興味を引きつけるための重要な第一歩です。
この書き出しによって、文章全体に一貫性が生まれます。
項目やエピソードの絞り方のポイントは何かを特定するよりは大きな項目を特定するイメージもオススメです。
例えば、居酒屋のアルバイトに力を入れましたで、特定するより、人間関係の構築とコミュニケーション能力の向上に力を入れました。
など学生時代は色々な経験や力を入れたことも複数あると思いますので、その中で自分自信の価値観を基に包括的になにに力を入れていたかで記載するとその後の話す内容も膨らましたり、絞ったり、一番伝えたいことが伝えらるようになります。
背景・課題:なぜそれに取り組んだのかを説明する
2つ目のステップでは、結論で述べた活動や項目に、なぜ取り組もうと思ったのか、その動機や背景を説明します。
具体的には、その活動を始める前にどのような課題や問題意識があったのかを記述します。他人や外部の課題を書くこともできますが、自分自信の課題解決のために、取り組んだ形の方が、自己認識能力や謙虚さが伝わり、他責思考か自責思考か伝えることが可能です。
「所属するサークルのメンバーの参加率が低かった」「アルバイト先でリピート客が少ないという課題があった」など、具体的な状況を示すことで、自身の主体性や課題発見能力をアピールできます。取り組んだ理由はなるべく自責思考での記載が良いかと思います。
どのような状況に対して自分がアクションを起こしたのかを明確にすることで、以降に続く行動の説得力が増し、ストーリーに深みが生まれます。
目標・行動:具体的な目標と自身の行動を記述する
発見した課題に対して、どのような目標を設定し、それを達成するために具体的にどのような行動をとったのかを記述します。
ここはガクチカの中で最も重要な部分であり、自身の思考力や計画性、実行力を示す見せ場となります。
例えば、「参加率を前期比で20%向上させる」という定量的な目標を立て、そのために「SNSでの告知を強化する」「イベント内容を4つのパターンでテストする」といった具体的な行動を時系列で説明します。
その際、チームの中で自分がどのような役割を担い、どんな工夫をしたのかを明確にすることが、自己PRにつながります。
できたことをアピールすることも大切ですが、何ができなかったかを理解し、できるようになる過程を重視してみてください。
結果・学び:取り組みから得られた成果と学びを伝える
自身の行動がどのような結果につながったのかを具体的に述べます。
その結果、「参加率が目標を達成し、前期比で30%向上した」のように、可能な限り数字を用いて成果を示すと、客観性と説得力が高まります。
目標達成の有無にかかわらず、その一連の経験を通じて何を考え、何を学んだのかを自身の言葉で言語化することが重要です。
成功体験からはもちろん、たとえ失敗した経験からでも、得られた教訓や次への課題を語ることで、自身の成長意欲や真摯な姿勢をアピールできます。
貢献:入社後にどう活かせるかをアピールする
ガクチカの締めくくりとして、これまでの経験から得た学びや強みを、入社後に志望企業でどのように活かし、貢献していきたいかを具体的に述べます。
学生時代の経験と、企業の事業内容や求める職務を結びつけ、自身が入社後に活躍する姿を採用担当者にイメージさせることが目的です。
「この経験で培った課題解決能力を活かし、貴社の〇〇という事業の成長に貢献したいです」といったように、企業研究に基づいた具体的なアピールが求められます。
これにより、入社意欲の高さと企業への理解度を示すことができます。
【テーマ別】ガクチカの魅力的な例文5選
これまで解説してきたガクチカ作成のコツや基本構成を踏まえて、具体的な例文をテーマ別に5つ紹介します。
学業、アルバイト、サークル活動など、多くの学生にとって身近なテーマを扱っています。
例えば、同じアルバイト経験であっても、課題発見から解決までのプロセスをどう切り取り、どう表現するかで、採用担当者に与える印象は大きく異なります。
これらの例文を参考にしながら、自身の経験を魅力的なストーリーに昇華させるためのヒントを見つけてください。
例文1:ゼミ活動で専門知識を深めた経験
私が学生時代に最も力を入れたことは、マーケティング戦略を研究するゼミ活動です。
当初、先行研究の論文を読んでも表面的な理解しかできず、議論についていけないという課題がありました。
そこで、専門知識を体系的に習得するため、毎週の課題論文に加え、関連書籍を2冊読むことを自らに課しました。
また、不明点は放置せず、教授やゼミ仲間に積極的に質問し、理解を深めました。
この取り組みを続けた結果、卒業論文では「SNSを活用した地方創生ブランド戦略」というテーマで研究をまとめ、優秀論文として評価されました。
理系分野の知識習得とは異なりますが、この経験で培った探求心と論理的思考力は、貴社で新しい市場を開拓する際に必ず活かせると考えています。
単位取得以上の学びを得られました。
例文2:アルバイトで売上向上に貢献した経験
私が学生時代に力を注いだのは、イタリアンレストランのアルバイトにおけるリピート率向上です。
私が勤務していた店舗では、新規顧客は多いものの、再来店につながりにくいという課題がありました。
原因分析のため、お客様アンケートを実施し、接客やメニューに関する意見を収集しました。
その結果、お客様とのコミュニケーション不足が満足度低下の一因だと判明しました。
そこで、お客様の好みに合わせたメニュー提案や、記念日でのサプライズ演出などをスタッフ全員で実践するよう働きかけました。
その結果、3ヶ月でリピート率を20%向上させることに成功しました。
この経験で培った課題分析力と実行力を、貴社の営業職としてお客様との関係構築に活かしたいです。
例文3:サークル活動でリーダーシップを発揮した経験
私は、所属するボランティアサークルのリーダーとして、組織の活性化に尽力しました。
私がリーダーに就任した当初、サークルはメンバーの参加意欲の低下という課題を抱えていました。
原因は、活動内容がマンネリ化し、各メンバーの役割が不明確なことにあると考えました。
そこで、メンバー一人ひとりと面談を行い、それぞれの興味や得意なことをヒアリングし、それに基づいた新しいプロジェクトチームを複数立ち上げました。
各チームに裁量権を与え、それぞれの役割を明確にした結果、メンバーの主体性が引き出され、活動全体の参加率は前年の50%から80%へと向上しました。
この経験から学んだ、多様な個性をまとめ、組織全体の力を最大化する調整力を、貴社のチームで発揮したいです。
例文4:留学経験を通じて異文化理解力を高めた経験
私は大学2年次にカナダへ1年間留学し、多様な文化背景を持つ人々と協働する力を養いました。
留学当初、現地の学生とのグループワークで、意見の対立からプロジェクトが停滞するという壁にぶつかりました。
私はこの状況を打開するため、まず各メンバーの意見を傾聴し、その背景にある文化や価値観を理解することに努めました。
そして、対立点だけでなく共通の目標を再確認することを提案し、粘り強く対話を重ねました。
その結果、チームに一体感が生まれ、最終的には全員が納得する形で成果物を完成させることができました。
この留学経験で培った異文化理解力と粘り強い交渉力を、グローバルに事業を展開する貴社で活かし、多様なチームでの成果創出に貢献します。
例文5:資格取得に向けて計画的に努力した経験
私が学生時代に力を入れたことは、独学での日商簿記2級の資格取得です。
大学の講義で会計に興味を持ったことがきっかけで学習を始めましたが、当初は専門用語の多さに苦戦し、模擬試験では合格点に遠く及びませんでした。
そこで、まず合格に必要な総学習時間を算出し、試験日までの残り日数から逆算して詳細な学習計画を立てました。
具体的には、毎日3時間の学習時間を確保し、参考書を12の章に分けて1週間で1章を完璧にするという目標を設定しました。
計画通りに学習を継続した結果、半年の独学期間を経て、一度の受験で合格できました。
この経験を通じて得た、目標達成に向けた計画立案力と自己管理能力は、貴社の経理職として正確かつ計画的な業務遂行に活かせると考えています。
「ガクチカがない」「強いエピソードがない」と悩む人必見!エピソードの見つけ方とは
就職活動を進める中で、「特別な経験や強いエピソードがないから、ガクチカに書けるエピソードがわからない」と悩む学生は少なくありません。
しかし、採用担当者は輝かしい実績だけを見ているわけではありません。
エピソードを見つけるのが難しいと感じる場合でも、視点を変えて自身の学生生活を振り返れば、アピールできる要素はいくつも見つかります。
ここでは、自分だけのガクチカは何がいいかを見つけるための具体的な方法を紹介します。
過去の経験を大小問わず全て書き出してみる
まずは大学入学後から現在までの経験を先入観を持たずに全て書き出してみることから始めましょう。
学業、ゼミ、研究室、サークル、部活動、飲み会、旅行、アルバイト、インターンシップ、ボランティア、留学、趣味、個人的な学習などどんなに些細なことでも構いません。
「頑張ったこと」「夢中になったこと」「困難だったこと」「悔しかったこと」といった感情を切り口に思い出すと記憶が整理しやすくなります。
この時点ではエピソードの優劣を判断する必要はありません。
この網羅的なリストアップが自分では気づかなかった強みやアピールポイントを発見する第一歩となります。
困難を乗り越えたり、工夫したりした経験を深掘りする
書き出した経験のリストの中から、特に「困難を乗り越えた経験」や「何かを改善するために工夫した経験」に注目し、深掘りしていきます。
「最初は無理だと思ったけれど、試行錯誤の末に達成できた」というエピソードには、自身の強みや思考の特性が凝縮されている可能性が高いです。
その時の状況、感じていた課題、設定した目標、具体的な行動、そして結果と学びを「なぜ?」「どのように?」と自問自答を繰り返しながら整理します。
この自己分析を通じて、単なる出来事が、課題解決能力や主体性をアピールできる一貫したストーリーへと変わります。
「輝かしい実績」でなくても良いと心得る
ガクチカでアピールすべきは、実績の華やかさではありません。
全国大会優勝や起業といった特別な経験がなくても、まったく問題ありません。
企業が本当に知りたいのは、結果の大小ではなく、目標に対してどのように考え、主体的に行動したかというプロセスです。
例えば、ごく普通のアルバイト経験であっても、「業務の効率化のためにマニュアルを作成した」「後輩の指導方法を工夫した」といった主体的な取り組みは、立派なアピール材料となります。たくさん遊んだこともガクチカになります。
他人と比較するのではなく、自分自身の経験に真摯に向き合い、その中での学びや成長を自分の言葉で語ることが最も重要です。
ガクチカのテーマとして避けるべき内容とは?
ガクチカのテーマ選びは基本的に自由ですが、中には採用担当者に意図が伝わりにくかったり、ネガティブな印象を与えかねなかったりする内容も存在します。
よくある失敗例を知っておくことで、自身の経験をより効果的にアピールするためのテーマ選びが可能になります。
企業の視点に立ち、ビジネスの場で評価される経験かどうかを客観的に判断することが求められます。
企業への貢献がイメージしにくい個人的な趣味
ゲームに熱中した経験や、特定のアーティストの応援活動といった、個人的な趣味に関するエピソードは慎重に扱う必要があります。
これらの活動自体が悪いわけではありませんが、その経験から得たスキルや学びが、どのように企業の業務に貢献できるのかを論理的に説明することが難しい場合があります。
特に、専門用語や固有名詞を多用すると、その分野に詳しくない採用担当者には内容が伝わらず、自己満足な話だと受け取られるリスクがあります。
もし趣味をテーマにするなら、目標設定や計画性、仲間との協調性など、ビジネスにも通じる汎用的なスキルを抽出して伝える工夫が不可欠です。
※刺さる人事や会社も当然あります。
受け身の姿勢が伝わるエピソード
企業が求めているのは、指示を待つだけでなく、自ら課題を見つけて行動できる主体性のある人材であることが多いです。
そのため、「大学のプログラムで留学させてもらった」「アルバイトで指示された業務を正確にこなした」といった、受け身の姿勢が伝わるエピソードは避けるべきですが、一方で素直さや無遅刻無欠席など当たり前のことができることも刺さるポイントになることもあります。
これらの経験は、自身の意思や工夫が介在していなく、行動の動機が他者にあると見なされがちです。
たとえ誰かに与えられた機会であっても、その中で自分が何を考え、どのように付加価値を生み出そうと行動したのか、という主体的な側面を強調することが重要です。素直に実行した理由を記載するとより良くなります。
常に「自分がどう働きかけたか」という視点でエピソードを語る必要があります。
まとめ
ガクチカは「学生時代に力を入れたこと」を指し、就職活動の選考過程で頻繁に問われる質問です。
企業はガクチカを通じて、学生の価値観や人柄、そして入社後のポテンシャルを評価しています。
自身の強みを直接的に伝える自己PRとは異なり、ガクチカでは課題解決のプロセスや経験からの学びを具体的に示すことが求められます。
本記事で紹介した基本構成や書き方のコツを活用し、企業の求める人物像を意識しながら、自身の経験を振り返ることが重要です。
特別な実績がなくとも、主体的に考え行動した経験を論理的に説明できれば、それは十分に魅力的なアピールとなります。
リクナビや最新のオファーボックスなどエントリーシート(ES)への記載だけでなく、ナビサイトに登録する際にも必要になってきます。
就職したい企業の求める人物像や社風に沿っていることが重要ですし、入社してすぐ退職、転職にならないように、見栄を張らずに、素直に丁寧に記載することも大切です。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方
履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説
転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介
「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む