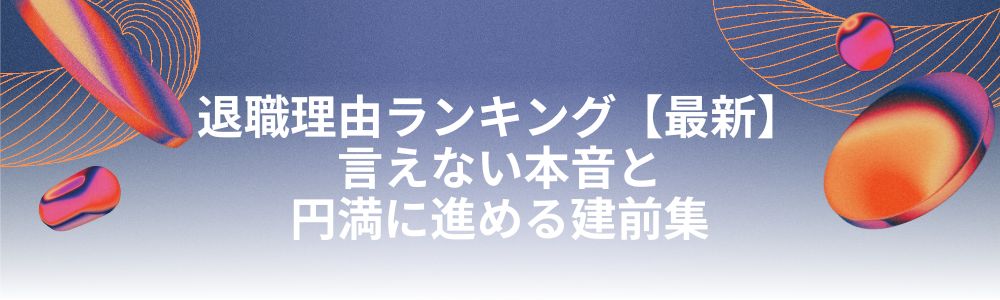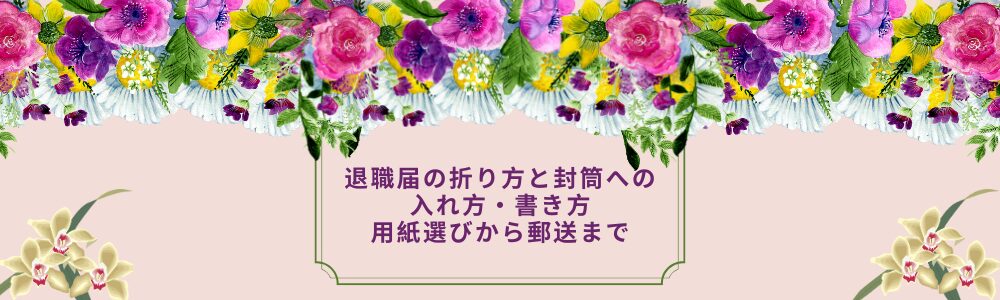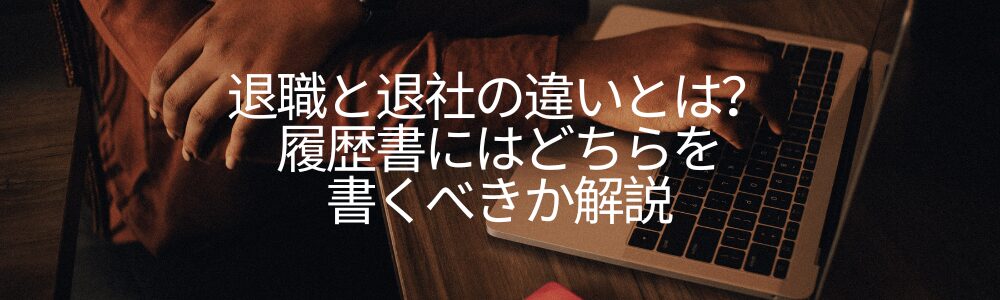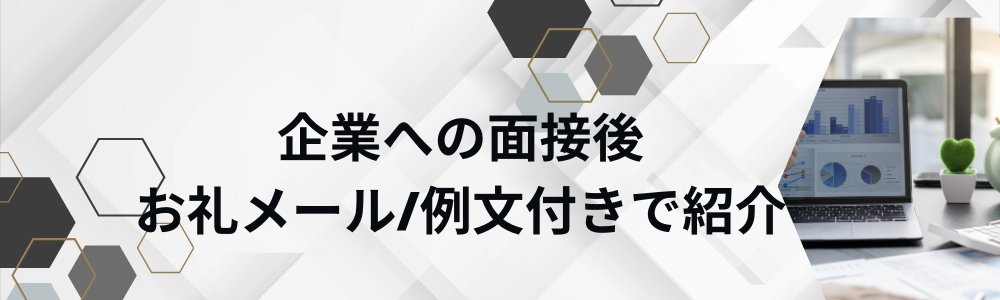

企業への面接のお礼メールについて例文つきで解説
転職活動における面接のお礼メールは、送るべきか迷う人も少なくありません。
特に中途採用では、これまでの社会人経験からビジネスマナーが問われる場面でもあります。
面接のお礼メールは必須ではありませんが、送ることで丁寧な印象を与え、入社意欲をアピールする機会になり得ます。
この記事では、面接のお礼メールの必要性から具体的な書き方、コピーして使える例文までを詳しく解説します。
面接のお礼メールは送るべき?選考への影響を解説
面接後のお礼メールが、どの程度選考に影響を与えるのかは気になる点です。
結論から言うと、お礼メールの有無が合否を直接決定づけることはほとんどありません。
しかし、送ることで採用担当者に好印象を与えたり、入社意欲の高さを示したりする効果が期待できます。
他の応募者との差別化を図る上でも、送っておいて損はないコミュニケーション手段の一つと捉えることができます。
面接のお礼メールは必須ではないが、丁寧な印象を与えられる
面接後のお礼メールの送付は、義務ではありません。
多くの企業では、お礼メールの有無を選考基準に含めておらず、送付が不要なケースも少なくないです。
送らなかったからといって、それ自体が不採用の直接的な原因になることは考えにくいでしょう。
しかし、面接に時間を割いてもらったことへの感謝を形にすることで、採用担当者に丁寧で誠実な印象を与えることができます。
基本的なビジネスマナーが身についているという評価にもつながるため、迷った場合は送付を検討するのが賢明です。
合否に直接影響は少ないが、面接のお礼は入社意欲のアピールにつながる
面接のお礼メールだけで合否が覆ることは稀であり、選考への直接的な影響は限定的とされています。
しかし、面接では十分に伝えきれなかった入社への熱意や、その企業で働きたいという強い意志を改めてアピールする絶好の機会となります。
特に、採用担当者が複数の候補者で迷っている場合、メールから伝わる強い入社意欲が後押しになる可能性も考えられます。
企業側としては、自社への関心が高い人材を採用したいと考えているため、お礼メールは志望度の高さを伝える有効な手段です。
面接のお礼メールを送る前に知っておきたい基本マナー
お礼のメールを送る際には、ビジネスマナーを守ることが不可欠です。
良かれと思って送ったメールが、マナー違反によってかえって評価を下げてしまう可能性もあります。
送信するタイミングや宛先の書き方、適切な手段の選択など、社会人として知っておくべき基本的なルールが存在します。
ここでは、お礼メールを送る前に押さえておきたい基本マナーについて解説しますので、送信前のチェックに役立ててください。
面接のお礼メールを送る最適なタイミングは面接当日中
お礼メールを送る最適なタイミングは、面接を受けた当日中です。
面接官の記憶が新しいうちに感謝の気持ちを伝えることで、丁寧な印象とともに熱意も伝わりやすくなります。
もし当日中に送るのを忘れた場合でも、諦める必要はありません。
遅くとも面接の翌日の午前中までには送信するようにしましょう。
数日が経過してしまうと、かえってタイミングを逸したと見なされ、ビジネスマナーを疑われる可能性も出てきます。
感謝を伝えるという目的を考え、できる限り迅速な対応を心がけてください。
宛先は採用担当者が基本!名前が不明な場合の対処法
お礼メールの宛先は、日程調整などで連絡を取り合っていた採用担当者にするのが基本です。
もし面接官の名前が明確にわかる場合は、その方個人に宛てて送るとより丁寧な印象となります。
役員や複数の面接官が同席していた場合、全員に送る必要はありません。
採用担当者宛のメールに「面接をご担当いただいた皆様にも、くれぐれもよろしくお伝えください。」といった一文を添える形で問題ないです。
万が一、担当者の名前が不明な場合は「採用ご担当者様」と記載します。
感謝を伝える手段はメールと手紙のどちらが適切か
面接のお礼を伝える手段としてメールと手紙が考えられますが、現代の転職活動ではメールが一般的です。
メールは面接当日中など、迅速に感謝の気持ちを伝えられる点が最大のメリットです。
一方、手紙やハガキはより丁寧な印象を与えますが、企業に到着するまで時間がかかり、採用担当者がすぐに確認できるとは限りません。
また、企業によってはセキュリティの観点から手紙の開封に手間がかかる場合もあります。
特別な理由がない限り、ビジネスの基本である速報性を重視し、メールを選択するのが無難です。
採用担当者に好印象を与える面接のお礼メールの書き方【構成要素別】
お礼メールの内容は、採用担当者に好印象を与えるための重要な要素です。
単に感謝を伝えるだけでなく、構成を工夫することで、入社意欲や人柄を効果的にアピールできます。
件名から署名に至るまで、各項目にはそれぞれ押さえるべきポイントがあります。
ここでは、お礼メールを構成する要素別に、具体的な書き方のポイントを解説します。
これらの点を意識することで、より質の高いお礼メールを作成できるでしょう。
件名/タイトル:「面接のお礼(氏名)」のように用件と名前を明記する
お礼メールの件名は、採用担当者が一目で内容を把握できるように、簡潔かつ具体的に記載することが重要です。
例えば、「〇月〇日の面接のお礼(自分の氏名)」や「【面接のお礼】〇〇〇〇」のように、用件と自分の名前を必ず入れましょう。
採用担当者は日々多くのメールを処理しているため、件名だけで誰からの何の連絡かが分からないと、他のメールに埋もれてしまったり、開封が後回しになったりする可能性があります。
分かりやすい件名を設定することは、相手への配慮を示すビジネスマナーの基本です。
宛名:会社名・部署名・担当者名を正式名称で正しく記載する
メールの冒頭に記載する宛名は、相手の企業名、部署名、役職、担当者名を正式名称で正確に書くのがマナーです。
「株式会社」を「(株)」と略したりせず、必ず正式名称を用います。
企業の公式サイトなどで確認してから記載しましょう。
担当者の氏名がわかる場合は「人事部〇〇様」、部署までしかわからない場合は「人事部御中」、部署も名前も不明な場合は「採用ご担当者様」とします。
宛名を正確に記載することは、注意深さや丁寧な人柄を示すことにも繋がります。
本文(書き出し):面接の時間をいただいたことへの感謝を伝える
本文の冒頭では、まず面接のために時間を割いてもらったことへの感謝を述べます。
「本日はお忙しい中、面接の機会を設けていただき、誠にありがとうございました。」といった形で、丁寧にお礼を伝えましょう。
この際、「本日〇時より面接していただきました〇〇です。」のように、いつ、どの面接を受けたかを簡潔に付け加えると、採用担当者が思い出しやすくなります。
日程調整の段階から丁寧に対応してもらった場合は、そのことにも触れると、より感謝の気持ちが伝わるでしょう。
本文(主文):面接の感想や入社意欲を具体的にアピールする
本文の主文では、面接の感想や入社への熱意を具体的に伝えます。
単に「貴社で働きたいです」と書くだけでなく、面接で聞いた話の中で特に印象に残ったことや、自身の経験をどのように活かせるかについて触れると、説得力が増します。
例えば、役員面接で伺った事業の将来性やビジョンに共感した点などを具体的に挙げることで、企業理解度の高さと入社意欲をアピールできます。
面接で十分に伝えきれなかった自身の強みを補足するのも有効ですが、長文にならないよう要点を簡潔にまとめることが肝心です。
結び:今後の選考に関する言葉と結びの挨拶で締めくくる
本文の最後は、今後の選考について触れる言葉と、結びの挨拶で締めくくります。
「面接の結果を心待ちにしております」や「ぜひ、次の選考の機会をいただけますと幸いです」といった一文で、選考への前向きな姿勢を示しましょう。
その後、「末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」といった、相手の企業の発展を願う言葉を添えるのが一般的です。
この結びの一文があることで、メール全体が引き締まり、丁寧な印象で終えることができます。
署名:氏名・大学・連絡先を忘れずに記載する
メールの最後には、署名を記載するのが一般的です。署名には、氏名(フルネーム)、電話番号、メールアドレス、そして所属(新卒の場合は大学名や学部)といった連絡先情報を正確に記載しましょう。採用担当者が誰からのメールかをすぐに確認し、必要に応じてスムーズに連絡を取れるようにするための重要な情報です。ビジネスメールの署名には、これらの情報の他に会社名、部署名、役職なども記載されますが、就職活動のメールにおいては、住所は必須ではありません。ただし、企業と郵送でのやり取りが発生する可能性がある場合は、住所を記載すると良い印象を与えることもあります。
氏名にふりがなを振っておくと、採用担当者が名前を間違えることなく確認できるため、より親切な印象を与えられます。普段からメールの署名設定をしておくと、記載漏れを防げます。
【状況別】コピーして使える面接のお礼メールの例文3選
ここでは、面接後のお礼メールの具体的な例文を3つの状況別に紹介します。
基本的な構成の例文から、面接で話した内容に触れて熱意を伝えるもの、面接での発言を補足したい場合のものまで、目的に応じて使い分けが可能です。
これらのメール例文を参考に、自身の言葉や面接で感じたことを加えてアレンジすることで、よりオリジナリティのある、気持ちの伝わるメールを作成できるでしょう。
例文1:基本形として感謝と入社意欲を伝える
この例文は、面接後のお礼メールとして最も基本的な構成です。
まず、面接の機会をいただいたことへの感謝を述べ、続けて面接で伺った話の中で特に興味を持った点や共感した部分に触れます。
これにより、単なる定型文ではなく、しっかりと話を聞いていたことが伝わります。
そして、面接を通して入社意欲がさらに高まったことをストレートに表現し、自身のスキルや経験をどのように活かしていきたいかを簡潔に付け加えます。
最後に、今後の選考に関する言葉と結びの挨拶で締めくくる、シンプルで汎用性の高い構成になっています。
例文2:面接で話した内容に触れて熱意を伝える
二次面接など、より踏み込んだ質疑応答が行われた後に適した例文です。
この形式では、面接で特に印象に残った会話内容を具体的に引用します。
「〇〇事業の今後の展望についてお伺いし、特に△△という点に強く惹かれました」のように記述することで、真剣に話を聞き、深く理解しようとする姿勢をアピールできます。
その上で、その事業に自身がどのように貢献できるかを結びつけ、入社後の活躍イメージを採用担当者に持たせます。
面接内容を自分なりに消化し、熱意として表現することで、他の応募者との差別化を図る構成です。
例文3:面接での発言を補足したい場合
面接で緊張してしまい、伝えたいことを十分に話せなかったと感じた際に有効な例文です。
特に合否への影響が大きい最終面接後などに用いることが考えられます。
メールではまず面接のお礼を述べた上で、「〇〇に関するご質問に、十分に回答できず失礼いたしました」とお詫びの一言を添えます。
そして、「改めて補足させていただきますと」と続け、簡潔に伝えきれなかった要点を記述します。
長文になったり、言い訳がましくなったりしないよう、あくまで簡潔な補足に留めるのがポイントです。
熱意を伝える最後の機会として、誠実な姿勢を示す構成となります。
評価が下がるかも?面接のお礼メールで避けるべき5つの注意点
良かれと思って送ったお礼メールも、内容や送り方によってはかえってマイナスの印象を与えてしまうことがあります。
ビジネスマナーを欠いたメールは、社会人としての資質を疑われることにもなりかねません。
誤字脱字といった基本的なミスから、送信する時間帯への配慮まで、避けるべき注意点が存在します。
ここでは、評価を下げかねないお礼メールの注意点を5つ紹介しますので、送信前の最終確認に役立ててください。
誤字脱字や敬語の間違いがないか送信前に確認する
お礼メールに誤字脱字や不適切な敬語があると、かえって「注意力が散漫な人」「ビジネスマナーが身についていない人」というマイナスの印象を与えかねません。
特に、宛先である会社名や担当者名を間違えることは、大変失礼にあたります。
送信ボタンを押す前に、必ず全体を最低でも2〜3回は読み返しましょう。
声に出して読んでみると、文章のリズムの違和感や間違いに気づきやすくなります。
せっかくの感謝の気持ちが、些細なミスで台無しにならないよう、送信前の最終確認は徹底してください。
定型文の丸写しで誠意のない面接のお礼の内容は避ける
インターネットで検索すれば、お礼メールの定型文やテンプレートは簡単に見つかります。
しかし、それらをそのままコピー&ペーストしただけの文章は、採用担当者に簡単に見抜かれてしまいます。
心のこもっていない、誰にでも送れるような内容では、感謝や入社意欲は伝わりません。
面接で実際に感じたこと、印象に残った話、それによって自身の考えがどう変化したかなど、自分の言葉で具体的に記述することが重要です。
定型文はあくまで参考程度に留め、オリジナリティのある内容を心がけることで、誠意が伝わります。
企業の就業時間外である深夜・早朝の送信は控える(日時を考える)
感謝の気持ちを伝えたいからといって、深夜や早朝など、企業の就業時間外にメールを送信するのは避けましょう。
受け取った採用担当者によっては、「生活リズムが不規則な人」「時間管理ができない人」といったネガティブな印象を持つ可能性があります。
お礼メールは、面接当日の企業の就業時間内に送るのが最も丁寧です。
もし当日中に作成が間に合わなかった場合は、翌日の始業時間以降、午前中に送信するのが望ましいです。
夜中に作成した場合は、メールソフトの予約送信機能などを活用し、相手の就業時間内に届くように設定すると良いでしょう。
カラフルな文字装飾や過度な絵文字は使用しない
ビジネス文書であるお礼メールにおいて、カラフルな文字装飾や絵文字、顔文字の使用は不適切です。
強調したい部分を太字にしたり、文字の色を変えたりする行為は、ビジネスマナーに反すると見なされ逆効果になる可能性があります。
こうした装飾は、幼稚でTPOをわきまえられない人物という印象を与えかねません。
感謝の気持ちや入社への熱意は、文章の内容そのもので表現するべきです。
シンプルで読みやすいテキスト形式が、ビジネスメールの基本です。
誠実な姿勢を示すためにも、不要な装飾は一切行わないようにしましょう。
現在勤めている会社のメールアドレスは使わない
現在、他の企業に在職しながら転職活動を行っている場合、お礼メールの送信に現職の会社のメールアドレスを使用するのは絶対にやめましょう。
会社の資産であるメールアドレスを私的に利用することは、公私混同であり、情報管理に対する意識の低さを露呈する行為です。
採用担当者から著しく評価を下げられる原因となります。
転職活動に関する企業とのやり取りには、必ず個人のプライベートなメールアドレスを使用してください。
Gmailなどのフリーメールで問題ありません。
また、会社のパソコンやネットワークを利用して送ることも同様に避けるべきです。
面接のお礼メールに関するよくある質問と回答
面接のお礼メールに関しては、送るべきタイミングや内容以外にも、細かな疑問が生じることがあります。
例えば、面接が複数回ある場合に毎回送るべきか、面接官が複数人いた場合の宛先はどうすればよいかなど、具体的な状況での対応に迷うケースは少なくありません。
ここでは、お礼メールに関するよくある質問とその回答をまとめました。
これらのQ&Aを参考にすることで、さまざまな場面で適切に対応できるようになるでしょう。
複数回の面接では毎回お礼メールを送るべき?
選考過程で複数回の面接が設定されている場合、お礼メールを毎回送るべきか迷うかもしれません。
基本的には、面接の機会をいただくごとに、都度お礼メールを送るのが丁寧な対応です。
ただし、毎回同じ文面を送るのでは意味がありません。
一次面接、二次面接と、それぞれの段階で感じたことや、新たに深まった企業理解、そこで得た気づきなどを具体的に盛り込み、内容に変化をつける工夫が求められます。
特に面接官が同じ人物である場合は、簡潔さを心がけ、しつこい印象を与えないように配慮することも必要です。
面接官が複数人いた場合、全員に送る必要がある?
面接官が複数人いた場合、全員に個別でお礼メールを送る必要はありません。
基本的には、採用窓口となっている人事担当者の方宛に一通送れば十分です。
もし、面接官の中で中心的な役割を担っていた方や、役職が最も上の方の連絡先が分かるのであれば、その方宛に送るのも良いでしょう。
全員に送るとかえって相手の手間を増やしてしまう可能性もあります。
その際は、メール本文に「面接をご担当くださった〇〇様、△△様にも、くれぐれもよろしくお伝えくださいませ。」といった一文を添えることで、他の面接官への配慮も示すことができます。
企業から面接のお礼メールに返信が来たら、さらに返信するべき?
送ったお礼メールに対して、企業側から返信が届くことがあります。
この場合、さらに返信すべきか迷うところですが、簡潔にお礼の言葉を述べるのが丁寧な対応です。
ただし、相手からの返信メールに「返信は不要です」といった記載がある場合は、その指示に従いましょう。
返信をする際は、「お忙しい中、ご丁寧にご返信いただき、誠にありがとうございます。」といった内容に留め、長々と続けないことが重要です。
相手の負担を考え、こちらでメールのやり取りを完結させるという配慮を示してください。
まとめ
面接のお礼メールは、選考の合否や内定を直接左右するものではありませんが、採用担当者に丁寧な印象を与え、入社意欲をアピールする有効な手段です。
送付する際は、面接当日の就業時間内というタイミングや、正確な宛名の記載といった基本的なビジネスマナーを守ることが前提となります。
インターネット上の例文をそのまま使うのではなく、面接で感じたことや学んだことを自分の言葉で具体的に記述することで、誠意が伝わります。
この記事で解説した書き方や注意点を参考に、自身の状況に合わせたお礼メールを作成してください。アドバイスとしては、面接のお礼より前の書類選考や日程調整の時のメールのやり取りも基本的なビジネスマナーがあるかの判断として企業側からよく見られていますので迅速かつ丁寧なやり取りを心がけましょう。
その他の就職役立ち情報箱を見る
-

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職理由ランキング【最新】言えない本音と円満に進める建前集
退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが会社に伝える退職理由です。最新の調査データを基にしたランキングを見ると、給与や人間関係への不満といった本音の理由… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部退職届の折り方と封筒への入れ方・書き方 用紙選びから郵送まで
退職届を提出する際は、内容だけでなく、用紙の選び方から折り方、封筒への入れ方まで、定められたマナーを守ることが重要です。 正しい手順を踏むことで、会社へ… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法
転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -


退職と退社の違いとは?履歴書にはどちらを書くべきか解説
「退職」と「退社」はどちらも会社を辞める際に使う言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。特に転職活動で作成する履歴書と職務経歴書では、退職と退… 続きを読む -

 BE GOOD編集部
BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説
履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む